(新約聖書 テサロニケ人への手紙第一 5章16節から18節)
2026年1月9日 15:49 コメントを書く Feedback
作句や初心者指導に行き詰まったとき、私はいつも青畝師の著書「俳句のこころ」をバイブルのように読み返してメンタルの軌道修正をしています。
その中のいくつかの俳話は、書き写して「作句の壺」のページにもリンクしています。
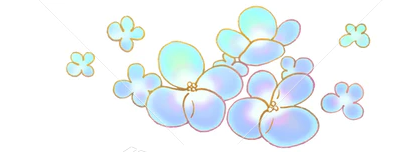
さて昨年後半はかなり多くの新メンバーを毎日句会に受け入れました。
会員資格者は、 みのるの俳句理念 に賛同いただいていることが必須という約束をしていただいていますが、経験を重ねないと理解できない要素も多く現実はなかなか難しいです。
そこで新年にあたり、奉仕活動としての ![]() の運営についてご理解を深めていただきたいと祈念し、興味深い青畝師の俳話をひとつご紹介ご紹介したいと思います。
の運営についてご理解を深めていただきたいと祈念し、興味深い青畝師の俳話をひとつご紹介ご紹介したいと思います。
![]()
ぜひご一読いただいて、このウエブサイトの活動を支えていただきたくよろしくお願いします。このページを印刷して読んでいただけるようにPDFも用意しました。
2026年1月8日 14:20 コメントを書く Feedback
システムの仕組みを補足説明をするつもりでしたが、過去に運営していた兼題句会をアレンジしたに過ぎないので省きます。ここがよくわからん…という方は、Feedbackからお問合せください。
![]()
俳句という縦書きの文芸をネットの横書きで楽しむという革命は四半世紀前に公開した ![]() が先駆者的存在だったと自負しています。その後つぎつぎと俳句サイトが林立し結社までネットで活動する時代になりました。
が先駆者的存在だったと自負しています。その後つぎつぎと俳句サイトが林立し結社までネットで活動する時代になりました。
私も今年82歳、終活を考えねばならない年齢になりましたが、90歳までは頑張れと初夢で青畝師に励まされてうかうかとそんな気になり始めています(^o^)
![]()
新しい活動スタイルを模索するなかで、毎日句会の参加資格取得のための無料添削はやめることにしました。若鮎句会がその代替としての使命を担います。
若鮎句会で一年間の学びをしていただいたら毎日句会、吟行句会にも加わっていただくという流れになります。意欲的で成長著しい方については一年を待たずに特待生として推薦をさせていただくこともあるかと思います。
![]()
定例吟行句会についても出来れば再開したいと願っています。そのためには若い世代の牽引者が必須ですのでそうした人材の発掘にも繋がればと願って若鮎句会を立ち上げました。
決して旧来メンバーとの差別化を意図するものではありまありません。どうか意のあるところをご理解いただき、これまで通り支えていただきたくお願いします。
![]()
吟行句会の場合、吟行地とは別に最寄りの句会場を確保するというのが最大のネックです。句会場への移動時間ももったいないです。
そこで句会場不要、紙や筆記用具も不要で四阿やベンチに分散してスマホ句会ができるよう独自のウエブ句会システムを開発しました。
多くても10人までの小句会なのでこれで十分かと思います。武蔵野女子会では既に活用されています。
とはいいながら昨年の楽しかった須磨浦吟行句会の昂ぶりを思い出すたびに隔年でもいいので ![]() 全国規模でのオフ吟行句会ができたら幸せだなぁ〜と。
全国規模でのオフ吟行句会ができたら幸せだなぁ〜と。
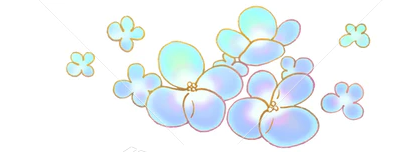
I have a Dream !
2026年1月7日 10:38 コメントを書く Feedback
2000年に ![]() を立ち上げて四半世紀が経ちました。
を立ち上げて四半世紀が経ちました。
紆余曲折しながらもこんなに長く運営できたのは参加者の皆様の協力と支えがあったからです。今年のお正月にその来し方を顧みつつ、つくづく自分は幸せ者だなと感謝しました。
![]()
25年前の毎日句会は参加資格の審査などなく俳句に興味のある方ならどなたでも受け入れていました。全国規模となり多いときには100人を遥かに超えミニ結社の様相を呈していた時期もありました。
ところが参加者の増加にともなってゴスペル俳句の理念など何処吹く風の心無い人が増え始め、やがて彼らが類をなしてサイトを席巻し始め収集がつかないほどに荒れ始めたので、やむなく毎日句会を閉鎖してしまったのです。
![]()
毎日句会閉鎖後の虚しさを救ってくださったのは、関西エリアの有志の皆さんでした。仕事の都合で私が活動休止している間もグループで吟行句会(スワン句会)を続けてくださり再開を待ち続けてくださったのです。
仕事が完全リタイアになった2011年から毎日句会を再開しました。今度は過去の苦い経験を活かして会員制の運用に変えて現在に至っています。
![]()
平和な運用が続くなか、初心者のための俳句サイト…という謳い文句を掲げながらある意味では差別的な運用であることがずっと気になっていました。
多くの俳句サイトが採用している投句箱運用なら選の結果が乱れることはありません。でも、
俳句は座の文学であること、俳句を通しての交わりこそが人生の支えになることを伝えるのが
の使命
だと考えていたのでその選択子はありませんでした。
二年ほど前に試行した「一日一句」という無料添削コンテンツも新しい仲間の発掘という意味では大いに寄与したのですが毎日というハードな対応が徐々に重荷になり不本意ながら挫折してしまいました。
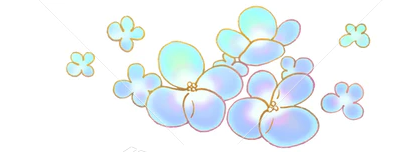
そんなこんなで今年のお正月期間に祈って構築したのが「若鮎句会」のシステムなのです。ページの案内や仕組みを見て頂けたら「なるほどね…」と意図を理解いただけると思います。
この仕組みが活かされるか否かは毎日句会メンバーの協力が不可欠です。その理由は初心者オンリーで運用した場合の互選結果がどうなるかを想像して頂けたらわかると思います。
毎日句会のメンバーは既に全員登録済みなので同じパスワードで参加いただけます。選句だけでもいいのでご協力いただければ限りなく理念に沿った互選結果となり初心者の上達にもつながると思うのです。
ぜひともご協力よろしくお願いいたします。
![]()
前置きがあまりに長くなってしまったのでシステムの詳細説明はまた後日にしますね。
2026年1月5日 11:48 コメントを書く Feedback
今年はじめての毎日句会みのる選をアップしました。
年末年始のみなさまの消息が目に浮かぶようで楽しく選ができました。
![]()
![]() が推奨する写生俳句は、ある意味で自分史を綴る日記だと思います。
が推奨する写生俳句は、ある意味で自分史を綴る日記だと思います。
吟行の難しい極寒のこの時期、やもすればテレビの画面や新聞で紹介されたニュースで作句したり、歳時記を繰りながらの俳句になりがちです。
これらの情報を引き金として過去の記憶へタイムスリップして句に詠む…ことは、決して悪いことではありません。
けれども、実体験のない情景を連想や想像だけで作り上げた作品は虚構になるので避けてほしいです。将来自分の句集を編むとき、虚構の句を並べても詠んだ当時の感動が蘇るということはないからです。
![]()
うけねらいの虚構の句づくりが習慣になってしまうと俳句は単なる言葉遊びになってしまいます。
俳句の上達はひたすら写生あるのみ、表現は稚拙であっても必ず実感を得て自分のことばで詠むという習慣を身につけることで個性が生まれるのです。
2026年1月1日 00:00 コメントを書く Feedback

あけましておめでとうございます。
今年もみなさまにとって良い年でありますように。お祈りいたします。
![]()
(イザヤ書40章31節)
2025年12月31日 12:36 コメントを書く Feedback
いつになく平安でいい意味で無聊な大晦日を過ごしています。
高齢化を言い訳についつい消極的になり永年ご協力頂いた定例吟行句会が休会になったのは昨年のことでした。
さらに今年は、初心者の育成をと意気込んだ「一日一句」、私自身への奨励のためでもあった秀句合評研究や秀句選評などもみな挫折してしまいました。
あれもこれもと欲張って力んだ結果オーバーワークになっていたのかもしれませんね。
![]()
今朝は、いつかみなさんにも公開したいと溜めてあった資料の中に「歩んだ道は --その主張--」という青畝師の記事を見つけたので読み返しました。
ともかくにも私の俳句生活が五十年だ。単調ではなかった。俳句を捨てようと思った日もあり、五里霧中でやってもきた…
という箇所を読んだとき、"天の上の存在に近かった先生がとても身近な同胞" であるかのような錯覚を覚えました。
半世紀にわたる俳句生活を回顧しての自伝とも言える内容ですが、サブタイトルに「その主張」とあるように師の確たる俳句理念を示されたものです。
青畝師に傾倒していた私は、知らず知らずのうちに同じような道を模索してさ迷っていたようにも思います。
![]()
その主張……すなわちそれは ![]() の理念にも通じると思いましたので、一日早いですが、この記事をGHメンバーの皆様へのお年玉として公開します。
の理念にも通じると思いましたので、一日早いですが、この記事をGHメンバーの皆様へのお年玉として公開します。
vお正月の炬燵の中で寛ぎながらお読みいただくのにちょうど良いと思いますので、ぜひプリントアウトしてゆっくりとご覧になってください。
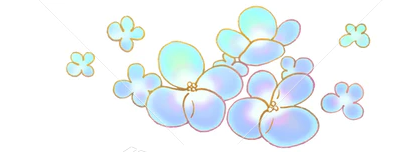
一年間ほんとうにありがとうございました。
諸事情により試練や戦いの中にあるメンバーも数名いらっしゃいます。どうか上からの慰めと励ましがありますように、この試練を乗り越えることができるよう見えざる御手をもって守り支えてくださるようにと切に祈ります。
![]()
2025年12月30日 10:22 コメントを書く Feedback
2025年も残すところあと一日になりました。
参加者の皆様のご協力によって大事なくホームページの運用が継続できましたことを心から感謝します。
オフライン活動が少なく寂しさを覚えた一年間でしたが、高齢化という実情を考えると詮無きことと思います。そんな中にあって秋に武蔵野女子会のメンバーが来神してくださり須磨浦吟行句会を実施できたことは何よりの慰めであり喜びでした。
![]()
最近では私自身も老化を実感する中 ![]() の終活のあり方ばかり考えるようになっていましたが、須磨浦吟行句会を機にそうではないと気付かされました。現実は受け止めつつも、前向きで新しい活動のあり方を考えるべきではないかと示されたのです。
の終活のあり方ばかり考えるようになっていましたが、須磨浦吟行句会を機にそうではないと気付かされました。現実は受け止めつつも、前向きで新しい活動のあり方を考えるべきではないかと示されたのです。
武蔵野女子会を核に関東エリアでの活動がさらに祝福されて拡大していくこと、関西エリアでも若い参加者を発掘育成してオフライン活動を復活させることが今の私に課せられた使命だと思えるようになりました。
![]()
聖書に『若者は幻を見、老人は夢を見る』という一節があります。同志社女子大学名誉教授近藤師の解説があるのでリンクを貼っておきます。
現代社会において高齢者が夢をもつことは難しいです。健康的にも目は弱く耳も遠くなり体中のあちこちが次々と痛み日々そのメンテナンスとの戦いで精一杯だからです。
けれども聖書の神様は「老人は夢を見る」と約束してくださっています。
もちろん自分好みの身勝手なものではなくて神様の示される大きな夢を共有させていただけるという意味ですね。
1963年 〝I have a Dream(私には夢がある)〟 と高らかに宣言したマーティン・ルーサー・キング牧師の夢は、約50年後の2009年に初めての黒人大統領オバマ氏の当選により確かに現実に近づきました。
み心に沿った夢を持ち続けることで神様はそれを支え、さらには実現させてくださるという証しだと思います。
![]()
![]() の進むべき道もまた言うほど甘くはなく所詮は儚い夢で終わるかもしれません。それでも祈りつつ希望をもって運営したいと思います。
の進むべき道もまた言うほど甘くはなく所詮は儚い夢で終わるかもしれません。それでも祈りつつ希望をもって運営したいと思います。
どうぞ来年もこれまで同様に祈り支えてくださいますようよろしくお願いいたします。そして来たるべき新しい年がみなさまにとって夢のある幸大き年でありますようにお祈りして感謝に代えさせていただきます。
2026 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2025 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2024 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2023 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2022 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2021 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2020 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2019 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2018 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2017 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2016 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2015 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2014 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2013 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2012 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2011 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2010 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2009 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2008 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2007 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2006 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2005 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2004 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2003 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2002 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2001 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。