2025年1月28日 10:10 コメントを書く Feedback
終活を視野に推進を見直すなかで、「四時随順」を ![]() 活動のアーカイブとして残したいという思いが湧きました。
活動のアーカイブとして残したいという思いが湧きました。
「俳句とエッセイ」という仕立てですが必ずしも作品の自解ではありません。
物質的な財産はないので、みのるが何を思い何を考えて生きてきたかという証しとして家族や孫たちに伝えたいと考えたからです。
今年に入ってから新作を追加したり、古いものを再編集しながら取捨したりという作業を始めています。更新情報にも反映させていますので紛らわしいと思いますがお許しください。
その対策として大きく再編集したものは、投稿日時を再編集日に書き換えてアップすることにしました。そうすることでブログの TOPページに表示されることになります。
![]()
励みになりますのでぜひお読みいいただいた感想をフィードバックしてください。記事ごとにお寄せいただいたフィードバックを「読者の声」として巻末に纏められたらよきメモリアルになると願っています。
2025年1月27日 11:42 コメントを書く Feedback
「毎日句会秀句鑑賞」というタイトルは冗長で分かりにくいと思って直感的な「秀句選評」に改名しました。
![]()
選句の基準というようなものはないのですが、巧みで上手い句ではなくて素朴で新鮮な感覚の句に選者としての興味をそそられます。
今週は奇しくも武蔵野女子三人の句を選んだことになります。考えて作るのではなく、ひたすら吟行して感じて詠む…を実践して励む彼女たちの健気な姿勢に感心させられます。
何が大切かということは頭でわかっていても継続して行動することは難しいですが、「老い」を言い訳にするのではなく私達も負けずに頑張りましょう。
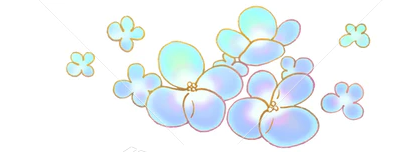
今日は秀句一歩手前の作品をとりあげてみましょう。
![]()
原句:山茶花の咲き満つ垣根鳥語降る
降る…といわれると高垣が連想され花垣と鳥影とで焦点が分かれてしまう。垣根から洩れ聴こえてくることで咲き満つ花垣がよりクローズアップされ蜜を吸う鳥たちの狼藉によって花が溢れている様子も連想できる。
![]()
原句:ふるまひ茶一会の人と話す四温
話す…を「わす」と訓読みさせるのはやや窮屈。春寒の園の休憩所などで来訪者に温かいお茶が振る舞われているのでしょう。日向ぼこ…とすれば隣り合う様子が具体的に浮かぶしお喋りしている様子も連想できる。
![]()
原句:思ひ出のほどかれ毛糸玉四つ
原句は微妙に時間経緯の表現になるのでやや切れ味に欠ける。高度なテクニックになるが、毛糸玉四つ…と詠み終えたあともう一度上五の、ほどきたる…に戻ったときの感覚を比べてみると余韻の違いが分かると思う。
![]()
原句:語尾揚るお国訛りや納豆汁
季語としての「納豆汁」を活かすためには、山形県で古くから親しまれている冬の家庭料理であることを匂わせるように詠みたい。語尾揚る…の措辞は具体的ではあるがやや説明的になるので連想に委ねるほうが良い。
![]()
原句:寒鯉の塊ほどく日差しかな
互選で高点を得たのは「塊ほどく」という措辞がうけたからと思うが、やや比喩が過ぎる感じがする。寒い間はほとんど動きを見せなかった寒鯉が動きはじめたことに水温む季節の到来を感じたと素直に写生したい。
![]()
原句:笛吹ケトル一直線の湯気立てて
ケトルが笛を鳴らし勢い良く湯気をたてている様子を写生したかったのは理解できる。ただ笛吹きと湯気立ての二つをいうと焦点が分かれてしまう。笛吹きは省略して季語の湯気立てを強調したほうが力強くなる。
![]()
原句:さざなみのやうに音たて落葉ふむ
落葉を踏む音がさざなみのようだという写生は無理がある。落葉踏む…を主役にするならもっと別の比喩が必要。さざなみのようだ…と言いたければ風に吹かれる落葉のほうが実感がある。比喩は正しく斡旋したい。
![]()
原句:山で飲る氷柱で作るロック酒
句意は明快だが作意が見え隠れして写生句としての実感に乏しい。山上で酒を楽しむ(飲る)ことが目的ではなく、無事の登頂を感謝して同伴者とともに軽く乾杯しているのだという実感を捉えたほうがいいと思う。
![]()
原句:日脚伸ぶ帰宅の道の夕日かな
夕日に向かって帰宅の道を歩いていたら日脚の伸びたことを実感した…というのが意図であるが、日脚伸ぶ…が季語なので、夕日が射すのは当たり前かつ説明。こうした観念から脱皮することが上達への道である。
![]()
禍を知らぬ子も手を合はす阪神忌
実景をそのまま写生した句ではあるが作者の小主観が弱いので報告気味になる。復興のために親世代が体験したことや人の絆の大切さなどを子供たちに語り伝えながら一緒に祈っているという姿に見えるように詠みたい。
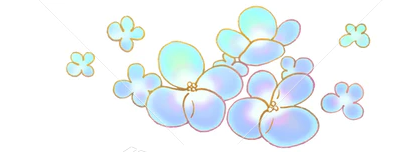
聖書に次のような言葉があります。
新約聖書 コリント人への手紙二 4章18節
![]() は、見えないものに目を注ぎ永遠の命を写生する俳句でありたいと願っています。
は、見えないものに目を注ぎ永遠の命を写生する俳句でありたいと願っています。
2025年1月22日 16:28 コメントを書く Feedback
新年度に向けて活動メニューを少しリニューアルしました。また明石句会については、現協力メンバーとご相談したうえでの決定になりますが定期開催を見送ることにしました。
![]()
郵送による無料添削を復活させました。
熱心に学んでくださる方には特別研修生としてメール添削への移行を承認したり、添削の学びで上達された方には毎日句会への参加資格を付与させていただくことにいたします。
![]()
トップページの [SELECT.Me] のメニューを下記に変更しました。
今年はこれらのコンテンツを重点ライフワークとして活動しようと思います。
生涯句集は残さないと決めているのですが、「エッセイ・四時随順」については最終100句を目標として完成させ、できれば小冊子に纏めたいと願っています。
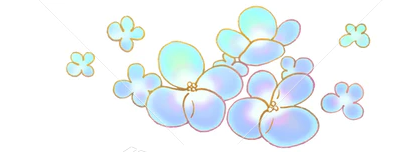
メンバーの高齢化に伴い定例句会はなくなりましたが、今後若いメンバーが与えられ自主的な活動が興されたら喜んで奉仕したいと思っています。
2025年1月17日 10:01 コメントを書く Feedback

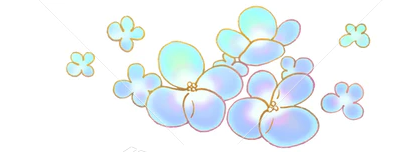
今朝5時46分から、神戸市中央区の東遊園地で阪神・淡路大震災から30年となる追悼行事「1.17のつどい」が開催されました。
この日はいつもこの時間に家内と二人で黙祷しています。
この追悼行事で灯籠を並べて描かれる文字は、毎年公募され、「がんばろう」から始まり、「わすれない」「むすぶ」「ともに」など歴年とともに変わってききており30年という節目の今年は、「よりそう」になりました。
今日、兵庫県公館で天皇皇后両陛下ご隣席のもと追悼式典が行われるとのことです。
2025年1月14日 08:27 コメントを書く Feedback

![]()
今年は、1995年(平成7年)1月17日5時46分52秒に発生した阪神・淡路大震災から30年になる。
先週の毎日句会に次なる作品があった。
着膨れて地震の日のまた偲ばるる うつぎ
30年を経てもなお生々しく当時の恐ろしさが思い出されるのである。
![]()
震災直後に詠まれた作品を紹介しよう。
避難所の焚き火に彼を探しけり 紫峡
当時紫峡師は阪急六甲駅近くにお住まいで、幹部同人のお一人が住んでおられた六甲篠原町地区が全壊というニュースを聞かれて避難所を探し回れた時の句である。
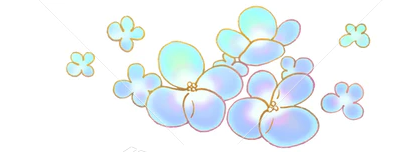
その後、震災の犠牲者を追悼して防災意識を新たにする俳句が作りやすくなるようにという趣旨で、鷹羽狩行氏が阪神淡路大震災忌を略して「阪神忌」を季語にしたいと提唱され、賛否両論あったが追々に詠まれるようになった。
![]()
阪神忌天幕の灯は野外ミサ 小路紫峡
これは震災一年後のまだ復興途上にある神戸の街を詠まれた作品。地震で倒壊したチャペルはまだ再建できていないので寒空のもとテントで礼拝を守っているのである。
![]()
阪神忌ピアノの傷を繕はず 小路紫峡
大切にしていたピアノが地震の被害で傷がついてしまった。このピアノが盾となって地震時の落下物から身を守ってくれたというようなことも考えられる。当時の体験を忘れないためにと繕わずにそのままにしてあるのである。
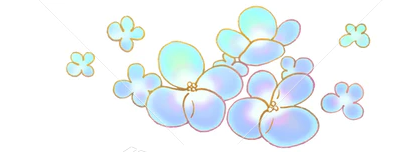
![]() でも下記のような句が詠まれている。
でも下記のような句が詠まれている。
黙祷に晨朝明くる阪神忌 みのる
ハイカーも碑に黙祷す阪神忌 みのる
灯籠につなぐ心や阪神忌 やよい
終ひ湯に至福を思ふ阪神忌 満天
忘の字の闇に灯るや阪神忌 あひる
生き延びし汝れも鬼籍や阪神忌 せいじ
点検も忘れしリュック阪神忌 もとこ
花時計移転に想ふ阪神忌 たか子
![]()
実体験をもとに感動を呼び起こして句に残すことは大切であり且つ鎮魂としても意義あることと思う。ぜひ挑戦してほしい。
2025年1月6日 12:25 コメントを書く Feedback
添削による学びは、何故そのように直されたのかを理解して納得することで上達に繋がります。それなら毎回その意図を説明すれば効果的かと言えばそうではないのです。
説明による学びは極めて近道に思われそうですが、労なくして得た知識は決して実作の役にはたちません。作者の復習努力によって理解し得たものしか身につかいないからです。茶道や華道、様々なスポーツ然り、HOW-TO本を山ほど読んでも決して上達に直結しないのと同じです。
理屈や理論は実作経験を通してを覚えるもの、一句一句に執着せず黙々と多作多捨の修練に徹することが結果として一番近道なのです。忍耐して一年間それを実践されたらなるほどと解ります。
さらに三年間継続できたら知らず知らずのうちにあなたは立派な俳人になっています。でも復習努力をせず添削されっぱなしのままで句歴を重ねても人生の支えとなる本物の俳句はものにできないと思います。
![]() の場合、添削の意図を説明することは原則として行いませんが、新しいメンバーも増えてきたので、新年にあたってヒントとなる部分だけを少しだけ説明してみようと思います。
の場合、添削の意図を説明することは原則として行いませんが、新しいメンバーも増えてきたので、新年にあたってヒントとなる部分だけを少しだけ説明してみようと思います。
![]()
添削後の作品の著作権は原作者に帰属しますがその取捨は自由です。納得の行かないものを無理に受け入れる必要はありません。どうしても抵抗がある…という場合は捨てて下さって構いません。
実は私もそうした経験があります。5年、10年を経てやっとその意図が納得できた…ということもあるからです。
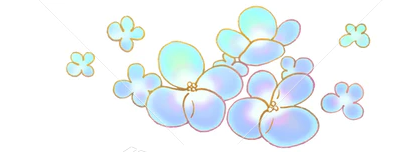
隠せざる齢うべなふ初鏡
原句:隠せざる齢そのまま初鏡
いまさら粧っても老いを隠すことは無理なのよねと達観して初鏡に対しているよ…というのが作者の意図かと思う。実力ある作者の句を添削するのはおこがましいと思ったが初鏡である故に特に齢を実感したという感興を強調したくてあえて添削した。初心者への指針とするためなのでお赦し願いたい。
![]()
日の枝に音符並びす寒雀
原句:寒雀譜面のごとく並びけり
ふくら雀となり押しくら並びするのが寒雀の特徴なので音符並びだけでは季語が動く。温かい冬日の絡む枝ゆえに欣喜雀躍して音符並びになるのである。音符並びの雀の句は類句も多く本来なら没であるが、季語が動かないように詠むのが写生の基本であることを覚えてほしくて取り上げた。
![]()
駅伝の目指すは箱根雪の富士
原句:韋駄天の目指すは箱根雪の富士
箱根駅伝と前書があれば誤解がないと思うが、韋駄天という措辞だけではよくよく分析すれば意味不明の句になっていることに気づいてほしい。走者と目指す富士と焦点が二つに分かれるのも面白くない。走者は省略し雪の富士にのみ焦点を絞ることで大景の句となり新春にふさわしい。
![]()
国内線搭乗口に松飾り
原句:乗り初めの搭乗口の松飾り
必然性があれば別だが「乗り初め」「松飾り」とお正月の季語が重なるのでひと工夫がほしい。松飾りによってお正月に故郷へ帰省する人たちの心の昂ぶりが伝わる。実景はそうではないのかも知れないが国際線ではなくて国内線とすることでより具体的に故郷感を出せると思う。
![]()
若水に明けの日差しの届きけり
原句:若水や明けの天空映しをり
若水といわれると御手洗や蹲、井戸などが連想されるので、そうした狭くて小さい水面に天空を斡旋するのは無理がある。瑞々しい日がさし届いたとするほうが若水の目出度たさにふさわしい。
![]()
無音界深々と降る夜半の雪
原句:無音とは深々と降る雪の夜
斯く哲学風の表現をしたくなるのは「作ろう」という意識が克っているからで主観や理屈の句に陥りやすく、かえって説明感や押し付け感が強くなる。素直に且つ出来る限り具体的な写生を心がけたい。「夜半の雪」は写生だが「雪の夜」は説明である。伝統俳句ではこの違いも重要。
![]()
観音の千手もゆるぶ小春かな
原句:冬うらら千手観音手のゆるび
うららかな冬日和ゆえに観音様の翳した緊張感のある千手も緩むのではと捉えた作者の小主観がこの句の手柄。実際はそんなことはありえないので「ゆるぶがごとき」としたくなるがこのケースでは省略して断定するほうが力強くてよい。「千手」と「手の」で手が二度重なるのを避けるために斯く添削したが句意は変わらない。
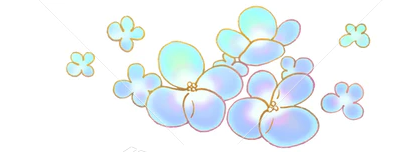
少し上達してくると平明な表現では物足りなくなり、格調高い句を詠もうとして言葉を選んだり、特異な措辞を斡旋したりして独りよがりな作品づくりに陥りやすい。
平明な客観写生でありつつ、作者の愛の目や優しさなどが伝わってくるように表現することのほうが遥かに価値があり大切なことだということに気づいてほしい。添削はある意味でその警笛でもあるのです。
2025年1月1日 06:42 コメントを書く Feedback

あけましておめでとうございます。
今年もみなさまにとって良い年でありますように。お祈りいたします。
![]()
(旧約聖書 詩篇37篇5節)