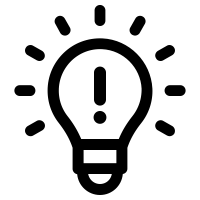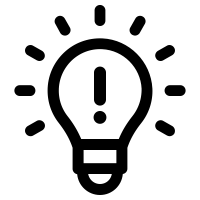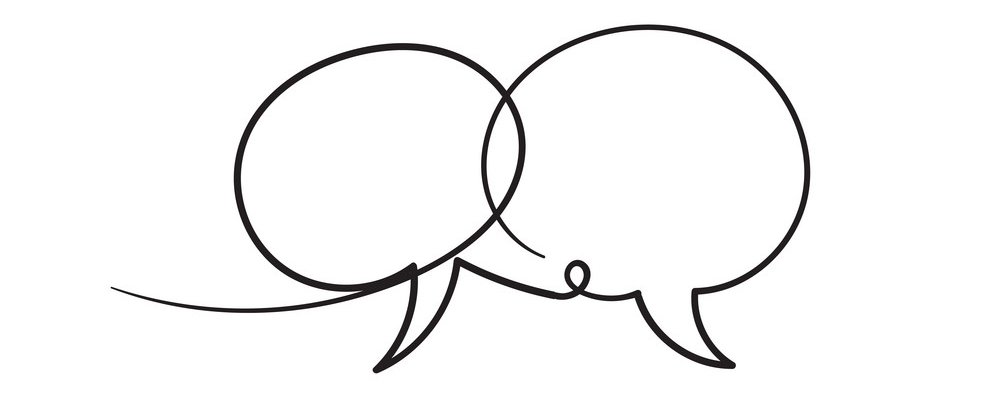
最新の7件を表示しています。
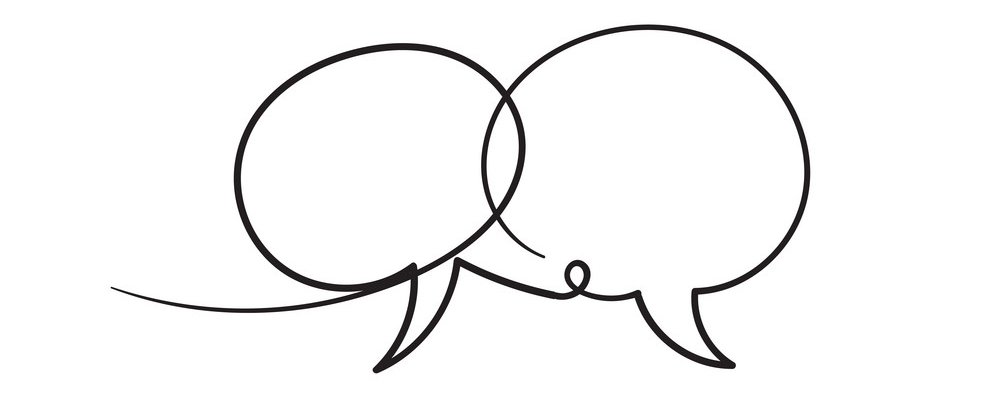
最新の7件を表示しています。

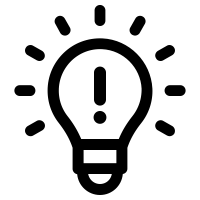

これみたいですね(^o^)
-- 自解(抄) --
私の若い時は現在のように写生万能を言わず、まず題を課せられてその題を案じながら句を作る習慣があった。例えば事実いま初詣しないで、与えられた初詣の題を中心にいろいろ工夫を凝らして作句していた。
そこで過去の経験を顧みて京都に下宿した頃の八坂神社を頭に蘇らせた。賑やかな四条通りが突き当たるところに西門があって、誠に優美な随身(矢大臣)二体が西面している。向かって右側は老人の随身、口をゆるく開けている。左側は壮年の随身、口を閉じている。
寺の仁王のようにこれも阿吽の相が示されているらしいが、老人の方は口を緩く開けたにこやかさに親しみをたたえ、お正月の私たちの心をよく見ているように感じられる。

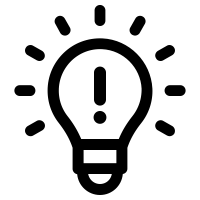

写真で見ると綺麗な鳥ですね。
-- 自解(抄) --
落柿舎あたりを歩いてみたく、ただぶらぶらと細い藪の道を拾う。そして誰にもあわぬ孤独をしみじみ味わった。つめたく熟れた烏瓜を引きちぎった。そのとき小鳥が忙しく渡っていった。
目の前に一群の緋連雀が来た。敏捷な挙動を取りながら統率が取れている。赤い冠毛がとても可憐だ。しかし次の瞬間には一羽もいなくなった。掃き捨てたように本当に見えない。

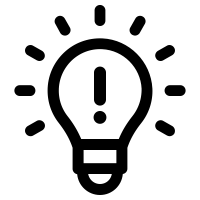

幼い頃よりの耳疾でよく耳が聞こえない。秋虫の音を聞きながら本を読みふけっている「耳しひ児」それは私なのだ。
紫峡師とご一緒して奈良県高取町ある青畝師の生家を何度か訪ねました。お庭に揚句の句碑があります。
![]()
-- 自解(抄) --
読書の楽しみは食欲よりも強いときが多くむしろ濫読という方だったかもしれない。大和という古い土地がら万葉集に親しむことも故なきことではなかった。
虫が鳴きそめる夜ごろは夏よりも読書力が旺盛で徹夜した日もあった。机の下でこおろぎが声を立てると驚いて立ち上がったりした。とにかくものをよく読んではひとり興奮したものだ。