2021年11月
目次
厩舎へと伸びしホースのかげろひぬ コメントを書く
(きゆうしやへとのびしホースのかげろひぬ)
厩舎(きゅうしゃ)は、元は家畜を飼う小屋のことであるが、競馬の普及で調教師が管理する施設・組織の総称として用いられる言葉になっている。ただ、揚句は、昔私も一緒によく吟行した関西学院大学の馬術部の厩舎だと思う。現在はすこ場所が変わったが昔は校舎のすぐ裏にあり自由に吟行が可能であった。ホース自身がかげろうことはないと思うのでホースの転がっているあたりは、馬を洗った水で地面が濡れていてそれが春の日差しで陽炎ので「ホースの」になったのであろう。馬術部の女子部員たちがかいがいしく馬の世話をしている様子はじつにのどかな雰囲気であった。
- 合評
-
-
厩舎という語感から、馬術のための施設を連想しました。馬の世話は早朝まだ暗いうちから始まりますが、陽炎が揺らめいているということは、太陽が高い午後、馬たちは放牧され、その間に馬房の掃除や水替え、飼い付けをしているのでしょう。人と動物がともに暮らす様子がとても良いです。 (むべ)
-
厩舎は家畜を飼育する施設ですが、競馬の馬が管理されている所でもあるようです。かげろひぬが季語ですからあたたかい春の午後かも知れません。ホースの中に残っている水も幾分温まって、掃除にも家畜の飲料にも冷たすぎる水の季節は終わったようです。 (あひる)
-
厩舎は馬でしょうか。牛でも良いのですがこの場合は馬だと思えます。長いホースはところどころ穴も開いているかも知れません。ところどころににじむ水に春の陽ざしがあたり陽炎が立っているのでしょう。 (素秀)
-
かげろひぬが春の季語。牧場だろうか、厩舎まで伸びたホースが陽炎っていることよ。ホースまでもが春の陽気を楽しんで踊っているかのようである。 (せいじ)
-
家畜の世話をするために厩舎へ水のホースを引き込んでいる。そのホースに陽炎が立っている。暖かくよく晴れた日に家畜が長閑に育っている。 (豊実)
春蘭や朽葉だたみにはぐくまれ コメントを書く
(しゆんらんやくちはだたみにはぐれけり)
鉢植えの春蘭でもそうですがまだ寒さの残る中、地際に短い花茎が立って蕾をつけます。やがて暖かくなると茎が伸びて花を咲かせます。みなさんの合評の通り揚句のそれは、鉢植えではなく山中で見つけたのでしょう。朽葉を押しのけるようにして顔を出したばかりの蕾だと思う。『◎◎だたみ』というのは一面にうち広がっている様子をいいます。朽葉だたみがお布団のように大地を覆って凍てから守り、染み込んだ栄養分によっていま元気な蕾を揚げているのである。
- 合評
-
-
蘭と聞くと鉢植えを思い浮かべますが、この蘭は野に自生するものでしょう。落葉の間から顔を出して可憐に花開いている、朽ちた葉は蘭の栄養にもなり守ってもいるようです。 (素秀)
-
春蘭が春の季語。朽ちた落葉を褥として春蘭が咲いている。野山に自生しているのか観賞用に栽培されているのかはわからないが、自然の力によって大切に育て上げられていることへの感慨を示している。蓮と汚泥の関係にも似た美醜の対比と「朽葉だたみ」という表現がうまいと思った。 (せいじ)
-
蘭といえば、鉢植えが思い浮かびますが、春蘭は山菜としても食されることがあるようです。朽ちた葉っぱが暖かく根本を覆い、栄養ともなって、春には可憐な花が咲くのでしょう。花ではなく根もとに目を注ぐ視線が新鮮です。 (あひる)
-
雑木林の枯葉の腐葉土に育まれて春蘭が咲いている。自然が息づいているという感じがします。 (豊実)
注連焚けば巻貝めきて灰となる コメントを書く
(しめたけばまきがひめきてはいとなる)
お正月の注連飾りがどんどの灰になったのですね。勢い良く一気に燃やされて形が崩れないで灰になったのが巻貝に見えたというのです。童心のような感覚で心を遊ばすことができたからこの句が授かったのです。兵庫では、焼いた灰を持ちかえり家の四隅に積むのが習わしで、家内安全、無病息災を願います。
その他地域によって田畑にまいて豊作を祈ったり、蛇やムカデなど魔除け封じというところもあるようです。
- 合評
-
-
巻き貝めきて…が思いがけない表現でした。灰になる前のひとときを、何と言おうかと、じっと見つめていたのではないでしょうか。戸口に飾られていた時とはあまりに違う姿です。 (あひる)
-
注連縄が燃えて形の残る灰は色も含めて巻貝のように見えた。形の崩れる前のひと時の状態を上手くまとめています。 (素秀)
-
注連焚くが新年の季語。どんどにくべた注連縄が燃えて灰になっているのだが、巻貝のように、縄がねじられたままの形で残っている。言われて見ればそうだなと思う。ちょっと触ると崩れ落ちて無定形の灰になってしまうのだが、そうなる前の姿をよく捉えていると思った。 (せいじ)
-
どんど焼きで注連縄の裏白が燃える時に、くるくるっと丸まったのが巻貝のように見えたのだと思います。 (豊実)
(ふくじゆさういもせならびのかげかさね)
素秀さん、さすがです。この句1月に出ていました。うっかりしていてごめんなさい。俳句の場合は特にですが、「妹背」は男女の夫婦のことです。キリスト教の結婚式では、「妹背を契る」という祝福の賛美歌が歌われます。福寿草の二つの花が互いに凭れあうように割いているのが仲睦まじい夫婦の姿に見えたのです。ご主人がお元気で幸せだった頃をふと思い出されたのかもしれないですね。お正月のおめでたい雰囲気がうまく表現できていると思います。
- 合評
-
-
妹背ならびという言い方は初めてです。少し大きめのと小さめのと、福寿草が仲のよい夫婦のようにくっつき合って咲いていたのでしょう。翳重ねが優しく美しい表現で、愛しげに眺めている様子が目に浮かびます。 (あひる)
-
新年を祝う盆栽かと思います。二つの福寿草が翳を重ねるほど近くに夫婦のように並んでいる。新年のめでたい気分で可愛く黄色い福寿草を愛でているのでしょう。 (豊実)
-
この句は2度目ではないでしょうか。顔を出した順番で少し大きさの違う福寿草を姉妹と見立てて影が重なるほど寄り添っていると。 (素秀)
-
福寿草が新年の季語。翳が重なり合うほどに接近して二つの福寿草の花が咲いている。一つは少し大きくもう一つは少し小さいのだろう。偕老が肩を寄せ合って日向ぼこを楽しんでいるようである。まことにおめでたい。 (せいじ)
(きんしゆうにそうでんせんのまぎれけり)
あくまで言葉のもつ印象ですが、紅葉といわれると「紅」の色を連想しますが、錦繍とか錦といわれると「紅」と「黄」などの斑の印象があります。
山は省略されていますが、送電線という措辞によってそれが連想できます。シンプリ極まりない作品なのですが、麓から伸びた送電線が山腹のあたりで錦繍に溶け込む感じに消えている様子がよくわかります。多弁にならず省略を効かすことで力強い句になっていると思う。
- 合評
-
-
美しい紅葉は神様の手のわざ、送電線は人のわざ。人工の物が自然の風景を台無しにすることもありますが、送電線は、たいした邪魔にはならず、何とか自然の中に受け入れられています。錦繍が圧倒的な美しさだったからでしょう。 (あひる)
-
紅葉の刺繍の送電線が織り込まれているようだ。無粋な電線も山の装いに一役買っているようようだと見たのではないでしょうか。 (素秀)
-
錦のように美しい山の紅葉……しかし、人住まぬエリアだからこそ鉄塔が立ち送電線が張られているのですね。本来は興ざめなはずの送電線ですが、人工を凌駕する天然のすばらしさが「まぎれけり」に表現されているように感じました。 (むべ)
-
折角きれいな紅葉の風景を送電線が邪魔しているのだと思います。邪魔とは言わず、まぎれけりと言うところに作者の優しさを感じます。 (豊実)
-
錦繍が秋の季語。ほぼ青と緑の夏の野山の中では、弓なりの送電線がくっきりと見えていたが、紅葉・黄葉して錦繍のようになった秋の野山では、送電線がどこにあるのか、多彩な色の中に入りまじってよく分からなくなったことよ。まぶしいほどの錦繍の美しさである。 (せいじ)
カウベルの登山電車に聞えけり コメントを書く
(カウベルのとざんでんしやにきこえけり)
確か加代子さんは何度かユングフラウに行っています。「白靴でユングフラウの雪を踏む 加代子」という句が青畝選に入選しました。季語の扱いに厳格な選者なら没句でしょうね。でも主季語は「白靴」であることは明白、こうした句を採って褒めてくださる青畝選にも感動しました。俳句は理屈で詠むものではないというよいお手本です。話はそれましたが、皆さんの合評が素晴らしく私が付け加えることはありません。
- 合評
-
-
登山電車が夏の季語。スイスでもいいのかもしれないが、ネットを調べると、箱根の登山電車とケーブルカーの乗換駅である強羅駅に「スイスから贈られた友好のカウベル」があるとのこと。強羅駅で登山電車から降りるときに扉が開いてカウベルの音が聞こえてきたではなかろうか。 (せいじ)
-
カウベルが聞こえてきたと言われると日本ではなさそうです。アルプスでしょうか。ハイジの歌声も聞こえてきそうです。 (素秀)
-
カウベルと登山電車で、すぐにスイスだと思いました。スイスの写真はいろんなところでよく見ます。でも、写真では電車にまで聞こえてくるカウベルの音は想像出来ませんでした。電車の窓は開いていたのでしょう。ベルの音とともに、夏山の清々しい空気も入り込んでいたのでしょう。 (あひる)
-
夏の季語「登山電車」というと身近には箱根登山鉄道を連想しますが、沿線に牛はいなそうなので、作者はスイスのユングフラウ鉄道にでも乗っているのでしょうか?車窓から夏のアルプスの絶景を堪能しています。雪山に反射する太陽、富士山山頂くらいの高度を走る電車で空の青さも格別でしょう。おや、カウベルが聞こえてきました。牛飼いのおじさんが放牧から帰ってきたようです。雄大なパノラマと人の営みの組み合わせがすてきです。 (むべ)
-
長閑な酪農の風景を登山電車の窓から眺めている。電車にまで聞こえるとは思ってなかった、牛の首に付けているカウベルが聞こえてきて感動したのではないでしょうか? (豊実)
朝市にマロニエ落葉ころがりし コメントを書く
(あさいちにマロニエおちばころがりし)
技工も何もなく素直に「マロニエ落葉」を配して異国の朝市だと連想させています。また風で運ばれてきたであろうことも想像できるので、半屋外の朝市でしょう。みなさんの合評にあるとおりパリのそれがすぐ目に浮かびます。確かに、むべ解にあるようにマルシェの石畳みが似合います。紫峡先生からは固有名詞にもたれた俳句づくりはなるべく避けるようにと戒められました。揚句もふつうなら海外旅行の一句として「マロニエの落葉やパリの朝市に」としたくなります。でも「バリ」を省くことで「ころがりし」という具体的な措辞を盛り込むことができました。でも、どちらが正しいのかは難しいところです。
- 合評
-
-
人々の暮らしが垣間見えてその土地が一気に近くなるのが朝市の魅力ですね。マロニエの一語で外国かなと思いました。作者はパリジャンに紛れてマルシェを訪れ、量り売りチーズなど買いつつ歩いていると、マロニエの落葉が風で運ばれ半屋内のマルシェの石畳みに。秋の深まりを感じました。 (むべ)
-
エッフェル塔からの流れだとパリの朝市かなと思いますが、そうでなくても朝市の通りを転がっていく落葉に朝の寒さや人通りなどが想像できます。マロニエは木も葉も大きいですから吹き溜まりのボリュームも踏みしめる音も大きいだろうと思えます。 (素秀)
-
この句を読めば、心はすぐに枯葉散るパリに飛びます。色とりどりの野菜や魚介類などが並び素敵な雰囲気ですが、作者はそこに転がった一枚の?落葉を主役にしています。その名も、マロニエとつけば堂々とした主役です。季語が生きるってこういうことかと思いました。 (あひる)
-
落葉が冬の季語。パリのシャンゼリゼ通りあたりの朝市の情景を想像した。マロニエというだけで洒落た雰囲気がただよう。寒さで乾ききったマロニエの落葉が、風や人の動きで、からからと音を立ててころがったところを捉えたのだと思う。金属性の音が心地よい。 (せいじ)
-
朝一で並べられた野菜の上に、風で飛ばされたマロニエの大きな落葉がのっかった。邪魔なので取り除いた。寒い朝一の一場面かと思いました。 (豊実)
(ちうともるエッフェルとうやくれはやし)
「宙灯る」という大胆な措辞がこの句の肝になっています。これによって夜空に浮かび上がるようにライトアップされたエッフェル塔の姿が具体的に連想できます。地上から打仰いだのではなく、むべ解のとおり高層ホテルの窓からの遠景のほうがよりその感じがするように思います。昼間あちこちと名所見学をしたのち、ホテルにつきチェックインして自分の部屋に案内されてホッとした気分でふと窓の外をみると、早やとっぷりと暮れた夜空の景に一変していて驚いたのである。海外吟では季感をとらえるのが難しいと言われますが、この「暮早し」はうまいです。
- 合評
-
-
ライトアップされた冬のエッフェル塔が見えるようです。塔は地面に踏ん張って聳えているものだと思いますが、宙に灯るとは、不思議な感じがします。暮れ始めた夜空に夢のように浮かびあがって見えたのでしょう。冷たい夜の空気が感じられます。 (あひる)
-
日没からライトアップされる美しいエッフェル塔。セーヌ川のクルーズ船からか、はたまたエッフェル塔がよく見えるホテルの窓からか、「宙灯る」に真っ暗な空との対比が表れているように感じました。日本の稚内より北にあるパリは、夕方5時には真っ暗、「暮早し」を実感できる立地ですね。明けるのも9時近くとかなり遅い…… (むべ)
-
暮早しが冬の季語。クリスマスシーズンにパリ観光に出かけたのであろう。ヨーロッパは緯度が高いから、日本よりもさらに昼の時間が短い。こんな時間にもう灯が、という驚きがよく出ており、それによって「暮早し」に実感がこもる。「宙灯る」にエッフェル塔の高さも見える。 (せいじ)
-
ふと見るとエッフェル塔に灯がともっている。パリの夜はことに早く感じているようです。観光旅行であちこち回っているとアッという間に夜になったと言う事でしょうか。 (素秀)
-
夕食前の時間がまだ十分ありそうです。パリの街を一歩きして、ライトアップされたエッフェル塔を眺めながらの夕食が楽しみだなあという感じがします。 (豊実)
(しんごうをむしせるかぜのおちばかな)
主役は風に押されて駆けてゆく落葉ですが、作者との位置関係に連想を広げることで一景が具体的になり、そこに作者の小主観も見えてきます。作者は背中を押す冷たい風に耐えながら赤信号の横断歩道で信号の変わるのを待っているのです。何人かの人も一緒でしょう。そこへ風の落葉が信号待ちしている人たちを後ろから追い越して横断歩道を駆けていったのです。まだ赤信号なのに待ちきれずに歩き出すせっかちな人も居ますよね。はやく青信号になって渡りたいという寒風裡の信号待ちの気持ちもが隠されていると思います。
- 合評
-
-
信号を無視しているのは風で落葉は無理矢理付き合わされているようなものなのですが、人の目に見えるのは落葉です。風に吹かれる落葉と信号を組み合わせたのが面白いところです。 (素秀)
-
人間社会の交通規則など関係なく自由自在に吹く風が、落葉によって可視化されています。信号無視という言葉にはマイナスイメージがあるように思いますが、この句からはくすりと笑いがこぼれます。 (むべ)
-
よくある冬の風景です。風の落葉が信号を無視・・と表現する作者のユーモア精神にほっこりします。寒い冬も心を自由に遊ばせて豊かな時間を過ごしたいと思いました。 (あひる)
-
落葉が冬の季語。落葉が風にはげしく舞っている。人間が後から作った交通信号など目に入らぬようだ。信号を無視したのは風か落葉か。風が無視を言い出し落葉がそれに同調したと認められるから、共犯を言い渡そう。擬人化が楽しい。 (せいじ)
-
この風は結構な強風ではないでしょうか?横断歩道を歩いている作者の目の前を冷たい北風に飛ばされた落葉が通過した。 (豊実)
(ちらばれるありにるろうのたみおもふ)
獲物に向かって急ぎ足で道をなしている蟻の行動とは対象的に揚句の蟻たちはてんでんばらばらに散って彷徨うように獲物を探し歩いているのです。その様子を流浪の民のようだというのは飛躍し過ぎのようにも思うけれど、季感との結びつきを考えるならば、干ばつ被害で貧している難民の様子などをたまたまテレビのニュースとかで見て強く印象されていたのでそこへ繋がったのかもしれない。
- 合評
-
-
夏の日の一こまです。人は蟻の散らばる様子を上から見下ろしています。そんな人間を知る由もない蟻たちは大騒動です。けれども、散らばった蟻たちはきっとまた仲間で寄り合って、怯むことなく力強く行列を作って活動することでしょう。散らばって右往左往する蟻たちに、流浪の民の底力を連想しました。 (あひる)
-
蟻が夏の季語。流浪の民といえばヨーロッパのロマの人たちを思う。蟻たちが何かに驚いて列を乱し四散していく様子から連想したのだと思うが、その頃、流浪の民を思わせるような事件があったのだろうか。作者が四散の原因を作ったとしたら、蟻たちに対してごめんと言っているような気もする。 (せいじ)
-
「蟻」は三夏の季語で、働き蟻が列をなしているのではなく、統制が乱れてあちこちにいるところがこの句の妙味ではないでしょうか。流浪の民というと、世界に散らばったユダヤ人(イスラエル人)かロマ人(ジプシー)あたりをイメージします。どちらもナチスの厳しい迫害に遭った人々でした。 (むべ)
-
庭仕事をしていて、思いがけず蟻の巣を壊してしまったのではないでしょうか?突然、家を失った蟻たちは流浪の旅に出かけます。 (豊実)
コスモスの翳より離し陶を干す コメントを書く
(コスモスのかげよりはなしすえをほす)
陶房に庭に手遊びのコスモスが植えられていて花を咲かせているのでしょうね。里山近くの小規模な営みを連想します。そしてコスモスもまた日当たりの良い場所に植えられていて濃い花影を落としていることがわかります。句のモデルとなった陶房の主は、それほど神経質に考えて動作をしているのではなく、ごく普通に陶房から出てきて何気ない所作で陶を干したのだと思う。その様子を離れて見ていた作者がそう感じたのであろう。
- 合評
-
-
作者は作陶をする人でもあったのでしょうか?秋桜がまとまって咲いているそばに、焼成前の器を干していたところ、太陽が動いて花影に入ってしまい、器の位置を動かした……ということでしょうか。秋桜の花影はうっすらしたものでしょうけれど、できるだけ日光をあてたい心遣いが感じられました。 (むべ)
-
コスモスの影ならそれほどのものでも無いと思えますが、陶芸家にはできるだけ日に当てようとする気遣いがあるようです。それに気が付いた作者にも陶芸の心得があるようです。 (素秀)
-
各地にある陶芸の里を思い出します。コスモスの咲く頃は日差しも夏ほどではなく、戸外でもゆっくりと均一に焼成前の器たちが乾いていくのでしょう。コスモスの翳にならないように置いた陶器師の心遣いに、作者は気付いたようです。 (あひる)
-
コスモスが秋の季語。素焼前の天日干しの情景と思われる。天日干しするのはひび割れや爆発防止が目的とのことであるから、よく乾かさなければならない。干し場の傍にコスモスが咲いているが、その翳がかからない場所で、いくつかの陶器が秋の日を均等に受けるように並べられている。「離し」に細心の注意を払っている様子がうかがわれる。 (せいじ)
(きこくのみいろづくかきにせいかあり)
からたちは白くて清楚な花を咲かせますがミカン科の植物です。鋭い刺があるため、外敵からの侵入を防ぐ目的で生垣に使われていましたが刺が嫌われ、また生垣の手入れも大変なことから都会ではまず見なくなりました。秋には熟して黄色くなりますが、果実には種が多く、また酸味と苦味が強いため食用にならないそうです。合評にあるようにこの生家は作者のふるさとの実家なのでしょう。帰省の道の途次から色づいた生家の生垣が遠目に見え始めて、からたちの花が咲く頃の青春時代の思い出などが脳裏に蘇りつつ懐かしんでいるのである。
- 合評
-
-
北原白秋の「からたちの花」の歌を断片的に思い出します。白い白い花、まろいまろい金のたま・・実際に生家を訪ねたのかも知れませんが、秋になって郷愁の中で詠んだのかとも思います。私もめったに行けない故郷の山や生家を思い出します。 (あひる)
-
色づく頃ですから晩秋です。少し寒い日の里帰り、徒歩でしばらく歩くとからたちの色づいた実が見えてくる。あの生垣はうちの家だとの感慨があります。 (素秀)
-
晩秋に久しぶりに再訪した生家。垣根の枳穀の実が熟しているのを見て、作者はあぁ、帰ってきたなぁという感慨を持ったのではないでしょうか。京都・東本願寺の渉成園は枳殻の生垣にちなんで枳殻邸と呼ばれていたそうで、なるほど棘があり防犯に適した木なのかしらと思いました。 (むべ)
-
枳殻の実が秋の季語。これが私の生家なのよと、枳殻の実の金色の生垣に囲まれた自分の生家を自慢しているような口ぶりが面白い。 (せいじ)
-
生家は作者の生家で、久しぶりに帰ってきた生家で子供のころから見てきた垣の枳殻の実に懐かしさを感じているのだろうと思いました。 (豊実)
-
枳殻(きこく)は、枳殻(からたち)の実をさしていうときの読みみたいです。

ふふみたる丁字の匂ふ夏書かな コメントを書く
(ふふみたるちやうじのにほふげがきかな)
含む(ふふむ)の解釈が分かれましたね。デジタル大辞泉によると、【ふくむ】と【ふふむ】とに区分されている。
ふく・む【含む】
-
かんだり、飲みこんだりせず、物を口の中に入れたままの状態を保つ。また、口でくわえる。「水を口に—・む」
-
成分・内容としてうちに包みもつ。また、ある範囲の中に要素として入っている。この温泉は硫黄分を—・んでいる」
-
思いや感情などを心の中におさめてもつ。「非難を—・んだ言い方」
-
事情をよく理解して心にとめておく。「その点を—・んでおいてください」
-
ある感情を表情や態度に表す。ようすを帯びる。「悲しみを—・んだ目つき」
-
中に包み持つような形になる。ふくらむ。
ふふ・む【▽含む】
-
花や葉が芽やつぼみのままである。「卯の花の咲く月立ちぬほととぎす来鳴きとよめよ—・みたりとも」〈万・四〇六六〉
-
㋐口の中に入れて持つ。ふくむ。「(玉ヲ)口に—・みて」〈記・上〉
-
㋑内に包み持つ。「鶏とりの子のごとくして、ほのかにして牙きざしを—・めり」〈神代紀・上〉
蕾の意だとすると季感として夏書と矛盾するので、ここは、せいじ解が的を得ていると思う。従って【ふくむ】の古語的表現だと解釈したい。夏書の句となると私もからきし自身がないが、素秀解を読んで「そうかも…」と納得した。
- 合評
-
-
ふふみたるという言葉が蕾のことか、口に含むことか迷いました。調べるとクローブの開花期は7~9月で、蕾がよく匂うともありましたので、そこからイメージしてみました。姿勢正しく夏書をしてる部屋に、甘くスパイシーな香りが漂ってきます。因みにわが家の瓶入り粉末クローブは、古いせいかいかにも薬効のありそうな香りがしていました。 (あひる)
-
灌頂や勤行前の口内のお清めに乾燥した丁子を刻んだものを口に含み噛んで使用する、ともあるので夏書修行の前に口に含んでいたのかと。香辛料でもありますから香りも良いものなのでしょう。 (素秀)
-
季語「夏書」は夏季にする写経のこととあります。窓を開けた部屋で作者が心鎮めて写経をしていると、チョウジの蕾が放つ香りが漂ってきて……チョウジはわからないのですが、西洋版チョウジのクローブの瓶をあけてみると、何とも言えない甘くてスパイシーな香りです。特徴的で作者ははっとしたのではないでしょうか。 (むべ)
-
夏書が夏の季語。丁字を沈丁花とすると季節が合わないので、ここはクローブのことではないかと思う。クローブは香辛料としてだけでなく生薬としても使われるそうなので、安居の期間中の体調を整えるために、クローブを口に含んで夏書に臨む僧たちがいて、それが夏書の部屋に匂っていたのではないだろうか。あるいは、中国では宮廷の長官が皇帝に拝謁するときにクローブを口に含んで息を清めたというから、そのような清めの意味もあるのだろうか。 (せいじ)
-
丁字(沈丁花)は春の季語で、夏書は夏の季語なのでちょっと迷いましたが、調べると、乾燥した丁字の花蕾は口臭を消すために口に含んで噛む香料として使用されていたようです。修行者が身を清めて夏書に集中していたのでしょう。 (豊実)
曲がりても曲がりても磴葛さわぐ コメントを書く
(まがりてもまがりてもとうくずさわぐ)
真っ直ぐに延々とつづく磴はよくありますが、揚句のそれは直角またはそれに近い角度で曲がっているというのである。そしてあたりは葛が生い茂っていて風に騒いでいるという。ということは、整備された寺領の磴ではなくて寂れた古城址とか古い遺跡ではないかと思う。曲がるたびに息継ぎ休憩しながら何処まで続くのかしらと不安な気持ちになる。この句の何処が良いのかと問われると返事に困るが、情景は具体的に連想できる。昔は人の生活があったのかもしれないがいまはただ寂れた遺構として残っているというものかと思う。
- 合評
-
-
石段はジグザクなのでしょうか、「曲がりても曲がりても」に長くて登るのも一苦労という印象を持ちました。そして生い茂る葛の葉は大きくて、風の抵抗でバサバサと音を立てています。秋の深山に分け入り、ふと自然の中にひとりの人間として置かれていることを感じたかもしれません。 (むべ)
-
あの角を曲がったら行き着くかと思えば、まだまだ続く石段。まだかまだかと思いながら登る。ふと見れば周りに茂った葛の葉が励ましているように、あるいはからかっているように、秋風に騒いでいます。 (あひる)
-
曲がりくねった石段の長い道を歩いている。道の脇に葛の葉がうっそうと茂っており、秋風に葉擦れの音がする。 (豊実)
-
葛が秋の季語。七曲りの石段か石畳の道に葛が生い茂っている。葛の大きな葉が風にひるがえり、葉裏の白を一斉に見せているさまが目に浮かぶ。 (せいじ)
(りゆうとうのなかまはづれのままはしる)
流灯は汐の流れや風に押されんがら帯状に屯して進んでいくが、なぜか一つだけ逆らうように単独行動を起こした。風の孕みぐあいや潮目などの関係でたまたま発生した偶然の出来事だと思うが、作者はその様を「仲間がずれになった」と感じたのである。面倒見の良い作者は生前、俳句はみんなで仲良く楽しむものだといい、グループの和を保つためにいつも目配り、気配りをする人であった。そのような性格ゆえに一灯だけまるで駆け足するかのように離れる様子を見て、いったいどうしたのだろうかと案じたのである。
同じ作者の作品を鑑賞しているとその境涯がわかるだけに先入観で推測してしま いがちだが、仲間はずれの灯に亡きご主人の魂を重ねているのではというような個人事情に踏み込んだ鑑賞は避けるほうがよく、あくまで一作品としての鑑賞を心がけたい。
- 合評
-
-
「流灯」は初秋の季語。ひとつだけ、主流から外れて流れていくものに作者は目を留め、しかも「走る」とありますので、かなりのスピードで作者から離れていく様子が浮かびました。死者の魂にそんなに急いでいかないで…という気持ちがあったのではないでしょうか。 (むべ)
-
仲間外れという言葉は切ないです。仲間外れの人や動物や物・・何故か応援したくなります。まして、亡き人と重ね合わせて見送る流灯、それが一つ離れたまま流れて行ったら・・応援したくなったのではないでしょうか。 (あひる)
-
流灯が秋の季語。灯籠流しの灯籠が、仲間はづれのようにひとつだけ別に流れている。それも走るように速い。海あるいは川の流れの速いところに一つだけつかまってしまったのではないだろうか。自分と重ね合わせるような出来事があったのかもしれない。 (せいじ)
-
仲間はづれという措辞が、亡き夫の一つの灯籠をいつまでも見送っていることをうまく表わしているように思います。 (豊実)
みじろぎもせぬ籠の鵜の瞳かな コメントを書く
(みじろぎもせぬかごのうのほとみかな)
- 合評
-
-
作者は鵜の瞳に何を見たのでしょうか。大人しく籠に控える様に良く躾けられていると見たか、これからの狩りに興奮を抑えきれないと見たのか。やはり肉食の鳥の本能を見たのだと思えます。 (素秀)
-
漁に出る前に籠で待機している鵜かなと思いました。囚われの身になって働かされる哀れさを感じました。 (豊実)
-
「みじろぎもせぬ」という措辞になんだろう?と惹かれました。籠の中の鵜はじっと動かず、作者の視線はさらにズームで鵜の瞳に。何を考えているのか、遠い目をしていたのではないでしょうか。 (むべ)
-
籠の鵜の動きではなく、その瞳に注目した作者の感性に驚きました。鵜の瞳をとおしていろいろなことが見えてきて、少しせつない感じです。鵜は夏の季語ですが、太陽の明るい光よりも、陰や水の冷たさを感じます。 (あひる)
-
鵜が夏の季語。鵜飼に使われるのは海鵜とのこと。昼間、籠の中で身じろぎもせず、生まれた遠い海の方を凝視しているのであろうか。「瞳かな」の詠嘆によって、鵜の悲しさが瞳に凝縮されているように感じる。 (せいじ)
(らくせきのきようふをかたるなつろかな)
冬でも火を入れている炉(夏炉)は、北国などの深雪地域で生活する人たちの風物詩かと思う。むべ解にあるように山小屋では炉というよりストーブというのが一般的なので、山小屋で登山家たちが落石体験を語り合っていると言うより、北国の民宿先である一山家を訪ねての吟行句ではないかと推察される。突然の噴火があったとか、長雨が続いたとかで裏山からの危機一髪の落石体験を宿主が熱く語っているというそんな風景が連想される。もっとも近代俳句ではストーブのようなものも含めて区別なく「炉」で詠まれることもあるが、できれば正しく使い分けたい。
- 合評
-
-
季語「夏炉」の炉とは囲炉裏のようなもの(暖炉ではなさそう)でしょうか?山小屋ではダルマストーブや薪ストーブをよく見かけます。作者はもう少し標高の低い、山麓の湯宿にでも滞在していたのでしょうか。下山した宿泊客と炉の周りに座っての語らい。お湯からあがってほっとしてやっと語れる大事件に、聴いている作者も一緒に驚いています。 (むべ)
-
落石と夏炉を組み合わせると、険しい山の山小屋の情景が浮かんできます。落石の恐怖を体験している人たちが、それでも山へ登り山小屋の炉を囲んでいることが分かります。山の魅力を知っている人たちの心は通じ合っているようです。夏でも、外はしんしんと冷えていることでしょう。 (あひる)
-
落石の恐怖は山男のあるあるなんでしょう。夏山登山の山小屋に集まった者達がそれぞれの体験を自慢がてらに話しています。 (素秀)
-
夏炉が夏の季語。山小屋だろうか、主人と客、あるいは客同士が、自分が経験した夏山の落石体験をさも恐ろしげに語っているのだと思う。少し大げさな物語の匂いがするところがおもしろい。 (せいじ)
-
落石にあった人がその恐怖を山小屋で語っているのでしょう。炉を囲んで話に聞き入る数人の姿が見えます。 (豊実)
置き忘れありし楽譜や牡丹の芽 コメントを書く
(おきわすれありしがくふやぼたんのめ)
大きく季語が離れていて動くのではと感じます。みのる選なら採れたかどうか自信ありません。でも青畝選です(^o^)
鉢物が置いてある屋内の情景であることも否定できませんが、窓辺だとすると他の花でもよくなり、より季語が動くように思うのでここは素直に園に植えられた牡丹の芽だとして鑑賞してみたい。「牡丹の芽」は、ぽかぽかした陽気に蹴爪のように赤く尖っているのを見て春の到来を感じる。ようやく暖かくなり子供たちが大きな音を出して屋外で合奏練習ができるようなった。そのような公園広場を想定してみた。練習が終わって自由時間になり春の園を駆け回っているうちに置き忘れられた楽譜ではないだろうか。その近くではまだ子どもたちの元気な声が聞こえているようにも思える。
- 合評
-
-
音楽教室かと思います。花瓶に牡丹の花と芽が置き忘れらた楽譜と並んでいます。どれどれと楽譜を見る作者の目もあります。 (素秀)
-
牡丹の芽が春の季語。初春のまだ寒い牡丹園で芽を出した牡丹を愛でていると、近くに楽譜が置き忘れられてあるのを見つけた。力がみなぎっている朱色の牡丹の芽から連想して、寒さの中、楽譜を置き忘れるほど懸命に何かの楽器を練習していた子どもを思ったのではないだろうか。 (せいじ)
-
先程まで公園のベンチで誰かが楽器の練習をしていたのでしょう。きっとその人も赤い牡丹の芽を見ていたような気がします。 (豊実)
-
牡丹というと、つい初夏に咲くあでやかな花を思い浮かべますが、その芽はまだ寒い時期に活動を開始するようです。もじゃもじゃと紅くて力強く、これから何者になっていくのだ?という感じです。楽譜を置き忘れた人と牡丹の芽を重ね合わせてみました。 (あひる)
-
「牡丹の芽」は初春の季語。まだ春浅い頃、何かの会合で貸会議室に入室したところ、前の利用者さんが置き忘れた楽譜を見つけた…というストーリーを想像しました。冬を越す力強い赤い芽と、練習を重ねているであろう利用者さんの前を向く気持ちが重なるような気がします。うちの娘もバイオリン譜は常時譜面台に置きっ放しです。 (むべ)
噴水のとまりあらはに裸婦の像 コメントを書く
(ふんすいのとまりあらはにらふのぞう)
序破急という感じに噴水の変幻を自動運転するようにプログラミングされた装置であろう。作者はそれを知らなかったわけではないが、瞬間を捉えるためにこのような表現にしたのだと思う。リズミカルに動いているときは裸婦像の肩から頭あたりまでは見えていて体の部分は隠れていたのだろう。やがて最終章となりひときわ高く上がった噴水によって完全に像が隠れた…と思った瞬間、ピタッと噴水が止まって裸婦像の全身が現れたということかと思う。「あらはに」の措辞は、噴水で隠されていたのが遮るものがなくなったという意味であって、あくまで彫像であるので羞恥というような感覚はないと思う。
- 合評
-
-
夏の季語「噴水」が蒸し暑さを忘れさせてくれます。作者と像との間を隔てていた、噴き上げる水が止まった瞬間現れたのはなんと裸婦。涼しさと驚きが入り混じります。 (むべ)
-
裸婦像を囲うように噴水が出ていたのでしょう。パッと止まると裸婦像が現れた。涼しげではあります。 (素秀)
-
状況が良くわかりますね。客が少ない平日は公園の噴水が止まっていたのかもしれません。渇いた裸婦の像が少し恥ずかしそう? (豊実)
-
噴水の、吹き上がっては落ちる水の動きに気を取られると、無の境地になりそうです。それがぱっと止まると、はっと我に返ります。突然、別の空間に立っているような感覚で、しかもそこには裸婦の像。夏だから、裸婦の像が似合いますね。 (あひる)
-
噴水が夏の季語。噴水が止まったとたん裸婦像があらわになった。水の泡から生まれたビーナスのようである。噴水は夕方の定時に止まるように設定されているのであろうか。噴水も涼しかったが、水の滴る裸婦像も涼しげである。瞬間写生とはこのようにするものかと思った。 (せいじ)
(しきどうのいつきとはるのひおけかな)
机上(きじょう)ということばがあり、一机は「いっき」とよむ。俳句では、一刷(ひとはけ、いっさつ)、一擲(いってき)などとともによく使われる措辞である。正岡子規を偲ぶ(悼む)作品は多いが、この句は春を題材にしていて明るい。実際に子規が使っていたであろう生活ぶりを再現させるために置かれた火桶だと想像してもよいが、そう解釈するとやや季語が動く感じがあるので、私は早春の寒さの残る時期に子規堂の見学者のために火を入れて用意されたものだと解釈したい。せいじ解の通り、子規を愛し俳句を愛する人と人とに通う心のぬくもりを感じさせる。
- 合評
-
-
春火桶という言葉があることを初めて知りました。無駄なものは置かれず、畳の部屋にすっきりと机と火桶が置かれている様子が浮かんできます。机と火桶は子規の生活に欠かせないものだったことでしょう。 (あひる)
-
春火桶が春の季語。松山市にある子規堂は、子規が少年時代に暮らした居宅を復元した記念堂とのこと。子規の部屋には一年中必ず机(子規が実際に使っていたものかもしれない)が一つ置かれているが、訪れたのが早春の頃だったので、俳句の心得のある記念堂の管理者が、火桶を部屋に置いたままにして春火桶にしていたのではないだろうか。初秋の頃なら、簾を掛けっぱなしにしていたかもしれず、そうであれば、「一机と秋の簾かな」と言えそうな気もする。勝手な想像だが。 (せいじ)
-
子規堂をまだ訪れたことがありませんが、愛媛県松山市の正宗寺境内にある木造平屋建ての記念堂とのこと。机も火桶もかつて少年・子規が使っていたものでしょうか。まだ春浅い光の中で、偉大な俳人子規の育った背景に想いを馳せて。 (むべ)
-
松山にある子規堂は一度行きたいと思いながらかなわずにいます。一机はいっきと読んだら良いのでしょうか。机と火桶に子規を偲んだようです。 (素秀)
-
「一机と春の火桶」という並列の措辞は俳句では少ないと思うのですが、この場合、子規が火桶で手をあぶりながら机に向かって座っている姿が強く目に浮かびます。 (豊実)
(なふだのみやくさうえんのさむかりし)
草には、一年草と二年草、多年草と球根とがあるが、薬草の多くは冬は枯れて地上には何もなくなる物が多い。揚句の薬草園、作者は芽の出る春や実のなる秋にも訪ねているのであろう。冬になって名札だけ残して無一物になった姿に思わず寒さを実感したのであるが、同時にむべ解にあるような命の尊厳のようなものをも感じさせている。俳句は基本的に対象物の旬を詠むことが多いが、あひる解の通り謙虚に対象物と心を通わせることによってどのような情景からでも句は授かるのである。
- 合評
-
-
冬なので薬草が生えていないのか?それとも手入れが行き届かず枯れてしまったのか?いずれにしても、名札だけというのが寒さをより強く感じさせます。 (豊実)
-
冬の薬草園にはほとんど草が生えておらず、土に薬草名の札が立っているだけ。寒さがより一層感じられます。しかし、土の下では新たに薬効のある球根が眠っているのかもしれません。 (むべ)
-
寒い時期、どうして薬草園へ出かけたのでしょうか。 目的は他にあって、薬草園はついでだったのかも知れません。案の定、薬草は繁っておらず名札のみだったようです。想定内でもちょっとがっかりです。それでも、そんなところからも俳句は生まれ出るのだと感心しました。 (あひる)
-
薬草園も季節外れ、名札は立っていても肝心の植物は芽も出ていません。いやぁ、寒い寒い。 (素秀)
-
冬の薬草園あるいはハーブ園では、多年草の植物はまだ地上に芽を出していないので、名札だけがその区画に突き刺さっているのであろう。園の実際の寒さ、名札だけで何もない閑散とした区画の寒さに加え、トリカブトのような有毒植物などは名札を見ただけでも寒さを感じたかもしれない。 (せいじ)
形見なるコート着てゐる礼者かな コメントを書く
(かたみなるコートきてゐるれいじやかな)
昭和59年の作である。いまならメンズ、レディスの区別なく「コート」と呼ぶが、この句の詠まれた時代のコートと云えば羽織のような婦人物のコートを連想したい。作者を訪ねて新年の挨拶にきたのは、生前親しくしていた友人のお嬢さんではないかと思う。見慣れたお母さんの形見のコートを羽織って現れた娘さんの姿に故人の面影を見ているようで嬉しいような懐かしいような気分を味わったのである。しばらくは故人を偲んで話が弾んだことであろう。
- 合評
-
-
新年に作者を訪ねて来た知人。亡くなられたご主人と親しい間柄の方だったのではと想像します。ご主人が愛用していたコートを大切に着てくれていることがうれしく、このコートを着こなしていたご主人の姿が鮮やかによみがえります。追憶とともに、切なさやさみしさも伝わってきます。 (むべ)
-
年賀の客ですが親族ではないような気もします。挨拶のあとに徒然と話を聞くと形見のコートを着てきたと。コートの持ち主は作者とより親しい間柄だったのかも知れません。 (素秀)
-
この礼者は父を亡くした若者ではないでしょうか?父の仕事を受け継いで、取引先に年始の挨拶回りをしているのでは。 (豊実)
-
礼者とは正月、年賀に回り歩く人のことだそうです。遠い昔、元旦に黒いコートを着て祖父のもとへお年賀に来た人の姿を思い出しました。形見なるコートは、言葉よりも深い気持ちを表したことでしょう。 (あひる)
-
礼者が新年の季語。ご主人の喪が開けて何年かして、ご主人の形見のコートをもらってもらった人が、それを着て年賀に来てくださった。それを見て、ご主人のなつかしさが甦るとともに、その方のご主人に対する敬意の表し方と自分に対する思い遣りに感謝し嬉しく思ったのだと思う。 (せいじ)
(ひつじたのまんなかなりしむじんえき)
実際は穭田の中にぽつんと無人駅だけがあるというわけではないだろうから、作者が遠景でそのように見える位置にいたということであろう。農家の集落は少し離れていて畦道のようなところを通ってアプローチするのだと思う。バスとも電車とも説明はしていないが、バスなら幅のある道路が必要なので目立つが電車の鉄路なら遠目には畦道に紛れて見えにくい…とそんな風景かと睨んでみた。一日に数本というダイヤかもしれないけれど農業を営みつつ生活する人たちにとっては大切なライフラインなのである。
さてこの句もまた「穭田」が季語として動かないかどうかを判定しなければならないが難しい。青田や稔り田であればそこに働く人もいたであろうが、刈り取りも終えやがて穭田になったいまは人影もない、過疎の地なので穭田で遊ぶ子供の姿も見えないのであろう。穭田が牧歌的な風景を醸しているとは思うが、素秀解、あひる解のとおり、作者はポツンと存在する無人駅の「寂しさ」を表現したかったのかも知れない。
- 合評
-
-
穭田は晩秋の季語。稲刈りの終わった田は少し青いひこばえも。小さな無人駅が広々とした田の風景のアクセント。もしかしたら単線かもしれませんが、駅舎だけでなく線路も見えます。自然のサイクルの中をつっきってゆく人の営みを感じました。 (むべ)
-
穭田が秋の季語。穭田の真ん中に無人駅があった。小さな無人駅が、いまや、稲刈りも終って一息ついた人っ子一人いない田園風景の要となっている。 (せいじ)
-
無人駅は人が居ないという、ただそれだけで淋しいです。その淋しさに追い打ちをかけるように広がる穭田、寒々とした風景です。でも、この田んぼの稲を刈り取った農家の方が、この辺りに住んでおられ、暖かい家族の生活も営まれているに違いありません。淋しさを強調されて、私の心は暖かいものを探してしまいました。 (あひる)
-
こちらは無人駅ばかりですから、そのまんまの風景はあちこちにあります。青田や稔り田と違ってなかなか侘しい景です。 (素秀)
-
東北地方のような延々と広がる穭田の風景の中にポツンと無人駅がある。田んぼもしばらくお休みで、なおさら無人駅には誰もいない。 (豊実)
エプロンのままグラス持つ聖夜かな コメントを書く
(エプロンのままグラスもつせいやかな)
紫峡師の作品で私の好きな句に、「婢(はしため)の皿を洗へば聖夜果つ」があります。「聖夜」の俳句としてとてもストーリーのある作品です。さて揚句の場合は、親しい仲間を集めての気さくなパーティーで作者はホストとしてエプロン姿のまま同席しているのであることがわかります。実際のクリスチャンホームでは、パーティーのようなお祝いのしかたはしないのですが、クリスマスは、信仰とか宗教というような理屈を離れてこの時期の楽しいイベントとして生活に定着しました。別に聖夜でなくても…といいだすと季語が動いてしまいますが、そのへんはおおらかに受け止めましょう。
- 合評
-
-
クリスマス・パーティーのホストとして慌ただしく楽しい夜の風景。キッチンにいたところ呼ばれてワインかビールの入ったグラスを手に、さぁ乾杯! (むべ)
-
聖夜が無ければキッチンドランカーですが、主婦の忙しいクリスマスがエプロンに上手く表れています。乾杯は料理の合間にというところでしょうか。 (素秀)
-
聖夜が冬の季語。いろいろな想像ができるが、作者のこれまでの俳句から考えて、まことに勝手ながら、ご主人を亡くしてひとりで迎えた聖夜を想像した。クリスマスなので、ひとりではあるが、いつもよりは少し豪華な夕食にした。ふたりならエプロンを外すことぐらいはしただろうが、それもせずにひとりワインを飲む。さびしい。クリスチャンでなければ特別な日でも何でもない夜である。しかし、聖夜という特別な夜は、そんな彼女をも優しく包み込んで慰めてくれる。そんな「聖夜かな」である。 (せいじ)
-
エプロンという言葉がこの句をいっぺんに楽しくしていると思いました。エプロンの白、クリスマスカラーの赤や緑、グラスの音やみんなの声まで聞こえるようです。「カンパーイ!」の頃には涼しい顔をしてお客さんのように一緒に座っていたいのですが、いつだってそうはいきません。 (あひる)
-
食事の準備をしてる裏方のエプロンをした彼女立ちに、クリスマスパーテイが盛り上がったところで、乾杯の音頭を取る前に声が掛り、一緒にエプロンをしたまま乾杯をした。 (宏虎)
-
クリスマスパーティーはとても楽しいですが、食事を準備する人はとても忙しい。料理をしながら、パーティーのおしゃべりにも参加している情景かと思います。 (豊実)
(ひつじたにのういんじまをおきにけり)
神戸に引っ越す前は大阪府高槻市の山裾になる古い集落の近くに住んでいました。そこにも広々とした稲田の真ん中に「能因法師の塚」というのがあり、こんもりとした木立が子どもたちの秘密基地のようになっていたのを記憶している。この句の能因島は奥の細道で有名な象潟のそれであろう。ちょっと意地悪な見方をしてみると、なぜ「穭田」という季語なのかという点である。芭蕉の奥の細道に思いを馳せて詠まれたであろうことは分かるが、芭蕉が詠んでいる作品はこの時期ではない。青田や豊秋の季語でも点景にはなると思うから、「季語動く」ことになる。たまたま吟行したときがそうだったからとうがった見方をするのも作者に失礼だと一寸悩んだ。
ふと気づいたのは、「置きにけり」という表現である。青田や稔り田の場合を想像してみると「置きにけり」ではなくて「浮かびけり」になるかなぁ…と。検索で見つけた写真を見ても確かに穭田にあるそれは陸続きになった感じで、広々と展けた風景の中にまさに「置きにけり」の感覚であったであろうと納得した。
- 合評
-
-
島だったのに今では陸続きとなった能因島という名の小山、回りでは稲作が行われているようです。地震という自然の営みは人にとって大災害だったと思いますが、人は立ち直り、立ち上がり、逞しく人の営み(稲作)を続けているのだと思いました。 (あひる)
-
象潟の田園風景を見て、昔は海だと言われてもなかなか想像し難いでしょう。ポツポツと残る樹木の小山を見て、作者は当時の風景を芭蕉の背中越しに見ているのかも知れません。 (素秀)
-
穭田が秋の季語。芭蕉も訪れたという象潟は、地震で地盤が隆起して消失し、その中にあった能因島も今は何の変哲もない小山のようなものだという。一面の穭田に囲まれた小山を能因島に見立てて往時を偲んだのではないかと思うがどうだろうか。 (せいじ)
(かこうへきいつそうもなきさむさかな)
「一草もなき」から休火山のカルデラではなく、なお活動して硫黄臭を放ち草木の生息を許さない活火山の火口壁であろうことがわかる。みなさんの合評にあるように阿蘇のそれが連想できる。この句の季語である「寒さ」は体感的な意味も含むと思うが、どちらかと云えば感覚というか心象的な意味が強いと思う。いわゆる「怖いもの見たさ」のそれであろう。
- 合評
-
-
中学の修学旅行が九州だった事を思い出します。初夏だったので気持ち良さしか感じませんでしたが、ゴツゴツとした火山岩の火口は殺伐とした雰囲気でした。冬ともなればいっそう寒さもつのる事でしょう。 (素秀)
-
阿蘇は実家から日帰りドライブで行ける距離でした。一草もない赤茶けた火口に、足を滑らせそうなスリルがありました。夏は小さなお土産屋さんも出ていましたが、冬は行ったことがありません。冷たい風が吹いていたら、風景はガラリと違ったことでしょう。 (あひる)
-
寒さが冬の季語。一草もないということは阿蘇中岳のような活火山の火口壁であると思われる。寒風の中、実感としての寒さを感じたのも事実であろうが、それを介して、一草もなき寒さ、すなわち、生命というものが全く存在しない世界の寒々しさをより強く感じたのではないだろうか。 (せいじ)
-
私も阿蘇山へツワーで登ったとき、火口を覗きましたが辺り一面、溶岩で草も生えておりませず、コンクリートの避難小屋が有ったことを覚えております。風を避ける物がないので寒かったのでしょう。 (宏虎)
-
阿蘇山の火口壁を思い浮かべました。噴煙と火口の荒々しい姿、そこに、風が吹けば寒くてたまんらんでしょう。 (豊実)
(たちまちにあゆざふすゐのなべはから)
魚や、野菜、果物などは養殖や温室栽培、はたまたバイオテクノロジーによって季節感が曖昧になる傾向があるが、俳句では自然の中で最も美味である「旬」の時期を季語とすることが前提であり約束であるので脱線した解釈は避けたい。ゆえに「鮎雑炊」は鮎の旬である夏の風物詩として鑑賞するべきであろう。鮎の塩焼きを雑炊に加えただけの簡単なものであるが、夏は冷たいものをという常識とは反対に塩あじの効いた鮎雑炊をフーフーと息を吹き付けながらいただくところに風情を感じる。「鍋は空ら」の素地から、家族か親しい仲間で賑やかに鍋を囲んでいる様子も見えてくる。加代子さんのことだから俳人仲間との吟旅の鮎宿かもしれない。
- 合評
-
-
たちまちという言葉にスピード感があり、たちまち句に引き込まれました。鮎雑炊の描写は無くて空っぽの鍋が! でも、どんなに美味しかったのか・・・食べてみたい・・と思いました。 (あひる)
-
この俳句の季節はいつだろうか。雑炊なら冬だが、ネットには、岐阜に鮎雑炊という郷土料理があり、夏の風物詩ともある。前句の「揖斐の秋」からすれば冬かもしれない。いずれにしても、美味しくて鍋がすぐに空らになった。落鮎なら少し大きめだから食べ応えがあったに違いない。 (せいじ)
-
若い食欲旺な一団が鮎雑炊というご馳走を、たちまちに鍋を空っぽにした。 (宏虎)
-
鮎雑炊とはご馳走ですね。おいしいのはもちろんですが、鮎はそんなに大きな魚ではないので、あっというまに平らげてしまったのではないでしょうか? (豊実)
(ゆみをはるやなまたやなやいびのあき)
揖斐川は鮎簗で有名ですね。揖斐の秋とあるのでせいじ解のとおり下り梁です。実物の簗を見たことがなくネット検索で揖斐の簗の写真を見る限りでは「弓を張る」がいまいちわかりにくいです。水量が多くて簗が撓んでいるように見えたのをそのように形容したのかなとも思うのですが自信ありません。ちょと変わった形の簗もありましたが「弓を張る」感じではありませんでした。「簗また簗や」と畳み掛けた表現がうまいと思います。川の全幅に渡って仕掛けたものではなくて人工的に魚道を工夫して岸近くに作られていて、それがあちこちにたくさんあって名物どころの下り簗の旬を実感させています。
- 合評
-
-
揖斐川の光景のよく見える句です。跳ねる落ち鮎、川の流れ、簗の並ぶ様。 (素秀)
-
簗は一つではないようです。簗また簗やと繰り返しているところに、わくわく感があります。揖斐川の秋も、だんだんと深まって、あっちでもこっちでも鮎取りに夢中になっている人が居たり、炭火で串焼きが始まっていたり・・。 (あひる)
-
秋の簗が秋の季語。秋の簗は、産卵後、川を下る落鮎などの魚を取るための簗とのこと。揖斐川の上流で弓を張ったようにして連なる下り簗を見たのであろう。堰の水の光や山の紅葉も見えるようだ。 (せいじ)
火だるまの苧殻の一つ遠ころげ コメントを書く
(ひだるまのをがらのひとつとほころげ)
ネット検索すると、「迎え火と送り火は一般的に「おがら」呼ばれる皮を剥いだ麻の茎を使う。おがらはお盆前になると花屋さん、スーパーで買うことができる。」とありますす。焙烙皿+焚き木セットといって割り箸サイズのものが流通しているが、揚句の苧殻は「遠ころげ」なので縁側や庭先のような狭い場所ではなくて浜辺とか川原で焚いている少し大ぶりのものではないだろうか。NHK の朝ドラ「おかえりモネ」のシーンでは漁師町なので浜辺で焚いていた。燃え盛っている苧殻に突風のような浜風が吹き付けて飛んでいった…と、そのようなことではないかと思う。一つだけが転がっていったという写生になにか霊的なものの働きを連想するか否かは鑑賞者に委ねられている。
- 合評
-
同様の句に「わが前へ前へ苧殻の火のころぶ」がありましたね。また、「遠ころげするはするまま豌豆むく」も思い出しました。私は苧殻のことをよく知りませんが、火の玉が転がっていって、危なくないんでしょうか? (豊実)
-
芋がらかと思ったら、送り火などに用いるという苧殻(をがら)でした。火だるま、遠ころげという言葉遣いにユーモアを感じ、「おやおや、ころげちゃったのね。」と楽しく想像しました。 (あひる)
-
芋殻が秋の季語。門火に焚いていた苧殻の一つが真っ赤に燃え盛ったまま遠くに転げて行ってしまいましたよ。「火だるま」「遠ころげ」の表現が的確かつ効率的であると思った。 (せいじ)
-
送り火でしょうか。燃え上がった苧殻が風に吹かれて転げていく。燃え尽きた苧殻はいかにもあちらに帰った祖霊のように見えたのかも知れません。 (素秀)
(とざんぐちはらぶともちといふをうる)
登山の句は得てして説明っぽくなるので類想が生まれやすいが、揚句はちょっと見つけた発見を上手に詠み込んで類想のない新しさがある。
普通のサイズの大福より少し大きめに作られているような気がする。ここで腹ごしらえをするひともいるだろうし、登頂後の空腹を満たすために買っていくヒトもいるだろう。本格的な登山ではなく普通に地域のひとたちに愛されている山岳信仰の山の雰囲気を感じる。そして腹太餅は登山口小屋の名物なのであろう。
- 合評
-
-
腹太餅で調べると大福餅とでます。登山口で売っているのは腹ごしらえをしてから山に登るためでしょうか。作者も珍しいものがあるものだと食べたようです。 (素秀)
-
登山口が夏の季語。腹太餅とは丸っこい大福餅のようなものであろうが、それはともかく、作者はむしろこのお餅の「腹太」という語感に反応したのではないだろうか。山に登るにあたり如何に腹持ちがしそうである。 (せいじ)
-
腹太餅というものを作者も知らなかったようですね。塩味のあんが入った餅のようですが、登山客目当ての商売ですね。山頂で食べた腹太餅はさぞかしおいしかったことでしょう。 (豊実)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
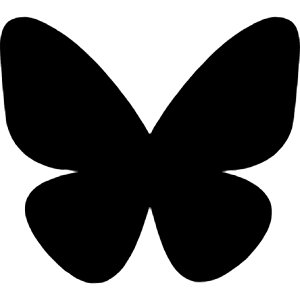 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()