2021年1月
目次
(がじようくるしたしきともらみなははに)
季語は「賀状」、「みな母に」の措辞は、作者はまだ未婚であることを暗示しています。この句の詠まれた昭和38年代は、まだ現代のように賀状に家族写真を印刷するというような文化は普及していなかったと思うので、差出人に家族名が書いてあったり、本文に報告が記されてあったんでしょう。親友たちの幸せそうな消息に嬉しさもあり、ちょと羨ましいなというような複雑な心境が汲み取れます。賀状を見て初めて知るということは、日々の生活で親しくしている友人ではなく、遠く故郷のおさな馴染のような雰囲気もある。懐かしさ、羨ましさ、寂しさなどを直喩せず客観写生によってそれらを連想させているテクニックを学びたい。
- 合評
-
-
親しかった友人らがみな母になってしまっていることを賀状を見ながらつくづく考えているのだと思います。中には第 2 子、第 3 子の誕生を賀状で知ることもあり、もし作者が独身なら、寂しい瞬間だと思います。(なおこ)
-
作者が独身であったか、既婚だが子はまだだったのか判りませんが、出遅れてしまった感が現れています。祝う気持ちはもちろんあるのでしょう。 (素秀)
-
ご自身はその時未婚だったのだろうと思います。自分より先に母親になっていく多くの親友のことを年賀状を見ながらに少し羨ましく思ったのかもしれません。 (豊実)
-
今日からの作品は昭和38年になります。
(しはぶきをぶつつけながらてがみよむ)
冬は大気が乾燥するので寒さも加って喉をいためやすい。また風邪をひいたりしても咳が出る。咳が出そうになったとき飛散を防ぐために普通は手のひらで口を覆いますね。ところがこの句では届いた手紙を読もうと両手で広げていたときに咳が出そうになり、思わず持った手紙を口にあててしまいます。咳がおさまって手紙の続きを読む、また咳き込むというような繰り返しの所作を句に仕立てたのではないかと思います。鑑賞という意味では意外と難しい句ですね。手紙に書かれていた内容が咳を誘発したとすると難解になるので、そこまで深読みせず普通に連想してみました。
- 合評
-
-
どんな手紙なのか想像するしかありませんが咳をぶっつけるとは乱暴です。速く読みたくてよりは大事ではない手紙を想像します。 (うつぎ)
-
ぶつつけながらという措辞に、この咳はただの風邪ではなく重い病気であると感じました。 (豊実)
-
咳は止まらないけれども手紙読む事は止められないようです。よほど待っていたのでしょう。 (素秀)
干からびし唇あけて風邪ぐすり コメントを書く
(ひからびしくちびるあけてかぜぐすり)
ちょっと調べてみました。唇は粘膜で皮膚とは違って粘膜栓によって常に潤いが保たれているそうです。体調を崩したりするとこの粘膜栓がうまく働かなくなり唇への供給に支障が出る。風邪をひく前に、必ず唇が乾燥するので唇の乾燥が風邪のサインだそうです。唇が乾燥すると薬を呑むために大きな口をあけるのも辛いものです。作者の油断したことを悔いる思いや、情けない気分が伝わってきます。
- 合評
-
-
風邪を引いて大分弱ってますね。乾いた空気で唇が乾き、口を開けるのも辛そうな感じが伝わります。 (豊実)
-
熱が出て口が乾いてしまっているようです。かさかさの唇を開けるのも辛そうです。 (素秀)
(かぶくさきわがやとなりぬたびづかれ)
「黴」は梅雨時の季語である。この句が詠まれたのは加代子さんがまだ独身時代で一泊吟旅をよくしていた頃だと思う。我が家に帰って旅の荷を解き、ひとときほっとした気分で楽しかった旅の余韻に浸る。ふと我に返るとなんとなく部屋の黴臭さが鼻につく。梅雨時はわずか数日締め切っていただけでも部屋中に黴臭が漂う。慌てて窓を開け外気を入れながら明日からはまた現実の生活に戻るのかと思うと旅の疲れがどっと出てくるのである。旅に出ている間に部屋が黴臭くなるということは一人住まいであることをも暗示している。
- 合評
-
-
旅の帰路、ふと日常の生活の大変さを思いだすことが多々あり気分も落ち込む。黴臭さの家は疲れている我が身もその一つとなるのか? (そうけい)
-
吟行旅なのか、しばらく家を空けていただけなのに帰って来るとなにやらカビ臭い。美しいものや珍しいものを見た後だけに尚更日常の生活の匂いが気になるのかも知れません。 (素秀)
-
一人暮らしなんでしょうか?長旅から自宅に戻ると、なんとなく黴臭く、旅の心が落ち着かない様子を感じました。 (豊実)
夜桜やにはかに減りし子供連れ コメントを書く
(よざくらやにはかにへりしこどもづれ)
新人社員に匿名して先に花筵の場所を確保させておき、夙川堤でアフターファイブの花見の宴をしたころをふと思い出した。まだ薄暮の頃に現地到着、用意した花見弁当で軽く腹ごしらえをしているうちに夕帳が包みはじめる。提灯に灯が点りいよいよこれから宴が始まるなと期待しながらふと辺りを見まわすと子供連れの家族の姿がすっかり減っていることに気づいたのである。客観写生のなかに作者のそうした少主観のこころの動きがにじみ出ている。うつぎ解、素秀解、豊実解ともどもそれぞれが実体験した思い出のシーンが具体的に再現されるのである。
- 合評
-
-
子供連れが俄に減ったとは只時間のことではなく夜桜の余韻に浸る呑み会だっり食事会だったり大人の時間を暗に匂わせている。 (うつぎ)
-
花冷えの頃なら夜桜も少し寒いかもわかりません。子連れの花見客は早々に帰ってしまい残っているのはこれから飲み始める者たちばかりです。 (素秀)
-
これからは大人の時間ということですね。夜桜の元、恋を語るのでしょうか? (豊実)
(あしくびにすなのおもさやかいをほる)
所有している、歳時記、季寄をすべて調べたが「貝掘り」を季語として記しているものはなかった。潮干狩の傍題季語としても見当たらず、当然ながら例句にもない。それでも一読して潮干狩の景だとわかるから不思議な作品である。「貝を掘る」を「潮干狩」に置き換えてみるとわかるが、「貝を掘る」のほうがより具体的に連想できる。潮の引いた後の干潟の砂は結構しまっているので足型はつくが足首まで埋まることはない。うつぎ解にあるように夢中で貝を掘っていて足が砂に埋まったのである。天国の加代子さんには失礼だが、原句では「潮干狩」であったのを青畝師が「貝を掘る」に添削されたのではと思うほど「貝を掘る」の措辞は素晴らしい。言葉の重さを実感させられる。
- 合評
-
-
手前に掻き出すように掘るので砂で足首が埋まってしまったと取りました。意識して掘ればいいのですが夢中になっていたのでしょうね。 (うつぎ)
-
掘った砂が自分の足を埋めてしまったのかなと思いました。夢中で掘り進んで足首まで埋まった砂の重さで気が付いたということでしょうか。 (素秀)
-
潮干狩りに熱中しすぎて、気がついたら、動けなくなるぐらい足首まで砂に埋もれてしまったということかなと思いました。 (豊実)
-
潮干狩りの句だと思います。裸足になって遠浅の砂浜に降り立ち、足首まで砂に浸かりながら貝を掘っている。動こうとしたらなかなか足が抜けない。「重さや」によって砂の重さがひしひしと感じられます。春の浜辺の明るさや、素足に心地よい水の暖かさも同時に感じました。 (せいじ)
禰宜立ちて年守る燭替へにけり コメントを書く
(ねぎたちてとしまもるしよくかへにけり)
季語の「年守る」は素秀解の通り。従ってとある神社で除夜祭が行われているのである。禰宜は神職の一つで宮司を補佐する者の職称で、この句の場合は宮司が粛々と祝詞を唱えているなか、控えて座していた禰宜が静かに立って短くなった燭を替えたのであろう。詣でる人は大勢なので特別に席は設けていないと思われる。作者は除夜詣での人垣の中に立ち神殿で行われている神事の様子を遥拝しているのであろう。主観を一切とりさった客観写生の句であるが、一年の穢れを払って良い一年を迎えるという厳かな神事の進捗を眺めながら作者自身の気持ちも同化しているのである。
- 合評
-
-
年明けの瞬間に蝋燭の火を絶やさないように、短くなった蝋燭を新しいものに替えて、これが今年最後の蝋燭であると思うと年明けに向けて気持ちが高まる。 (豊実)
-
大晦日の夜、神社に参籠して元旦を迎えようとしている人たち。ひとりの人もいれば、家族で来ている人たちもいる。作者もその中の一人なのでしょう。禰宜がすっと座を立ってさりげなく蝋燭を替えてくれた。ともに年を守りながらも奉仕に徹する禰宜の姿が凛々しく感じられました。 (せいじ)
-
年守る、大晦日に寝ずに年明けを迎えること。短くなった蝋燭を禰宜が静かに替えている。神社で年越しを迎えているのでしょうね。厳かでしんと張りつめた空気です。 (素秀)
ほとばしる咳あちこちや楽終る コメントを書く
(ほとばしるせきあちこちやがくおはる)
「咳」は冬の季語。冬は大気が乾燥することが多く寒さも加わって喉をいためやすく咳がでる。当時の劇場は温湿度を管理した現代の空調とは違い暖房だけなのでより空気が乾燥するのである。句意は素秀解、うつぎ解のとおりである。ひとりが咳くとつぎつぎと連鎖してあちこちで咳する人が増えたのである。「ほとばしる」は、勢いよく飛び散ること、うつぎ解にあるようにまさに我慢の尾が切れた感が強い。
- 合評
-
-
コンサートの観客は咳であろうと物音は許されない。演奏が終わると同時に我慢の尾が切れあちこちで咳をしている人がいる。それを見逃さなかった作者。(うつぎ)
-
演奏が終わったとたん、あちこちで咳が聞こえてくる。皆我慢していたのですね。それが堰を切ったように、まさしくほとばしって出ているのだと思います。 (素秀)
-
演奏会の幕間の咳ですね。今のコロナ禍では、それもはばかられますが・・・。 (豊実)
とぢ糸のゑくぼゑくぼや干布団 コメントを書く
(とぢいとのゑくぼゑくぼやほしぶとん)
「布団」は一年中寝具として用いているが、もともと寒さを防ぐもので寒い時が寒い時が最も感じが深いので冬の季題となっている。夏の布団は「夏布団」といって区別する。うつぎ解の通り「ゑくぼゑくぼ」のリフレインによって冬日を吸ってぱんぱんに膨らんだ布団の様子を具象化しているところがこの句の手柄である。布団を干すに足る温かい冬日の差すお天気であることも連想したい。
- 合評
-
-
ゑくぼの可愛い比喩に感心しました。リフレインによってよく膨れた布団のゑくぼの数や作者の喜びが伝わってきます。 (うつぎ)
-
干された布団がほっこり膨らんで、とぢ糸がゑくぼに見える。ゑくぼゑくぼというのが可愛いです。 (なおこ)
-
布団づくりの仕上げはとじ糸で決まる。パンパンになったところへ表から裏へ針が決まりとじれば小気味よく凹み(えくぼ)ができる。その布団、せんべい布団にもなるが干布団となればほぼ新品レベル、えくぼ、えくぼとその中にはやく横になりたい気分になる。(そうけい)
-
布団を干した、綿を固定しているとぢ糸に目線が行くのは女性らしいと言えるかと思います。(素秀)
-
ゑくぼのリフレインが可愛らしく、布団のふっくら感がよくわかります。(豊実)
滴りやうけとる桶にはねかへり コメントを書く
(したたりやうけとるおけにはねかえり)
「滴り」は崖や巌のあいだから自然ににじみでる水が、苔などを伝わったりして滴り落ちる点滴のことで清涼の感が深い。清水のように多量には出ず間欠的に雫となって落ちるのである。力を蓄えるかのようにゆっくりと雫の玉が大きくなりやがて力がみなぎり引力に負けて落ちる。ある程度の高さから落ちるのであろう落ちた時に桶の底に刎ねるのである。句意については素秀解が的を得ていると思う。うつぎ解にもあるように「うけとる」の措辞は出そうで出ない言葉と思う。滴りと桶が阿吽にキャッチボールをしているかような間を感じさせる。
- 合評
-
-
岩肌から沁み落ちる水を受けるために桶が置いてある。旅人が飲むも良し、涼をとるために顔を洗うのも良しでしょう。桶に跳ねる水の音はただただ涼し気です。(素秀)
-
情景の切り取りや簡潔な表現に呆然とする。「滴り」で思い出したのは洞窟の涼しさだ。桶となると・・・そのはねかへりの涼しさに浸っていたくなる。(そうけい)
-
桶に跳ね返る音や光が感じられいかにも涼しげです。何処かは判らないが「うけとる」の措辞が自然の恵みに対する有り難さや美味しい水を想像させます。(うつぎ)
-
命を支える水。一滴の跳ね返る水を見て、山の自然に感謝する気持ちになります。(豊実)
-
光景がいろいろ感じ取れて深い一句ですね。例えば庭に水を撒くためにある庭先の蛇口でもいいですし、台所とも読めます。または、寺院にある手水のような場所でもいいかもしれません。「滴り」の季語の深さや広さを感じました。その滴りをうけとめる桶。「はねかへり」の措辞がこの句に生き生きとした動きを表しています。私は、洗い物などを終えた、夜の厨の景を浮かべました。(更紗)
-
夏の清涼感に溢れた一句です。跳ね返るとありますから、岩から浸み出した水滴を桶に受け取り始めた瞬間を描写していると思われます。生活のために水を汲んでいるのか、お茶を楽しむためなのか、その目的は分かりませんが、うけとるという言葉によって、私たちの生活が受け取ることによって成り立っていること、私たちはただ恵みを受け取るだけの存在であることをあらためて思わせられました。 (せいじ)
三日月の消えたる爪や春の風邪 コメントを書く
(みかづきのきえたるつめやはるのかぜ)
男性にはピンときにくい句ですね。私もネットで調べて爪の根元にある白い三日月状の部分を爪半月と呼ぶことを知りました。意味はせいじ解の通り。女性は美容のためにも爪の手入れをよくするので、作者は自身の健康管理のモニター代わりにいつも爪半月をチェックする習慣があったのかもしれない。何となく今日は気だるく春風邪気味だなと思って爪を見たら三日月が消えていることに気づき、春風邪をひいたのは体調管理を油断していたせいだったのかなと納得しているのである。
揚句を一読したとき、季語の「春の風邪」が動くのではないかと感じた。でも「風邪に臥す」に置き換えてみると素秀解の通り深刻すぎて爪どころではなくなるし、「春憂ふ」にしてみると爪半月との関連がやや離れすぎる。「春の風邪」には春愁の雰囲気も込められているのでやはり動かない季語だと納得させられた。
- 合評
-
-
爪の付け根にある半月状の白い部分が春の風邪を引いて消えてしまったのだと思います。一度風邪を引いただけでは、爪の白い部分が急に減るものではないと思いました。冬の間に何度か風邪を引き、だんだんと「三日月」が減っていったのではないかと思います。先日の合評に取り上げられていましたが、冬は指先の皹や痛みに焦点が当たっていました。(順に合評をしているので思うことかもしれませんが)皹は回復したものの、改めて見ると「三日月」が消えた(体力が落ちてしまった)、という感じかと思いました。(なおこ)
-
女性らしい目線のお句ですね。「三日月の消えたる爪」の措辞で、爪の根元にある爪半月(甘皮に覆われていない白い所)に焦点を絞ってます。また、春の風邪の季語も効いてます。普段、爪をみがいたり、甘皮の処理などお手入れもしていたのではないでしょうか?風邪を引いてしまったことで、甘皮のお手入れもできておらず、三日月が消えてしまった、、しかし、季語が春の風邪ですから、この微熱ほどの風邪心地さえ楽しんでおられるような感じにもとれました。(更紗)
-
爪の三日月は根元の白い部分かと。病気になったり新陳代謝が悪くなったりすると消えるとも言われています。春の風邪ですから冬の風邪ほど深刻な症状は出ていない雰囲気です。ふと爪を見ると白い部分が無いなあ、と気が付いてもそれほど心配していないように感じられます。(素秀)
-
この三日月は、おそらく、爪の根元にある白い部分のことでしょう。健康を害すると白い部分が減ると言いますから。爪の三日月が消えてしまった。いつ治るのだろう、春の風邪は厄介だなあというため息が聞こえて来るようです。(せいじ)
-
春の風邪が主役ですね。三日月の尖った端(爪)に雲がかかるどんよりとした曇りの日に風邪を引いてしまったのでしょう。(豊実)
(しやしんやにきやくなしさきゆうたださむく)
みなさんの推察どおり鳥取砂丘での写生句ではないかと思う。日本海から吹き付ける冬の季節風に耐えられないほどの寒さを覚えているのであろう。そうけい解にあるように「ただ寒く」という措辞が効果的で、強風で砂丘を駆け巡るように砂塵が舞いあがる様子、荒々しい冬波が沖からうち畳むように寄せてくる様子などを連想させている。美しい起伏や風紋などを詠もうと張り切って吟行に来たけれど、あまりの寒さに全く集中できず、ただただお手上げ状態であると詠んでいるのである。「写真屋に客なし」によって、お天気の良い日なら多くの観光客で賑わう名所であることをも連想させている。
- 合評
-
-
風や砂が飛び交う中の砂丘。だいじなカメラをかばいながら客を待っている。それに追い打ちをかけての寒さは「ただ」を付けたことで哀愁をも感じさせてくれる。(そうけい)
-
広い砂丘が見える場所に一軒の写真屋がポツンとある。その写真屋には人気がない。それ故、砂丘が寒々しく感じられる。(豊実)
-
自分も鳥取砂丘だと鑑賞しました。丘のように盛り上がった砂浜を越えるように冷たい海風が吹いてきます。荒涼としか言えない景色です。団体客がいなければ人影もまばらで、ただただ寒いだけだと感じたのだと思われます。(素秀)
-
冬の鳥取砂丘を思いました。砂丘をバックに記念写真を撮ってくれる写真屋さんなのでしょう、客なしと断定することによって無人の冬の砂丘がことさらに寒く感じられます。吹きすさぶ風の音、砕ける波の音も聞こえてくるようです。誰もいない砂丘に向かって何か叫びたくなりますね。(せいじ)
木の葉髪おしこまれたる帽子かな コメントを書く
(このはがみおしこまれたるぼうしかな)
季語は「木の葉髪」で「十月の木の葉髪」という諺もある。ようやく冬めくころ木々の葉が落ちるように人の髪も常よりは多く脱けるのをいうが、中高年の白髪混じりの薄髪の形容として詠まれることも多い。わびしい感じの心象と取り合わせで詠まれた例句が多いなか、揚句は直喩で詠まれれていて珍しい。それほど目立たなくても気にする人にとっては一大事。隠そうという意識があるわけではないが無意識に深々と帽子をかぶってしまうという句である。「おしこまれたる」の措辞が主人公の気持ちを代弁していると思う。
- 合評
-
-
最近特に白髪、抜け毛で帽子が欠かせなくなった。私にとってこれを如何に隠すかというための帽子。「おしこまれたる」の措辞で帽子の気持ちにハッとさせられ、このようなことでも句材になるのかと教えられた。身の回りを見直そう!(そうけい)
-
帽子の側に立っておしこまれたると詠まれている。豊かな黒髪ではなく木の葉髪をです。滑稽味充分、作者の技量を感じます。(うつぎ)
-
冬に髪が抜落ちるとは言うものの、この帽子の中には女性のふくよかな髪があるように思いました。(豊実)
-
晩秋から初冬に夏の疲れで木の葉のように抜け落ちる髪を木の葉髪。抜け落とすまいと帽子に押し込んで守っているのでしょうか。木の葉髪の季語は男性に対するイメージが強いのですが、帽子に押し込むほどの量ならば女性を見て、あるいは本人のことかと思います。(素秀)
(DDTにほふしよくじやおほさうぢ)
おかっぱ髪の女の子たちが DDT を頭から噴霧されている終戦直後の映像を見たことがある。現在は有害とされているがこの句の詠まれた昭和35年ごろはまだ消毒剤として使われた。季語は「大掃除」、歳時記では春に分類されているが、明治以後、市町村役場が4、5月ごろ日をきめて大がかりに掃除させた習慣のこと。家を開け放ち縁の下には消毒剤の DDT を撒き、道にはズラリ畳が干され、役場からゴミ集めが来る。現在では死語に近い季題である。ちなみに大晦日近くの「煤払い」は家の中の大掃除であり歳時記にあるそれとは規模が異なる。
うつぎ解にもあるとおり私の記憶にかすかに残っている当時の大掃除は家族総出の大仕事、畳を出し終えたあと朝のうちに用意されたおにぎりなどを縁側で頬張りながら、畳の乾くのを待つのである。大掃除中の家は筒抜け状態、ときおり通ってくる春の芳しい風とともに消毒剤として撒かれた DDT の匂いも混じるのである。それほど臭いものではなく運動会のライン引きに使う石灰の臭いに近かったように思う。住宅の洋風化で畳の需要も激減し、町の衛生環境も改善され時代とともに「大掃除」や「畳干す」の季語は死語になりつつある。
理解できないような古い季語の鑑賞は無意味…という声も聞こえてきそうだが、そうではない。人の一生は短く、同じ時代に生きる人との交流だけではわずかなことしか知ることができない。けれども様々な時代の様々な立場から描かれた作品を鑑賞することで、考えに深みや幅ができてくる。古典を学ぶ意義はそこにあると私は思う。
- 合評
-
-
電気掃除機のまだ無い時代夏冬ニ度の大掃除は家族全員での一日仕事でした。畳を干して叩き元に敷く前に DDT を撒いてました。昼食時は未だ掃除の半ばで DDT が凄く匂ったのでしょう。作者は匂いをどう感じたのか私には食事など考えられない嫌なものでしたが個人差がありますね。(うつぎ)
-
小学生のころ(昭和 30 年~ 36 年)は一年おきぐらいの間隔で畳替えをしていたと思います。畳の下に新聞紙を敷くのですが、その新聞紙の上に DDT を均等に撒きます。DDT の匂いはそれほど悪くはありません。いまでこそ使用禁止になっていますが、当時は DDT を撒いてすっきりした気分になったと思います。この句を読むと、家族全員(おそらく三世代)で大掃除をした後、満足感に浸りながらみんなで夜の食卓を囲んでいる様子が目に浮かびます。お酒もついていたのではないでしょうか。(せいじ)
-
DDTはあの殺虫剤かと思われますが、この昭和35年ごろにも使われていたのでしょうか。大掃除で撒いたDDTの匂いの中で昼食となったのかと。現在、日本では使われていませんがマラリア予防などで活躍している国もあります。想像するしかありませんが、どんな匂いなのでしょうか。 (素秀)
オーバーをぬげばエプロンしてをりぬ コメントを書く
(オーバーをぬげばエプロンしてをりぬ)
オーバーはオーバー・コートの略で、歳時記には「外套」の傍題として記されている。さてこの句、自画像のように感じるが第三者の写生にも見える。どちらにしても、主人公はエプロンに気づいておらず、オーバーを脱いではじめて気がついたのである。「あらま!」という瞬間の驚きと、ややあってこみ上げてくる滑稽さとがないまぜになった愉快さがこの句の命になっている。オーバーの裾からエプロンがはみ出ていれば気づくはず、昭和35年あたりは、膝下までスッポリ包むようなオーバーが普通だったように思う。
うつぎ解にあるように「身辺の些細な事でも句になる」ことを教えられる。日常の何でもないことを句材として捉えられるのが、作者の個性でもあるが「天性」のひとことで片付けてほしくない。吟行や鍛錬合宿で写生の修練に励み、毎週のように鑑賞会で学んだりという熱意と努力の積み重ねによって引き出されたものであることを証言しておきたい。
- 合評
-
-
昨日よし子さん(了解済)が同じ格好でやってきました。鍵がないと大騒ぎになりオーバの下のエプロンのポケットから出て来て大笑い。作者も横着して出たもののオーバーを脱がないといけないようなハプニングが起こったのではないだろうか。それは判らないが些細な事でも句になる良いお手本だ思う。(うつぎ)
-
同じ経験があります。オーバーを着ているうちに、エプロンをつけていることは忘れてしまっていて、オーバーをぬいだときに「あっ!エプロンしてた」と思い出します。その「あっ!」という瞬間を句にしたのだと思いました。(なおこ)
-
生活の中の些細な出来事かも知れません。料理の最中に材料が無いのに気づいて急ぎ買い物に行くため、とりあえずオーバーをエプロンの上に羽織ったのです。自分でも横着だなと、思っているようです。(素秀)
明日よりの仕事を思ひ春著脱ぐ コメントを書く
(あすよりのしごとをおもひはるぎぬぐ)
春着はお正月に着る晴れ着のこと。春着の季語の気分を借りて初出勤の前日の感慨を詠んだのである。春着をきて家で寛ぐ人はいないと思うので、親しい仲間の家に招かれ歌留多会などをして楽しくお正月を満喫したのであろう。うつぎ解にあるような年賀式とかへの出席であったかも知れない。正装しての一日の疲れを感じながら、「今年のお正月もこれで終わってしまった。また明日からは仕事がはじまるわ」とやや物憂い気分で春着を脱いでいるのである。脱いだ春着はまたきちんと手入れして収めなければいけないから、よけいに気が重くなるのであろう。「春着」の例句は、着ているときの様子やその気分を詠んだ例句が圧倒的に多く、常識的な類句になりやすい。揚句は脱ぐときの気分を捉えたところが新しいと思う。
- 合評
-
-
この時代の職場の初出を想像しました。女性は春着で着飾りこの日は新年の挨拶だけで仕事はない。でも華やいだ気分も今日だけのこと明日からは仕事だと気持をきっぱり切り替えて春着を脱いでいる句と読みました。(うつぎ)
-
仕事始めが4日だとすると3日の事だと判ります。春着を脱ぐのだから仕事を持った女性だとも。思ひは、あっという間に終わってしまったお正月を惜しむ気持ちも出ているようです。(素秀)
-
正月気分は今日までだ、明日からまた仕事を頑張るぞと心で思い口に出したとしても、春著を脱ぐという具体的な行動をとらなければ、気分はなかなか切り替わらない、今日春著を脱ぐことが仕事始めなのだと自分に言い聞かせている。「春著脱ぐ」に潔さを感じました。(せいじ)
-
今日から昭和35年の作品になります。
風邪声を出して誘惑ことはりぬ コメントを書く
(かぜごえをだしてゆうわくことはりぬ)
対面でこのお芝居をするのは無理だと思うので電話でのやりとりでしょう。この時代はまだアナログ通信の時代、回線容量を制限するために音声フィルターで低音域と高温域をカットしていたし、カーボンマイクだったので、誰の声でも同じように聞こえる。喋り方とかアクセントでしか個人を特定しづらかった。凡士解のように空咳をするとか鼻をつまめばごまかせた時代である。
さて「風邪」は、冬の季語、それを理由にことわらねばならないこの季節の誘惑とは何だろうかと連想するのである。お芝居や映画、ショッピングというのであれば季感が弱いし、小旅行のお誘いだとすれば春風邪か春隣の雰囲気になる。さしづめ寒い屋外イベントの類ではと見当をつけてみる。うつぎ解のように男性からのお誘いだったのかもしれない。わかりいやすく何でもない報告句のように思えるかも知れないが、「誘惑」という措辞が鑑賞する人のとらえ方によって色々に連想がふくらむ。ここがこの句の非凡なところかなと思う。
- 合評
-
-
風邪声を出してだから意図的に出したのでしょう。風邪気味であるが押して行くほどの誘いでもない。断ろう。男性からのデートの誘いだったかも、連想が広がります。(うつぎ)
-
風邪を引いているわけではないけれど、風邪のような声が出ている、もしかしたら本当に風邪かもしれないけれど、それほどの風邪ではない、というくらいの、しゃがれ声が出ていた。しなければならない仕事・用事があったので、遊びの誘いを断ったのだと思いました。(なおこ)
-
一瞬、本当は風邪を引いてないのではと思いましたが、それでは季語が現実に存在しないことになりますね。誘惑とは何かなあと想像が膨らみますが、風邪を引いて残念ながら自粛したと詠みました。(豊実)
-
声だけで誘いを断るのですから、これは電話かと思います。なんの誘いでしょうか。誘惑ですから魅力的なことだと思われます。食事か飲み会か、断る理由は金銭的なことなのか。風邪声と誘惑だけでいろいろ想像は膨らみます。言い過ぎない俳句と言う事になるのでしょうか。(素秀)
-
二つのシチュエーションが想定される。ホントの風邪かエセ風邪か、電話か会ってのことか。ランチか映画か小旅行などの誘いに風邪を理由に断ったということだが、エセ風邪で電話であったように感じる。たとえば鼻を摘まんで話したりして。断った理由はわからないが気が進まなかったのだろう。 (凡士)
(たんじつのきりあげばなしうそがでる)
誰にでも経験のあるシーン、季語の「短日」もよく効いていて動かない。むしろ、効きすぎ、つきすぎ、と見る選者もいるかも知れませんね。そこは微妙ですが青畝選ですから良しとしましょう(^o^)
どのような嘘をついたのかについては、いろいろ連想が働きますが、「短日」「切り上げ話」という感じからすると凡士解のとおり街中で偶然でくわした立話の雰囲気があります。本当の仲良しなら「お茶でもどう?」となりそうなところですが、そうではない相手。うつぎ解、素秀解のとおり、よほど鈍感な人でなければ、切り上げ話の様子から言い訳のための嘘だと薄々感じとれるはずです。一瞬白けた感じの間があいて、「あ!じゃあまたね」と分かれます。まるで四コマ漫画を見ているようで滑稽ですね。そのあたりが青畝選たる所以かなと私は思いました。
- 合評
-
-
日が暮れる前に帰りたくて、嘘をついてしまった。そんな自分を客観的に見ている。(なおこ)
-
女性は話しだしたらきりがない。日が暮れるのに時間が勿体ない。切り上げるのに嘘が出たが嘘と判り合っているようなユーモアを感じる。またテンポのよさが短日の忙しなさをより感じさせる。 (うつぎ)
-
長話をしていたら日が暮れてきた。嘘をついてでも話を終わらせたのですが、長話のお相手も何となく察してお別れしたように思えます。 (素秀)
-
日が短いので早く家に帰りたい。「ちょっと、家の用事があるので・・・」と嘘を言って抜けだした。(豊実)
-
ときどき見かけることがある、路上で立ち話している二人を用事を済ましての帰路にも見ることが。作者は路上か喫茶店かで初めは楽しく話していたがそろそろ日が暮れる、特に用事はないが話にケリをつけないとこのままでは終わりそうにない、そこで歯医者に予約しているとか親が来るので迎えいかないととか理由をでっちあげて終わらせようとしたのではないか。男の場合でも偶然会った人に飲みに誘われたとき、いや今日は用事があるのでと適当に理由をつけて断るときもある。(凡士)
秋天のかけら見えざる間借住み コメントを書く
(しゆうてんのかけらみえざるまがりずみ)
まず季語のチェックから。この句の「秋天」ですが、かけらすら見えてないんですよね。現実に存在しない季語を詠みこんでも季語として働かないから没だという厳しい指導者もいます。部屋の絵画に描かれた薔薇とか、駅のポスター写真の紅葉や桜を詠んでも駄目だということになります。でも青畝師はこの句をよしとされました。
私が紫峡師から諭されたのは、「季語の有無ではなくて季感の有無」ということでした。では、季感という観点からもういちど揚句を読み直してみましょう。せいじ解、凡士解のとおり、せっかくの爽やかな良いお天気なのに間借住みゆえに見えない秋天に対する無念がはっきり感じとれます。そして「春天」「夏空」「冬天」に季語を置き換えてみましょう。どう考えても「秋天」の季語は動かないですね。これが季感なのです。季語が入っていても季語が動いたり季感が感じ取れない句もときにはあります。「季感の有無」と「季語が動かないかどうか」というチェックを忘れないようにしましょう。
- 合評
-
-
間借住みから下宿かと思われます。小さい窓があるのか、ひょうっとしたら窓のない部屋であったのかも解りません。外は秋、晴天の秋空も見えない生活ですが、それを嘆いているようにも思えません。 (素秀)
-
窮屈なアパートを想像しました。狭い住まいでの生活を詠んでいながら、どこまでも広く高い秋天を讃える句に思えました。心はどこまでも高く広いところにある、という作者の想いを感じました。(なおこ)
-
今で言う籠り生活ではないかもしれませんが、間借りのその部屋には窓がないのでしょう。秋の空の元、特に出かける当てもなく、一人で寂しい感じがします。(豊実)
-
私も学生時代 3 畳一間の学生アパートでしたが空は覗けました。作者のアパートは都心の当時筍のように林立した文化アパートで、隣とは隙間もないような状態でしたのでしょう。平日はともかく休日は悲しかったでしょうね、特に爽やかな秋の空も自室から見えないのは、部屋で寛げないので公園にでも出かけて本など読んでいたのでしょうか。 (凡士)
-
間借りをしていた学生時代を思い出します。河原でよく寝転んで空を見ていましたが、秋の空は格別です。その素晴らしい秋天、見えない無念を通して見えざるものへの心の渇きを表しているように感じました。それほどまでに美しい秋の空です。 (せいじ)
ヨットの帆全身つつみ降ろされぬ コメントを書く
(ヨットのほぜんしんつつみおろされぬ)
西宮戎神社の前のえべっさん筋を浜の方へ突き当たると西宮マリーナという小規模なヨットハーバーがある。加代子さんとも何度か吟行した場所である。マリーナにはいくつかの大学のヨット部の艇庫もあり、練習を終えて戻ってきたヨット部員の様子を写生したのだと思う。ネット検索するとわかるが、一般的なヨットは後部につけるメインセイルと前側につけるヘッドセイルの2枚で構成されている。近くで見ると意外と大きく、ロープを緩めて帆を降ろす時に風を孕んだ真白な帆が婆娑と部員の全身をつつむように降りた様子を詠んだのである。今は新西宮ヨットハーバーが整備されて以前のような賑わいはなくなったが、時々は訪ねて加代子さんを偲んでいる。
帆を揚ぐる二の腕太き日焼かな みのる
加代子さんとここで吟行した折に授かった句である。心ゆるせる句仲間と一緒に吟行すると不思議に佳句が生まれるから不思議である。コロナに怯えることなく昔のように楽しく吟行できる日が戻ってくることを祈るばかりである。
- 合評
-
-
ヨットの帆は帆布といってバックの素材にもなる布なので高価であったのでしょう、クルージングごとに帆を丁寧に畳んで艇庫にしまったのだと読みました。ハーバーに係留されているヨットは帆柱だけで帆は外されていますね。現在の帆は化学繊維だとおもいます、したがってカラフルになっています。ヨットの句の多い作者はヨットクラブに入っていたのか、ボーイフレンドがヨットを持っていたのか、当時としては結構先端をいっていた女性のようですね。 (凡士)
白き点まき散らしたるヨットかな コメントを書く
(しろきてんまきちらしたるヨットかな)
「白き点」「撒き散らしたる」という措辞から、遠景であると同時にやや高い位置から俯瞰的に景が展けているようすも窺える。小高い岬の展望台かホテルからの窓景色かも知れない。昔小樽へ旅行した時に小樽祝津パノラマ展望台から見た景色を思い出した。なおこ解のとおり水平線まで真平らに展けた夏の海面(湖面)も連想できます。誰でもが見たことのある風景を、素直に詠んでいて作意がない。私たちの作句も斯くありたい。
- 合評
-
-
「白き点」と「ヨット」と「まき散らしたる」としか述べていないのに、一番、青い海が見えてきて、太陽の日差しに海がキラキラしているのが見えてきますから、俳句は本当に不思議だなと思います。 (なおこ)
-
目を瞑ると夏の琵琶湖や須磨ノ浦の風景が見えるようです。溽暑を吹き飛ばして爽快な気分に浸っている作者を想像しました。 (せいじ)
-
この句の鑑賞はまずどこの光景か、琵琶湖か西宮浜か湘南か、私的には琵琶湖を想像したい、八景の風光明媚な湖にあまたの白い帆。ついで句の背景、戦後復興期を経て高度成長のかかる頃、太陽の季節に代表される第一次ヨットブームというところでしょう。現在のようなカラフルな帆は少なく白い帆ばかりだったようですね。 (凡士)
-
白き点というだけで遠景であることがよくわかります。どれぐらい沢山のヨットがあったのでしょう。 (豊実)
-
今日から昭和34年作になる。
タイプ打つ胼の指先浮かせつつ コメントを書く
(タイプうつひびのゆびさきうかせつつ)
俳句では、冬の季語「ひび」にこの字をあてることが多いようです。英文タイプなら多分ブラインドタッチで打つのでしょうが、時代背景から想像すると和文タイプですから、タイプライターを扱う手順も今とは少し違うのでしょう。特に痛みのひどい指を浮かせながら打っているのです。凡士解のとおり、いまは空調環境が整備されているので、そこまではひどくならないと思うが、女性の場合は、日課のように家事の水仕事があるので、うっかり手入れを怠るとやられることもあるそうで辛い季節です。
- 合評
-
-
胼、皸、霜焼、子供のころはありました。胼、皸はよく使う指にできるので浮かせても結局は使わざるを得ないでしょう。絆創膏で巻いた指が痛々しいですね。栄養、空調完備の現代ではみられない昭和 30 年代ごろまでの風景でしょうか。 (凡士)
-
すごくわかりやすいですね。胼の痛みを我慢して仕事を続ける辛さが伝わってきます。 (豊実)
スケーター転ぶ帽子が先に飛び コメントを書く
(スケーターころぶぼうしがさきにとび)
「句またがり」と呼ばれる文字構成。「スケーター」「転ぶ帽子が」「さきに飛び」と切って読むと、「転ぶ帽子?」となる。そうではなくて、「スケーター転ぶ」で切れて「帽子が先に飛び」と読まなければいけない。披講子泣かせの俳句。季語は「スケーター」でスケートリンクでの写生でしょう。帽子が先に飛ぶくらいなので、凡士解、うつぎ解のとおり、かなりのスピードが出ているものと思う。こんなふうに詠まれるとまるでその瞬間をスローモーション映像で見ているように感じる。なおこ解のとおり、まさしく瞬間写生。普通なら「スケーター転び帽子が先に飛ぶ」と詠んでしまいそうなのを「転ぶ」「飛び」という瞬間写生に青畝師が添削されたのではという感じもする。青畝師から同様の添削を受けて句が一変した経験が私にもあるからである。
「ぶ」「び」の違いによってこの句が生きていることを学びたい。また、句またがりの句は駄目、という指導者もいると聞くが、私は異を唱えたい。正調で詠む習慣をつけるために、字余り、字足らずは駄目という、初学者に対する戒めと同様で、絶対ということではない。初学を卒業し、表現上のテクニックとして使いこなせるようになれば問題ない。
- 合評
-
-
バランスを崩し帽子が脱げたと思ったらすぐ転んでしまった。転んでも少しは滑るから帽子と離れてしまった。それがあっという間のこと。中七の転ぶで切っているのと飛びの措辞でスピード感が出ている。作者が滑っているのか見ているのかどちらでしょう。 (うつぎ)
-
スケーターで切ると、転んだのは帽子と読めます。強風で飛ばされた帽子が先に転がった様子を思い浮かべました。 (豊実)
-
今はなき箕面スパガーデンスケート場を思い出します。句も屋外を想像したいです。結構上手なスケーターなのでしょう。後ろ手に組み前かがみで滑っていたが転んだ。作者にはその瞬間、宙に浮いた帽子に目が引き付けられて、帽子が先に飛んだとか帽子だけが先へ行ったなどと見えたのでしょう。帽子は毛糸ではなくハット、スケーターは男か女か、会社帰りか休日かなどいろいろ想像が膨らみます。 (凡士)
-
スケーターが斜めになっていて、帽子が宙に浮いている図が目に浮かび、瞬間写生の句として面白く感じました。 (なおこ)
-
転ぶ前には身体のどこかに力が加わっているはずであり、その見えない力が帽子が飛ぶことで顕在化した。転ぶときの瞬間をうまく捉えていると思いました。 (せいじ)
お互ひに見立てあひして戎ぎれ コメントを書く
(おたがひにみたてあひしてゑびすぎれ)
戎切れ(夷布)というのは、恵比寿講の日の誓文払いに、呉服屋が見切売りする小ぎれのこと。詳細については、なおこ解にあるとおり。今日では陽暦で行われ、デパートなどでもその前後一週間ほど安売りをするという。また呉服店など、ふだんの残りぎれや売れ残りの品を「夷布(えびすぎれ)」といって売り出す。
ホトギス新歳時記には、陽暦で秋の季語になっているが、角川歳時記では陰暦で冬の季語とされている。宗教行事として捉えるなら陰暦かなと思う。
女性は、このような安い端切れ布を買って、パッチワークなどで小物を作って楽しむのだと家内に聞いた。句意は明快、更紗解のとおり数人の女性が、ぺちゃくちゃおしゃべりしながら物色している様子が目に浮かぶ。この句の詠まれた時代、天神祭をはじめ地域の祭事の日には、オフィスは半ドンになるというような粋なはからいもあった。楽しそうな雰囲気からして小春日和の午後、勤め帰りのビジネスガールの仲良し組という感じもする。男には作れそうにない句である。確かに近年は例句も見かけないが、死語になったわけではなく、ところによっては現代も続いているようだ。
- 合評
-
-
えびす講でこういう慣習があったことを初めて知りました。お互いに見立て合いをする、女性にとって至福の時ですね。臨場感があります。 (うつき)
-
恵比寿講が難しいですね(笑)。恵比寿講を詳しく知らなかったので、辞書で調べてみました。「商家が商売繁盛を祝福して恵比寿を祭ること。旧暦 11 月 20 日に行うことが多いが、1月 10 日、1月 20 日、10 月 20 日に行うところもある。(冬)」とありました。戎ぎれについては寄切れとあり、「たち切れの布を合わせて縫ったもの」とありましたので、何かカラフルな布やシックな布など小さなたち切れを縫い合わせた着物?(ふだんの店先では、出合えないような着物だったり)をお友達と恵比寿講の日に店先で「これはどうかしら?」「お似合いよ」とお互い見立てあっているのかなと思いました。 (更紗)
-
戎ぎれ、恵比寿講?昭和 30 年代にはこういう市とか売り出しがあったのでしょう。きれ=布地ですから友達と見立てあいしている句でしょう、反物か最近インバウンドで注目の小切れかはわかりませんが。同じ昭和の人間でもよくわからないことがあるのですね。 (凡士)
-
戎ぎれを歳時記で調べると、陰暦十月二十日「恵比寿講」の日、京都の商人が商売上のかけひきでついた嘘を払うために、安売りをする。呉服店など、ふだんの残りぎれや売れ残りの品を戎布といって売り出す、と書かれていました。ほかの辞書には、冬の季語と書かれていましたが、陽暦の場合や地方によっては冬の季語になるのでしょうか?戎講の日に連れとお互いに似合う寄切の布を見立てている。「ぎれ」を平仮名にしているところに、作者の女性らしさを感じました。 (なおこ)
(かいてゐるはしからタイプひみじか)
この句が詠まれたのは、昭和33年~36年の間続いた高度経済成長期(岩戸景気とも言われる)である。ワープロなどはまだ普及していない時代、企業内外の正式文書はみなタイプライターの女性社員が清書していた。「書いてゐる端から」は、たくさんあるものを次々に処理していくさまの「片っ端から」の意。私の努めていた職場では、数人のタイプライタが別室で作業していたが、揚句の場合は、豊実解のように原稿を書いている人と隣り合ってタイプしている情景かもしれない。
日の短い冬の季節は、オフィスの窓が薄暗くなるも早い。そろそろ退社時間の定時が近づいているというのに、次か次からと原稿が溜まって終わりそうにないのである。「日短」の季語は、「ひいみじか」と「ひ」を間延びさせて発音するのですが、休憩する間もないくらいの忙しさに疲れて、「今日も残業になるのかしら…」と、少々辟易している「ため息」のような夕ごころの気分も代弁されている。
- 合評
-
-
「日短」の読みについて教えていただき、ありがとうございます。こちらのお句、何か締切りに追われているのでしょうか。きちんとした清書ではなく、原稿に書き直したり、校正を入れたり、今まさに書いて「ゐる」ものをタイピングする…その繰り返しなのでしょう。もしかしたら、出版社や新聞社だったりするのかもしれません。時間厳守に忙しく追われている様子が「日短」の季語に表れています。 (更紗)
-
原稿の締め切りが近づいている。手書きで走り書きをする端から秘書がタイプ打ちをしている。あっという間に日が暮れる。 (豊実)
-
昭和30年代の職場の書類仕事はどうだったかはよくわからないが、手書きで枚数を要するものはカーボン複写だっただろうし、社外への正式な書類はタイプで打っていたのだろう。句のタイプは多分和文タイプだろうから英文タイプに比べ手間暇と時間がかかったように聞いている。長文なので書いてからタイプするのでは日が暮れてしまうから、原稿を書く人の隣に座り書くのを見ながらタイプしていたという句。当時の女性の専門職は電話交換とタイピストだったのかもしれない、3丁目の夕日の職場版を彷彿させる。(凡士)
(たんじつやみたきえいがはにほんだて)
映画がフィルム上映の時代は、封切館で上映され傷つき劣化したフィルムが配給会社から格安で借りられたので、弐番館、参番館がこれらを抱き合わせて二本立て、三本立てというように低コストで上映された。二本立ての場合、落語の前座と真打ちのように位置づけられてメインの方があとから上映される。現代は、ほぼ完全にデジタル上映に移行したので、二本立てというのは見られなくなった。
さて、「短日」は、日照時間の短い冬の日のこと、特に主婦や女性は、夕食の用意、洗濯物の取り入れなど、慌ただしく夕仕事をこなさねばならない季節である。買物か小用があって街に出たついでに、見たい映画が上映されていたので、上映時間表を見るとちょうど前座が始まりそうな時間帯で、二本目の上映が始まる時間は微妙である。映画館へ入ろうか、いや、やっぱり我慢して家へ帰ろうかと思案にくれているのである。季語自体には一切触れていないし、説明もしていないけれど、この季語なくしては成り立たない作品。季語が動かないように詠む…のお手本と思う。
- 合評
-
-
見たい映画ではあるが二本立て、二本見るには日が短すぎる。どうしたものか…。作者の心情がよく表れている。 (うつぎ)
-
昭和30年代故郷の人口3万の町にも映画館が2軒ありました。当然2本立て、映画は田舎の最大の娯楽でした。句は短日ですから、冬の昼間司葉子か若尾文子か主演の文芸ものを観たいが、2本とも観たら暗くなってしまう、どうしようかと逡巡する作者の若い頃の思い出を詠んだのでしょう。 (凡士)
-
昭和 33 年は、まだ私は産まれてなく、映画二本立てのことも詳しくはありませんが、良い俳句は、時代を問わずに読み継がれると思いました。今ですと、『おうち時間に、パソコン・タブレット・スマホで、月額〇〇円で映画見放題!夕方までに二本見られる!長い夜に二本見られる!』と個人のライフスタイルに合わせて、句が鑑賞できると思いました。昼と夜、どちらにもとれるので、まるで二本立ての俳句だと思いました。 (なおこ)
-
そういえば、以前は映画の二本立てがありましたね。二本とも当たりのときもあれば、もう一本はそれほど興味ない作品もありました。こちらの句はきっと後者なのでしょう。楽しみにしている映画作品のロードショーがある。でも、二本立て…。短日やとありますので、まだまだ日が短くいつの間にか夕暮れになってしまう景と見に行こうかどうしようかと悩ましいな。という情景が浮かびました。 (更紗)
-
長い夜の時間をどうやって過ごそうか?楽しそうな映画が二本もある。そうだ、今宵は映画三昧としよう。 (豊実)
-
しばらくは、昭和33年の作が続きます。
(はなしよりなみださきだちあきともし)
合評は、青畝選の秀句から学ぶべき点を共有する座なので懐疑的な鑑賞や雑談は慎みたい。まずは季語(季感)の見極めから、なぜ秋灯なのかを考えてみた。物語や書物に関わる事象であれば、普通は「秋灯下」をあてると思う。一方、突然の悲報を受けて駆けつけたとすると、秋灯である必然性が弱く、冬灯でも春灯でも同じになるので季語が動いてしまう。こんなふうに消去法でしぼっていくと季感として動かない「秋灯」は、初盆もしくは故人を偲ぶ初彼岸などのたぐいではないかと想像する。
あとづけの情報になって申し訳ないが、昭和33年の作なので、まだ結婚される前になる。思うに、仕事の都合などで遠く離れた故郷での葬儀には出席できなかったが、初盆への招きを受けて帰省した折に訪ねたというような情景かと連想してみた。親友の親族か、もしくは親友本人のよきせぬ不幸であったかもしれない。逆縁ほど辛いものはない。どちらにしても遺族の心痛がわかるだけに、胸につかえていたつもる話も悲しさに押しつぶされて涙になったのであろう。
省略が効いている故に、連想をひろげていくと一編の小説にまで飛躍していくが、正解は天国で加代子さんと出会った時に訊ねるしかない。いづれにしても「秋灯」の季語がどんなふうに仕事をしているのかを中心に置いて連想を働かせたい。
- 合評
-
-
何か悲しい出来事が大切な人との間に起きた。秋の夜にその人と約束をして出会ったが、顔を見ただけで涙があふれる。 (豊実)
-
ただただ切なく胸に沁みる句です。話すことより涙が先に出てしまう。悲しみの涙なのでしょう。私も先立たれたご主人の遺影の前での光景かと思いました。毎日、夕刻あたりにその日の出来事などを語っていたのかもしれません。ある秋の日、ふと遺影の中のご主人を目にされて、話よりも涙がさきだってしまったのかもしれませんね。秋灯がとても切なく、季語が動きません。 (更紗)
-
誰がどんな…と色々な場面を想像させる句ですが青畝師の序文からご主人の遺影を前にされての句のように思えます。多くを語らず秋灯でぐっと読者に迫って来るものがあります (うつぎ)
-
二人だけか、何かの集まりか、書物を紐解くかシチュエーションはいろいろありますが、作者は顛末を知っていて、顔を見るなり、本題に入るなり涙腺が緩んだと読めますが、もっと奥深く源氏物語のような「もののあわれ」を詠まれたのかもしれません、秋灯がそのように読ませます。 (凡士)
-
どなたとどのような話をするためにお会いしたのか分かりませんが、親しい間柄の人に大事な話をしに行ったところ、顔を見ただけで涙が溢れた。日暮れの早くなった秋の夕方、頬を伝う涙が、灯にぼんやりと照らされているイメージがわきます。 (なおこ)
涼風がもちあげてゐる卓布かな コメントを書く
(りようふうがもちあげいえゐるたくふかな)
「涼風」という季語の本質から考えると屋外の景を連想するのが自然だと思う。緑の木立の中のカフェテラスを連想してみた。テーブルにかけられた純白の卓布が、ときおり通う森の涼風を孕んで膨らんでいるのである。風に意志があるかのように擬人的に表現してあるところが作者の小主観であり、この句の手柄でもある。鑑賞に絶対はないので、読者がそれぞれの体験と重ねて連想をひろげていけばよい。現実的な景を連想してもいいし、ロマンチックに連想してもいい。鑑賞も又、読者の個性であり、感性である。直訳だけでよしとするのではなく、伝わってくる作者の感動を捉えるように心がけることが大事だと思う。
- 合評
-
-
俳句を見た瞬間に、扇風機の風がひらひらと卓布をもちあげている光景が目に浮かびました。もちあげている、というから外からのものであっても、強めの風だと思います。掃除のあとに部屋を見渡している光景なども目に浮かび、365 日休みのない、主婦のまなざしを感じました。 (なおこ)
-
卓布はテーブルクロス、涼風は真夏でなく秋に近い頃の風かなとおもいます。卓布がめくれるぐらいですから結構な風でしょうがそれを“もちあげている”という措辞で日常のなんでもない一コマを詩にしています。 (凡士)
-
加代子句集は年代順(昭和33年~昭和60年)の編纂されています。三が日が過ぎたので編集上、掲載順に戻します。季節がバラバラになりますがよろしくお願いします。

(すごろくのせいせいるてんおもひけり)
「生々流転」の四字熟語は、生まれては死に、死んでは生まれを何度も繰り返すことの意。仏教では、悟りを得る事ができない人は、六道という世界を巡り続けるという意味があるという。賽の目次第で運命が変わる双六は、確かに自分の意志ではコントロールできない人生と似ている。けれども、「現世を生きる者は皆、生々流転の原理を踏襲しているのだ」という感じで用いられることから、個人の人生の起承転結を比喩することばではなさそう。双六の出世街道を快調に進んでゴール目前という人が突然ふりだしに戻ってしまったり、裏目裏目と裏切られて「もうだめだわ…」と思われた人が起死回生逆転するというシーンもある。そのような運命のいたずらを双六ゲームに重ね見たのではないかと思う。
「生成流転」といへば、高浜虚子の「この池の生々流転蝌蚪の紐」という句碑が西脇の西林寺の池のほとりに建っていて、まだ初心者であった頃に紫峡師と一緒に眺めたことがある。先生は腕を組んでじっと句碑と対峙しておられた。在りし日の虚子先生を偲んでおられたのであろう。私はその横で、「なるほど、こんなふうに詠むのか」と目から鱗の衝撃を受けた思い出がある。
- 合評
-
-
双六の面白さの内にも上がったり下がったり自身の人生を重ね合わせての句でしょう。今後はどうなのだろうか。生生流転の四字熟語がそこ迄思ったやうに読者に感じさせる。 (うつぎ)
-
双六を生々流転と捉えたのですね。確かに次々と賽をふるが立ち止まったり、後戻りしたり、変なところへ飛んだり、常に前進ばかりではありません。この言葉は作者の人生をなぞらえたのか双六の面白さを表現したのかどちらでしょうか。(凡士)
-
双六は「勝ちたい」と思ったり「はやくゴールしたい」と思うものですが、その双六を『生々流転』と表現したところがすごいな、と思いました。進むときもあれば進まない時もあり、その時々に様々な感情がわきます。作者は双六をしていて、さまざまな感情を味わい、あがったときに「勝った」「負けた」ではなく、まるで『人生』のような味のある自分の道のりに、満足感を感じたのではないかと思います。 (なおこ)
(ひやくまいのねんがじやうにもこせいかな)
この句を一読して、「あたりまえでは?」と一瞬思った。でも数千句の作品から加代子さん自身が絞りこみ、さらに最終的に青畝師が選ばれた400句のうちの一句である。きっと何か理由があると思って何度も読み返してみた。ふと、「にも」という言葉に意味があるのではと気づいた。「俳句で何よりも大事なのは個性だよ」という青畝師の教えが常に作者の頭にあった。個性、個性と自分に言い聞かせるように意識していた作者には、そのような俳句的な視点で物を観察する癖がついていたのだと思う。一枚一枚、賀状を眺めながら、そこに差出人それぞれの個性を見出して納得しているのである。
- 合評
-
-
色々の年賀状の個性ひいては書いた人の個性を感じながら一枚一枚読んでいるのでしょう。 (うつぎ)
-
元日に年賀状を見ていて、写真付きのものや、手書きのもの、派手な柄や地味な柄があり、それぞれの個性が出ていると、思われたのだと思います。 (なおこ)
-
年賀状俳句は添削指導でことごとくボツでしたが、掲句のようなとらえ方があるのかと参考になりました。たしかに皆さん賀状の図柄もコメントも違います、これを個性ととらえたところがいいですね。今年にかぎって賀状のコメントはコロナ一色でしたが。 (凡士)
(ふくじゅさういもせならびのかげかさね)
うつぎ解にあるように、「翳かさね」に注目してほしい。「妹背ならびに寄り添ひぬ」「妹背ならびに咲きそろふ」と詠んだのでは平凡で、「翳かさね」と詠まれたので福寿草に日が差していることがわかる。お正月なので縁起物の福寿草の小鉢が出窓に置かれていて、その窓辺へ冬日が差し込んでいる情景まで見えてくるのである。昭和 60 年の作なので、亡きご主人との幸せだったお正月を懐かしく思い出しておられるのかもしれない。
- 合評
-
-
鉢植えか土手に咲いていたか、茎分かれした福寿草が高低差をつけて二輪咲いていたのでしょう、冬の光をうけ影がひとつに重なっていた、それを夫婦のようととらえたのでしょう。 (凡士)
-
縁起物の松竹梅の盆栽に福寿草も植わっていたのか。この頃はまだ群生地があったのかもしれない。大きさの違う二つの寄り添った福寿草を妹背ならびと言われれば兄妹ではなく夫婦でしょう。翳を詠まれたのが巧みです。 (うつぎ)
-
吟行の途中に福寿草をみつけました。二輪の福寿草のこっちが妻でこちらが夫かしら。重なり合って寄り添って、いいわね。とご主人のことを想いながら福寿草を愛でているのだと思いました。福寿草の黄色からは、明るく、そして哀しみの想いを感じました。 (なおこ)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
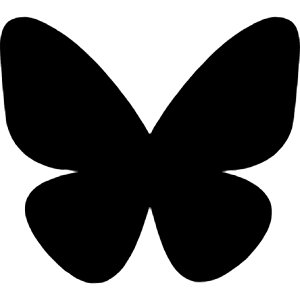 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()