2014年5月
目次
至近で鑑賞した打ち上げ花火である。脳天を打ったのは揚花火が空中で炸裂したときの爆発音である。遠花火の場合は花火が開いてから少し間を置いて音が聞こえるのであるが、揚句の場合、ほぼ同時であったのでこの驚きとなった。中州で打ち上げられるのを直近の川床で眺めているという風情と見る。「脳天打ちて」の措辞によって音の大きさと頭上に仰いでいる花火であることがわかる。
- feedback
-
-
一斉に空を見上げている群衆のざわめきも聞こえてきます。「脳天打ちて」は度肝を抜かれるような、近すぎてうるさい様な、でも花火はこうで無くてはと思っている。作者の心模様を語っている。
-
「脳天打ちて」強い激しい音が伝わってきて、鑑賞している自分の脳にまで響いてきそうな錯覚があります。
噴水のひっこめば像いぶかしみ コメントを書く
大小の噴水が中心の像を取り囲むように踊っている。噴水の動きはプログラムされていて一通りの演出が終わると何秒間か小休止するが、その一瞬の静寂がうまれたときふと像の表情がためらったように感じたのである。像の表情が変わることはないので作者の心象眼がそう見たのである。無心に噴水をうち仰いでいた幼子が噴水が止まった瞬間、「あれ??」と不思議そうな表情になるが、その感覚に似ている。「ひっこめば」の措辞がそれまでは高々と立ち上がっていた噴水がピタッと止まった瞬間を具体的に連想させている。
- feedback
-
-
像からみれば噴水は上がっていて普通、曝されているようで早く上がって欲しい。女性の私はそうとりました。こういう一瞬を切り取れるようになりたいものです。
-
噴水の前にあるベンチに座り心は何処かに彷徨いぼんやりと見るともなしに噴水を見ていた。そして突然噴水の水が出ていないことに気づいた。あれ?と思っているとまた水が踊り始めた。「ああ、そうか」とわかったもののなにやら可笑しい。彷徨っていた心が目の前の現実に引き戻された瞬間、少し悩んでいたことも小さいことに思えたかもしれない。
-
豪快に噴水がとび出したかとおもえば急にとまったり、真中の像の不審な表情は作者自身の感覚だと思いました。
洗面器金魚の紅がはじきあひ コメントを書く
同じサイズの白い洗面器に金魚を入れてそれぞれ評価されるような風景を見たことがあるので、おそらく品評会での写生であろう。当然ながらコンデションのいいものを選んで出品されているのでどれも元気がいい。「紅があじきあひ」という的確な写生によってその様子が具体的に伝わってくる。
=feedback
-
白いホーローの洗面器に入れられた金魚は、まさに紅はじきあひです。大和郡山吟行の金魚園で見た風景そのままですね。
-
洗面器ですから限られた大きさです。その中での金魚の動きを紅がはじきあひとは言い得て妙、「金魚が紅を」ではなく「金魚の紅が」と色を主眼にしているところが素晴らしい。
-
金魚の品評会があるんですね。写真から雰囲気が伝わってきました。鑑賞文を読む前は水換えのために洗面器に退避された金魚をイメージしていました。金魚は洗面器の中の狭く浅い水の中。掲句の周りでも子供が見ているかもしれませんね。
卓を打ち雨とびあがるビアホール コメントを書く
詠まれている季語はビアホール(ビアガーデン)であるが季感はあきらかに夕立である。作者は客として写生していると思われるので営業中に突然夕立に襲われたのであろう。瞬時の出来事に右往左往する客や従業員の姿が目に浮かぶ。もしあなたがテレビニュースのカメラマンでワンショットでこの状況を伝えるとしたら何を撮るでしょうか。作者は激しく卓を叩いて跳ね上がる雨脚を捉えることでそれを伝えたのである。俳句における写生の視点は、カメラアングルと同じである。揚句は焦点を絞ること、省略することの大切さを教えてくれる。
- feedback
-
-
都会のビルの屋上によくあるビアホール。開放的な場所も夕立にあうとなすすべもない。今まで楽しんでいたテーブル席は激しい雨に修羅場と化したのである。
-
ビアホールで楽しくビールを飲んでいたら突然の雨。作者は、その突然の降り出し方も雨脚の強さにも愉快な気分になっているようです。掲句には愉快なリズムを感じます。「打つ」も「とびあがる」もどちらも「雨」の写生なのですが「雨」を挟んだことで愉快な響きになっていると思います。
-
突然の夕立も一興と悲惨さを感じさせない夏のエネルギッシュなビアホールを想像します。省略が効き打つ、とびあがるの措辞がはたらきました。
避暑ホテルのロビーの大きなガラス窓に透けて借景の夏山が見えている。袖という比喩は山裾の意で比較的低い緑の山々が互いに袖を合わすように重なって見えている。見える距離や樹木の関係で全く同じ緑ではないので特にそのように感じたのである。能勢路や丹波路あるいは大和路あたりの風景かと思う。
- feedback
-
-
玻璃は硝子のことと調べて知りました。よくわからないことを調べてみると、調べる前にぼんやりと掴んでいたことがまるで違っていたということが、毎日句会のほうでもあります。意味がわかると途端に景や思いがはっきりします。日本語はたくさんの表現や言葉があるのだと感じるこの頃です。
-
夏が動かないかどうか先ず考えました。冬は枯一色、秋の紅葉も春の芽ぶきも重なりの稜線は鮮明ではないのでやはり夏という季感は動かないと納得。透明な大玻璃の涼しさも夏を思わせます。
素十句集には揚句のほかに「花びらを流るゝ雨や花菖蒲」「花びらを打ちたる雨や花菖蒲」という作品も隣り合って掲載されているが、ぼくは揚句が最も秀逸だと思う。花びらを走ったのは雨ではなく雨の珠である。本格的な雨ではなくてしとしとと降る雨が大小の雨粒となって花菖蒲の大きな花びらにとどまっている。そのうちの一つが次第に大きくなったか、小さなものが合体したかの瞬間、耐えきれずにつつと花びらを走り落ちたのである。花びらを打ちたる雨・・・は、かなり強い雨が連想される。流るる雨はどことなく説明的で平凡である。素十がわざわざこの三句を並べ掲載した意図はわからないが、打ちたる雨→流るる雨→走りし雨という順に推敲したのではないかと思う。
- feedback
-
-
一読した時は景がさっぱり見えませんでした。鑑賞分を読ませて頂き、「走りし雨」の様子がよくわかり味わい深い句となりました。観察し推敲するということを教えられました。
-
「走りし雨」の措辞が花菖蒲のみごとな花びらを際立たせています。他の作品も併記されたのがとても分かりやすく、推敲の後を感じさせる美しい句だと思います。
高木の朴はやわらかな広葉を広げた上に玉杯のごとく咲くので下から仰ぐ形では見えない。揚句は山道から見下ろした谿の樹間に咲く朴の花であろう。朴の花との出会いに感動しその荘厳さに暫く見とれていたとき朴の葉を揺るがせて一陣の風が木立を駈け抜けて行った。静から動への一瞬の変化に感興を覚えたのである。泰山木も似た花であるが葉が分厚く「風渡る」の雰囲気は醸せない。
- feedback
-
-
先日病院の駐車場で、甘い香りに探すと朴の一番花でした。一本だけでしたし、やはり仰ぐというよりも、斜めに見上げるようにして見ることができました。たくさんの蕾もよく見えました。しばらく見ているとまた甘い香りが風に乗り漂ってきて少し幸せな気分になりました。
-
作者は山道をのぼってきて眺望の開けた場所でひと息入れている。大ぶりの葉に乗っているような朴の花の揺れ、渓を渡る風も涼し句感じられたことと思います。
母乳がでない原因は、体質的な理由だけではなくて、生活環境などメンタル的な影響も大だと聞いたことがある。思うに母乳絶対主義の姑と同居している場合などでは特に悲惨である。揚句の場合、仔細は説明されておらず、また一人称とも三人称ともとれる句意なので短編小説風に連想が広がってゆく。
- feedback
-
-
女として子を授かったものの乳の出ない悲しさ。この句は男の人だから詠めた句と思います。衣更の季語が哀れを誘います。
-
授乳中は子供の鳴き声が聞こえても乳が張り出てきてしまうことがあります。ですから着るものには気を使います。今と違って掲句の時代は着物もさぞ汚れたことでしょう。少し前まで暮らしの中で女性の身繕いは苦労があったろうと思います。衣替えの時期、授乳期のそんな話題になり、「乳のでない人は苦労がなくていいわね」などうっかり言われてしまう。軽く聞き流して微笑むけれど心の奥は哀しい。そんなことを思う句でした。
籐椅子を奪われたりし食後かな コメントを書く
吟旅の宿での写生と解せば分かりやすいかと思う。宿についてお風呂を愉しんだあと、食事の準備が出来るまでの間、籐椅子に座って湯ほてりを冷ましながらくつろいでいた。やがて食事が済んだのでもう一度戻りたいと思ってみてみたら、先に食事が済んだ仲間に椅子席を奪われていてちょっとがっかりしたのである。ごくふつうの何でもない事柄なのに写生の力によって個性的な作品となるから面白い。
- feedback
-
-
夫婦での旅行、食事が済み次第縁側の籐椅子に座るつもりが先に夫がどっかと座ってしまいました。
-
我が家は 8 人の四世代同居。食後に寛ぐ間もないほどの賑わい忙しさですが、時おり、お腹が満たされた心地よい疲労感の中で揺り椅子に座って休みたいと思う時があります。騒ぐ幼児にかこつけ片付けまでの時間を少し早めに食卓を立ったのに、揺り椅子に先客がいた時の軽いがっかり感。共鳴しました。
-
別荘へ一家総出の避暑であろうか、食後の子供たちが1台の籐椅子を取り合って遊んでいる。昼はおばあちゃん専用であったのに。幸せなご家族全体の情景が想像できる。簡単明瞭にして余情のあるこんな句に憧れる。
-
食後かなの惜辞がとても生きています。食後の一服に籐椅子の座り心地を愉しもうと期待していた残念感が伝わります。
バス涼し歌が自然にとびだして コメントを書く
品女さんの代表作の一。愉しそうな吟旅のバスで詠まれた句である。品女さんの句集にあてた青畝師の序文のなかにこの作品に触れられたヵ所があるので少し長くなるが紹介しておく。
富士の麓へ吟旅があった。バスに乗ってたいくつするじぶんに涼しい歌声がきこえはじめた。歌手は品女さんだった。品女さんが強いられるままに歌ったのではなく、勝手にとび出したまま歌ったのである。楽器が鳴り出すというふうな自然はまことに邪気がない。その後彼女の美声に惚れて南国土佐をいくたびせがんだことだろう。
- feedback
-
-
万緑の中を走り抜けるバス旅行を連想した。眼も保養され開放された気分になって歌の一つも歌いたくなります。
-
バスの中でのうきうきした楽しい気分が伝わって来ます。子供の頃から音痴な私はバス遠足などでマイクが回って来たりするのは苦手でしたが、今も気持ち良く歌える人が羨ましいです。歌を歌える人は楽しみの幅が広いだろうなあと掲句のような場面に憧れます。
-
譜面があれば歌われる品女さんの楽しいお仲間とのバス旅行の様子がうかがわれます。
滝茶屋は常に飛沫をかぶるので湿気が多く木材の傷みも早い。揚句の滝茶屋も例外ではなく、土台の木材が腐食しているらしく歩く度に床板がふわふわとして心許ない。危険と言えば危険なのであるが、茶屋主も利用客も慣れているので頓着しないのである。
- feedback
-
-
滝のそばは湿気が多く木材も早く痛みがち、客が歩けば床がきしみ並んでいる卓も不安定です.
-
当たり前のように軋み卓が動く、当たり前になってしまっていることに気づかれた。
-
滝茶屋に行ったことはないけれど、言葉からくるイメージでは緑の木々に囲まれ激しく滝が落ちている傍にある古びた和風のお店。そこで滝を眺めつつちょっと軽い食事に入ったのだろうか。そこは滝がある山中の岩の多い場所柄か少し不安定である。だけどその不安定な感じや床の軋む音などが滝の涼と共にはるばる見に来た気分を盛り上げてくれる。そういう光景をイメージしました。
はゞたける日覆の石にひきずられ コメントを書く
揚句の日覆は布地で暖簾風のもの。風に煽られるので足元に紐で重石がくくられているのであるが、強い風が吹くと重石に抗って羽打つようにはばたくのである。対象を熟視した結果、日覆に意のあるが如く感興を得たのである。老舗の看板暖簾であることも想像できる。
- feedback
-
-
はゞたける日覆が一番作者の言いたかったことだと思います。石をひきずるようにもがいてる本当に意志があるように感じられます。
桟橋を駈け来て夕立傘もたず コメントを書く
漁舟用かあるいはヨットハーバーの桟橋であろう。駈け来て・・という措辞から、ある程度距離のある後者ではないかと思う。舟の手入れをしていたところへ不意打ちのような夕立に襲われたので急いで駈け戻ってきた人を写生した。ごく平凡ともわれる写生であるが、作為のない瞬間の切り取りによって躍動感が生まれている。作為の見られる作品には力がない。
- feedback
-
-
色々にとれそうですね。桟橋の誰かに会いに駈けてきた途中に夕立にあいずぶ濡れになってしまった。私は愛しい人に向かって駈けてきた人を思い浮かべました。
剪りのこしたる山百合のそつぽ向き コメントを書く
山野に自生している山百合であろう。揚句の山百合は群生ではなく、散らばって咲いていたのであろう。山道から林中に立ち入って何本か目に留まるのを剪ってもとの道に戻って振り返ったら、見落としたと思われる一本に気づいたのである。「そつぽ向き」という捉え方が感性であり、百合の特徴をよく捉えた措辞である。
- feedback
-
-
山で生活する人は、山の恵みを全部自分のものとはせず、必ず残しておく。綺麗な山百合もそうなのではないかと思う。何気なく振り返ったなぞへの山百合は、どう思ってそっぽむいたのかちょっと聞いてみたい気がします。
苺の食べ方には、砂糖派、練乳派、あるいは牛乳派など、それぞれ好みとか流儀があるようで、揚句の苺には帽子のようにたっぷりと砂糖がまぶしてあるのである。我が家では牛乳+砂糖少々で頂くが、スプーンでぐちゃっと苺をつぶしてたべると最高。苺を食べるときは何となく小さい頃の懐かしい味という感じがあり、苺にかかっている砂糖が帽子のようだと感じるのもそんなメルヘンチックな感興を覚えたのであろう。
- feedback
-
-
苺を食べるときは、なぜか幸せな気持にしてくれます。白い帽子を思わせるほどの砂糖に子供の頃の楽しい思い出につながったのでしょう。紅い苺と白い砂糖の対比も綺麗です。
前脚をふんばりて蟻立ち止まる コメントを書く
何でもない句であるが、蹲ってじっと蟻の動きを観察している作者の姿が見えてくる。蟻の前脚は後脚の四本より短い。忙しなく歩きながらふと立ち止まって頭をもたげた蟻の姿勢は確かに踏んばっているように見える。一見報告のように思える作品であるが素十俳句と同じような小動物に対する優しいまなざしを感じる。水原秋櫻子は素十の作風を「ものの芽俳句」と揶揄したが、美辞麗句によって修飾された作品よりも、幼子のような素直な観察と発見こそが本物であるとぼくは思う。
- feedback
-
-
紫峡先生も素十の作風がお好きだったそうです。何気なくしかし観察力のある句です。いつも無心に動いている蟻にもなにかふと思ったことがあったのかもしれません。
冬のあいだ閉ざされていた登山小屋にはまだ南京錠がかけられたままである。その南京錠が逆立っているのを見て、冬山の激しい風雪にもみくちゃにされたであろうことを連想した。山開きとともに賑わう山小屋も秋風が吹く頃になると役目を終え、管理人はまた小屋に南京錠をかけて下山するのである。
- feedback
-
-
南京錠をかけて山小屋を閉じるのは、山岳地帯の小屋なのでしょう。まだ山開きには間があり訪れる登山者も少ないころの風景と思います。
春蝉やかかるところに高木あり コメントを書く
春蝉は四、五月頃出現する。好んで松林にすむので松蝉とも言われ、高木の梢に多いため発見も難しい。夏の蝉ほど力強い啼き方ではなく、人里離れたところで、静かに、松風の音とともに聞こえてくる感じである。揚句の作者は、春蝉の啼くのが聞こえたのでふとその方向を見やると、松林の中に一本の高木が抽んでているのに気づき、声の主はあのあたりかもしれないと思ったのである。松のことは一切いっていないが、春蝉の習性からそう連想できるので景が具体的になり且つ美しい。
- feedback
-
-
春蝉は小柄なうえに体が黒く翅が透いているので見つかりにくい。声もそんなに大きくなさそうです。どこで啼いているのだろうと見上げると、思わぬ高木あった。
蜘蛛の囲のがんじがらめに常夜灯 コメントを書く
常夜灯は防犯のために夜の間ずっと点灯させているもので、いまふうで言えば街路灯や防犯灯の類いである。電灯のない昔は石灯籠のようなものが使われていたようであちこちに文化財として残っているのを見かける。そんな使われなくなった常夜灯が蜘蛛の巣だらけであったのを見て、あたかも蜘蛛の巣の虜になっているように感じたのである。綺麗な囲をつくる種類ではなく糸くずがぐちゃぐちゃになったような土蜘蛛の巣ではないかと思う。土蔵の鍵穴や縁の下、軒裏などに雨を避けて巣づくる土蜘蛛にとって使われなくなった常夜灯は格好の場所なのであろう。
- feedback
-
-
植込みの深い社寺に据えてある石灯籠、今は燈を入れることもなく蜘蛛の居城となっています。
朝ごとに髪を梳くのは女性の日課であるが、今朝は特別に早起きして入念に整えているのである。来客があるかあるいは外出の予定があるのでおめかしもしなければならない。朝涼しの季語の斡旋によって、そうした期待とともに気持ちの昂ぶりが感じられる。女性にしか分からない微妙な感覚ではないかと思う。
- feedback
-
-
昔の女性は髪が長く、つげの梳き櫛で汚れを落としさっぱりと髪を整えるのが習慣でした。外出でもするするつもりだったのでしょうかね。
ぺちゃんこの財布で競馬賭けてゐし コメントを書く
競馬は、平安時代に神事の競べ馬として 5 月に行われたものであったようだが、今日では競馬場で行われるレースとして詠まれることが多い。年間を通して開催されるため季感としては弱いが、東京競馬場で行われる日本ダービーが伝統あるためそれをさして夏の季題として扱われている。揚句のモデルは、財布にスポットをあてることで負けが込んでいることが分かり、人物像の悲壮な表情や必死な姿勢まで容易に連想できる。
- feedback
-
-
次こそは次こそはとつぎ込んでいる打ちに負けが込んで・・・・空の財布で帰られょうか。賭け事をする人の心理だと思います。
補聴器がぴいぴい衣更ふるときに コメントを書く
昨今の補聴器はコードレスであるが、ひと昔前は本体を胸ポケットに入れてコード付きのイヤホーンを耳に挿す形であった。更衣のために外した補聴器がハウリング現象を起こしてぴいぴいと鳴るのである。分身である補聴器が更衣を疎ましく思って悲鳴を上げているように作者は感じた。下五は、衣更ふるとき・・で正調になるところをあえて「衣更ふるときに」と字余りに詠んだのは、何となく物憂い感じを出すための作者の意図である。推敲不足による字余りと意識してそうするのとでは全く別なのである。
- feedback
-
-
耳穴に入れる補聴器が普及していますが、高齢者には自分で調節できる首から掛けられるひも付きの補聴器が好まれます。着替えの時などは、やはりピイピイと悲鳴をあげてました。一心同体なんです。
大輪のゆるめば牡丹寧からず コメントを書く
やや峠を過ぎた感のある大輪の牡丹を観察してどことなく愁いを含んでいるように感じた。丁度見頃となった牡丹の花弁は、ほどよくバランスを保っていて安心感があるが、やがてその緊張がゆるみはじめると不安がただよいはじめ、ちょっと油断すると風のいたずらなどで一瞬に散華してしまう。大輪であればなおさらである。
- feedback
-
-
時間、雨、風、強い日差しにさすがの立派な牡丹も憂いてきます。
-
寧からず・・いい言葉ですね。色々な言葉の勉強になります。大輪の牡丹ほど寧からずの印象があります。先日の乙訓寺の牡丹はよく手入れされ白い牡丹は殊のほか美しくはかなげに見えました。
駈けてゆく駿馬に似たる卯波あり コメントを書く
卯波は陰暦四月(卯月)のころ波頭白く海面に立つ波のことである。潮と潮とがぶつかりあう潮目には複雑な波が立ちやすく、風の強い日には白波を超えて別の白波がたたら駈けしていくような豪快な沖風景に出会うこともある。その俊敏な波の動きから白馬が駈けていく姿を連想したのである。
- feedback
-
-
まるで馬のように白波が駈ける。ちょうど今頃の海ですね。
虻は空中をホバリングして自分の縄張りを見張っているという習性があるそうで、特に好天の日によく見かける光景である。牡丹園の宙に静止して飛んでいる虻を見てあたかも牡丹を護衛しているかのように感じた。もう一匹の虻が縄張りに入り込んできて頭突きの応酬があったことも考えられる。
- feedback
-
-
宙の虻がホバリング状態で牡丹を護衛していると捉えられた発想がうらやましい。虻にとってまさしく私の大事な牡丹なのでしょうね。
暴れ天竜とも呼ばれるほど流れの激しい天竜川には、5月のシーズンを迎えると渓谷を跨いであちこち鯉幟が掛けられる。固有名詞を句に詠む場合、その特色が一句の舞台装置として不動でなければいけないが、揚句の場合、暴れ天竜の雰囲気を借りて風に泳ぐ鯉幟の躍動感を連想させている。固有名詞の使い方としてよいお手本となろう。
- feedback
-
-
最近は川を跨いで掛けられた鯉のぼりをあちこちで見かけます。川風に気持ちよさそうに泳ぐ姿は、見ているほうも心が解放されます。大きな天竜川なら尚のことでしょう。
びしょ濡れの水車も春の光かな コメントを書く
春の訪れとともに疎水の流れもだんだんと水量を増し力強く奏ではじめる。その水をくみ上げる水車もまた掬い溢れた水をこぼしながら回るのでびしょ濡れ状態である。遠目に見る水車は、春日を弾いて輝き、飛び散る水が春光をまき散らしているのである。
- feedback
-
-
小屋につけられた大きな水車でしょう。びしょ濡れで水を弾き飛ばす勢いが感じられます。春がやってきんだなぁ・・と道端に佇んでおられるのでしょう。
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
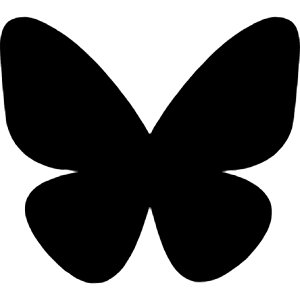 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()