2021年12月
目次
(ほほのはなしばらくありてかぜわたる)
朴は高木で大きな広葉のうえに宝珠のような花を掲げるので、地上から仰いだのでは見えにくい。揚句のような雰囲気を捉えるには、渓に咲く朴が見下ろせるような山峡の宿の窓からみた情景かと思う。あたりを払うかのような朴の花の孤高さに感動していると、一陣の微風が渓を駈けぬけた。その瞬間わななくように広葉が震えたけれども花は何事もなく泰然としていたのではないかと思う。その風はすでに其処にはなく渓の間遠へと去っていったのである。
シンプルに詠まれていて且つ具体的な描写である。朴の花でなくてはこの感興は得られないだろうと思う。余談になるが朴の花と云えば川端茅舎を語らずにはおれない。
朴散華即ちしれぬ行方かな 「ホトトギス」昭和16年8月号巻頭
茅舎は脊椎カリエスのため殆ど病臥の日々であった。ベッドから窓越しに見える位置に大好きな朴の木を植えてもらっていた。父が植えてくれた朴の木は、8年目にして初めて白い花を付けたという。揚句は茅舎最晩年の作で「毎日ベッドで眺めていた朴の花の姿がいつの間にかなくなってしまった。朴の花はその生命を終えてしまったのであろうか。」という句意である。
うつぎ解にあるように咲いては閉じる花の命は三日ほどで、落花はせず花の形のまま広葉の上に朽ちて錆びるという。花の一部始終を見ていた茅舎に、ある日ベッドの視界から花が消えていた。「即ちしれぬ行方かな」は茅舎自身の姿を重ねた写生かもしれない。
示寂すといふ言葉あり朴散華 高浜虚子
亡くなった当日に虚子が詠んだ茅舎への弔句である。「示寂するという言葉がある。仏道修行を貫徹した高僧の入寂のことである。病苦のなかにあっても倦まず弛まず句修業に励んだ茅舎の死もまた示寂である。いま朴の花が散華して茅舎を供養しているだろう。」というような句意であろう。茅舎は闘病10年、『朴散華』の句を詠んだ年、昭和16年7月17日に自宅にて永眠。享年満44歳であった。
- 合評
-
-
朴の花が開いている時間は短いけれども、吹き渡る風はさわやかである。この風と花をもうしばらく味わっていたいものだ。 (素秀)
-
朴の花は2,3日で錆びたようになり凋んだり散ったり、だが今日の花はまだ清らかに大きな杯を青空に掲げている。五月の心地よい風が香りも運んでくるようだ。 (うつぎ)
-
朴の花が夏の季語。朴の花は散らずにしぼむというが、一陣の風に耐えきれずに花のまま落ちてしまったのだろうか、それともまだ持ち堪えているのだろうか。この句は、落ちてしまった花がまだ持ち堪えているときの状態、朴の花と初夏の風とがせめぎ合っている暫時を切り取っているように思われる。 (せいじ)
-
朴の花が一日ほどで散ってしまうことを知っている作者は、咲いている花の命の儚さを愛おしく思っているようです。枝先にまだ残っているのか、散ってしまったのか、どちらにしても優しく渡る風の中でのささやかなひとコマです。 (あひる)
-
「朴の花」が初夏の訪れを告げるように咲きました。開花すると一日ほどで散ってしまう短いいのち。朴の木は樹高があり大きな葉に隠れて咲くので、人の目線では花に気づかないこともあるのですが、風に運ばれてくるうるわしい香りに作者は捕らえられたのではないでしょうか。「暫くありて」に貴重な出会いに感謝する心を感じました。 (むべ)
-
朴の花は寿命が短いようです。鮮やかに咲いた白い大きな花も吹き渡る風に散ってしまったのでしょう。 (豊実)
(はなびえのやみにあらはれかがりもり)
「花篝」という季語があり、夜桜の風情を引き立てるため花の下でたかれる篝火のこと。ゆらめく炎に照り映える花の姿は凄艶かつ幽玄を極めるという。
いまどきはライトアップが主流で揚句のような風情が体験できるところは少ない。火勢の弱くなった篝に薪を足すために目立たないように闇の中から現れた篝守の姿を写生した句であるが、「花冷えの闇に」という措辞が心憎い。しかしここでは桜も花冷えも脇役、寒々しい闇を切り裂くようにゆらぐ篝火の幽玄さとその影に紛れて黒子のように奉仕している火守人の姿に深い感興を覚えたのである。学ぶべきは「篝守」とすることで篝火をも連想させている点であろう。
- 合評
-
-
夜桜は昼とは違う風情があるがよく冷える。不意に影法師となって現れたのは篝守、薪を足し勢いを得た篝りはより花を浮かばせ美しい。花だけではなくすべてが美しい。 (うつぎ)
-
「花冷え」という季語から、桜は咲いていますが空気が冷え込む夜を想像しました。闇にふいに現れたのは、松明を持った篝守。篝火は大きく燃えて夜桜を映します。パチパチと薪がはぜる音も聞こえてきそうです。 (むべ)
-
最近はそうでもありませんが、夜桜は結構寒かった記憶があります。花篝は風情もありますし、つかの間の暖も取れたのではないでしょうか。 (素秀)
-
今ならライトアップをするのでしょうが、揺れる篝火はもっとしみじみと、夜桜のいろんな表情を見せてくれそうです。そして、そこには消えやすい篝火を守る人も居るようです。闇の深さに配慮したり、火が消えていないかと気にかけたり、そんな人の心も夜桜を味わい深いものにしてくれます。 (あひる)
-
夜桜を楽しんでいるのですね。ゆらゆらと燃える松明の光に浮かび上がる桜には風情がありますね。 (豊実)
-
花冷えが春の季語。寒さが戻って冷え込んだ夜の花見、暗くて花が見えないなあと思っていると、人が突然あらわれてびっくりしたが、その人は花篝の世話をする人であった。花冷えの中、こうして花見客の世話をする篝守への感謝の気持ちも漂わせている。 (せいじ)
(ぐぼうじのさかおりくればとりあわせ)
鶏合は雄鶏どうしを闘わせること。昔宮中で上巳の日(三月三日)に鶏を闘わせたことに因んで春の季語となっている。弘法寺(ぐぼうじ)は、千葉県市川市真間山にある日蓮宗の本山。この地域は畜産ことに養鶏が盛んなことでも全国上位に入る。お詣りをすませ弘法寺のある真間山からの坂道を下りてきたら地元の人達が人垣をなして騒いでいるのに遭遇したのである。人垣越しに覗いてみると鶏合であった。さすが鶏どころだなと合点したのである。
この句が詠まれたのは昭和初期、動物愛護が叫ばれる現在とは時代が違うがにわとりの産地でもあるここでは賭事としてではなく生産者同士のスポーツ的な春の行事として行われていたものと思いたい。でなければ季語が効かないからである。また固有名詞が詠み込まれている作品には何らかの意図があるはずなので、下調べしてその土地の風土にも思いを馳せて鑑賞すると的が絞りやすい。逆にいうと意図もなく安易に固有名詞を詠むことは戒めたい。
- 合評
-
-
殺生を罪とする仏教寺院と血が出るまで戦わす闘鶏場余りにも対照的です。参詣者も鶏合を覗いていたかも知れない。人間は勝手なものだ。 (うつぎ)
-
「鶏合」は闘鶏、春の季語。もともとは陰暦3月3日の宮廷行事だったものが、庶民の間では賭事として定着したようです。坂上にあるお寺から参拝を終えおりてくると、闘鶏が行われていて、賑やかに掛け声など聞こえたかもしれません。庶民の暮らしが生き生きと伝わってきました。 (むべ)
-
今では天下泰平を祈願する神事としている神社もあるようですが、鶏合(闘鶏)は血の飛び散るような激しい闘いのようです。すぐに賭け事と結びつけて考えました。わが家の近くの男山には石清水八幡宮がありますが、坂の下には遊郭の名残の街並みがあります。石清水坂下り来れば花街かな・・と真似してみました。 (あひる)
-
鶏合が春の季語。坂の上はお寺の清浄な空間、坂の下は闘鶏による賭け事の場、聖と俗が坂によって結ばれているところが面白い。参詣で有名な寺社には遊興施設はつきものであるから、さもありなんと思ったのかもしれない。70歳を過ぎた我が身なれど、なお雄鶏の闘志にあこがれる。 (せいじ)
-
お寺に続く坂道を降りてくれば闘鶏に興じる人たちが。先ほどまでの清浄な心持ちがたちまち俗な遊びに傾いていくようです。 (素秀)
-
真言宗の教えを広める弘法寺の静と俗世間の荒々しい鶏合の動にギャップを感じたのではないでしょうか? (豊実)
ひざまづき蓬の中に摘みにけり コメントを書く
(ひざまづきよもぎのなかにつみにけり)
文法に忠実に詠むなら「ひざまづき蓬の中に蓬摘む」になるでしょうね。下五の「蓬」を省略して「摘みにけり」としたことで余情たっぷりの詩になっています。一面に生えた蓬原にひざまづいて蓬を摘んでいるのだろうということはすぐにわかりますが、「蓬の中に」とは言えそうでいえない表現です。蓬摘みの主人公をズームアップで捉えていた画像を徐々にズームを引いていくと広い蓬原が展け、そこにひざまづいて虜のようになっている絵が見えてきそうです。
むべ解にある「けり」ですが、〔…た。…たそうだ。…たということだ。〕と明確に断定する場合と〔…だった。…だったのだなあ。…ことよ。〕と余情を込めた詠嘆の意とがある。俳句では後者の用例が多く揚句も同様と思う。句意は明快ですが、一人称として「たった一人で」ともとれますし「複数の子どもたち」を写生した三人称のようにもとれます。素十さんの句だとわかっているのでひょっとすると奥様の様子を遠見してそれを一人称で詠んだのかもしれないです。
- 合評
-
-
田舎で蓬餅を作るのに蓬を摘んで来るのは子供の役目でした。群がって生えているところを見つけ座り込んで摘んだものです。この句も沢山広がっている中に跪いてと取れますが同時に蓬の香りが立ち籠めている中とも取れる気がする。 (うつぎ)
-
あちこちと探さなくてもいいのでひざまづいて蓬摘みに専念している。蓬の香りに包まれています。 (素秀)
-
歩きまわって摘まなくても、ひざまづけば周りにふんだんに蓬が萌え出ているようです。蓬を摘むと言うのではなく、蓬の中に摘むというひとことで、蓬のひんやりとした感触まで伝わります。 (あひる)
-
「ひざまづき蓬の中に」という措辞で、広々とした春の野一面に蓬が萌え出た光景が浮かびました。上五と中七で空間が広がり、下五で作者が夢中で蓬摘みをしていた姿が想像できます。「けり」は過去の詠嘆なので、作者が子どものころ、もしかしたらすでに世を去った家族との蓬摘みを懐かしんでいるのかなとも思いました。 (むべ)
-
蓬が春の季語。ふと、蓬を摘ませてもらっているという感覚になったのではないだろうか。「蓬の中に」がうまいと思う。春の到来を喜び、大自然に感謝する気持ちが素直にあらわれている。 (せいじ)
-
蓬の若芽を摘もうと、ひざまづいて夢中になっていると、気がつけば蓬の中に埋もれてしまった自分がいたのでしょう。 (豊実)
(ひひらぎのはないつぽんのかをりかな)
よい教材だと思うのでこの作品から学ぶべきポイントを探ってみましょう。
木犀の花一本の…、蝋梅の花一本の…、白梅の花一本の…
香りに特徴のある花木なら何でも意味が通りそうです。「柊」でなければ駄目という要因を探求しなければこの作品は「季語動く」になってしまいます。斯く云う私も自信はありませんが…
上に揚げたものは共通してまず花が目立つので気づいて近づいていくと良い香りがするというものです。
では柊はどうでしょう。葉隠れに咲く小米のような花で目立ちません。霜が降りていたり小雪を被っていたりすると全く気がつかないでしょう。枯れ庭を散歩していて、ふと一隅の仄かな香りに気づき近づいてみると楚々と花を付けた一本の柊が芳香を放っていた…という状況ではないでしょうか。作者もそうしたプロセスで花柊と出会い、その一期一会の感興を「花一本の香り」と詠んだのではないかと思います。
たった一本の香りが庭全体を統べている…と解釈した記事もありましたが、皆さんの合評のとおり仄かな香りなので一寸違うのではと思います。柊の香りが一本の線のようにスーと臭覚に届いたのでは…という、うつぎ解は面白い連想ですね。「一本」の 'よみ' は「ひともと」でもいいと思います。ひともと…と読ませたい時は「一と本」と表記する人もいます。
- 合評
-
-
「柊の花」は冬の季語。実家にも成木がありましたが、たくさん花をつけていても、近づかないとわからないほどほのかな香りでした。一木全部で精一杯咲き、香っている自然の営みに、作者は感動したのではないでしょうか。 (むべ)
-
柊の花は奥ゆかしい花です。とけとげの葉の奥で自己主張をしません。仄かな香りは撒き散らすのではなくスーと一本の線となり匂ってくると感じられたのでしょう。花と心を通わせての言葉だと思う。 (うつぎ)
-
金木犀ほど強くはありませんが柊も似た香りがします。わずかな芳香に花一本としたのかと思われます。 (素秀)
-
寒々とした風景の中で、柊の花が目立たずとも、澄んだ香りを放っています。この一本の木から流れ出る静かな香りに、人の心も動き始めます。 (あひる)
-
柊の花が冬の季語。柊の花は目立たないが芳香があるのでそれと分かる。冬枯れの中、柊一本が気を吐いている。 (せいじ)
-
その場所は何もない寒さを感じる静かなところだが、花の香りが漂っていた。その香りを辿ると、一本の柊の木に花がひっそりと咲いていた。 (豊実)
(ただよへるてぶくろのあるうんがかな)
戦後になり鉄道などの新しい交通体系が発達し運河は人々の生活から離れ水たまりとなったり埋め立てられて道路になったり放置されて汚れているものもある。近年ようやく水辺環境の見直しと共に運河の持つ魅力を再認識する動きが出てきいる。
揚句の運河は時代背景からしてしっかり役目を果たしていたのでしょう。作業していた人が落とした軍手かもしれないし、子ども用とかの可愛い手袋かもし れない。感覚の鋭い作者は、寒風の吹く橋の上から運河を見下ろし、芥にまぎれて漂っている手袋を見つけて困っているであろう持ち主を思い、持ち主からはぐれて冷たい水に彷徨っている片手袋にも心を通わせて憐れみのような感慨に浸っている感じがする。
- 合評
-
-
運河に漂う「手袋」と言うだけで読者のそれぞれの感情を呼び起こしてくれます。片方の手袋だけが漂っていたかもしれません。持ち主はしばらく眺めた後悲しさと寒さをこらえて立ち去って行ったことでしょう。運河に漂う手袋だけで一編の小説を読んだような気がしました。 (よう子)
-
手袋が落ちているのを時々見ますが、落とした人は悲しいだろうなーと思います。落とされた手袋も淋しいだろうなーと、そんな筈はないのに思います。 (あひる)
-
手袋の例句で必ず出てくる句ですが、客観写生の究極にあるような句だと思います。大きな運河と卑小な手袋の対比で凍えるような冬の季節感を感じさせます。 (素秀)
-
「手袋」という季語ひとつで、人気のない寂れた冬の運河や、運河にかかる太鼓橋や、その上を渡る北風まで想像してしまいました。「漂へる」とありますので、作者はしばらく手袋を見つめていたのかなと思います。四半世紀前ですが、中国の蘇州という運河や園林のある街に約一年住んでいました。運河はいずれの季節も絵になるのですが、冬は格別でした。 (むべ)
-
手袋が冬の季語。町なかにある夕暮れの運河であろうか、手袋がひとつ漂っている。子どものものだろうか、軍手だろうか、はたまた、女性の手袋だろうか、いろいろと想像をかき立てられるが、運河に漂う手袋ひとつで冬さぶの趣きが深く感じられる。 (せいじ)
(たでのはなとよのおちぼのかゝりたる)
鑑賞は間違い探しではなく、よかった探しです。安易に季重なりと決めつけてはいけません。一方が主であることが明らかなときや同季の季語の場合は問題視しません。
この句の詠まれた時代にはまだコンバインは普及しておらず手作業で稲刈をしていたと思う。刈り役が数束づつ刈り取っては切り株の上に置きます。それを括り役が藁で縛り稲架にかけるのです。畦際で刈り取ったものは畦にもたせかけるように置くのでこぼれ落ちた稲穂が畦の蓼の花にかかっていたのでしょう。落穂は稲束を括るときや稲架にかけたりするときに抜け落ちたり持ち運ぶときに穂先がちぎれ落ちたりするもので、あまりに多い時は拾い集めたりもしますが通常は目こぼしして鴉や野鳩、雀たちが恩恵を受けます。あぜ道吟行でみつけたそれは、まるまるとよく太った籾をつけていたのでしょう。今年も豊作でよかったなと安堵しているのです。「豊の落穂」という詠嘆がにくいですね。
クリスマスなので一寸余談。むべ解にもあるように、イスラエルの律法には「落穂は貧しい人のために残しておき畑主が拾い集めてはいけない」とあるそうで、旧約聖書「ルツ記」には有名な下記の記述があります。
ルツはボアズの畑に行き、落穂を拾わせてもらい、姑ナオミの面倒を見た。畑主のボアズは、ルツのそうした姿を見て心を打たれ、ルツと結婚した。
ルツとボアズの子オベデは、ダビデとキリストの先祖に当たります。
- 合評
-
-
田圃の畦道に咲く蓼の花。その上に稲穂がおじぎして乗っかっている光景を思い浮かべました。中東では貧しい人が(米ではなく麦ですが)落穂を拾えるようにわざと少し残しておく習わしがあったそうですが、もしかして刈り残しがあったのでしょうか?有り余る豊かさを感じました。 (むべ)
-
稲刈りか脱穀も済ませたのかもわかりません。畦の蓼の花に落穂や藁屑がかかっている。豊な収穫を感じます。豊の落穂の言い方は覚えておきたいと思います。 (うつぎ)
-
蓼の花も当然満開なのでしょう。引っかかるように掛かった一本の落穂に豊かな秋を感じさせます。 (素秀)
-
この句の蓼の花は田圃の畦道に咲いていたイヌタデ(赤まんま)かと思います。その赤まんまの上に本当の米(落ち穂)が被さるように落ちています。ほんのちょっとした光景ですが、秋の爽やかで明るい風景が広々と見えるようです。 (あひる)
-
秋の句である。この句も季重なり。畦道の蓼の花に落穂がかかっている。豊作だったからそうなのであろう。よく見ている。「豊の落穂」の省略がすばらしい。小風景の描写によって豊作の喜びを謳い上げた感じがする。赤飯に似ている蓼の花と落穂との米粒つながりがまた面白い。 (せいじ)
-
これも季重なりですね。稲が豊作だったのでしょう。田んぼの畦に蓼の花が咲いていて、その上に落ち穂がのっかっていた。情景の主体は蓼の花かと思います。 (豊実)
(ゆゆけさやつきのうつれるかわぶとん)
それにしても素十俳句には複数季語が詠み込まれたもの多くて悩ましいですね。豊実解の通り「露」は物理的な季語ですが「露けし」は感覚的な季語として詠まれている例が多いです。朝日を弾く露は見事ですがすぐに消えてしまうので、<露の身・露の世・露の命>など、はかないものの譬えに詠まれることもある。革布団は夏の季語として詠まれた例句もあるが、揚句のそれは四季を問わず置きっぱなしの感じで「露けさや」と詠まれているので一句の季感としては初秋のころであろう。
使い込まれた革座布団は艶があるが鏡のようにくっきりと月がうつることはないと思うので「月光のうつれる」の意ではないかと思う。せいじ解にあるように端居処に夏の名残として置かれたままのそれか、大学の研究室などに頓着なく置かれているものであろう。白々と月光を弾いてあたかも露に濡れたように光っている革座布団に感覚的な「露けさ」を覚えたのである。季重なりとかの約束に縛られず自由に詠むおおらかさが素十俳句の特徴だと思うけれど、決して季感にブレが生じないように詠むことが重要なので初学の間は真似しないでおきましょう。
- 合評
-
-
革布団は余り家庭では使われないのではと思う、病院とか歯医者とか特殊な所を想像しました。革にぼやける月も白く冷たくもう秋だ、どことなく露っぽく心も晴れない。 (うつぎ)
-
革布団は余り家庭では使われないのではと思う、病院とか歯医者とか特殊な所を想像しました。革にぼやける月も白く冷たくもう秋だ、どことなく露っぽく心も晴れない。 (うつぎ)
-
革の座布団は見たことも触ったこともありませんが、ソファーなどの感触に近いと思えば何となくわかります。黒い革なら月の光も反射しそうです。そろそろ涼しさも感じられる初秋の雰囲気です。 (素秀)
-
革に月がうつるという状態を見たことがなく、戸惑いました。月が湿気を帯びた革座布団にぼんやりと白く反射していたのかなと思います。実際、見たことがあったとしても、俳句に詠むことはなかっただろうと思います。自然や生活の中で何かに気付くこと、心を動かすということ・・その大事さを改めて思いました。 (あひる)
-
「露けさ」「月」「革蒲団」と夏から秋への移ろいを感じさせる季語が三つあり、主季語は露けさととりました。窓の近くに置かれていた革製の座布団は表面がつるつるのいわゆるガラスレザーで、明るい月光を反射するほどです。座布団を触ってみるとしっとりと湿り気があり、まだ日中は暑いのですが、夜の涼しさにほっとして、秋の気配が漂います。 (むべ)
-
露(秋)月(秋)革蒲団(夏)と季語が三つあるが、季節としては初秋ではないかと思う。端居のためか、革製の座蒲団をそのまま縁側に置いていたのだろう。その座蒲団に秋の月が映っている。夜露に濡れて湿っぽいことよ。「露けさや」の詠嘆が季節の移り変わりの早さも含意しているように思われる。 (せいじ)
-
露は早朝の現象なので、この月は朝の月かなと思いました。革蒲団は縁側にでもあるのかもしれません。 (豊実)
打水や萩より落ちし子かまきり コメントを書く
(うちみずやはぎよりおちしこかまきり)
蟷螂の生涯を調べました。秋に産み落とされた泡状の卵はそのまま冬を越して翌年の4〜5月ごろ初夏の兆しが感じらる暖かい日に孵化します。大きさは5mm〜10mmぐらいで薄茶色、翅はまだ生えてないとのこと。体の小さいコカマキリ(小蟷螂)という種類もあるようですが、揚句は「子かまきり」なので孵化後の心もとないミニサイズのものでしょう。梅雨明けくらいまでは幼虫のままだそうです。
鑑賞に戻ると、この時期の萩は、ようやく丈を伸ばし枝先の眠り葉が目覚める頃で花も蕾もついてないので季語としては働きません。打水を兼ねて庭木にもシャワーしていたら萩叢に紛れて気づかなかった子かまきりが水の勢いに負けてぽとりとこぼれ落ちたのです。「お〜、ごめんごめん。頑張れよ!」とエールをおくる気分なのでしょう。
共食いするので知られる蟷螂は、幼虫といえども肉食なので萩の若葉に寄ってくるアブラムシなどを捕食して成長するのだと思います。夏の間に何度か脱皮を重ねて成虫になります。冬眠はしないそうで秋の繁殖期を経てやがて枯蟷螂となり生涯を終えます。百姓の家庭で幼い頃を過ごした素十さん、小動物の生態にも精通していたのでしょう。季感は打水ですが健気に生きている小動物の生命を写生した句ともいえますね。
- 合評
-
-
打ち水が萩にかかり水の勢いで落とされたのか水に滑ったのかかまきりの子が落ちてきた。素十師が句にしない筈ないですね。主季語の打ち水、萩の玉雫、子かまきりの汚れのない浅みどり、どれからも夏の涼しさを感じます。 (うつぎ)
-
「萩より落ちし」は子かまきり修飾しているので、打ち水と子こかまきりの取り合わせかなと思います。また「や」で切れているので打ち水が主役かなと思います。子かまきりは打ち水による涼の演出の脇役といったところでしょうか? (豊実)
-
打ち水をしたら萩の生垣からかまきりの子が落ちた、見たままを句にしています。や、と切っていることでも主季語は打ち水だと思います。晩夏か初秋かまだ暑い盛りに打ち水をしたら、かまきりの子が現れて少しですが秋の気配を感じているようです。 (素秀)
-
季語が三つ、恐れなく?入っていて、自由だなと思いました。打水も萩も子かまきりの映像をはっきり見せてくれる欠かせない役割かと思えます。写真というより、動画のようです。 (あひる)
-
季語が三つあり、夏と秋が混在しているが、季節としては萩が咲きはじめる9月はじめ、まだ暑くて打水をする頃、かまきりが生まれる頃ではないかと思う。かまきりは生まれるとすぐに斧をふりかざすというが、水を打たれて萩から落ちた子かまきりが斧をふりかざしているところを想像するとまことに愛らしい。 (せいじ)
-
「打水」「萩」「子かまきり」季語をいずれととれば良いのかわかりませんでした。切れ字「や」につながる打ち水なのかもしれませんが、打ち水によって地面に落ちてしまった幼いかまきりに「ああ、大丈夫?ごめんね」という温かい視線を感じ、最後まで読むと子かまきりが主役なのかなと思いました。 (むべ)
(つまつれてへいさうちやうやはなぐもり)
一人称の句と見るか三人称として捉えるかで鑑賞が分かれますね。もちろんどちらが正解ということはありません。三人称の句として連想を広げていくと一篇の短編小説が書けそうです。でも制服や徽章から階級の判別はできたとしても同伴の女性が妻だと断定するのは難しいかと思います。また当時の世相からしても休暇中とは云え軍服のまま奥さん同伴で花見にでかけるのはかなり勇気のいることではなかっただろうかとも。ということで私もうつぎ解同様に一人称で鑑賞してみました。一人称で連想してみるとシンプルでわかりやすく思わず笑ってしまうような状況が見えますね。「花ぐもり」はちょっと気恥ずかしいという作者の気持ちの代弁ではないかと思う。誤解を避けるためには「妻つれて曹長然や花ぐもり」とする手もあったと思うがそんなことを気にしないのが素十俳句だと思う。
- 合評
-
-
兵曹長は旧海軍の少尉の下、上等兵曹の上に位置する階級だそうです。下士官を束ね、ふだんは厳しい印象のある立場の方が、奥様を連れてなんだかちょっと照れ臭そうにしている光景が浮かびました。海軍省軍司令部は千代田区霞が関にあったそうで、「花ぐもり」の桜はなんとなく皇居のお堀の桜かなと思いました。 (むべ)
-
奥様を三歩後ろに連れられちょっと得意気です。曹長の様に胸を張り肩をいからせ威厳を示そうとしています。滑稽味もあります。花曇りとはいえ明るさも感じます。 (うつぎ)
-
兵曹長や、と強調していますから二人連れで花見をしているのを見て少しびっくりしたのかと思います。兵曹長と判ったのも軍服を着ていたから。兵役の合間のつかの間の休日だったのでしょう。 (素秀)
-
花ぐもりが春の季語。一読、戦前の花どきの靖国神社が頭に浮かんだ。伝聞でしかないが、兵曹長はたたき上げの兵のトップで、かなり威張っていたらしい。妻は数歩後を歩いているのではないだろうか。花ぐもりの何となく気の塞ぐような季語がよく合っていると思った。 (せいじ)
-
いつもは威張っていて近づき難い兵曹長が、妻を同伴している。この人にも家庭があり、夫という立場もあるのだと、ふとその心を垣間見た時の句かと思いました。花ぐもりという言葉に、兵曹長の内に秘めた憂いとやさしさを感じました。 (あひる)
-
奥様といっしょに亡くなったお父様の墓参りに行ったのかと思います。花ぐもりのように、お父様への何かすっきりしない気持ちがあるのかもしれません。 (豊実)
(らうかんのよこたはるありよるのうめ)
「横たわる老幹」と言われると臥龍梅ですね。でもなんで夜なの?たまたま夜だったかから?一瞬悩みましたがすぐわかりました。そうです「白梅」であることを暗示するための「夜の梅」なのではないだろうかと。日本文学には「夜目にも白く」の用例が多く合評にもあるように今や慣用語です。素十がそこまで計算づくで詠んだとは思わないのですが悔しいくらいよく効いています。おそらく樹齢数百年というような老幹なのでしょう。地に臥して朽ち果てたような幹から徒長枝をだし、白々と花を咲かせ、清楚な香りを放っている老梅に生命の尊厳を感じたのではないかと思う。臥龍梅は全国各地にあり名所となっているものも多い。
- 合評
-
-
夜目にも梅の木はよく見えているようです。老木の横に伸びた幹に立ちあがる花は白梅でしょうか。 (素秀)
-
最大限に省略されている句です。苔生す古木の臥龍梅でしょうか。夜目にも白い花が浮きたち佳い香りを放っています。(うつぎ)
-
「梅」が季語。作者は夜の観梅に出かけたのでしょうか。「横たはるあり」という措辞が、梅の木の存在感をよく表していると思います。梅の花の色は白かったのでしょうか、遠目には闇に浮かぶように見え、近づいてみると思いがけず幹の形が特徴的で、木肌も老木であった……という驚きのようなものも感じました。 (むべ)
-
昼ではなく夜の梅であるところに味いがあると思いました。老木のずっしりとした横たわる幹に静かな貫禄があります。 (豊実)
-
実家の庭に老幹が横たわった見事な白梅があり、2月に生まれた私は、祖父により梅見ちゃんと名付けられそうになりました。母が必死で反対して博美になったそうですが、夜も芳しい香りを放っていたその梅を思い出しました。 (あひる)
-
梅が春の季語。夜の梅園は芳しい匂いを放っている。梅の木がたくさんある中に老幹が横向きになった古木もあって目に留まった。夜の梅は匂いの世界。姿かたち、樹齢は関係ない。しかし、この梅の木はよく頑張ってるなあ、と思う。「横たはる」に古木に対する優しいまなざしを感じる。 (せいじ)
(しゆんすいやじやかごのめよりげんごろう)
春水と源五郎という二季の季語が詠み込まれているが、この句から「啓蟄」を感じないだろうか。雪解けで嵩を増した水が高く積まれた蛇籠の裾をひたひたと濡らしはじめたのを見て「春水や」の詠嘆になったと思う。源五郎は泥土の中に潜って冬眠するとのこと、温んだ水に目を覚ました源五郎が蛇籠の目から寝ぼけ気味にひょろひよろとでてきたという図式ではないだろうか。季節に敏感でない俗人にはただの報告にしか思えない作品かもしれないが、私達俳人は、啓蟄の感興あり、水温むの感興あり、のどかな春の里山の景や人々の営みの様子まで見えてきそうなこの作品に大いなる感動を共感するのである。
- 合評
-
-
水にも生き物にも春の息吹が感じられます。蛇籠の目が楽しいですね。こんな所にいたのか、恰好の場所じゃないかと作者の声か聞こえて来ます。 (うつぎ)
-
観察と発見の句でしょうか。細かいところに気がつくかどうかだと思います。ゲンゴロウが網目から顔を覗かしただけですが、春が立ち上がってくるようです。 (素秀)
-
春水が春の季語。蛇籠という言葉をはじめて知ったが、水嵩を増した春の水に蛇籠も水に浸かっていて、その網目から源五郎が出てきたところを捉えたのであろう。春の到来を喜んでいる趣きがあり、源五郎は夏の季語であるが、この句では春水の引き立て役になっている。 (せいじ)
-
春になって水も温み、蛇籠の目から源五郎が這い出してきた。この源五郎は陸を歩いているのかもしれない。素朴な自然がいいなあと思いました。 (豊実)
-
蛇篭がわからず調べました。護岸や土留めに用いられ、竹網や金網に砕石を詰め込んだものとのこと。砕石の間を雪どけの水が流れ、出口の網目からけっこう勢いよく出ているのではないでしょうか。あれ、源五郎が一緒に飛び出してきました。水がきらきら光っています。 (むべ)
-
蛇籠とは、河川の護岸工事などで斜面を補強するために、竹や鉄線で編んだ長い籠に砕石を詰めたものとのことです。その砕石の間に潜んでいた源五郎が温んだ春の水にちょろりと出てきたようです。たいして変化の無さそうな自然の中にも、作者がじっくりと目を注いでいることがわかります。 (あひる)
(みおひいてはなるゝひとつうきねどり)
俳句は17文字という制限ゆえに助詞や接続詞、時には主語までもが省略されることが多く文法的に理解しようとすると脱線しがちです。それを補ってくれるのが季語の働きでもあるのです。季語の本質を理解しそれを踏まえて鑑賞することが必要なのです。浮寝鳥を歳時記で調べると、
毎年越冬のため、日本に渡ってきて川や湖沼で一冬を過ごす水鳥の群れ。鴨・雁・白鳥などが水面に浮かんで眠るさまをいう。
とあり、基本的には群れを意味します。「離るる一つ」の措辞は「群れから離れる一つ」の省略形、つまり one of them ですね。従って揚句は、「浮寝の群れから水尾を引きながら離れようとしている一羽がいるよ」ということになります。
水尾は船の航跡の場合は「水脈」と書きます。いづれも進もうとするときに後方に生まれるものなので自分の意志で進んでいるのである。二羽なら恋路かもしれないが一羽なので「あれ、どうしたんだろう」という感興を覚えたのである。一羽といわず「一つ」と言ったのも「夕鴨の二つ三つ」の句のうつぎ解にあるように少し離れた景であることを暗示していて「点の集団から離れようとていく一つの点」を数えた「一つ」である。
『どんな群れにも変わり者はいる』という、うつぎ解に天国の素十師も呵呵大笑拍手を送っていることであろう。
- 合評
-
-
寝ている鴨の群をじっと見ていたのでしょうね。急に泳ぎだした一匹に注目して詠んだ句かなと思います。 (素秀)
-
眠った鴨が水尾をひくだろうかと、不自然な感じがしました。たぶんそうではなく、浮寝鳥の群れから一羽の鴨が目を覚まして、ちょっと自由行動に出たのではないでしょうか。鴨にも意思があるのだと思うとかわいいです。 (あひる)
-
浮寝の群れを離れようとしている一羽、流されているのではなく水尾を引いて泳いでいるのだ。どんな群れにも変わり者はいる。作者は驚きとユーモアを以て眺めているのではないだろうか。 (うつぎ)
-
何故か群から抜け出した一羽の鴨。泳ぎながら浮寝鳥の姿勢になり、惰性ですーっと水尾をひいている。寒い池の風景かと思いました。 (豊実)
-
「浮寝鳥」は冬の季語。場所は湖か池か、一羽が眠りながら漂い、すーっと群れから離れていく光景が浮かびました。草も枯れ木々も葉を落とし、冬の静けさに包まれるような気持ちになりました。 (むべ)
-
浮寝鳥が冬の季語。浮寝鳥が流されて一羽だけ群れから離れてしまった。浮寝鳥が水尾をひくというのはあまり見たことがないが、一陣の強い風に煽られてかなりのスピードで流されているような印象を受ける。一匹の羊を探す羊飼いのように、一羽の浮寝鳥を心配そうに見守る作者の優しさを感じる。 (せいじ)
流灯に下りくる霧の見ゆるかな コメントを書く
(りゆうとうにおりくるきりのみゆるかな)
加代子さんの句にも霧と花火の取り合わせがありましたね。霧はいつも良き脇役を演じてくれます。流灯は、盂蘭盆 (うらぼん) の16日の夜、灯火をともした灯籠 (とうろう) を川などに浮かべて流し、お盆に帰ってきた魂を見送る宗教行事です。出発は川であることが多く帯状に流れ出たそれは、やがて広い海へと散らばっていきます。みなさんの合評にあるように、ゆっくりと降りてくる霧に浄土からさしのべられた迎えの梯子のように感じたのです。ふとヤコブの梯子、天使の梯子を思い浮かべました。これは旧約聖書創世記28章12節の記述に由来します。ヤコブが夢の中で、雲の切れ間から差す光のような梯子が天から地上に伸び、そこを天使が上り下りしている光景を見たとされる箇所があり、このことからやがて自然現象もそのように呼ばれるようになったようです。現代人の感覚ではやや観念的に思うかもしれないですが、この句の詠まれた時代背景を考えると納得でしょうかね。
- 合評
-
-
川での精霊流しを想像しました。折しも発生した川霧が灯籠の灯りをより仄かにしあの世へと魂を誘っているように見えます。霧は特別な効果をもたらしていますが季語は流灯だととりました。 (うつぎ)
-
流灯と霧はどちらも秋の季語ですが、霧が主役だと思います。「下りくる」で、今まさに流灯に霧が迫ってきている情景が見えます。 (豊実)
-
灯籠が流れる様子は幻想的です。霧もまたゆっくりと流れたり下りてきたり幻想的な動きをします。この二つのものが融合しそうな情景に、呆然と見入っている作者が浮かびます。 (あひる)
-
灯籠流しの光景。「下りくる」という言葉に、急激に霧がかかってきた印象を持ちました。霧が灯籠を包む幻想的な景色に、彼岸と此岸の境に立って、死者の魂が帰っていく様子を眺めているような、そんな光景ではないでしょうか。霧という季語がぴったりの句だと感じました。 (むべ)
-
流灯と霧ともに秋の季語ですがここは流灯が主季語で問題ないところ。流れていく灯籠を川霧が追いかけて次第に見えなくなる様子を、この世とあの世を分ける境と見たのかも知れません。 (素秀)
-
流灯が秋の季語。盆の終る16日の夕方、灯籠を海に流していると、流れ行く灯籠の彼方に夕霧がかかり始めた。「見ゆる」とあるので、かなりの速度で霧がかかり始めたのではないだろうか。「流灯に下りくる」という表現が、来迎図のような雰囲気を醸し出している。 (せいじ)
(よのいろにしずみゆくなりおおぼたん)
色の概念は基本的に二次元だと思うので「夜の色」といわれると違和感がある。「夕闇に…」ならわかりやすい。けれどもこの色は「大牡丹」にもかかっているのではないかと考えてみた。ここにもまた時間をかけて艶やかな大牡丹と対峙している作者の姿がある。やがてその大牡丹の色は夕闇と同化するかのように ゆっくりとフェードアウトして沈んでいく…ゆえに「夜の色」なのかなと。さらに、ほとんど見えなくなるまで佇んで居たのではないかと思わせる余韻も伝わってくる。私の先生である紫峡師は瞬間写生の人であった。時間の経過を詠むと句が弱くなると教えられた。しかしこの作品にはそんな弱さは感じない。
- 合評
-
-
昼はあでやかな大牡丹であっても夜は暗さに飲み込まれるように姿を無くして行く。その違いに心を動かされたようです。 (うつぎ)
-
夜の帳が降り辺りはすっかり暗いのですが、作者の目には大きな牡丹が見えたのでしょうか。日中太陽光のもとで見る女王の風格とはひと味違う牡丹の姿に、黄泉の国に迷い込んだように錯覚したかもしれません。 (むべ)
-
日が暮れて段々見えなくなる牡丹の花を夜に沈むと表現しています。夜の色は漆黒でしょうが牡丹の花はますます重たくなるように感じられます。 (素秀)
-
大牡丹と言えども、夜の闇には沈むしかありません。けれども、沈んだとしても流石に大牡丹、消えてしまうことはなく、まだ幽かに花の姿を見せているようです。またまた、牡丹と沈む (あひる)
-
夜の色とはなんだろう?夜のネオン街か?街灯が灯る公園か?自宅の庭の夕暮れか?いずれにしても、牡丹の花は大きいので、沈みゆくとは言え、消えてしまうのではなく、暗くなってもまだ見えている牡丹を楽しんでいるのだろうと思います。 (豊実)
-
牡丹が夏の季語。夜色ではなく夜の色なんだと思った。大きな白い牡丹の花が夜のとばりに包まれて色を失っていく。夜の深みに沈潜するかのように、多彩な色のある世界から夜の色の世界へ。「沈みゆくなり」の断定的な詠嘆に、あらがうことのできない大自然の営みを感じる。 (せいじ)
(まつしろにゆくてうづめてやまこぶし)
最近は街路樹や公園樹として園芸種のものが増えてきているのでややこしいです。季語として詠まれるものは「田打桜」とも呼ばれる山辛夷のことで「辛夷かな」と詠まれていても山辛夷のことである作品が多いです。この句の生命になっているのは「行手うづめて」の措辞です。普通なら「真白に山路うづめて花辛夷」としてしまいそうですが、「山辛夷」で山道であることを暗示し、「行手うづめて」とすることで作者と辛夷とに少し距離があることがわかります。そして下り坂なら「うづめて」の感興は無理だと思うのできっと上り坂だと思う。ただそんなふうに綿密に考えて推敲されたのではなく虚構のない素十の写生眼だと思うのです。対象物をよく見て心を通わせる…という写生の基本を教えられる作品だと思う。私の大先輩に次の作品がある。
出現の聖母をおもふ辛夷かな 佐久間慧子
早春の山路であたりを払うようなに真白な辛夷と出会ったときに、ふと迫害の聖徒達に現れたという聖母マリアの姿を重ねたのである。街路樹の辛夷を見て安易に句に詠んでも季語の本質から外れがちになる。花木や草花を詠むときは自然環境での特徴(季語の本質)をよく学んで使うように心がけないと季語が動いてしまうことになる。
- 合評
-
-
山辛夷は田打桜ともいわれ花が咲けば田を耕すころと昔の人は目安にしていたとか。真っ白に咲いた辛夷は遠目にもよく目立ちます。山里の早春を感じているのでしょう。 (うつぎ)
-
辛夷が春の季語。琵琶湖西岸の高速道路を北上すると真っ白な辛夷の花が行く手の山の斜面を覆うように咲いている。その景色をなつかしく思い出した。清潔感のある気持ちのよい句である。 (せいじ)
-
琵琶湖の西の山々に自生した辛夷の花を何度か見たことがあります。春先、まだ寂しげな山のあちこちに、たくさんの純白の花が咲き誇っていました。辛夷はやはり白を詠わなきゃと思うほどです。この句でその白をとても懐かしく思い出してしまいました。 (あひる)
-
「辛夷」は街中でもよく見かけますが、こちらは北辛夷とも言われる「山辛夷」ですので、作者は山道・岨道を歩いているかもしれません。辛夷より花や葉は一回り大きく樹高も高そうです。歩いている道の果ては、真っ白に咲き誇る山辛夷の花に呑み込まれている。少し遠くからの景色かなと思いました。 (むべ)
-
辛夷の花が満開の山道を進んでいるようです。散った花びらを踏んでいくのも憚れますが、春を満喫しています。 (素秀)
-
辛夷の白い花が美しい。行手をうずめるぐらいなので、山道の両脇に大きな辛夷の木があるのでしょう。 (豊実)
(このなかのあいぞうさびしてんかふん)
子育てを卒業されたみなさんがそれぞれの体験に照らして鑑賞されていたので楽しく拝見しました。一読心象句の匂いも感じるが、子の様子を冷静に観察しての写生句でもある。ところでこの句ネット検索すると「増殖する俳句歳時記」に記述があり興味深い鑑賞であったのでそのまま転載しておきます。
湯上がりの子供に、天瓜粉(てんかふん)をはたいてやっている。いまなら、ベビー・パウダーというところ。鷹羽狩行に「天瓜粉しんじつ吾子は無一物」があって、父親の情愛に満ちたよい句だが、素十はここにとどまらず、さらに先へと踏み込んでいる。こんな小さな吾子にも、すでに自意識の目覚めが起きていて、ときに激しく「愛憎」を示すようになってきた。想像だが、このときに天瓜粉をつけようとした父親に対して、子供がひどく逆らったのかもしれない。私の体験からしても、幼児の「愛憎」は全力で表現されるから、手に負えないときがある。その場はもちろん腹立たしいけれど、少し落ち着いてくると、吾子の「愛憎」表現は我が身のそれに照り返され、こんなふうではこの子もまた、自分と同じように苦労するぞという思いがわいてきた……。さっぱりした天瓜粉のよい香りのなかで、しかし、人は生涯さっぱりとして生きていけるわけではない、と。そのことを、素十は「淋し」と言い止めたのだ。「天瓜粉」は、元来が黄烏瓜(きからすうり)の根を粉末にしたものだった。「天瓜」は烏瓜の異名であり、これを「天花」(雪)にひっかけて「天花粉」とも書く。
- 合評
-
-
今ではあまり使われない天花粉は夏の季語。幼い子の風呂上がりに天花粉をはたきながらどんな会話をしていたのでしょう。幼いながらすでに他者に対する愛と憎しみを持っているとわかり、作者は人の持つ業のようなものの萌芽に静かなショックと言いようのない淋しさを感じたのでしょうか。 (むべ)
-
子供も機嫌によっては甘えたり離れたりするのではないでしょうか。天花粉をつけている時に母親の方が良いとか言われたように思います。 (素秀)
-
素十俳句は写生に徹底しているとの先入観があったので、驚きました。天花粉をつけてもらうほどの幼子の心に、怒りや妬みや憎しみのような感情を垣間見たということでしょうか。まだ人生は始まったばかりなのに、この子も愛憎という心を抱えて生きていくのだと、切なさを感じた瞬間だったかもしれません。 (あひる)
-
天花粉が夏の季語。子の中の愛憎とは何か。あせもにならないようにと湯上りの子どもの全身に天花粉を叩いてつけながら、可愛いわが子なれども、第一子の時よりも手を抜いているような、子どもに対する愛情に差があるような気がして、そのような己を淋しく感じたのであろうか。あるいは、おさなごの仕草からおさなごの心にもすでに愛憎が芽生えていることを発見し、淋しく思ったのだろうか。難しい句である。 (せいじ)
-
親と別れて施設に預けられた子供かなと思いました。お風呂に入って天花粉を塗ってもらったが、施設に馴染めず、親が恋しく淋さを募らせている。 (豊実)
ひるがへる葉に沈みたる牡丹かな コメントを書く
(ひるがへるはにしずみたるぼたんかな)
じっと腕組みをして牡丹と睨めっこしている素十の姿が浮かびます。牡丹の葉はさほど大ぶりではなく、花はみな枝先に咲くので好天であれば葉に埋もれるということはない。揚句の場合、時折吹いてくる強い風に重い牡丹の花を支えていた茎先が耐えきれずにうなだれて大騒ぎする葉の茂みに花が顔をうづめたのであろう。うち騒ぐ葉の中に花が埋もれたのをあたかも沈んだかのように見えたのである。軽薄に批評すると「他の花でも同じなので季語動く」といいたくなりそうだが、重く大輪の牡丹ならではの特徴を捉えていると思うので季語は動かない。
- 合評
-
-
風に牡丹の軸が傾き翻った葉が花を隠している。沈みたるは深く観察し花と心を通わせて得た言葉でしょうか (うつぎ)
-
牡丹は大きい花ですから風に揺れている様子を沈むと表現したのかと思います。 (素秀)
-
夏の季語「牡丹」が、強い風で裏返った葉に少し隠れるように咲いています。花容がすべて見えているのではなく、隠れている状態を詠むセンスがすばらしいと思いました。 (むべ)
-
牡丹が夏の季語。あの大きな牡丹の花が、一陣の風にひるがえった葉っぱの海に、沈んでしまったかのようであることよ。「沈みたる」がすばらしい。牡丹の花の沈下を介して初夏の風が主役に躍り出たような印象を受ける。 (せいじ)
-
初夏に咲く牡丹、いつもは花の邪魔にならないように?葉は垂れ気味に広がっています。この日は風が吹いて、花が隠れるほどに葉が騒いでいたのでしょう。沈みたる…は、なかなか思いつかない表現ですが、高貴で優雅な牡丹に似合うような気がします。 (あひる)
-
春の嵐が去った後でしょうか?翻った葉で半分ほど沈んでしまったが、大きく咲いた牡丹の花は美しい。 (豊実)
夜振の火くゞり出でたる小門かな コメントを書く
(よぶりのひくぐりいでたるみなとかな)
みなさんよく調べて鑑賞されるので、私自身が勉強させていただいている。普通は、夜振りの火の方を主役に詠んでしまうが揚句は「小門かな」と結んで小門を主役に詠んでいる点が非凡である。この詠法によって小門潜りでた夜振りの火が本流へ舵をとって進んでいったあとの余韻を感じるのである。GH初期のころよく支えてくださった志乃さんに次の句がある。
月の出に舫ひ解かれし小舟かな 志乃
月見船が出でゆく様子を詠んだこの作品も余韻たっぷりで雰囲気がとても良く似ていると思いませんか。瞬間写生でありつつ余韻が残る…私もそんな作品づくりを目指したいと思う。
- 合評
-
-
「夜振」は川漁(夜焚は海漁)の漁法とのこと。小門は狭い水門のことでしょうか。水路から川へ小門を通って舟が静かに滑り出ていく様子を、松明の火が「くゞり出でたる」で見事に表現していると思いました。 (むべ)
-
船を係留しているのは川かなと思いました。支流から本流に出ていく時に低い水門をくぐっていきます。潮の満ち引きによっては頭がギリギリの場合もあります。夜目には火だけが現れたようにも見えたと思います。 (素秀)
-
小門(せまい水門)と書いてある記事もありました。暗い水門からくぐり出てくる、漁のための夜振の火…、瞬間の一場面を見事に切り抜いていると思いました。 (あひる)
-
夜振、夜振火が夏の季語。小門を「みなと」と読むことを始めて知った。夜振は夜に松明などをともして魚を取る方法とのことであるが、夜振の舟が松明をかざして小さな港から闇をくぐり抜けるようにして出てきた、ということではないだろうか。火を主人公とし、漆黒の闇から火が「くぐり出でたる」と見たところが印象的である。 (せいじ)
-
鵜飼の船が小門から出漁する風景だと思います。火くゞり出でたるという措辞に火が小門に当たりそうな程の勢いを感じました。 (豊実)
(ゆうがもやふたつみつづゝみおあかり)
夕日が落ちたあとの微光に水尾だけがキラキラ光る様子はとても美しい。うつぎ解にもあるが「二つ三つ」とはなかなか云えない表現ですね。「づつ」とあるのでばらばらの複数ですね。肉食動物のエサとなる生物は群れを作ることで、少しでも食べられるリスクを減らしているそうだが、鴨が陣をなすのも例外ではない。揚句の夕鴨は陣を離れたあと思い思いに葦叢などへ退避するために移動をはじめているのであろう。
- 合評
-
-
夕暮れに鴨の群れもそれぞれの番に戻って散っていくようです。群れから離れていく水尾が2本だったり3本だったり夕陽に光っています。 (素秀)
-
二羽三羽ではなく二つ三つと数えているのは距離のある上から眺めているように思う。次々と夕日を浴び水尾を引きながら塒に向かっている明るい夕景である。 (うつぎ)
-
冬、夕暮れの鴨はどことなく寂しいです。水尾に月の明かりか、街の明かりが反射し、鴨自体はシルエットになっているのかも知れません。鴨も作者も、そろそろ塒に帰る頃でしょう。おやすみなさい。 (あひる)
-
鴨が冬の季語。長浜城の近くの琵琶湖畔で夕暮れの鴨の群れを見たことがある。この句は、そのような夕暮れの鴨たちが作る情景の一つであろう。陣を崩した鴨たちが、二羽、三羽となって、水尾を引いて離れて行く。絡み合った水尾が冬の落暉に映えてやさしく煌めいている。無駄な言葉が一つもない。 (せいじ)
-
池に多くの鴨がいるが、二羽か三羽ごとにわかれて静かに寝床に着こうとしている。鴨の水尾が夕日に光っている。 (豊実)
秋風やくわらんと鳴りし幡の鈴 コメントを書く
(あっかぜやくわらんとなりしはたのすず)
「ホトトギス」虚子選初入選となったこの句、大正十二年の成田山参詣の際に詠まれたものです。あひる解の通り、秋桜子が添削したと伝えられています。榠櫨(くわりん)と同じ発音なので、声にするときは「からん」と読みます。幡の鈴というのは、うつぎ解のとおり。「ばんのすず」と読むほうが正しいのかもしれません。からんからん…と鳴り続いているのではなくて一陣の秋風が吹いてきて、からん…と一声鳴らしたという状況と思う。秋風という季語の本質が実にうまく捉えられている句だと思う。素十が写生(実感)した「がらん」と秋桜子が添削した理想(らしさ)の「からん」との違いについて考えてみた。「からん」はどこか作り物の感じがして、私には「がらん」のほうがしっくりくるように思う。
- 合評
-
-
ばんは本堂、内陣の柱に添わせ一対で吊るされている荘厳の裾に鈴の付いた錦だと思う。作者は秋の澄んだ風と音にまた仏の前にいる心地よさを感じていようです。私達にも静かな鈴の音が聞こえてきます。 (うつぎ)
-
もともと飾りのついた旗のようなもの。風に吹かれるとぶら下げられた飾りがカラカラと音を立てる。趣は風鈴の風情ですが重量感が違うのでくわらんと聞いたのかと思います。 (素秀)
-
秋風が秋の季語。お寺かお宮の境内であろう。澄み切った鈴の音が聞こえる。ああ、幟旗についている鈴が鳴ったんだ。くわらん、くわらん。秋風が鈴に働きかけ鈴がそれに応えているように。秋風がこの場を支配している。その中に私もいる。 (せいじ)
-
昔の仮名遣い「くわらん」が印象的です。調べていると面白い記事に行き当たりました。初案は「がらん」だったのを、秋櫻子の助言で「くわらん」に変えたのだと・・。確かに「がらん」よりも「くわらん」の方が澄んだ秋の気配を感じます。(秋櫻子と素十は法医学教室の先輩後輩の仲だったそうですね。) (あひる)
-
仏具としての「幡」はその名に使う場所を冠したもの、使う目的を冠したものなどいくつか異なる分類で多くの種類があるようです。ここでは「秋風」という季語から命終の時に立てる幡、命過幡(めいかばん/みょうかばん)を想像しました。ひとつのいのちが終わる時、秋風が「くわらん」と送ってくれた……秋の澄んだ空気の中、惜別の切なさを感じました。 (むべ)
-
幡の鈴がどういうものか良くわかりませんでしたが、鈴の音に秋を感じたのでしょう。鈴を鳴らすほどの秋風なので台風が近づいているのかもしれません。 (豊実)
-
投稿いただいた記事は編集してここに転記されます。
アーケード聖樹の星とふれあはず コメントを書く
(アーケードせいじゆのほしとふれあはず)
いよいよ最後の作品です。来週の GH定例は師走の街を吟行することになっているので丁度よいお手本です。豪華に華燭された都会のアーケードもあるし、◎◎銀座というようなローカルなアーケードもありその雰囲気は様々です。揚句の場合は前者の感じですね。捉えている事象や表現は平凡で平明ですが、あひる解、むべ解にあるように「高い」といわずに高さを連想させているところがうまいですね。「ふれあわず」は、「触れそうでいて触れ合わない」が省略された印象があり、天井とツリーに天辺にある星とが極めてすれすれの関係にあることを見事に表現しています。
- 合評
-
-
アーケードの天井に届く程の高さの立派なクリスマスツリーですね。ツリーの天辺の星が大きく輝いています。 (豊実)
-
アーケードからツリーの大きさが想像できます。やはりふれあはずが良いです。ほぼ一年間加代子さんの句を読んできたわけですが、あらためて俳句に触れることはその人に近ずくことだと思いました。 (素秀)
-
アーケードの天井に届きそうなほどに聳え立つ聖樹。でも、「届きそう」とか「聳え立つ」と表現すると、平凡になってしまいますね。南上加代子さんの感性、さすがと思いました。私の母は94歳ですが、大分で若い頃から高野素十先生、倉田紘文先生を師としていました。作風の違う南上さんの俳句をとても楽しませていただきました。 (あひる)
-
聖樹が冬の季語。クリスマスセールの始まった商店街の広場に聖樹が飾られている。「ふれあはず」という短い的確な言葉によって、アーケード(の天井)と聖樹の(天辺の)星とが互いに触れるか触れないかぐらいの位置関係にあることがわかる。商店街のアーケードはかなり高いので、見上げるほどの大きな聖樹であったのだろう。 (せいじ)
-
アーケードを歩いていると少し広くなっているところに高いクリスマスツリーが飾られています。てっぺんには星が飾られていますが、アーケードの天井にはかろうじて接していないようです。ツリーの高さを高いという言葉を使わずに表現しているところがすばらしいです。星は静かに行き交う買い物客を見下ろしています。クリスマス・シーズンの華やかさ、賑やかさが伝わってきました。 (むべ)
-
加代子句集の鑑賞は今日で最後になります。
アンコールどよもす我も手套ぬぎ コメントを書く
(アンコールどよもすわれもしゆとうぬぎ)
17文字の字配りが9・3・5という面白い作品です。これを「アンコール・どよもす我も・手套ぬぎ」と解釈するとわけのわからない句となる。
どよもすようなアンコールの拍手に思わず私も手袋を脱いで拍手を送ったよ
ということですね。むべ解にあるように観客もきちんと正装して聞いているというコンサートの様子が連想できます。だから大声で「アンコール!」などとは叫ばず、割れんばかりの拍手を送っているのです。
- 合評
-
-
年末の年越しコンサートのようにも思えます。アンコールの拍手が会場中に鳴り響くころには手袋を脱いで思わず立ち上がっていた自分がいる。 (素秀)
-
昨年11月ふじこヘミングさんのピアノコンサートに行ってきました。コロナ禍で、アンコールの大きな声は聞かれませんでしたが、後ろの方の席で手袋をしたままだった私は、高く音をたてたくて、手袋を脱いで拍手をしました。句の中に拍手という言葉はありませんが、どよもすと手套ぬぎで拍手の音が聞こえてきます。 (あひる)
-
「手套」は冬の季語。室内で手袋をつけていたということは、フォーマルな装いでのコンサートでしょうか。観客は立ち上がってアンコール!と拍手を惜しまず、作者も手袋を脱いで心からの賛辞を贈ります。感動が伝わってきます。「どよもす」は「響もす」なのですね。ひらがなの使い方、勉強になります。 (むべ)
-
アンコールの手拍子が鳴り響いている。手袋をしていたのでは音が小さいので、急ぎ手袋を脱ぎ手拍子に参加した。演者が舞台に再登場し、拍手が盛り上がる。 (豊実)
-
手套が冬の季語。コンサートホールにアンコールの拍手が鳴り響く。私もそれに賛同して手袋を脱いでアンコールの拍手をしましたよ。素晴らしいコンサートであったのだろう、「手套ぬぎ」に心からの賛同があらわれている。 (せいじ)
あはあはと霧にひらきし花火かな コメントを書く
(あはあはときりにひらきしはなびかな)
「ひらきし」という措辞が使われているので揚花火のことだとわかります。季語の解釈は素秀解の通り。歳時記は便宜上四季に区分されていますが、俳句鑑賞をする上で 季感というのは二十四節気ある ことを忘れてはいけません。揚句の主季語は花火ですが秋口になると雨が晴れたあと夜になって気温がさがると霧が発生します。そのような状況下で決行された花火大会なのでしょう。くもりガラスの向こうで花火が開いている…そんな感じなのかもしれませんね。
「あはあはと」とひらがなが使われていますが漢字で書くと「淡々と」になるでしょうか。むべ解にあるように、ことばの意味は同じでも実景を連想する上で視覚的にも絶妙の効果を醸しています。
そして句全体の文字配りをみると「霧」と「花火」を漢字にすることで一句中の力点とし、あとはひらがなで「はんなり」した感じになるようにとの作者の意図が感じられます。
淡々と霧に開きし花火かな
どうですか、全然違うでしょう。初心者は、難しい漢字をあてることが格調高い俳句だと勘違いしがちですが、わざわざ難解な漢字をあててルビをふるというような句作りは自己満足の世界です。
- 合評
-
-
打上げ花火を初秋、手花火を晩夏の季語とする歳時記も多いようです。霧の夜空に開く花火は淡く光って幻想的に見えたのかもしれません。 (素秀)
-
花火が夏の季語(秋の季語とするものもあるようであるが)。霧は秋の季語だが年中みられるし、この句の場合は花火の引き立て役になっている。花火大会の日、霧がかかったが強行した。色が薄くぼんやりとしていたけれども花火が上がった。健気にもぱっと開いた花火に人々の歓声がやまない。「あはあはと」と花火が懸命に頑張っている姿が切ない。 (せいじ)
-
花火は私にとっては夏の思い出ですが、季語としては秋とのこと。けれども「冬の花火」という曲もあるようです。この句の季節感は霧に表現されているかなと思いました。霧の中の花火を見たことがなく、あはあはという言葉も遣ったことがなく、憧れを感じます。 (あひる)
-
「霧」が三秋、「花火」が初秋と季重なりの句になるでしょうか。花火といえば漆黒の夜空にくっきりと、というイメージですが、ここでは霧によって淡く仄かに見える花火です。二つの季語がお互いを生かす取り合わせだと感じました。「あはあはと」という副詞が色彩の淡さを絶妙に表現しています。 (むべ)
(きやくせきのはうへひとだまなつしばひ)
この夏芝居は怪談ものでしょうね。大劇場ではなくて小さな芝居小屋とは半屋外のような田舎芝居の感じがします。したがって仕掛けで動くようなものではなくて黒子が人魂に似せた明りを竿先に吊り下げて巧妙に揺らしながら客席の方まで近づいてきた…という感じです。芝居の仕掛けだとわかっていても女性客や子どもたちがきゃあきゃあと大騒ぎしているようすが見えてきてユーモラスです。
- 合評
-
-
怪談話の舞台は観客を驚かせる仕掛けがたくさんあります。早変わりや人魂もそうでしょう。客席へ飛んでくる人魂にさぞ客席も沸いていることでしょう。 (素秀)
-
小学生のころ祖母に連れられて観た歌舞伎座の四谷怪談を思い出しました。子ども心にとにかく怖くて、人魂が客席のほうまで来ることはありませんでしたが、もう二度と来ないと思いました。大人たちが喜んでいたのが不思議でしたね。外連と絡繰り、夏の暑さを吹き飛ばす臨場感が伝わってきました。 (むべ)
-
思わず笑いそうになりました。夏の芝居小屋で、お客さんを怖がらせようと小道具の人魂を客席に迫るように動かしたのでしょう。それをすかさず俳句にする南上加代子さんのお人柄を楽しめました。 (あひる)
-
夏芝居が夏の季語。怪談物が演じられているのであろう。突然、人魂に見せかけたものが客席の方に飛んできた。音響効果も手伝って客は肝を冷やす。そのような仕掛けで涼しさが演出されている。俳句の方も「人魂」に肝を冷やしてしまった。 (せいじ)
-
この夏芝居は怪談かと思います。今時の劇場のようなハイテクはないでしょうが、何らかの人魂の仕掛けが客席にとんできて、恐怖を感じたのでしょう。 (豊実)
-
加代子さんの作品鑑賞も残すところあと3句になりました。
(らうかんのたけばしをそへなつりようり)
みなさんの合評にもあるとおり、琅玕の竹箸…からはとても瑞々しい感じが伝わってきます。この竹箸の原材料は遠隔地から取り寄せたものではなくおそらく地場の竹林のものでしょう。ゆえに竹林の多い京都の感じがします。夏料理といえば旬の鮎料理でしょうか。渓流の水音が間遠に聞こえていたり、木々や竹林の風のさやぎなども通ってきそうな、高貴な雰囲気があります。随分と高級料理の感じがしますが夏料理の句を詠むために奮発したのでしょう。
- 合評
-
-
琅玕の竹箸の解釈に悩みました。翡翠のような竹箸、あるいは、翡翠の箸置きかなあと思いました。いずれにせよ、高級な料理を目の前にした至福のひと時です。 (豊実)
-
琅玕の竹箸で一番に思い出したのは、昔、京都貴船の床料理を食べに行った時のことです。勢いよく流れる清流の上に床が設えられ、上には青楓が被さっていたような。そこにどんなお箸が添えられていたか、実は忘れましたが、まさに琅玕の竹箸がお似合いの料理と雰囲気でした。 (あひる)
-
夏料理が夏の季語。料理に添えられた箸に目を見張ったのであろう。夏の中国料理ではないだろうか。ネットによると、最高級の翡翠を琅玕とよぶらしいが、琅玕には「美しい竹」という意味もあるらしく、育って二年目ぐらいの滴るように深く美しい緑色の竹を指すということであった。そのような美しい箸、一度見てみたいものである。 (せいじ)
-
琅玕、最高級の翡翠または美しいもののたとえとも出てきます。青竹の箸がよほど美しかったのだろうと思えます。 (素秀)
-
「琅玕」という言葉を知らず調べました。暗緑色または青碧色の半透明の硬玉だそうですが、ここではその色彩・光沢から派生した美しい青竹の意味のようです。作者の目の前に夏料理が運ばれてきて、添えられた青竹のお箸の美しさにほれぼれしています。清々しい畳のお部屋、簾のむこうには青楓が揺れ、清流のせせらぎが聞こえてきそうです。 (むべ)
(なれもあもはいざらふようたくすずし)
加代子さんにかかるとどんなことでも俳句になってしまうので不思議ですね。みなさんの鑑賞も様々で楽しいです。あひる解ではないですが私も揚句のシチュエーションを推理してみましょう。空席の卓上には灰皿は置いてなくて客が席についたときにウエイターが「タバコは吸われますか?」と確認してから必要なら灰皿を持ってくるというシステムなのかなと思いました。
「私達ふたりとも吸わないので要りません…」と、笑顔で答えている様子が見えてきます。喫煙するテーブルではうっかり卓の上に吸い殻をこぼしたり、何かと不衛生な感じがあるのですが、清潔に保たれている卓上を見て涼しさを覚えたのです。「涼し」の季語によって室内ではなくて涼風の通ってくるような浜辺か緑の中にあるカフェテラスの雰囲気を感じます。汝も吾も…という措辞からはごく親しい間柄の二人連れだろうということもわかります。
- 合評
-
-
二人の人が登場しますが、汝とは誰なのか、二人とも煙草は吸わないようで、最後は卓涼しと爽やかな感じで結んでいます。少し謎めいて推理したくなるところがこの句の魅力かなと思いました。 (あひる)
-
煙草を吸わない者同士がテーブルを挟んで談笑しているようです。不要な熱を発生させるものもありませんし、飲み物ぐらいしかないテーブルも涼し気に感じます。 (素秀)
-
喫煙しないお二人が差し向かいで話している様子が浮かびました。灰皿のないテーブルはすっきりしているのでしょう。「汝も吾も」という措辞がユダヤ人哲学者ブーバーの『我と汝』を彷彿とさせます。「あなたと私」という出会い・関係性は人知を超えた存在がアレンジしたものなのかもしれません。 (むべ)
-
涼しが夏の季語。夏の暑い日に二人で喫茶店に入った。喫煙席と禁煙席が分けられていたのかもしれない。どちらにしますかと聞かれて、あなたも私も煙草を吸わないから灰皿は要らないわね、禁煙席にしましょう、ここは煙たくもなく涼しくて気持ちがいいわ、といった風情だろうか。 (せいじ)
(ぎようぎよきたまごのかずよれいぞうこ)
必要な食材を取り出そうとして冷蔵庫の扉をあけた瞬間の印象ですね。たしかに冷蔵庫が普及し始めた頃は、ドアポケットにありましたね。行儀よき…の措辞がうまいです。上下や向きも揃えてきちんと並べてある様子が見えてきます。かなり几帳面な感じがわかるので他の食材なども容器を揃えたりしてきちんと整理されていそうな冷蔵庫です。「数よ」は、あひる解にあるような主婦の感覚でしょう。たくさん並んでいるという意味の他にきちんと在庫管理されているのです。
- 合評
-
-
玉子は常備する食材の基本とも言えます。消費期限もありますから冷蔵庫にきちんと並べて食べる順番も決めているようです。食材の豊富な冷蔵庫を見るときの安心感なども感じられます。 (素秀)
-
冷蔵庫の中が片付いていると気分もスッキリします。「行儀よき」で卵が並んでいることが分かり、「玉子の数よ」で作者が料理に使う卵の数をいつもごく自然にやりくりしていることが想像できます。私も今朝、全部ゆで卵にしたら夜の献立に困るかも知れない・・お菓子を作りたくなっても出来ない・・などと、並んだ卵を見ながら考えました。 (あひる)
-
冷蔵庫が夏の季語。冷蔵庫の扉の裏側にパックで買ってきた玉子がパックに収められたまま置かれている。「数よ」とあるので、残りの数の数えやすさを「行儀よき」と表現したのではないだろうか。パックの玉子が、行儀よく並んだ生徒のように感じられたのであろう。 (せいじ)
-
もしかして、冷蔵庫の扉裏の卵ケースが誕生した時のことかと思いました。それまで、冷蔵庫でころころしがちだった卵がきっちりと収納されるようになりました。 (豊実)
(のうぶたいどうぜんとしておそざくら)
季語が遅ざくらなので、屋外の能舞台です。屋外の能舞台の多くは社寺に設けられており神事の催物として演じられる。境内の桜花の梢がくれの奥に舞台が見えていると連想すると「洞然として」の感じは理解できる。この遅ざくらは、ソメイヨシノよりも遅い時期に咲く八重ではないかと思う。八重の梢は質感もあるので、枝の向こうの舞台はより洞然とした感じかなとも思う。せいじ解の通り、舞台で舞が始まる前の静かな情景である感じがある。
- 合評
-
-
洞然という言葉には奥深く静寂なニュアンスを感じました。能舞台はおそらく普通の演劇の舞台に比べて奥行きがあり、上演されていない時は大きな穴が開いているかように見えたのではないでしょうか。遅ざくらという季語に春の盛り、優しい風に揺れる桜を想像しました。 (むべ)
-
檜造りの簡素な能舞台で、何の催しも行われていない、がらんどうな様子が目に浮かびました。正面の板壁には緑の松が描かれているかもしれません。舞台の傍には遅咲きの桜が咲いて、人の気配があまりない、静かな空間と時間の流れを感じました。 (あひる)
-
洞然をどう読むかで解釈も少し変わってくるようです。静かな洞穴のようだと読むと能舞台に桜の散る写生、雑念が無く心が空のような様と読むと静かな能舞台に自分の心情を映しているようにも思えます。 (素秀)
-
遅ざくらが春の季語。能舞台は薪能(夜間の野外能)であろう。「洞然」の意味は、普通は「がらんどうなさま」とのことであるが、よく調べてみると「洞穴などの中から聞こえてくる音のさま」という意味もあるようであるから、闇の中に浮かび上がる能舞台から、重々しいシテの音声、謡曲などが、洞穴で声を発したときのように響いて聞こえてくるということではないだろうか。篝火に照らされた遅咲きの桜が能舞台に色を添えている。 (せいじ)
-
洞然とは雑念がなくて心が空なさまのことのようです。遅ざくらなので、場所はどこかの高い山ではないかと思います。能舞台の神聖な空気が漂う中で桜が美しいです。 (豊実)
(ふじなみのみやとぞとうをふさぐふじ)
藤の名所となっている神社を訪ねて吟行したのでしょうね。「磴をふさぐ」といわれると参磴をまたいで藤棚が作られていて大きく垂れた藤房が磴を塞ぐほどなのかなと考えてしまうがさてどうだろう。あるいは懸かり藤を垂れた大樹の枝が参磴へ迫り出しているという状況も考えられる。あひる解のとおり「磴をふさぐほどに」と理解すると、右に左にと多くの種類の藤棚があり、参磴は直線ではなく曲がっているので、普段なら梢がくれに見える参磴が満開の藤で隠されて見えないという状況かもしれない。いろいろと連想は出来るけれども鑑賞としては、名所の藤が今を盛りと賑わっている様子として捉える程度でもいいのかと思う。
- 合評
-
-
石段を塞ぐほど垂れた藤の花が藤波の宮だと主張している。見事な藤すだれを見た途端に出来た句のように思えます。藤ではじまり藤で終わる並びも見事です。 (素秀)
-
藤浪の宮と言われるほど藤が見事な御殿があるのでしょう。その御殿にある石段の道に、道をふさぐほどに、藤がたわわに咲いている。 (豊実)
-
藤浪の宮という名前だけあって、磴をふさぐほどに藤が生茂って咲いているよ!…と天真爛漫に驚きと喜びを表しています。因みにわが家は有松という名前ですが、松は有りません。 (あひる)
-
藤が春の季語。春日大社のようなお宮であろう。宮へ上る石段を藤の房が上から垂れて途切れることなく続いている。藤浪の宮とはよくぞ言ったものであることよ。藤の花の濃い香りに包まれた至福を感じる。 (せいじ)
鎮魂のしらべとともに花ふぶく コメントを書く
(ちんこんのしらべとともにはなふぶく)
鎮魂という言葉からするとお葬式ではなく慰霊の儀式かと思う。桜の時期に模様される儀式と云えば、戦没者関係がおおく特に学徒出陣、特攻隊などを悼むものが多いと思う。揚句の場合、そこのところは具体的に述べていないが、人生これからという多くの若者たちが戦争の犠牲になったことは悼みても悼みきれない痛恨である。「しらべ」とあるので合唱しているのではなく黙祷裡のうちに BGMとして鎮魂のメロディーが流されているのであろう。
- 合評
-
-
葬式とも考えられます。出棺を待つ人たちに桜の花吹雪が。慰めにもなり、また悲しみも増すのかも知れません。 (素秀)
-
大きな悲しみが鎮魂という言葉に含まれています。多くの人が忘れ去っても、昨日のことのように傷口がいたむ人々が居ます。桜ふぶきが、しらべに和して慰めているようです。春のあたたかさが感じられます。 (あひる)
-
鎮魂とありますので、作者は何らかの儀式に出席していて、奏楽に耳を傾けつつ窓から会場の外に目をやると、桜花がはらはらと散っている……という光景を思い浮かべました。「花ふぶく」と動詞の季語がとても良いなと思いました。桜も亡くなられた方を送ろうと花びらを落としています。作者の静かな悲しみが伝わってきます。 (むべ)
-
花ふぶくが春の季語。何かの慰霊祭であろう。慰霊碑の建立とともに傍に植えられた桜樹も大きくなった。鎮魂歌が流れる中、桜の花もそれに呼応するように吹雪のように舞い散っている。人と自然がともに死者を慰めるしばしの時がこの場に現出している。 (せいじ)
-
戦死者を鎮魂するセレモニーでピアノ演奏が流れている。散りゆく桜が鎮魂を深める。 (豊実)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
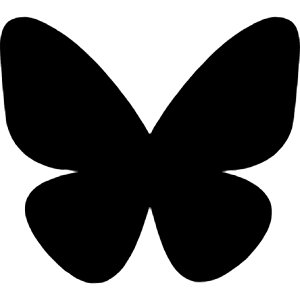 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()