2022年3月
目次
(たんぽぽのサラダのはなしののはなし)
ぺちゃくちゃおしゃべりしながらの楽しげな吟行風景を連想します。たんぽぽがサラダの食材になるという食通の情報に作者は驚いたのであろう。それが引き金となり次々と食材になる野草の話題がとびだして、盛り上がっているのである。うららかな野遊びの雰囲気があります。
- 合評
-
-
サラダは素十さんの時代にお洒落ですね。たんぽぽが食材に?それならすぐ見つけられる。他に酸い葉、アマナと野の話が広がっていき楽しい一時だったのでしょう。きっと女の人もいたと思う。 (うつぎ)
-
もしかしたら、子供がままごとでたんぽぽをサラダにして遊んでいるのかも。たんぽぽが咲く広々とした野原がそこにある。 (豊実)
-
「たんぽぽ」が春の季語。葉のサラダをいただいたことがありますが、ルッコラとかクレソンとかが近いかなぁと思います。ここではもしかしたら花もサラダになる話?他にも春の野にはいろいろ食べられる草花がありますね、と春光のもと盛り上がる様子が伝わってきます。ちなみに春の草の中で美味しいなぁと思ったのは蕾の姫女苑の天ぷらでした。 (むべ)
-
たんぽぽのサラダは、シャンソン歌手で食通の石井好子さんのエッセイで読んだことがあるような気がします。葉っぱを食べるのですが、食用に栽培もされているようでした。パリのレストランで出てくる洒落たサラダといった印象です。たんぽぽというかわいい響きと、のの繰り返しがテンポよく、また、たんぽ- ぽをサラダで食べるという楽しい驚きがこもっているように思いました。野に咲く草や花を見ながら、話が盛り上がったのかも知れません。 (あひる)
-
摘んできたたんぽぽをサラダで食べる話しから野山の草の話しになっていったのでしょうか。そういえばたんぽぽは漢方の薬にもなりますね。友人たちとの歓談でしょうか。それとも講義の合間の雑談かも知れません。 (素秀)
-
たんぽぽが春の季語。たんぽぽのサラダというものをはじめて知った。素十さんも洒落ている。連れだって春の野に遊び、たんぽぽがたくさんに咲いているのを見つけた。誰かがたんぽぽのサラダの話をした。えっ、たんぽぽも食べられるの? どんな味? などと話が盛り上がる。のどかな春の一日、野原でそんなお話をしましたよ。 (せいじ)
(くにまづしだいがくまずしそつげふす)
この句の詠まれた時代の世相を反映した作品ですね。貧しい時代ゆえに大学でも学びも充足感を感じることなくついに卒業を迎えた。みなさんの鑑賞同様にこれからは自分たちが頑張ってこの国を豊かにせねば…という決意、意気込みが込められいます。
- 合評
-
-
国貧し大学貧しの対句の調べが世界はもとより日本も激動の時代、ほんとうに何もかも貧しいのだと強調しています。卒業するにあたって良い国になるよう頑張ろうの気概が強く感じられます。 (うつぎ)
-
「卒業」が春の季語。重みのある一句。三段切れにならないように日々努めているのですが、達人はこのようにとても効果的に使うことができるのですね。欧米列強がせめぎ合う中で日本もドイツや中国を向こうに回していた時代。国内では米騒動が全国規模に波及した時節でもありました。医学を志した素十さんの、国の発展に貢献していきたいという気概も感じました。 (むべ)
-
作者が卒業したのは第一次世界大戦の終わりごろだと思います。何もかもが貧しかった時代、卒業後も終戦後もまだ世の中は騒然としていたようです。卒業す・・・には、そんな時代に巣立っていく若者たちの心意気と、希望と、不安が入り混じっていたのではないでしょうか。 (あひる)
-
卒業が春の季語。日本がまだ貧しかった時代、自分は大学にまで進ませてもらい、いま卒業式を迎えることができた。本当にありがたいことである。これからは国のために尽くそうという強い決意が、あまり見かけない三段切れに感じられる。 (せいじ)
-
一見、川柳かと思うような句です。当時の世相からも裕福な大学生活を送れようはずもなく、苦労の末に卒業できたのでしょう。医学博士にもなった超エリートですらこの苦労です。今の学生はコロナでまともな勉強もできないと嘆いていますが、果たしてコロナがなかったとしてちゃんと勉強したのだろうかと思います。 (素秀)
-
素十さんは1918年に東大医学部を卒業されています。その時代のご苦労を推し量るのは難しいのですが、なんとか大学を卒業し、新たな道への決意をされたように思います。 (豊実)
(えぞにうのほくかいだうにひやくしやうす)
「北海道に百姓す」で開拓農家であろうことが連想されます。開墾エリアの直ぐ近くの原野に雑草として生えているのでしょう。「蝦夷にう」と書くらしいので、あたかも北海道にかかる枕ことばのように響きますね。蝦夷地の場合、雪や気温の関係でまともに百姓できる期間も短く夏の間の農作業はとても忙しそうです。
- 合評
-
-
えぞにうは北海道の原野の象徴として語られているように思う。えぞにうの生う原野に、その北海道に百姓として生きている。気概と誇りを感じとっているようです。開拓の歴史も感じさせます。 (うつぎ)
-
「えぞにう」が晩夏の季語。北海道ではありませんが、沢沿いを歩いていて見たことがあります。どちらかというと湿り気のある半日陰のような場所に生えていました。そのような土地は作物を作るにも、そもそも開墾するにも、大変な労力と忍耐が必要だったことでしょう。先人の開拓の魂のようなものを受け取りました。 (むべ)
-
えぞにゅうは初めて知ったのですがセリに似た北海道特有の山菜とのことです。広大な農地と原野、背の高い白い花が揺れるのを見て北海道での農業を思ったようです。 (素秀)
-
「えぞにう」が夏の季語。えぞにうの花が咲いている北海道の原野と、大きく開拓された農地を間近に見ての作品ではないかと思った。「百姓す」は大変な苦労をしているという意味だろう。「~に~に」と畳みかける言い方とあいまって、開拓した人たちの長い苦労をねぎらい、ほめたたえる気持ちが読み取れる。 (せいじ)
-
えぞにうに…は蝦夷に雲丹かと思い、考えていました。原野に自生する大型の植物のことだったのですね。えぞにうが晩夏の季語。北海道で百姓をするということは、えぞにうと共に生きること、えぞにうの茂る原野と格闘することでもあったのかと思いました。 (あひる)
-
えぞにうは北海道独特の背の高い白い花。広々とした畑で、北海道の開拓時代にも思いを馳せているのでは。 (豊実)
盆経といふは斯く斯く斯く斯くと コメントを書く
(ぼんきやうといふはかくかくかくかくと)
みなさん体験があるのでいろろに鑑賞されて面白いですね。お盆に帰省して家族と遺書にお盆のお勤めに参加しているのでしょう。都会の盆僧は忙しくておしゃべりしないで帰りますが揚句は田舎でお勤めがすんでお茶の時間に棚経の解説をしてくれたのでしょう。それもまたお経に輪をかけたような小難しい説法で退屈しながら聞いている様子かと思いました。滑稽味がうまいですね。
- 合評
-
-
「盆経」が秋の季語。斯く×4回の繰り返しがとても面白い句ですね。くすっと笑わせるユーモアを持っています。 (むべ)
-
斯く斯く斯く斯くという繰返しに遊び心を感じます。盆経とはこれこれ云々と、僧侶が説明をされているのでしょうか。盆で帰省した家族も顔を揃えて、皆が神妙に頷きながら聞いているのかも知れません。欠伸を噛み殺している人もいるかも知れません。 (あひる)
-
盆の棚経を上げに来る僧は1日に何軒も回るので家々でゆっくり時間をとっておれません。斯く斯くの繰り返しのリズムは盆ならではの読経のテンポの速さをユーモラスに語っているのだ思う。 (うつぎ)
-
斯く斯くは内容を省略して言う事ですから、これを2回重ねているのはさっさと終わらせて欲しいということでしょうか。毎年聞いていることだし、もう解っているよと言いたいのかも知れません。 (素秀)
-
盆経が秋の季語。盂蘭盆会に自宅の仏壇の前で僧侶にお経をあげていただく盆経(棚経)そのものはすぐに終わるものらしいが、その後、僧侶が、盂蘭盆会の典拠となっている盂蘭盆経について蘊蓄のあるところを長々と披露しているのではなかろうか。「斯く斯くと」説かれるごとに「斯く斯くと」ありがたさも増し加わったかのようであるが、実はそうではなく、説教の長さに辟易しているのではないかと思われる。 (せいじ)
-
お経が延々と続いている。聞いていてもその教えの意味はわかりにくいが、同じようなことを斯く斯く云々と繰り返しているのだろう。 (豊実)
空をゆく一とかたまりの花吹雪 コメントを書く
(そらをゆくひとかたまりのはなふぶき)
風に高舞う花吹雪を詠んだ句であるが、「空をゆく」と詠まれると「中空」の感じよりも更に高さを感じるので、山桜ではないかと思う。よく見るといちようにまばらに飛んでいるのではなく粗密があることに気づいた。花びらには意志はないので党派を組むということはないのだけれど、医師界、俳句界を問わずとかく人があつまると派閥を組みたがる。それに比べると自然は自由でいいなぁ…というような素十さんの本音も見えるように思うのは考え過ぎかも…
- 合評
-
-
遅れてはならじ我も我もとひと塊となり風に吹かれてゆく花びら、美しいと同時に潔さが寂しい。 (うつぎ)
-
これも有名な句です。桜は散り始めると早いもので、まとまっていっせい落ちてくるように見えます。まさしく一塊です。花吹雪は豪華絢爛ですが、花の終わりも近く一抹の寂しさも窺えます。 (素秀)
-
気持ちの良い句です。空は青空に違いありません。一陣の風に花びらが桜の木から流れ出す様子を時々見ますが、それを上手く表現する力がなかなか授かりません。 (あひる)
-
「花吹雪」が春の季語。桜の木本体から少し離れて空をバックに、一陣の風に流れ飛ぶ花吹雪を想像しました。「一かたまりの」がなかなかできない表現。時々あっと驚く自然現象に行き当たるのも、授かるということなのでしょうか。 (むべ)
-
花吹雪が春の季語。花吹雪の中にいるとわからないが、少し離れたところにいると、一陣の風に花吹雪がひとかたまりとなって空に舞い上がったのが見えたのであろう。なるほどと思わせられる。「一とかたまり」と「一」だけを漢字で書いているところが印象的である。 (せいじ)
-
「空をゆく」なので、かなりの強風なのかなと思いました。突風で一気に花が散っている。華やかであり、刹那であり。 (豊実)
(うつくしきしゆんくわうのかういちじかん)
素十さんは、新潟の医科大学に赴任していたので佐渡へ渡る連絡船かと思いましたが、フェリーだと2時間半かかるそうです。
もうひとつジェットフォイルという翼船のような高速艇がありこちただと65分だそうです。けれども「美しい春潮の航」と詠まれるとのんびりとしたうららかさが感じられるので慌ただしい高速艇は似合わないように思う。なので観光遊覧船なのかなと思う。穏やかな海は春光をはじいて波がきらめき、頬を撫でる春風はやさしく心地がよい。そのような癒やしの一時間である。
- 合評
-
-
「春潮」が季語。短い船旅が見せてくれた海の景色や潮の香を堪能したのでしょう。海を渡る風を体いっぱいに感じながらの一句。 (むべ)
-
観光船か連絡船か空は晴れて凪ぎ波はきらきらしています。景色を見ながら潮の香を満喫しているのでしょう。何気なく言っているようで一時間はとても巧いと思いました。 (うつぎ)
-
今は橋でつながっていますが昔はフェリーでした。仕事で出掛けたとしてもフェリーでの1時間少々が良い休憩になったり食事時間になったものです。情緒があって良かったなあと思います。 (素秀)
-
春の海の観光船を思いました。神戸や淡路で乗った観光船も一時間くらいだったかなと。美しきという平凡な言葉が、みんなの心にある春潮の思い出や想像を押し広げてくれるようです。もう、閉ざされた冬の海ではありません。 (あひる)
-
春潮が春の季語。限定する必要はないのだが、九州の門司で育ったので、虚子の「春潮といへば必ず門司を思ふ」を思いつつ鑑賞した。門司港では久女が出迎えた。作者も虚子の一行に加わっていたのかもしれない。連絡船か観潮船か、小一時間の船旅を一緒に楽しんだのであろう。門司を離れて60年、関門海峡の美しい渦潮がなつかしい。 (せいじ)
-
この一時間で春の穏やかな海の香りを堪能したのでしょう。神戸あたりから四国に渡ったのかもしれません。 (豊実)
(ざんせつにあさあさゆきのすこしづつ)
春になると昼間の気温は上昇して雪を溶かすのであるが、夜明けには放射冷却が生じて一気に気温が下がるので雪になるのだと思う。こうした循環の繰り返しでようやく本格的な春となる。「朝朝雪」の解釈を難しく考えると複雑になるが「朝ごとの雪」という解釈でいいと思う。雪間という感じではなくて常に日裏となるようなところにいつまでも残っているというような残雪かと思う。
- 合評
-
-
前日に降った雪が解け切らず、朝見るとその上に今朝もゆきがまた降っている、きのうもそうであったなあ、朝朝雪の少しづつ重なってゆくかも、早く暖かくなって欲しいと詠まれたのでしょう。朝朝雪とは感心しました。 (よし子)
-
寒さが戻り朝朝の雪が残雪の上に薄く被さる。春の訪れは一気とはいかないものだ。にで切れて朝朝は少しづつに掛かっていると解釈しました。 (うつぎ)
残雪に朝朝ですから、昨日の朝も今日の朝もと読みました。朝に外を覗いて見ると雪が降っていたようだ。畑や道の雪はとうに融けているけど、残雪には残っている。 (素秀)
-
「残雪」は春、「朝雪」は冬の季語。朝方外に出てみたら、残る雪の上にさらに朝雪が少しずつ静かに降り積もっている、そのような光景かなと思いました。朝に朝雪は当たり前と言えば当たり前なのですが、「今、ここ」という印象を強く受けました。 (むべ)
-
「朝朝雪の少しづつ」の理解は、朝ごとに雪が少しずつ積もるとも取れます。けれども、瞬間を切り取ったとすれば、今朝、残雪の上に朝雪が少しずつ積もり始めたともとれます。この場合、「朝に朝雪」という表現が「夕に夕立ち」のようで、少しおかしいのかも知れませんが、私は一読そのように理解してしまい、そこに魅力も感じました。 (あひる)
-
残雪が春の季語。雪が解けかけていたのに、今日の朝はまた冷え込んで、雪が降っている。しかしこの時期、雪間には積もらず、残雪の上に少しづつ積もるだけであり、しかも朝の間だけである。「朝朝雪の」によって朝だけであることを言いたいのだと思った。 (せいじ)
-
助詞「に」に迷いました。残雪が少しずつ溶けているのではなさそうです。寒の戻りで、また、残雪の上に毎朝雪が少しずつ積もったのではないでしょうか?暖かい春が待ち遠しい。 (豊実)
(みずううみのほとりのゆきまひろびろと)
雪解けで見えてきた大地の部分が広がっているという意ではなく、雪間となった斑の大地がひろびろと展けている風景だと思う。いままでは雪の原であったところが日毎に雪間となって変わっていくのに春の到来を実感した句ではないかと思う。「湖のほとり」というので美しい湖畔の風景描写になっているので異国情緒も感じますが、せいじ解の十和田湖畔あたりかもしれないですね。
- 合評
-
-
早春の湖畔の風景が見えてきます。黒い土の雪間が広がり雪の白と同じ位になっているのかもしれない。湖は真っ平ら確かな春を感じとっているようです (うつぎ)
-
湖のほとりに積もっていた雪がかなり解けて、土の面積がかなり広がってきた。あちこちに草の芽も顔をのぞかせているようです。 (豊実)
-
琵琶湖や余呉湖の春を連想しました。待ち焦がれていた春の陽射しが、湖岸の積もった雪を思いがけない速さでとかし始めたのでしょう。気が付くと、もうひろびろと黒い土が見えています。驚きと喜びの気持ちが表れています。 (あひる)
-
もう雪の溶けている所の方が多いようです。溶けて黒い土が見える部分には草の芽も見えているのでしょう。山の湖に春も深まってきたな、と感慨もあります。 (素秀)
-
「雪間」は仲春の季語。どちらの湖でしょうか。雪がとけ黒々とした地肌が見えています。下五の「ひろびろと」で見えている面積広く雪どけが進んでいることがわかります。私は田沢湖とその向こうに秋田駒ヶ岳という景色を想像しました。 (むべ)
-
雪間が春の季語。なぜか十和田湖畔を思い出した。雪がとけて地肌が出ている黒い部分と、雪がまだ残っている白い部分が共存している時期、前者が後者よりも広がってきた。本格的な春の到来が待ち遠しい。ちなみに、十和田湖畔には高村光太郎の乙女の像が立っている。 (せいじ)
(むぎやきのをんなのむねのあたりのひ)
麦焼きはコンバインで細かく刻まれて畑に積み残ったものを焼くので、野焼きほど大火になることはなく女性の役割であったのかもしれない。それでも風の強さによってはときに炎がたつこともあるのだろう。ときに逸る火を懸命になだめている姿を逞しいなと間遠から眺めているのである。
- 合評
-
-
麦刈りから脱穀と終え散らばった藁屑、禾屑を掻き集め燃やす最後の始末は女性の仕事だったのかもしれない。胸までも高く上がる炎をものともせず農婦の逞しさを感じているようです。 (うつぎ)
-
「麦焼」が夏の季語。「麦打」で出た「麦埃」を焼く作業だそうで、見た目より重労働との解説を読みました。男性だけでなく女性も、大勢で一気に行う作業だったのかもしれません。風にあおられたのか、思いがけず火の勢いが出て少し心配そうです。 (むべ)
-
麦の刈り取りと麦打ちという脱穀作業を終えた後の麦焼き、それはそんなに楽な仕事ではないのでしょう。小柄な女性が胸のあたりまで上がる火と格闘しながら麦焼きをしています。女という言い方に優しさを感じます。作者のお母様の苦労の姿が重なったのではないでしょうか。 (あひる)
-
籾焼きのようなものでしょうか。麦を打ったあとの殻などを焼いているのですが、思いがけず火が高く上がって胸のあたりまでに。少し慌てている女の人を見て作者も驚いているようです。 (素秀)
-
麦焼きが夏の季語。麦打ちをした後に出たのぎなどの塵を焼いて処理する作業は、村人総出で行ったのではないだろうか。その中には若い女性もいる。麦焼きの火が女性の胸のあたりの高さにまで達しているのを見て、若い男性が危ないよと声をかけたのかもしれない。胸を焦がすような恋を予感させる。 (せいじ)
-
胸のあたりに火があるということは、炎と格闘しているのではないでしょうか?麦焼きの炎が隣の畑に延焼しないように、燃えている麦の穂を長い棒のようなもので寄せている。風が吹いているかもしれません。そんな作業でも女性が行う女性の逞しさがあります。 (豊実)
(ふるさとをおなじうしたるしうてんか)
「ふるさと」「秋」から連想できるのは帰省の雰囲気ですね。「帰省」は、父母のもとを離れている学生や社会人が、休暇を利用して帰郷すること。多くは夏休みを利用することから、俳句では夏の季語とされるがお盆の時期も含まれていると思う。季語をもって夏の句だ、やれ秋の句だと決めつけたがる人があるが、あくまで季感であるので決めつけないで幅広く鑑賞すればよいと私は思う。
普段は異なる地域で仕事をしている幼馴染がそれぞれ帰省してきて故郷で再会して懐かしんでいる様子と思う。「やっぱりふるさとの空は綺麗だなぁ〜」などと他愛のない会話ながら癒やしの時空を謳歌しているのである。私の大好きな作品で、「
素十がしたためた色紙 」もあるのでご覧ください。
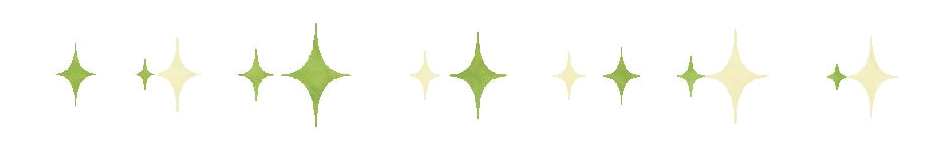
余談ですが、ひいらぎ時代に紫峡師もお誘いして六甲山で一泊吟行したことがあります。当時大先輩ながら私をかわいがってくださった方がおられました。同じ紫峡門ながら博識な彼の作風はやや癖があり、「みのるさんの句は素直でいい、俺はどうしてもひねらないと気がすまないから駄目だ…」などと話しながら、六甲山牧場で一緒に隣りあって吟行しました。そのときにふとこの素十さんの句が頭をよぎって授かった句があります。
俳風を異にして佇つ秋風裡 みのる
句会でこの句が紫峡選特選に入って、二人で大笑いしました。
- 合評
-
-
今、素十さんは故郷に帰ってきているのではないでしょうか?秋空の下、故郷の仲間と談笑している。 (豊実)
-
生まれ育ったところは違うかもしれないが今住んでいるここは人々も仲良く自然豊かなまほろばの地、ここが皆のふるさとだ、ととれば秋天下がぴったりな気がします。 (うつぎ)
-
「秋天」が季語。作者は茨城県出身とのこと。その後新潟、東京、ドイツなど勤務や留学であちこちに住んだようです。生まれ故郷を遠く離れた土地で偶然にも茨城の同郷の方に巡り合い、その驚きやうれしさが高く澄んだ秋の空に吸い込まれていくようです。 (むべ)
-
秋天下とはどこだろうかと思いました。地方から都会へ出て来た同郷の人々が秋の一日そろってどこかへ出かけたのか、故郷に帰って集っている人々か、話しているうちに同郷だと分かったのか。どちらにしても、同じなまりの和やかな会話が聞こえて来そうです。同郷というだけで心が打ち解け、爽やかな秋空の下、開放感が広がります。 (あひる)
-
たまたま旅の道連れになった人が同郷であった。秋の空の下での偶然を喜んでいるようです。 (素秀)
-
秋天が秋の季語。「ふるさと」は生まれ育った土地であるとともに父母のことでもあると思った。家を離れている兄弟姉妹がふるさとに戻り一緒に稲の収穫をしている。さわやかに澄みきった秋の空のもと、阿吽の呼吸で稲刈りが進んでいる様子がうかがわれる。 (せいじ)
その寺につきたるときの夕牡丹 コメントを書く
(そのてらにつきたるときのゆふぼたん)
せいじ解にあるようにまさに長谷寺のボタンを連想しますね。私も左右にお店や家並みの立ち並ぶ長い長い参道を歩いて長谷寺についかことを思い出しました。「その寺につきたるときの」という説明文のような措辞が長い道のりを歩いてようやくついたよ…ということを代弁していてうまいなぁと思う。そしてホッとした気分とともに夕帳のなかに仄と存在を示している牡丹の幽玄さをも見事にとらえている。実感なくしては詠めない作品であると思う。
- 合評
-
-
長い道程を経て、夕暮れになってようやく辿り着いたお寺。明るい牡丹が出迎えてくれて、ほっとした。 (豊実)
-
「牡丹」は夏の季語。「その寺」はどのお寺でしょうか。何かアクシデントがあり、予定より遅れて夕方にお寺に到着したところ、仄暗い境内で白い牡丹が作者を出迎えてくれました。下五まで読んで夕方だとわかるところがすてきです。 (むべ)
-
早くに着く予定であったのにすっかり遅れてしまった。牡丹は暮色に沈もうとしているが白は浮立ちよく匂っていた。その時の印象が何時までも忘れられない。 (うつぎ)
-
牡丹は一日咲いて夕方を迎えました。作者はその寺を目的に旅をして、やっと夕方着いたようです。この時の出会いはこの時にしかない風情であり、心情であったと思います。一期一会を思いました。克明に描写したわけではないのに、読む人の心の中で絵が浮かび上がります。 (あひる)
-
その日の旅の終着は牡丹の寺。ようよう着いた時に出迎えてくれた白い牡丹の花。少し涼しくなりかけた夕方にほっとした心持です。 (素秀)
-
牡丹が夏の季語。奈良の長谷寺を想像した。長谷寺を旅したときを回想し、その情景を恍惚として目に浮かべているようである。長谷寺は山の中にある。やっとたどりついたお寺、門前の石段の傍一帯に牡丹園が広がっている。夕映えた牡丹の大きな花たちが、疲れた私を癒してくれたよなあ。 (せいじ)
(ぐわんじつはおおふぶきとやいさぎよし)
雪国での詠嘆だと思われる。深雪に閉ざされて外出もままならず籠りがちの日々は気持ちも曇りがちである。せめてお正月くらいは明るい日差しがほしいなと願う。しかしどうやら予報は大吹雪とのこと…しかたがないなと諦めるところまでは理解できるが、「潔し」とはまた豪快な諦め方である。希望の余地のない最悪の気象状況が「潔い」という意味と、それもまた詮無しと割り切って受け止める側の「潔さ」との二つの潔さが感じられる。
- 合評
-
-
潔しが独特の表現だと思いました。少々雪が深くても、初詣には行けるのですが、大吹雪となるとそうもいかないでしょう。けれども相手は大自然、雪国ではそんなことでいちいち心を悩ましてはおれません。その時その時の対処をするだけです。吹雪でも大吹雪でも来るなら来いと、雪国で生きる人の強さを見るようです。 (あひる)
-
元日は大吹雪となるらしい。新年早々威勢のいいことだ。残念というより自然現象には逆らえない。すっかり受け入れています。むしろ中途半端より大吹雪がいいのだとさえ。 (うつぎ)
-
「元日」が新年、「吹雪」が三冬の季語ですが、こちらの句では大吹雪が主役かなと思います。そして下五の「潔し」は澄み切って清々しい感じでしょうか。人の態度ではなく、元日に大吹雪をもたらす自然界に……新潟在住ですと、大吹雪の中で新年を迎えることもあるのかなと想像しました。年賀のご挨拶まわりはできませんね。 (むべ)
-
元日に冬山登山でもするのかと思いましたが、雪国なら吹雪もありえます。大吹雪ならいっそ潔いよく家に籠るかと。 (素秀)
-
素十俳句は主観をあまり表に出さないとのことなので、「潔し」は自分の心情ではなく、自然の思い切りのよさを表しているのではないかと思った。天気予報によると元日は大吹雪になるらしい。年明け早々なんと大盤振る舞いすることよ。 (せいじ)
-
「とや」を調べたところ、元日は大吹雪になるということだの意味になるようです。とすると、時は年末。元日の晴天を期待していたが、大吹雪なら、それはそれで、身を引き締めて新年を迎えよう。 (豊実)
欠航といふも冬めくもののうち コメントを書く
(けつかこうといふもふゆめくもののうち)
俳句鑑賞は、いきなり直訳しようとせず、季語の本質を受け止めるところからという原則を忘れないようにしたい。「冬めく」という季題があって「欠航」と言われると、躊躇なく荒々しい日本海の冬浪を連想させられる。汽車や飛行機だとすると季語が動いてしまうからである。春、夏、秋と安定して航行されていた船路であるが、冬に入ると海の荒れる日には欠航となる。生活の中でそのことは体験済みなので、「今日は欠航」だと聞き、「またそういう季節がめぐってっきたのだな」と納得しているのである。冬が深まるにつれやがて雪に閉ざされるであろう北国の冬の到来を感じされられる句である。
- 合評
-
-
「冬めく」が季語。なんとなく船舶の欠航を想像しました。フェリーターミナルで出発を待っていたら、欠航のアナウンスがあり、ああ、冬だなあという感慨を持ったのでしょう。冬の日本海、海も荒れているようです。 (むべ)
-
欠航というと台風か吹雪、そして飛行機か船かと思います。冬めくという季語と、素十さんの時代から考えて、吹雪の船着き場をイメージしました。確かに欠航という事態には冬ならではの季節感が重なります。写生句ではないけれど、読んだ人の心の中に冬の船着き場がありありと浮かび「やれやれ・・」と引き返す作者や他の乗客の表情が見えるようです。 (あひる)
-
欠航の知らせを聞いてあきらめの気持ちでしょうか。冬だから仕方がないよなと思いながらも、さてどうしようかと考えているようです。 (素秀)
-
連絡船を待っていると欠航のアナウンスがあった。海が荒れて雪も激しく降っているから、やはりそうか、冬だから仕方がないよなと、心の整理に取り掛かる。少し理屈っぽいが、否定的な気持ちを俳句にぶつけて慰めを得ているような気がする。 (せいじ)
-
船か飛行機か?欠航の理由は何か?わかりませんが、旅に出発できなくなった心の寂しさ、残念さを、冬めくという季語に合わせたように思います。 (豊実)
(ひともとのあたりにきなきおおふゆき)
一読、コマーシャルに出てくる日立の樹を連想したが、あれは常緑樹。うつぎ解にある野間の大欅はぴったりかもしれない。私は畑の中に聳える桐の大樹を連想してみた。桐の民俗学と題した一文から引用してみましょう。
昔の農村では女の子が生まれると桐の木を植える習わしがありました。これは、桐の生長が早く15~20年で成木となることから、その子がお嫁入りする際に伐って箪笥や長持に仕立て、嫁入り道具として持たせるため。江戸時代にはかなり広まっていた様子…
大木になるので庭には植えずに畑の一隅に植えたと言われているらしい。私の住む開発団地近くの古い集落にも畦の横にドカーンという感じにうち仰ぐほどの大木の桐が立っている。おそらく昔の風習の名残であろう。「訪へば畑から声や桐の花」というような例句もあり、自宅前の畑に植えられた桐であることが
わかる。
常緑樹であっても冬らしい姿の木であれば冬木と詠んで差し支えないが、揚句の場合は枯れ木の感じがする。大枯木とせず大冬木にした理由は計りかねるが、完全な裸木ではない樹種だったことが考えられるので花殻などの残ったまま枯れる桐ではないかと想像した。
- 合評
-
-
他を寄せ付けない雰囲気の大きな裸木をイメージしました。孤高の大木です。樹齢何年でしょうか、この地域の歴史をずっと見下ろしてきた大木が今日も変わらず見下ろしているようです。 (あひる)
-
冬景色の中に何処からでも見える村の要の大木です。裸木となっても他を圧するほどの堂々たる威容です。能勢の野間の大欅と重なります。 (うつぎ)
-
広い草原か丘に立つ大木でしょうか。畑の中の社の神木かも知れません。周りは冬景色、大樹も葉が落ちて裸木になっているようです。 (素秀)
-
「冬木」が三冬の季語。たった一本、ぽつんと立っている大きな木と、それを見上げている作者を想像しました。枯木ではないので葉を落としていない常緑樹かもしれませんが、冬ざれた印象を受けます。シンプルですが「あたりに木なき」の中七で木の存在感が迫ってきます。 (むべ)
-
冬木が冬の季語。なぜか、銀杏の大木のような気がした。葉を落とし裸木となった銀杏の大木。冬の寒さに耐え、ひとり堂々と立つ姿が神々しい。まさに神さぶである。「あたりに木なき」が平明かつ的確である。 (せいじ)
-
一本の堂々として立っている冬木。その周りには他の木はない。人生もこの冬木のように、どっしりとありたいものだ。 (豊実)
ははそはの母にすすむる寝正月 コメントを書く
(ははそはのははにすすむるねしやうぐわつ)
年老いた素十さんのお母さん、お正月で帰省してきた息子に手づくりのお節を食べさせようと甲斐甲斐しく厨に立っているのでしょう。そんな健気な母に声をかけたのである。
おかあちゃん、そんなに世話やかんでもいいから…
みなさんの合評通り、実に端的な詠嘆ながら深い深い情が伝わってきます。
- 合評
-
-
母の枕詞は「たらちねの」「ははそはの」の二つありますが掲句は、柞と母の音の反復が小気味よく俳句は調べが大事と改めて気付かされます。最小限の言葉で労りの心が溢れんばかりです。 (うつぎ)
-
高野素十さんについての倉田紘文さんの文章を思い出しました。素十さんのお母様への思いが五七五の言外に溢れていると思います。言葉の羅列よりも多くを語れる、俳句というものに驚きです。 (あひる)
-
母親を労わる気持ちが良く伝わる一句です。俳句に枕詞は音数がもったいないかとも思うのですが、母を思う気持ちが強調されて効果的だなと思います。 (素秀)
-
寝正月が新年の季語。「ははそはの」は、同音の反復にて「母」にかかる枕詞らしい。一年中働きづめの母、正月ぐらいは休んでほしいという母に対するいたわりの句であろう。母親の身体の具合がちょっと悪いのかもしれない。ちなみに、父の場合は「ちちのみの父」というそうである。 (せいじ)
-
「寝正月」が新年の季語。「ははそはの」がわからず調べました。「柞葉の」は母にかかる枕詞とのこと。さしずめ「母上」といった雰囲気でしょうか。上代の万葉集のような、お正月らしいあらたまった雰囲気がよく出ています。作者の母上か、奥様の母上かわかりませんが、お節作りなどお忙しく立ち働いた母上を労う作者の優しさを感じました。 (むべ)
-
正月には、ははそは(柞の葉)は枯葉なので、寝正月でのんびりしている母親の足元に柞の落葉が風に吹かれて近づいたのではないでしょうか?老いた母親を思いやる気持ちを感じます。 (豊実)
(きざはしのしたにむらがるしばびかな)
「きざはし」は、「階段」の古語的表現で俳句ではよく使われます。語源は、きざ(段の意味) + はし(橋)だそうなので、高さの異なる場所にかける橋、つまり階段ということでしょうか。揚句の場合、階段に重要な役割はなく高みから見下ろした景という意味合いかと思います。
季語は「芝焼く」だと思います。新芽が出る前の2月ごろだということなので早春の雰囲気です。芝生の表面にいる病害虫や雑草の種子を除去するのが目的で芝焼きすることで芽吹きの時期が早まる効果もあるそうです。芝焼きができるのは高麗芝などの暖地系芝に限られるそうです。
日本三名園のひとつ、岡山の後楽園でも毎年芝焼きが行なわれており春を迎える準備として早春の風物詩となっているとの情報もあるので、野焼きというより名苑の芝焼き風景のような感じかもしれないですね。
- 合評
-
-
「芝火」が春の季語。ある程度高さのあるところから下を眺めての一句とみましたが、「階」が何のことかわからず悩みました。「群がる」に火がメラメラ勢いよく燃えている印象を受けました。火は生き物みたいな感じもあります。 (むべ)
-
棚田を階に見立てているのかなと思いました。上から見ていると一番下の土手で燃えている芝火は炎や煙が群がっているように見えまたまだ勢いがあるようだ。 (うつぎ)
-
河川敷の野焼きでしょうか。作者は土手の上から見ています。下に降りる階段の直ぐ近くまで火は迫っていますが、芝が焼ける炎は小さく心配はしていないようです。 (素秀)
-
芝火が燃え広がる様子を階段の上から見学していたのではないでしょうか?自分が立っていた階段の下まで、思っていた以上にかなりの勢いで火が迫ってきた。 (豊実)
-
階がどのような状況なのか、はっきりわかりませんが、群がるという言葉から何か怖いような感じがします。作者は階の上に居て、下では芝火がちりちりと迫ってきているようです。火事になることはないにしても、春の風物詩だとしても、どことなく火は人の気持ちを煽ります。 (あひる)
-
芝火が春の季語。土手には下に降りるための石の階段がよくある。作者は、土手の上から、地をなめるように燃え広がる芝火の幻想的な風景に見入っている。そこにはやがて、新しい良い芝の芽が出てくるはずである。 (せいじ)
(むらさきのあはせそでぐちこむらさき)
うつぎ解の「全く頓着ない男の人」ではないつもりですが、素十さんの観察力や感性には心底感心します。同系色の濃淡の組み合わせはファッションセンスのの基本ではかと思うのですが、昨今はセオリーもルールも無視してとにかく斬新さだけがもてはやされる世情のようで大いに抵抗がある。秀句鑑賞とは関係ないけれど俳句もまた然りと言いたいのである。
- 合評
-
-
袷の裏はちらっと見える、見せるお洒落の大事な部分です。淡い紫に合わせた濃紫の袖口に気付いた作者の美意識に感心します。奥様のその日の召し物でしょうか。全く頓着ない男の人もいると思えば面白いです。 (うつぎ)
-
「袷」は初夏の季語。表地が紫、袖口からのぞく裏地が濃紫の着物を着ている方がいらしたのでしょう。見えないところにも気を配る日本人ならではのおしゃれ心に作者は感じ入ったのではないでしょうか。国語便覧に載っている平安時代の襲色目を想像しました。 (むべ)
-
着物は全然詳しくはありませんが、袷の袖口は袋状に裏地を縫うようです。裏地に柄を入れたり差し色を付けたりがおしゃれなのでしょう。淡い紫に袖の濃紫は粋に見えたようです。 (素秀)
-
濃紫は紫陽花のことかなと思いました。袖口が紫の袷を着た女性が紫陽花の花をそっとさわって愛でている。色合わせがとても美しい。 (豊実)
-
袷は裏地のついた着物で、冬の綿入れは表地と裏地の間に綿を入れた物です。この綿を抜いたのが袷で、綿抜という言葉もあるようです。初夏の季語とされています。紫の着物の袖口からちらりと覗いた濃紫、その濃淡におしゃれ心が溢れています。そして、それに気付くこの作者のような人が居てこそ、おしゃれは楽しくなります。 (あひる)
-
袷が夏の季語。紫色の袷、濃い紫色の裏地が袖口からちらっとのぞいているのだろうか。なんとお洒落な袷であることよ。袷というものを見たことがないので、このように想像した。 (せいじ)
(たまといてすなはちたかきばせうかな)
芭蕉が巻き葉をとき始めるまでには、ゆっくりと日にちがあるのだと思うが、一度解きはじめら陽気に後押しされて一気に翼を広げるのでしょうね。その瞬発的な力強さが「即ち高き」の措辞で言い尽くされています。
- 合評
-
-
玉解く芭蕉は花が表れる迄のボールのような玉だと思っておりました。巻葉を解けば直ぐに見上げるほどになった。ダイナミックさと緑の風を感じます。 (うつぎ)
-
「玉解く芭蕉」が夏の季語。『ホトトギス季寄せ』第三版には「玉巻く芭蕉」(初夏)しかありませんでした……芭蕉の新葉は巻かれた状態から美しい大きい葉を広げるとあっという間に樹高を伸ばすということでしょうか?夏の日差しや緑滴る景色が浮かびます。ご近所に芭蕉の木があるのでこれからの季節注意して観察したいと思います。 (むべ)
-
子供の頃は芭蕉のことを実のならないバナナだと思っていました。似ていますし少し良い匂いがして夏場はカブト虫なんかが集まってきます。見上げるように巻葉が広がる頃はもう夏です。 (素秀)
-
玉解く芭蕉という季語は初めて知りました。ボールのように丸まっているわけではなく、くるりと筒状の葉っぱがバサリと解けて一枚の大きな葉っぱになることなのですね?するとたちまち見上げるほどの高さの雄姿になったというのかなと思いました。即ちという言葉は私には馴染みが薄くて「たちまち」とか「当然のように」とか、イメージで捉えました。 (あひる)
-
玉解く芭蕉が夏の季語。初夏、堅く巻いた芭蕉の新葉がほぐれて、見上げるほどの高さにまで葉が広がった。「即ち」に当然の帰結なんだがなという思いを忍ばせつつも、奇跡のような自然の営みに驚嘆している。 (せいじ)
-
丸まっていた若葉が広がって成長していく芭蕉をそのまま描いている。「即ち」にその大きさへの感動が表れています。 (豊実)
(おはらめのおおやがすりにころもがへ)
大原女は鎌倉時代から昭和初期まで約800年にわたって続いた大原の風習だそうで、揚句に詠まれそれは本物だったのでしょう。大矢絣というのは大胆に描かれた矢絣ということでしょうね。それにしても素十さん女性のファッションにも通じていて詳しいですね。脱帽です。
- 合評
-
-
久留米か伊予絣の藍木綿が涼しげです。大きな矢絣ですから若い大原女さんが浮かびます。きっとうっとり眺めていたことでしょう。 (うつぎ)
-
大原女が大矢絣に更衣をしたというだけですが、大原女に色っぽさを感じます。大原女の仕事はオフなのかもしれません。 (豊実)
-
絣は織り方のことで、材質は絹や木綿、麻などがあります。大原女さんたちが身に着けるのは野良着だと思いますので、夏向きの薄手の木綿に更衣したのでしょうか。矢の模様は季節を問わず用いられるそうです。過日、今も残るという一人の大原女さんをテレビで見ましたが、小さなリヤカーを引いて、大原の花や野菜を京都の街で売っていました。最後のお一人だったかも知れません。 (あひる)
-
おまつりとしての大原女行列では柴を頭に乗せて練り歩くようですが、行商として食料品や季節の物も売り歩いたようです。矢絣で涼し気な風情になった頃は何を売ったのでしょうか。 (素秀)
-
「更衣」が初夏の季語。大原女は昭和30年代にその役割を終えたそうです。作者が見かけたのは観光用大原女ではなく本物の行商人としての大原女だっただろうと推測します。大原女の着物はもともとは地味な単色だったようですが、近代には柄の入った美しいものに変化していった歴史があるようです。大矢絣の着物に変わったことから、京都の夏の訪れ、大原女の健康的な美しさ、さわやかな風などを想像しました。 (むべ)
-
更衣が夏の季語。矢絣は矢羽根の柄を織り出した絣。その矢羽根が大きいのが大矢絣だろうか。大原女の着物が大矢絣になったのを見て夏が来たことを思う。まさに夏は来ぬである。更衣の前の着物にも思いが馳せる。 (せいじ)
(いくたびのくさつのたいかせいすいき)
火事が冬の季語とされたのは、直火で煮炊きや暖をとっていた時代、冬は空気が乾燥するの火事が大かったことから生まれたと思う。近代ではある意味で死語に近い季語だと思う。眼前に火事をみて詠まれてものではなく、冬の時期に草津温泉を訪ねたときの感慨句であろう。「大火」という冬の季語を借りてその歴史を詠んだあたりがとてもうまいと思う。
- 合評
-
-
草津温泉は明治2年、36年、41年、昭和16年などに大火災があったようです。盛衰記は『源平盛衰記』のことかなぁと思いました。木曽義仲が巴御前を落ち延びさせ、巴御前が刀傷を癒やしたのが草津温泉という伝説があるので、歴史ある温泉場は火災をくぐりぬけ今も人々を癒やしている、という感慨を詠んだのかもしれません。 (むべ)
-
草津温泉は江戸から明治何度も大火に見舞われようです。今はこうして何もなかった様に街は繁栄しているが著せば一つの盛衰記になると思いを馳せているようです。 (うつぎ)
-
広島の草津も群馬の草津もなんどもの大火をくぐり抜けてきたようです。昔は一度火が出れば、街中が焼け野原になるのは珍しくなかったのでしょう。盛衰記に記されている内容を見て、遠い昔のことではあるけれど、今のことのように想像して、その大変さに思いを巡らしたのでしょう。 (あひる)
-
草津盛衰記なるものがあるのかと調べましたがそれらしいものも見当たらず、果たして草津城なのか草津温泉なのか悩みました。草津温泉の大火事は何度もあったようですが、滅びてはいないので盛衰記というのもどうなのかなと思ってしまいます。 (素秀)
-
大火が冬の季語。草津は群馬県の草津温泉のことではないだろうか。明治2年に大火があり、江戸時代にも何度か火事に見舞われたらしい。盛衰記と言えば源平盛衰記を思い出すが、人気の草津温泉にも大火による栄枯盛衰があったことを知り、感慨深く思ったのであろう。この句とは関係ないが、今はコロナ禍による衰退の時期と言えるかもしれない。 (せいじ)
-
草津城の城址に立ち、戦国の大火に思いを巡らせているのではないでしょうか。大火の歴史を経て今がある。 (豊実)
(つきのきやくあるときはまたはぎのきやく)
作者自身がホストなのはあるいはゲストなのかは判別しにくいが、昼間は萩を愛で、夜は月を愛でるというシチュエイションかと思う。
秋の二大季語を堂々と並列させるあたりは、「ただこれ写生」に徹した素十俳句なればこそというべきか、
俳句も亦結論はありませぬ。それで結構です。忠実に自然を観察し写生する。
それだけで宜しいかと考へます」(素十の言葉より)
感じたことを感じたままに、見えたものを見えたままにシンプルに詠むことの難しさを思う。
- 合評
-
-
夜は月を愛で昼は萩を愛づ。招いたのか招かれたのかは判らないが秋の代表の季語二つからきっと気の合う仲間で句会も催されたことでしょう (うつぎ)
作者が客になったとも読めそうですが、これは客を招いたととる方が自然でしょうか。 (素秀)
-
すてきですね。作者を訪れる風流なお客様。十五夜に月見に招いた客人が翌月には萩見の客人として再訪したよ……つまり同じ方???よほど気が合う方なのかもしれません。肝胆相照らすかなぁと思いました。 (むべ)
-
月を愛でる人は、また萩を愛でる心をも持っている。この庭に、ある時は月を見に、ある時は萩を見に来る作者自身や幾人かの俳句仲間のことではないかと思いました。自然を味わうゆったりとした心を感じます。 (あひる)
-
月の客、萩の客が秋の季語。月を愛でるために集まったこの人たちは、自分も含めて、萩を愛でるためにも集まるに違いないと確信している。あるいは、萩を愛でるためにも集まったよなあと過去のことを言っているのかもしれない。「月日は百代の過客にして・・・」を思い出す。造化を前にしたとき人は自分が旅人であることを諾う。 (せいじ)
-
萩は夜には見えないので、灯りがついた庭園に訪れた人が、空に月、庭に萩を同時に鑑賞しているのだろうと思いました。とても風情のある空間です。 (豊実)
自動車のとまりしところ冬の山 コメントを書く
(じどうしゃのとまりしところふゆのやま)
私も素十の自画像俳句とみました。誘われてのかなり遠距離のドライブ、ずっと眠っっていたが、「先生、着きましたよ!」との声に覚めると眼前に枯れ山が聳えていたのでしょう。雪の山…とは言っていないのでマイカーで直接横付けできる里山の感じがします。
うつぎ解のような受け止め方も否定できず、そうだとすると一篇の小説めいてきます。自動車で来て予想外の場所に止まった。誰が何の目的で…という展開になります。
- 合評
-
-
自動車がまだ普及していなかった頃一台の乗用車が止まった、誰だろう、何処から、何用で、しかも冬の山があるだけのこの山里に、作者は物珍しそうに眺めている人のひとりではないだろうか。 (うつぎ)
-
この句がいつ詠まれたものか分かりませんが、素十晩年に近いならもうマイカー時代は来ていたと思います。自分で運転はしていないので、とまりしところなのでしょう。連れて行かれたのは冬の山であったが、もう着いたのかと驚きもあるようです。 (素秀)
-
「冬の山」が季語。当時自動車という言葉はどのような響きを持っていたのでしょう。現在ほどボーダレスでもなく短時間で遠距離を行けたわけでもないとすれば、この「自動車のとまりしところ」という上五中七で、定住地からずいぶん遠くに来てしまったなぁという気持ちがあるのかなと思いました。そこに泰然と人を寄せ付けぬ雪山がありました。 (むべ)
-
自動車が普及し高速道路やスカイラインが整備され始めたころであろう。雪のない都会から、雪で覆われた冬の山を間近に見ることができるところまで、すぐに来られる時代になった。便利になったなあと思う反面、苦労が足りない分、感動が薄れる気分もあるのではないだろうか。 (せいじ)
-
冬の山が季語。この句の作者は、観光バスだったらお客さん、ドライブだったら助手席か後に乗っていた人でしょう。連れて行かれた所で降りてみると、そこには美しい冬山が聳えていて「おおーっ!」と感動しています。運転の人はこの感動を聞いて喜んでいます。 (あひる)
-気の向くままドライブで山を登り、気がつけば雪に囲まれていた。景色の良さそうなところで車を止めて深呼吸。 (豊実)
(きりのたになにもみえざるおおいさよ)
霧のないときの峡谷の風景が目に残っているからこその実感だと思う。これも俳句ではよくでてくる題材であるが「大いさよ」と詠んだところがいかにも素十らしいところである。視覚としてとらえた大いさというよりは、大自然をつかさどっている見えざる(神)の摂理の大いさであるような気がする。
- 合評
-
-
そこに谷があるのに、霧が立ちこめて谷さえも見えない。霧という自然現象に大いなる自然の力を感じます。 (豊実)
霧が発生すれば道路も見えなくなるからすぐ山を下りよと急かされたことがある。あっというまに谷を埋め一面の海となった霧を大いなるさまと詠嘆しています。 (うつぎ)
-
渓谷の深い霧を詠んだ句でしょうが、大いさよ、の言い方は最近あまり見ないかなと思います。大いは大きの音違い、さの接尾語を付けて名詞にする、参考にしたいと思います。 (素秀)
-
霧の中に立つと、不思議の国に居るような幻想的な気持ちになります。物が見えないほどの深い霧は、怖ろしさを感じさせます。故郷に程近い由布院は朝霧が深く、街全体が霧の海に隠されてしまいますが、それは「大いなる」とか「大いさ」という言葉にぴったりだと思いました。 (あひる)
-
「霧」が三秋の季語。「霧の谷」という上五でどこか高い場所から谷間の村落を見下ろすような距離感を感じ、中七で「何も見えざる」と状況がわかり、「大いさよ」下五の詠嘆でスケールの大きな絵が浮かびました。美しさ、逞しさなどと言いますが、大いさという名詞形があるのですね。日本語は奥深いです。 (むべ)
-
霧が秋の季語。グランドキャニオンのような大きな渓谷に霧が雲海のように立ち込めている様子を目に浮かべた。何も見えないので余計に大きさを感じる。「大いさ」から、大いなるものへと連想が飛んだ。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを思った。 (せいじ)
(ふゆなみのひやくせんまんのみなきふく)
よく俳材として捉えられる風景で題材としては平凡であるが、「百千万」と畳み掛けた措辞がうまいと思うし、荒々しい波の様子を「起伏」と詠んだところが非凡である。内海ではこのような状況はまずないので日本海あたりの冬の海かと思う。
- 合評
-
-
言われてみれば冬の海は全くそのとおりで納得させられる。その先をどう感じるか読者に託されている句だと思う。 (うつぎ)
-
『冬波』が季語。作者はどこで海を眺めているのかなと想像しました。もし新潟にいたなら、冬の日本海を眺めていたのかもしれません。波が高く暗く荒々しいほどに起伏しており、空もどんよりと雪雲が覆っている……北国の雰囲気を感じました。 (むべ)
-
冬の海の立ち上がっては崩れる波をずっと見ている作者がいます。波の音や風の音も聞こえそうです。 (素秀)
-
海…とひとことで言うけれど、そこには百千万の波がある、そして一つ一つの波が全部動いている。ふと、そんなことに気付いたひとときではなかったでしょうか。春の海のたりのたりではなく、冬の海は冷たく尖っていたことでしょう。 (あひる)
-
冬波の写生である。おそらく日本海の冬波であろう。高くなったり低くなったりして大きくうねる波、ずいぶんと多いなあ、いや、すべての波がそうなっているよ。「皆」ですとんと胸に落ちる。 (せいじ)
-
海の波の一つ一つは同じよう見えて実は全て形が異なっている。地球上にはいろんな命があって、冬の厳しさにも耐えながら、一つ一つが個性を持って生きている。 (豊実)
(ふゆやまによしのじふゐをのこしたる)
吉野拾遺といへば GHの吉野一泊吟行で訪ねた天誅組終焉の地を思い出す。そのあと東吉野の里山にある原石鼎の庵にも立ち寄って句会もしたけれどその隣に廃校舎が資料館として残されていたが、そこに吉野拾遺も収蔵されていたかもしれない。いかにも枯山が似合いそうな雰囲気の場所であった。
- 合評
-
-
「冬山」が季語。『吉野拾遺』という説話集の固有名詞から、この冬山が吉野にあることがわかります。閉ざされ人を寄せ付けぬ山の姿と、霊験譚の持つミステリアスな雰囲気が重なり、共鳴しあっているようです。 (むべ)
-
冬の吉野にやってきた。南朝はここに4代続いた。吉野拾遺をよすがに当時の生活の一端を知ることできるが寂しくせつなく奥深い冬の山そのものだ (うつぎ)
-
誰の作とも知れず、歴史資料として読めなくとも南朝の逸話、説話として残った吉野拾遺を雪に隠された冬山と見たのかなぁと思います。 (素秀)
-
吉野拾遺は後醍醐天皇崩御の際に出家遁世した松翁が記したものとのことですが、後世の偽作という説が有力だとか。内容は多岐に渡るようですが、そのようなものを書き残した心情は、何か物悲しく、冬山の風情に繋がる物だったのかも知れません。 (あひる)
-
吉野拾遺は南朝にまつわる人々の逸話を記した南北朝時代の説話集とのことであるが、後代の偽作とも言われているらしい。作者は、冬の吉野山を訪れ、資料館かどこかで「吉野拾遺」が展示されているのを見たのではないだろうか。偽作かもしれないが、南朝の人々を思い、年を経て、冬山の雪の中に埋もれていた- かのような歴史悲話を掘り起こし、説話集としてまとめた人がいることを知り、心を動かされたのではないだろうか。 (せいじ)
-
吉野捨遺のことを知らないので何とも言えないのですが、もの寂しく静まっている冬山を見て後醍醐天皇の時代の戦乱に思いを馳せているのではないでしょうか? (豊実)
春の月ありしところに梅雨の月 コメントを書く
(はるのつきありしところにつゆのつき)
ある人の鑑賞を引用してみる。
季語は「梅雨の月」で仲夏。水分をたっぷり含んだ感じに二つの月の等質性がある。といって、二つの月の纏っている雰囲気は明らかに違う。この等質性と差異性の微妙に本句の面白さがある。たんに時間の推移を詠んでいるわけではない。
時間の推移を詠んだだけではただの報告である。こう云われてみるとそうなのかなとも思うが、この微妙な感覚を理解するのは難しい気もする。ところで倉田紘文師の著書にこの句の詠まれた背景が書かれてあった。
戦時中、高浜虚子は信州小諸に疎開し、終戦後もしばらくはそこに住んでいた。この句は、素十が春月の頃一度その虚子の住む小庵を訪れ、そしてこの度再訪したら、折しも梅雨の月がその庵の同じところに同じように懸かっていた、ということに興趣を抱いて詠ったのである。
戦中戦後と世情は大きく変化した中で、大自然の摂理は何も変わらなのだ…というようなメッセージもああるように思う。折しもロシアによるウクライナへの侵攻の虚しさを思うとき人の愚かさを実感する句でもある。
- 合評
-
-
梅雨最中、思いがけず見ることの出来た綺麗な月に先ず感動しています。春の朧月も同じところに上っていたが表情が違う。梅雨の鬱陶しい中少し明るい気分で見上げたのでは。 (うつぎ)
-
春、作者は月を見上げ、何か思いを巡らせることがあったのでしょう。それから月日が経って、ふと見上げると同じところに違う風情で梅雨の月が出ている。ああ、あの時あんなことを思ったなあ…と、過ぎた日のことを感慨深く思い出しているのかも知れません。 (あひる)
-
数ヶ月の時間経過で同じ場所の月も全然違う趣きがあるようです。何の説明もしていない所がミソでしょうか。 (素秀)
-
梅雨の月が夏の季語。同じ形の月、おそらく満月であろう。厳密には同じ位置ではないと思うが、同じような位置に、同じように湿っぽい月が、しかし、少し趣きを変えて出ている。同じ月なのに微妙に違うのである。それを味わっている作者がいる。 (せいじ)
-
「春の月」から始まり、春の句かな?と思いきや下五に「梅雨の月」と来て夏の句だとわかるとことに工夫があると思いました。そういえばこの場所で春にも月を眺めたなぁという回想でしょうか。季節や時刻は移ろっても、月はまた同じ位置に昇っている、そしてそれを見ている自分も……回り巡る仏教的世界観も感じました。 (むべ)
-
春の月を見た時と同じ場所で梅雨晴の夜に月を見ている。季節の移り変わりと満月の情趣を感じている。そこは素十にとって特別な場所なのかもしれません。 (豊実)
(しろうまのどろのうちあといちにほん)
代馬というのは「代田を掻く馬」という意味で、苗をを植えつける前頃の農村風景として季語となっている。よく調教された馬にとっては、この鞭はある意味合図のようなものであったろうと思う。泥田のなかでの作業なので当然その鞭跡にも泥が付着しているのである。二三本でも四五本でもない「一二本」というところが、よほどのときしか鞭を使わないのだとわかる。農家の人たちは相棒としての牛馬をとても大切に扱ったと聞く。強制力を加える鞭ではなく、いわゆる愛の鞭であろう。
- 合評
-
-
ここぞという時に鞭が飛ぶのだろうと思います。ばんえい競馬で障害を上がる時のような感じでしょうか。代かきが終われば泥も洗い流されて美味しい餌が待っています。 (素秀)
-
代掻きは牛馬にとっても一番の役どころ。頑張ってくれの泥の鞭あとは可哀想でもあるがよく働いた証でもある。馬に対するねぎらいの眼差しも感じる。 (うつぎ)
-
「代馬」は夏の季語。代掻きのために牛馬が使われていた時代を想像しました。水を張った中で田をならすのは本当に大変な作業だったことと思います。馬も人も泥だらけになったことでしょう。田んぼ全体の景色から馬のお尻のあたりにズームされ、鞭痕にリアリティと迫力を感じました。 (むべ)
-
代馬は泥にまみれて働き時々は鞭に打たれます。子供心に一生懸命働いているのに可哀想と思いながらみていました。住吉大社の御田祭で見ることができます。 (よう子)
-
子どもの頃のある日、数人の人と一頭の馬が代田掻きに集まっていました。その馬が畦の毒草を口にしたのか・・理由は私には分かりませんでしたが、大暴れを始めて大変だったことがあります。大人たちは大騒動でしたが、間もなく落ち着くと明るく笑い合って、また馬と人とで代田の労働が続きました。その時、鞭が使われたかどうか・・記憶にありませんが、鞭が必要な時もあるのだとこの句を拝見して思いました。農業をする人々の逞しさを感じた出来事でした。 (あひる)
-
代馬が夏の季語。今は機械化によって軽減されているが、代田を掻くのは重労働である。「泥の鞭あと一二本」に人馬一体となって懸命に代田を掻いている様子がうかがわれる。人も馬も必死なのである。「泥の」にリアリティーがある。 (せいじ)
-
競馬でもそうですが、馬を扱う人間と馬の間で心は繋がっているとは言うものの、鞭には痛々しさを感じます。ましてや、鞭のあとが泥でついているとなると痛々しさが増します。その一二本は強烈な感じがします。 (豊実)
(かれづるにゆきやはらかにひつかゝり)
枯蔓をへし折ってしまうほどの豪雪ではなく、みなさんの合評どおりにふんわりと綿をかぶったように春の牡丹雪が積もっているのである。「枯蔓」も冬の季語ではあるが、雪の様子からは春の感じが強い気がする。
- 合評
-
-
大きな雪片の牡丹雪かもしれません。枯れて魂が抜けたように見える蔓にとって引っかかった雪は小さな救いです。 (うつぎ)
-
枯れてかさかさになった蔓にも、ひとひらひとひら、雪がひっかかり始めました。少々無惨になった冬枯れの風景の中の一つ一つが、真っ白なやわらかい雪にゆっくりと覆われていくことでしょう。 (あひる)
-
雪の降り始めのようです。枯蔓に引っ掛かる程度でまだ隠すまでの積雪ではない。豪雪の前のひとときでしょうか。 (素秀)
-
「枯蔓」と「雪」が三冬の季語。枯蔓はそれだけでも十分に趣きがありますが、雪が柔らかくひっかかったようにのっている様子が浮かびました。静かに雪が降って来る、時々ばさっとしづる音がする……そのような冬らしい光景だったのではないでしょうか。(むべ)
-
枯蔓と雪が冬の季語。作者は降り出した雪を眺めている。「柔らかに」とあるので綿雪ではないだろうか。ひとひらの雪が、張り出した枯蔓に、行く手を阻まれた瞬間である。引っかかっちゃった! 雪はじっとそのままそこに留まる。よく見ている。 (せいじ)
-
二つの季語(枯蔓と雪)がありますが、雪の句ととりました。私は森林ボランティアをやっているので、樹木の成長や景観を損ねる枯蔓は取ってしまいたくなります。そんな枯蔓でも雪がふんわりと包むと、雪に趣が感じられます (豊実)
(かうぎうについてあるいはみをそらし)
耕牛は代馬とは違って広い畑を耕すのに使われたと思う。代田を掻くとりも力が必要だったと思う。開拓の荒れ地であればなおさらであろう。
速度が一定になるように曲がらないようにとくびきをコントロールしている様子ではないかと思う。引っ張られるときには前かがみになるし、速度がで市議たときには渾身の反り身で抑えなければ行けない。機械で耕すようにスムーズにはいかないのである。「耕牛について」なのでそんなふうに捉えてみた。
- 合評
-
-
耕牛は昔は良く見る風景で見るのがたのしみでした。作者も楽しんで見てたでしょう。 (よし子)
-
牛は賢いなと感じながら見ていたことを思い出します。犂を引いて前を行く牛と犂を倒れないように立て前屈みで後ろを行く人。端にきて方向転換する時など腰を伸ばして休んだのでしょう。牛と人のコンビで耕されて行く様子を作者は興味深く眺めているようです。 (うつぎ)
-
子供のころはまだ農耕馬や牛が残っていてのんびり国道を歩いている光景なども覚えているのですが、田畑を耕すところを見た記憶はありません。鋤を付けた牛の後ろから大きく手綱を引いて操るイメージです。 (素秀)
-
「耕牛」は春の季語。私は日本国内では耕牛を見たことがありませんが、インドシナ半島では犂を牛に装着させ田畑をおこしていました。こちらの句でもふと犂耕だったのかも…と思いました。前かがみの腰が辛い姿勢なので。犂を装着するのも、牛や馬を調教するのも難しく、熟練の人でないと扱えない農具ですが、使いこなせるようになると作業効率が格段に上がると教わりました。「或は身を反らし」で、こつこつと根気のいる農作業に携わる人々へのリスペクトも感じました。 (むべ)
-
耕牛が春の季語。実際に見たことはないが、牛に鋤を引かせて田を耕している農夫の姿を描いたものであろう。時に、前かがみになった体を反らせて背筋を伸ばしている。田を耕すのは牛を使ってもなお重労働である。 (せいじ)
-
耕牛が春の季語。大きな鋤をつけられた牛と、その牛を操る人が春の田を鋤き返しながらて進んでいる様子を思いました。時に身を反らせながらの力いっぱいの労働が、春の風景の中に溶け込んでいるようです。 (あひる)
-
大きくは牛に鋤を引かせて畑を耕しているが、一部は人が鋤を手に持って耕している。「身を反らし」という措辞が、鋤を振り上げる様子をうまく表わしていると思います。 (豊実)
(かりがねのこえのしばらくそらにみち)
日本国語大辞典の引用によれば、
そもそも雁の声は「かりがね(雁音)」の意であり、「かりがね」が後に雁の異名となったのは、鳴き声が雁を象徴するほどに特徴あるものだったからであろう。
とのこと、雁は和歌にもよく詠まれますが、その声鳴き声を絡ませているものが多く、寂しさや悲しみを感じさせるものとして登場します。
雁は、鴨の仲間と同じく秋にやってきて一冬を過ごす。それゆえ秋を告げる鳥として詠われることが多い。雁は飛びながらも妻を呼ぶ声をあげることから、鹿笛同様のイメージと結びついている。哀愁のおびた雁の声が空の上に満ちた感じはどことなくせつない。
- 合評
-
-
「雁」が秋の季語。雁の鳴き声はなんとも哀愁に満ちていますね。群れで鳴きながらの雁行を作者は見上げていたのでしょうか。空には雁の姿が見えなくなってもまだ鳴き声の余韻が残っているようです。 (むべ)
-
雁の群が幾つもあるようです。次々と飛んでくる雁の声がいつまでも聞こえます。 (素秀)
-
雁の声がしばらく聞こえたということは、おそらく、雁が空を旋回しているのでしょう。また、「満ち」で雁が群であることがわかります。 (豊実)
-
雁の群れが、わが家の屋根の上を通り過ぎたことが二回ほどあります。羽音と共に何羽もの声が力強く響き、感動しました。それが遠く外国から飛んできたと思うと尚更でした。一声二声ではなく、力付け合うかのようにいつまでも響いていました。 (あひる)
-
雁が秋の季語。列を組んでつぎつぎと渡ってきる雁の鳴く声が空いっぱいに響き渡る。すでに低空飛行に移っているのかもしれない。「しばらく」がうまい。- 雁が空を埋めている時間であるだけでなく、雁の渡ってくる季節になったなあと感慨にふけっている時間でもあるだろう。 (せいじ)
(ももちどりだうたふいまだととのはず)
順次新たに構築されていく寺院と見ることもできますが、百千鳥の季語を斡旋しているので既に年月を経た寺領の杜が存在していることがわかる。事故か自然災害、あるいは戦火なで被害を受けた堂塔の再建もしくは修復工事の様子とみるのが適切かと思う。様々祭事があるので何とか春までにはという期待とは裏腹になかなか進んでいないのである。
- 合評
-
-
「百千鳥」は春の季語。寺院の堂塔は目下改修工事中、春には完成予定なのでしょうか。寺院の裏手に広がる森から、にぎやかな鳥たちの合唱が聞こえてきます……春に向かう新たで溌溂とした気持ちを感じました。 (むべ)
-
再建なのか修復なのか、鳥たちが賑やかに鳴く頃が来てもまだ終わっていない。灌仏会も近いのにと心配しているのでしょうか。 (素秀)
-
寒い時期に始めた堂塔の修理が春になってもまだ完成していないのかなと思いました。百千鳥はそんなことにはお構いなしに、春の活動を始めて賑やかです。堂塔さへ完成すれば、この風景は整うなーと待ちわびる気持ちで詠まれたように思います。 (あひる)
-
百千鳥が春の季語。「堂塔」から、東大寺二月堂の修二会を想像した。お水取りがすめば春が来るといわれるが、それにさきがけて、はやくも、多くの小鳥が群れをなして鳴いていることであるよ。本格的な春の到来を待ちわびる気持ちが表れているように感じた。 (せいじ)
-
建立中のお寺でいろんな小鳥が囀っているのでしょう。まるでお寺が完成するのを楽しみにしいるようです。 (豊実)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
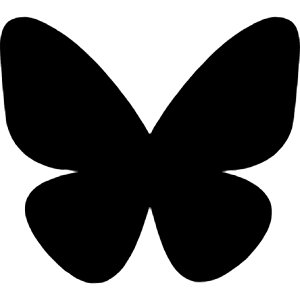 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()