2021年2月
目次
ねむり草目覚めぬ一葉ありにけり コメントを書く
(ねむりぐさめさめぬひとはありにけり)
「ねむり草」は、季語「おじぎ草」の別名、葉は合歓に似て夜は葉を合わせて眠ったように見えることから俳句では「ねむり草」として詠まれることも多い。葉に触れると、うなずくように垂れるので含羞草として親しまれている。葉の動作に特徴であるのでそれを詠んだ例句が多いが、夏の山野草として淡い紅色の小さな花が、毬のように集まって咲く素朴な姿も連想に加えておきたい。早朝の避暑散歩の道すがらに見つけた驚きではないかと思う。
- 合評
-
-
含羞草と言わずに、ねむり草と言い、目覚めぬ一葉と続けているのは、目覚めたくない何かがあるのかなと思いました。 (もとこ)
-
開かない一つの葉っぱがあった。珍しいものを発見した驚きと喜びが感じられる。すべての葉っぱが揃って開いているよりもかえって味わいがあると言えるかもしれない。 (せいじ)
-
含羞草は夏の季語。触ると葉を閉じてゆきます。閉じるメカニズムは解明されていても何の為に閉じるのかはよくわかっていないようです。夜も閉じるので光合成をしないなら無駄な水分の蒸発を防ぐためなのでしょうか。 (素秀)
-
子供の頃おじぎ草を触って遊んだ覚えがあります。復活するまでしばらくじっと見ているが、一枚の葉っぱだけ復活しない。葉っぱ一枚にも個性があるのですね。 (豊実)
(きみわるきけのひとすじやぼたんなべ)
季語の「牡丹鍋」は、猪鍋のこと。牡丹は猪の隠語で唐獅子が牡丹に戯れる「石橋(しゃっきょう)」の舞などからの連想だと言われる。山鯨というのも猪肉のことで、獣肉を食べることを忌む風習があったので「薬喰」として多く用いられ、東京でも「山くじら」の看板が出ていたものである。関西では丹波が有名なので冬の寒いこの時期に猪肉を振る舞ってくれるという山宿吟旅の句であろう。肉皿に毛が残っているなどレストランや旅館では許しがたいことも山宿のもてなしでは頓着せず笑い事で済まされる。でも、女性や神経質な人にとってこれほど気味の悪いことはない。宿主は狩猟会の一員で許可を得て捕獲してきた猪を自ら捌いているのかもしれない。炉火が焚かれ煤汚れした狭い部屋で鍋を囲んでいる風景も連想できる。
- 合評
-
-
牡丹鍋にたった一本でも毛が入っていたら確かに気味が悪い。町の料亭ではなく、山の民宿のようなところで食べた牡丹鍋ではないだろうか。家の人が自分で猪をさばくとすれば毛が紛れ込むこともあるのかもしれない。滅多にあることではないだろうが民宿なら如何にもといった趣を感じる。 (せいじ)
-
冬の牡丹鍋は体が温まりとてもおいしい!でも、鍋の中に生々しい毛が一本。ちょっと、ゾクッとする。 (豊実)
-
今日から昭和42年の作品になります。
杣の家おしつぶされさう年木積む コメントを書く
(そまのいえおしつぶされさうとしきつむ)
季語の「年木」は新年に使う薪のことで年内に伐採する。年の瀬になり家々で割った年木が軒下に積まれ、新しい木の香りに新春を迎えると言う山国の風習。この句に詠まれているのはおそらく北国の杣の住む山家ではないだろうか。家が隠れてしまうほど軒高く砦のごとく積まれた年木を見ての感興である。積まれた年木の嵩からしてお正月のみならず雪に閉ざされて補給できなくなる冬の間のための薪であろうことも予想されるので北国であろうことも連想できるのである。
- 合評
-
-
積み上げられた年木が多すぎて家のほうが小さく見えるほどなのでしょうか。豪雪地帯かも知れません。今のうちに年木を出来るだけ用意する必要があるのかも。 (素秀)
-
新年を恙無く迎えるためには、燃料の薪をかなり多く集める必要があったのでしょう。山の寒さの厳しさを感じます。 (豊実)
-
家がおしつぶされそうというのであろうか。いや、そうではあるまい。杣山にある大きな屋敷内での見聞ではなかろうか。年内に伐った年木が自らの重みでおしつぶされそうなほどに積み上げられている。この屋敷では正月用にこんなにもたくさんの薪が必要なのかと驚いているのであろう。 (せいじ)
旅なれやもろこし売にあへば買ひ コメントを書く
(たびなれやもろこしうりにあへばかひ)
「なれや」は「慣れや」の意ではなく古語表現で断定の助動詞「なり」の已然形に助詞「や」の付いたもの。「…だからだろうか…」の意味で、古歌にはよく詠まれている表現である。日常の生活であれば衝動買いはしないけれど、楽しい旅の気分がそうさせたのであろう。季語の「玉蜀黍」は9月頃に収穫するのでこの句は秋の旅である。加代子さんのことだから当然吟旅だろう。吟行の道すがら露店で焼いて売っているのを見つけて躊躇なく買って食べたのである。楽しそうな雰囲気も伝わてくるから一人旅ではなさそう。単に焼きもろこしを買ったという事実の鑑賞にとどまらず、秋の爽やかな旅気分が季感であることを汲み取ることが大切である。
- 合評
-
-
旅先で食べるとうもろこしは美味しい。とうもろこし売と二言三言交わす旅先での出会いも楽しいと思います。 (なおこ)
-
もろこし売に出会ったので、いつものようにもろこしを買った。旅なれしている心の余裕を感じました。 (豊実)
-
旅の楽しみのひとつはもちろん食です。旅なれやという言葉で続く句に、非日常のウキウキした気持ちが溢れています。 (もとこ)
-
日常の買い物では買い控えも考えるが、旅慣れた今、気持ちに余裕もある。もろこしおいしそうだ。躊躇なく買う。 (そうけい)
-
旅先の露店で美味しそうな香りをたててトウモロコシを焼いていた。旅の気分もあって買ってしまったと聞こえますが、もちろん後悔しているわけではありません。旅の楽しみの一つだと。 (素秀)
-
旅は心が浮き浮きする。ついつい衝動買いをしてしまった。買ったらすぐに食べる。旅の玉蜀黍はことのほか美味しかったに違いない。 (せいじ)
(をりをりのかぜそうまとうかけあしす)
季語の「走馬灯」について復習しておこう。箱型の外枠に薄い紙または絹布を貼り、中に人や鳥獣などを切り抜いた厚紙の円筒を立て、その心棒の上に風車状のものを取り付けてある。中央に小蝋燭を立てて火を灯すと円筒が回り外側に映った黒い影が走るように見える灯籠で軒先や窓に吊るす。俳句では盆の季語とされている。風習としては盆に限らないがその頃に多く、江戸時代からあった。「廻り灯籠」とも詠まれる。
盆は先祖の霊を迎えまつる行事であるので、先立たれた家族への思いを感じさせる句である。「をりをりの風」の解釈が難しいが、蝋燭の熱でゆっくり回っていた灯籠がときおり通ってくる風に加速されて急に早く回ったりするのであろう。先祖の霊が風とともに帰ってきたかように実感したのかもしれない。もとこ解、そうけい解のように記憶にある過去の折々のシーンを意味しているようにも思う。「駈足す」の措辞とあい働いて駈けめぐるあまたの懐かいシーンとともに光陰矢のごとしの感をも連想させられる。鑑賞者のそれぞれの境涯に応じて共感の重なる佳句である。
- 合評
-
-
をりをりの風を風のみの意味と取るか、走馬灯と合わせて今までのいろいろな出来事と取るかと思うのですが、人生の様々の事を思い出し、感慨に浸ると取りたいと思います。 (もとこ) -
-
風で切れを入れ破調の句になっている風と走馬灯しか言ってませんが破調の効果で多くを語らずとも余情溢れる句になっている。 (うつぎ)
-
時々吹く風に走馬灯が早くなったり遅くなったりする、駆け足と言う事で風の涼しさが判ります。 (素秀)
-
おりおりの風とは記憶の中にまき起こったいろいろな思い出、亡き人たちの影。走馬灯に重ね合わせ、思いめぐらしている。 (そうけい)
-
そこに風が吹いているわけではないと思いますが、走馬灯のそれぞれの影絵が風に吹かれて走っているような。 (豊実)
-
走馬灯は風がなくても中の蝋燭の熱で回転するが、内側の枠の軸の上に風車が取り付けられているので、風が吹くとその回転が速くなる。窓辺に吊るされている走馬灯が、折々の風を受けて回転が速くなり、影絵の人や馬が駈足をしているように見えたのであろう。じっと見ていないと授からない句ですね。 (せいじ)
柄がからみあふさくらんぼ分けにけり コメントを書く
(えがからみあふさくらんぼわけにけり)
家族か仲良し組かで食後のデザートを分けている様子が見えてきますね。俳句友達の多い加代子さんのことですから酒田あたりの俳友から宅急便で送られてきた到来ものかもしれない。笊にいれてザザッと水で洗うと柄が絡み合ってしまったので、ちぎれてしまわないように気をつけながら分けているのです。私事で恐縮だが、1976 年(昭和 51 年)山形空港に全日空のジェット機が初就航したとき、地元在住のひいらぎ長老の三婦人が来神されることになり、紫峡師からの依頼で私がマイカーで六甲山へご案内したことがある。大変感謝され、後日、感謝状とともに佐藤錦がいっぱいに詰まった他急便が届いたことをふと思い出しました。
- 合評
-
-
絡まっている柄を解きながら丁寧に人数分に分けた。柄がとれてしまえばさくらんぼの値打ちがなくなる。そんな気持ちが垣間見えます。 (うつぎ)
-
柄がからんでいるところから収穫の光景が浮かびます。さくらんぼは二つがセットになっているイメージもあるので、頂きものの箱詰めかも判りません。 (素秀)
-
柄がからみあうほどたくさんのさくらんぼがあるのだと思いました。たくさんのさくらんぼを頂いたので、お裾分けするのかもしれません。 (豊実)
-
さくらんぼといえば佐藤錦を思い浮かべるが、昭和 40 年代のさくらんぼは今ほどの甘さはなくかなり酸っぱかったような印象がある。値段も高かったのではないだろうか。柄が絡み合っているというところにリアリティーを感じる。 (せいじ)
-
さくらんぼの美しい紅色と、大粒の実、ツヤが見えてきます。上五中七をさくらんぼの描写だけで大胆に使っていると思います。「柄がからみあふ」とあるので、綺麗に並べられて販売されているさくらんぼではなく、収穫中のさくらんぼであると思いました。さくらんぼ狩りか、農家の方々を対象に描写されているかは分かりませんが、「分けにけり」の措辞から、笑顔でさくらんぼを持っている人々が見えてきます。 (なおこ)
(むぎやぶしうたひなつろもたきくれて)
せいじ解のとおり五箇山吟旅の民宿で詠まれた句でしょう。むかし加代子さんに誘っていただいてグループの一泊吟旅によくでかけました。厳冬期の高野山などにもでかけましたが、この句は「夏炉」が季語です。夏も塞がずにおき、必要に応じて焚く炉のことで、高地の山小屋や避暑地、また北国などで雨の小寒い日などは夏炉を焚くことがある。開いたままで焚かずにあるものも含めて夏炉で詠む。麦屋節というのは、平家の落人が、刀を鍬や鎌に持ち替え、麦を刈る時に唄ったことからその名がついたとされる。ネットで検索すると越中五箇山麦屋節保存会の笠を手にした男性の勇壮な踊りが見つかる。句材にといろいろと気遣ってくれる宿主のもてなしに感謝しているのである。あいにくの雨で外には出にくい状況下での配慮であったのかもしれない。
- 合評
-
-
夏炉から、北国、山間部の宿か。麦屋節はテンポも早く踊りも付くという。唄を聞き元気をもらえたであろうその上に夏炉まで焚き、(火を見ることも相まって)そのもてなしに癒されたことか! (そうけい)
-
昭和40年初めに観光地として栄えていたのかどうかですが、現代の視点だと観光だと思えます。合掌造りの民家で民謡を聞き炉には火も入っていた。昔ながらの暮らしを偲べたのではないでしょうか。 (素秀)
-
夏炉を前に麦屋節の調べを聞きながらその日が過ぎていく。山深い里を開拓した先祖と自然に感謝をしつつ。 (豊実)
-
富山県五箇山地方の合掌造りの民家を訪ねたときの句ではないだろうか。夏であったがまだ寒いので炉を焚いてくれ、その地の民謡である麦屋節を唄ってくれた。その他にもいろいろなもてなしを受けたのではなかろうか。心も体も暖まる歓待ぶりに感動したのである。 (せいじ)
(しゅんとうやふじんのこえのまとめられ)
第二次世界大戦後に発足した国際連合(国連)は、女性の地位向上に取り組みます。1967(昭和 42)年には、あらゆる女性差別をなくす「女子に対する差別の撤廃に関する宣言(女性差別撤廃宣言)」がつくられました。こうした時代背景の中で日本でも男女平等への動きが加速していきます。この句が詠まれたのは、ちょうどその時期にあたりますね。昨今は「春闘」という季語も実感が失われつつありますが、この句は当時の世相を感じさせる作品です。差別の実態を写生する中に希望が窺えることを学びましょう。コロナ禍のいま、私達もまた不安や焦燥を詠むのではなく、希望や勇気につながるような作品を残すように努力しましょう。
- 合評
-
-
この時代メーデーの日は御堂筋を大声で旗を掲げ沢山の団体が行進しているのをビルの窓から眺めていた頃が懐かしい。昨年迄はそうではなかったが今年は労組が女性の声も要望の中に入れてくれている喜びの句ではないだろうか (うつぎ)
-
職場において、意見を述べる事も容易ではなかった時代に、春闘という労働者共有の場で婦人の意見も取り入れられるという力強さが、まとめられという言葉に表れていると思います。 (もとこ)
-
記憶にはあるが、実感とは遠い季語です。この句が詠まれた頃は女性も拳を突き上げて声を出していたのだろうと思います。 (素秀)
-
昭和 40 年代は春闘も激しく交通機関がストライキのためによく止まったものである。労働者は全国的によく組織されていて、働く女性の声も春闘の要求に取り入れられていった。女性である作者はそれをうれしく思っている。女性の闘士も今より多かったような印象がある。 (せいじ)
-
今、オリンピック委員会で男女平等が改めて話題になっていますが、昔は女性が声を出すのは大変で勇気がいることだったのでしょう。 (豊実)
-
これより昭和41年の作品になります。
よく釣れし公魚魚籠に嵩なさず コメントを書く
(よくつれしわかさぎびくにかさなさず)
氷上から穴をあけて釣るのが醍醐味なのでしょうが、日本ではもっぱらボート釣りのようです。揚句は多分余呉湖での作と思います。一本の道糸に何本もの針をつけて釣るので好調のときは数珠つながり状態で釣れ上がってきます。面白いように次々と釣れるので大満足です。魚籠は竹細工で編まれた籠でボート釣りのとき釣れた公魚を活かしておくために水中につけておくのだと思います。最近はプラスチック製に代わっているようで風情がないですね。どれほどの釣果かとわくわくしながら魚籠を覗くいている様子が見えます。がっかりしているのではなく意外に嵩低くだったことに驚いているのである。
- 合評
-
-
公魚釣りは一度に何匹も掛かります。よく釣れし、と切れを入れる事でそれを強調出来るように思います。 (素秀)
-
奥琵琶の余呉湖で公魚釣りを見たことがある。氷に穴を掘って釣る穴釣りではなく岸釣りであった。公魚は初春、産卵のため岸に寄って来るらしい。公魚は小さいからよく釣れても魚籠に一杯にならない。今さらのようであるが実際に見て気付いたのである。 (せいじ)
-
公魚は小さい魚なので、数を釣ったわりには魚籠が重くならず物足りない感じがするのでしょう。でも、唐揚げがおいしいですね。 (豊実)
凍雑巾バケツの中に立ちにけり コメントを書く
(いてざふきんバケツのなかにたちにけり)
私も含めてですが、家事経験のない男性陣の鑑賞はやや甘いようです。絞ったあとバケツの中に放置した雑巾が凍てて立っていたというのでは無理があり、うつぎ解のとおり、朝掃除をはじめようとバケツに入れた雑巾が凍てた形のままで立ったという驚きだと解するのが正解でしょう。確かに小学校の掃除当番でそんな体験をしたような記憶が薄っすらとあります。
- 合評
-
-
凍りついた雑巾をバケツに入れると形のままに立った驚き、それだけ今朝は凍てている。水か湯を入れてへなへなと崩れていく雑巾まで読者に想像させます。 (うつぎ)
-
小学生の頃、冬の朝の掃除でバケツに掛けた雑巾が凍っていた経験があります。それくらい寒いとバケツにお湯を入れてくれたものです。そんな事を思い出しました。 (素秀)
-
昔子供のオムツがパリパリになった事を思い出しました。暖冬でこの様な風景は無くなりました。身震いするほど寒いのだけれど、立ちにけりと、何処か滑稽な、苦笑いする様な情景が浮かびます。 (もとこ)
-
バケツの縁に乾しておいた雑巾が朝見たら凍っていた。水か湯を入れる前にその雑巾をバケツに放り込んだところ、その雑巾がバケツの中に立ったというのである。思いがけず立ったところに小さな感動がある。 (せいじ)
-
最近は暖冬で身近ではこんなこともなくなりました。恐ろしく寒い感じがします。 (豊実)
身にしむや私語をとめられ聖堂に コメントを書く
(みにしむやしごをとめられせいどうに)
「シトー会西宮の聖母修道院」での句だと思う。阪急夙川駅からバスに乗り柏堂駅の一つ先の鷲林寺南口で下車、更にそこから山道を十数分歩くと修道院があり、私も何度かご一緒したことがある。大聖堂の脇に見学者用の席があり、ミサの様子が生で見学できる。「聖堂へ」ではなく「に」であるから既に聖堂に座していて私語を咎められたのである。シスターたちの捧げる賛美が、大聖堂に谺すように響くさまは実に荘厳でまさに異次元の世界である。うっかり「すごいわね…」と感嘆のことばが漏れたのである。「身に入む」は、秋も半ばになるにつれ冷たさが身に入む…という意の季語であるが、心象表現として使われている例句が多い。紅葉季のお庭はとても美しく入り口の売店にはシスターたちの手作りクッキーなども販売されているので、コロナ自粛が解けたらぜひ吟行したいところです。
- 合評
-
-
礼拝が始まるので私語を止められたのでしょうか。静寂にピンと張りつめた空気が感じられます。 (素秀)
-
聖堂「に」なので、今まさに聖堂に歩いて入ろうとしているところでしょう。秋深まる中で厳かな礼拝の空気が感じられます。 (豊実)
-
聖堂とは湯島聖堂のような孔子廟だろうか、それともカトリックの大聖堂だろうか、いずれにしても、そこで私語を諫められたのである。はっと気が付いて反省もしたであろう。身にしむほどの秋の冷気と聖なる空間の凛とした厳粛さとがよくマッチしている。 (せいじ)
(にちようはびようにんのごとこたつにゐ)
「病人のごと」の措辞が、疲れ果てて何もする気力がないという状況を連想させていますね。「日曜は」とあるので、それまでの一週間目一杯働き詰めであったこともわかります。炬燵に入ると足に根が生えたようになるとよく言われますが、吟行にでかけて気分転換をはかるという元気もないのです。
- 合評
-
-
日曜日は何もしないで炬燵に居よう。平日は目一杯働いているのだからと諾いつつも怠惰をとがめる気持ちも少しあるようだ。病人の比喩にそう感じました (うつぎ)
-
寒くて動きたくないという気持ちは良く判ります。半纏でも羽織って手足を炬燵に入れてしまえばもう出たくないまるで病人のようだがと、自虐しているようです。 (素秀)
-
日曜はというフレーズで月曜から土曜まで働き、病人のごとと、疲れ果てている様子が窺え、暖かい炬燵の筈なのに、何か物寂しい情景が浮かびます。 (もとこ)
-
冬さなか炬燵に入ったらなかなか出れないという魅力か魔力があります。ましてお休みの日曜日に炬燵に入ったらそこから一歩も動きたくない…わかりますその気持。 (ぽんこ)
-
病人でもないのに炬燵でじっと暖を取っている。何と怠惰なことかと思いつつも今日は日曜日だからと自分で自分を納得させている。炬燵の暖かさがうれしい厳冬の朝のひとこまでもあろうか。 (せいじ)
-
月曜から土曜まで働くと、日曜日は炬燵に入ったまま動けなくなる。疲れて、寒くて、炬燵から出るのが大儀だ。まるで病人みたいだ。という作者の心情だと思いました。誰もが経験のある事ではないかと思います。がんばっている自分に労いをかけていると思います。 (なおこ)
-
平日はかなり多忙で疲れがたまっているのでしょう。炬燵の暖かさとありがたさを感じているのだと思います。 (豊実)
幔幕をつきやぶらんと鹿逃ぐる コメントを書く
(まんまくをつきやぶらんとしかにぐる)
文字としては「鹿」とあるが「角切」の句であることは明白である。どちらも秋の季語ですがその本質は少し異なります。「鹿」は秋の交尾期の牡鹿を意味し、特にこの時期の牡鹿の鳴き声は鹿笛と言われて遠くで聞くと哀れである。一方「角切」は、奈良公園に放し飼いにされている春日大社の鹿の角を落とすことをいう。交尾期を前に気の荒くなっている牡鹿同士の格闘を防ぐのと、人を傷つけることを予防するためである。「幔幕をつきやぶらんと」という捉え方が非凡で、逃げ惑う牡鹿の猛々しさや必死に追いかける勢子たちの様子まで見えてきます。拙作を例に出して申し訳ないが「天狗杉武者震ひして雪落とす」の句も、季感は「雪」ではなく「雪解」である。新しさを追求するときに単なる文字としての季語に囚われてはいけないということを学びたい。
- 合評
-
-
映像を見ると、下がり藤の紋の幔幕に囲まれた鹿園で、追い立てられ逃げる鹿が倒されて、角を切られていました。立派な角を持った鹿が、切られると情けないような姿でした。つきやぶらんと逃げますよね。 (もとこ)
-
春日大社の鹿の角切りですね。鹿が暴走する迫力が伝わります。 (豊実)
-
幔幕は何の行事が行われていたのでしょうか。書かれていませんが角切りだろうと。鹿という動物はなにやら哀れを思わせます。 (素秀)
-
この句の季題は「鹿の角切」であろう。角切は春日大社の秋の神事である。交尾期の牡鹿は猛々しいが、勢子たちに力ずくで押さえ込まれて角を切り落とされる。角を失い幔幕を突き破らんとするほどの勢いで一目散に逃げて退場する鹿に哀れみを覚える。 (せいじ)
-
奈良の秋の風物に鹿の角切があります。逃げまどう鹿を勢子が投げ縄で追う情景だとおもいました。 (ぽんこ)
軒すだれなくなつてをる野分かな コメントを書く
(のきすだれなくなつてをるのわきかな)
「野分かな」の切字になっていますが、「野分跡」の雰囲気であることがわかります。台風ほどのひどい風ではないからと侮っていたら収まって外へ出たら「あらっ!」という驚きでしょう。夏の間つかっていたすだれは止めてある紐なども古びて弱っていたのかもしれないです。素秀解のとおり、ホッとした安堵感も感じます。「とばされてをる」だと説明になるが「なくなってをる」と表現したことで驚きがあり、作者の小主観が隠されている。
- 合評
-
-
夜の激しい風が過ぎ去り、翌日の野分後は、すだれが無くなって明るい空が前よりも広がっているような気がします。 (もとこ)
-
台風が来て、軒のすだれが飛んで行ってしまったのだと思います。「なくなってをる」とあるので、なくなってから気づいたと思います。 (なおこ)
-
軒の簾はそろそろ片付けるつもりだったのに、野分がそれを吹き飛ばしてしまった。夏から秋へ、季節の移り変わりがしみじみと感じられる。 (せいじ)
-
一晩で過ぎ去った台風のようです。朝、気が付くとすだれが飛ばされて無くなっている、うっかりしまい忘れていたのでしょう。このくらいで良かったと諦めの気持ちも出ています。 (素秀)
-
昔は今のような台風情報はなかったでしょうが、台風に備えて軒すだれぐらいは収納しておきたかっったですね。軒すだれを吹き飛ばされてあっけらかんとした感じです。 (豊実)
(かみのはとあそびにきたるひがたかな)
干潟は、波浪の影響を受けにくい穏やかな入り江や湾内で砂泥を供給する河川が流入する場所に多く、漁港なども発達します。近くに海に向けて大鳥居の立つ海神社があり、参道の延長線上に干潟がひらけていて、浜辺には漁網などが干されている…そんな漁師町の風景を連想します。ハト類は木の実・草の種を主食にしているため干潟とは縁が薄いですが、干潟の生まれる春は鳩の繁殖期にあたるので餌探の行動範囲も活発になるのでしょう。ミネラル類が不足するので塩分補給のために海水を呑むアオバトという種類があるのをテレビで見たことがあります。
※鑑賞は直訳で終わらず、できるだけ連想をひろげるようにしましょう。隠された作者の小主観を汲みとる学びも必要です。
- 合評
-
-
鳩は八幡大神の使いであったり、吉兆を知らせる縁起の良い動物です。干潟に来るイメージはあまり在りませんので、遊びに来たと表現したのかと思います。 (素秀)
-
干潟にいる鳥類は鷺、千鳥、鴫などの仲間で食性の違う鳩が来ているのでおやっと思った作者。神社にいる鳩を神の鳩と言い遊びに来ていると俳諧味豊かに詠んでいます。 (うつぎ)
-
神の鳩とは、神社に棲みついた鳩のことではないだろうか。干潟のできる海辺の近くに神社があり、そこから鳩の群が飛んで来て貝や小魚を啄んでいる。干潟は鳩たちの恰好の遊び場となった。 (せいじ)
-
ノアの箱船の物語では鳩がオリーブの枝をくわえて戻ってきます。広い干潟に降り立った一羽の白い鳩がノアの箱船の物語を思い起こさせたような気がしました。(豊実)
飛びまはる元気な籠の虫買ひぬ コメントを書く
(とぼまはるげんきなかごのむしかひぬ)
昭和年代は竹で作られた虫籠でしたが、昨今はプラスチックやガラス製の飼育ケースが主流になって風情がないですね。昔は祭りの夜店などで籠入りの虫が売られていました。作者はそれを買ったのです。竹製の虫かごを釣り忍のように縁に吊るし、端居しながら庭から通う涼風とともに虫の音色に寛いだものです。そんな風流を愉しむ余裕すらなくなりつつある世相は悲しいですが、せめて私達俳人はその境地に遊ぶ心を忘れずにいたいです。10年ほどまえ、品女さんのご主人が鈴虫の繁殖を趣味にしておられ、帰省した折に託されて青畝師のかつらぎ庵(甲子園)までお届けしたことを思い出しました。
- 合評
-
-
鳴き声のいい鈴虫などは土を入れた壺などで飼うので籠はきりぎりすかなと思いました。きりぎりすは夏に鳴きますが秋の季語で涼し気ないい声です。何の虫であれ風流な人ですね。元気なのを選んで元気に鳴いてもらわねば。虫の声で句を作ろうと思われたことも想像させます。 (うつぎ)
-
買ひぬとあるので、売っている虫としては、スズムシやマツムシかと思われます。昼間に飛びまはる竹籠の中の虫は、夜になれば良い声を聞かせてくれるのでしょう。(もとこ)
-
飛び回るでスズムシやコオロギなどの鳴く虫では無いのかなと思いましたが、普通に籠で飼う虫は声の良い鳴く虫です。よほど籠の中で跳ねまわっていたのでしょう。どうせなら元気なほうが良いに決まっています。(素秀)
-
秋のひと日、虫籠を買う。籠は竹籠であろう。どの籠が部屋に合うだろうか。しかし作者は、籠ではなく虫の様に目を向ける。コオロギ系かキリギリス系かは知らないが、飛びまわっていて元気のよい虫を選ぶ。今夜はきっとよい声を聞かせてくれるに違いない。 (せいじ)
-
加代子さんはこの時体調を崩されていて、籠の中で元気に飛び回る虫に励ましてもらっていたのではと推察しました。 (豊実)
青海苔の原となりたる干潟かな コメントを書く
(あをのりのはらとなりたるひがたかな)
青海苔といへば養殖が盛んであるが、天然物のそれは河口付近の淡水と海水が混ざった汽水域で冬から早春にかけて自生する。11 月〜 2 月までを寒海苔、4月〜 5 月を張る海苔という。天然物の青海苔は四万十川の河口付近でとれるものが有名で、素秀解のとおり石がごろごろした場所に引っかかる感じだと思うので、干潟のイメージとは似つかわない。ひょとしたらこの青海苔は、海で育つ「あおさ」のことではないかと思う。あおさがびっしりと渚に打ち上げられる情景はよく見る。正確に言えば青海苔とあおさは別物である。時化あとの干潟かもしれない。
- 合評
-
-
青海苔も干潟も春の季語ですが、どちらが主季語かと考えると干潟の方かなと思われます。砂浜というよりは石の河口あるいは海岸のようです。 (素秀)
-
春の大潮の浜は遠くまで干上がって干潟をなす。その干潟が一面青海苔に覆われている。鮮やかな緑が草原を思わせる。干潟と青海苔という二つの季語が相俟って春の浜辺の大景を美しく描いている。 (せいじ)
花むしろ按摩をさせてをりにけり コメントを書く
(はなむしろあんまをさせてをりにけり)
確かに一人称にも三人称にもとれる句です。この句の詠まれた昭和40年、日本は高度成長期にあり、食べて呑んで騒いで日頃の憂さを発散するというような現代のお花見とはちがって、花下に寛いでゆったり、のんびりと酒宴をたのしむという雰囲気があったと思う。季語の「花筵」もブルーシートではなくて、本物の茣蓙をうち広げ、長老格のスポンサーが上座でご機嫌だったりというような情景も見た記憶がある。この句はそのような贅を感じさせる花筵のようすを写生したのではないだろうか。「なんとまあ」と、ややあきれ顔で眺めている作者の姿も連想できる。
- 合評
-
-
作者が按摩をさせているのを見ている方だと思います。この年代の方は(私の父母の年代)、家人にしてもらう時には、させてをりという言い方はしないと思います。季語花むしろのゆったりした情景の中で、按摩までしているのんびりした花見が浮かびます。見ながら微笑んでいるような。 (もとこ)
-
作者が花見をしながら肩か腰を揉んでもらっているのか、揉んでもらっている人を見たのか、どちらとも取れそうです。どちらにしても桜を見ながら身も心も緩んでいそうです。 (素秀)
-
家の庭の桜の木の下に敷物を敷いて花見をしている。今日ぐらいはと夫に按摩をねだる。夫はそれに応える。花の美しさと夫の優しさに肩の凝りが少しづつ解れていく。させちゃったと舌を出しているような茶目っけが感じられる。 (せいじ)
-
愛する人に按摩をしてもらっているのでしょうか?按摩をする手に花びらがひらり。 (豊実)
身づくろふ気配ただよふ朝寝かな コメントを書く
(みづくろふけはいただよふあさねかな)
春の季語「朝寝」の句としてはユニークな作品です。吟行大好きだった加代子さんなので一泊吟旅での作品ではないかと想像しました。夜の句会を終え、翌日に備えておしゃべりもそこそこに、明日は早起きして朝食前に吟行しましょうと約束して早々に床につきます。数人が同室で寝ているのですが、すぐに寝つける人と昂ぶってなかなか眠りにつけないタイプがあります。翌朝寝覚めのよい人たちが早朝吟行に出かけるために身繕いをしはじめます。寝付きの悪かった作者は、うつらうつらするまどろみの中でその気配を感じたのですがすぐには身体がいうことをきいてくれないのです。季語の「朝寝」がその雰囲気を代弁しています。「身づくろふ気配」に女性を連想された、もとこ解には脱帽です。宿浴衣や寝具をそっと片寄せたりしているのでしょう。男性の場合は、「○○さん、朝吟行の時間だよ!」と叩き起こしているでしょう。
- 合評
-
-
共働きの夫婦で起きる時間が違う場合もあるかと思います。方やそろそろと起き出して朝の用意をし始めているのかと。起こしてはいけないので静かに行う配慮もありそうです。寝ている方もそれに気がついていて甘えているようです。 (素秀)
-
男性に身づくろふ気配とは表現しないと思うので、旅の宿で同室の女性の気配だと思います。同室の人を気遣って、こっそりと身支度している相手の様子を感じながらも、朝寝から目覚めたくない、ちょっとイラッとした気持ちかも。 (もとこ)
-
家の外では人が動き出した気配を感じ、そろそろ見繕いをしなくっちゃという気持ちはあるのに、眠りからさめてもなんとなくうだうだしている春の朝。 (豊実)
-
ついついしてしまう春の朝寝である。身づくろいをしているのは夫だろうか。まだ完全には目覚めていないので、ぼんやりとその気配だけを感じている。朝寝の心地よさと同時に、「気配ただよふ」によって、ちょっとばかりの居心地の悪さが伝わってくる。 (せいじ)
教はりしもの芽をまたぎ次を問ふ コメントを書く
(おそはりしものめをまたぎつぎをとふ)
早春の山野をグループで吟行している風景が見えてきます。「またぎ」がそれを連想させています。好奇心旺盛な新人が物知りの先輩に次から次と教えを乞うているのでしょう。一人称で詠まれていますが、主人公は同行者で問われているのは作者自身である可能性もあります。こんなことでも句材になるのかと思うくらいわかりやすい作品です。加代子さんの身辺句は、平明な言葉づかいと徹底した省略のテクニックが個性を生み出しています。知識や語彙がなくとも素直で新鮮な句が詠めることがよく分かりますね。
- 合評
-
-
山歩き吟行なのか、新芽を見つけてはこれは何なのか聞いている作者が目に浮かびます。下五の次を問ふ、は見習いたい止め方かと思います。 (素秀)
-
もの芽、またぎ、次を問うで春の野の息吹や作者の躍動感が伝わってきます。言葉の効率のよさを学ばねばと思います。 (うつぎ)
-
いろいろな草の芽、木の芽をひっくるめて「ものの芽」というと歳時記にありますが、この場合はまたぎとあるので、草の芽でしょう。春の野山で何の芽であるか教えてもらいながら、次へ、次へと問い、春が来ているという喜びを感じます。 (もとこ)
-
いろんな草の芽の名前を教えてもらいながら小径を散歩しているのでしょう。次の別の芽に興味をそそられ、つい、またいでしまったその芽にちょっとごめんなさい…。 (豊実)
-
もの芽は地面から萌え出た草の芽であろう。野山にそれを探し名前を教えてもらっている。「次を問ふ」によって草の芽の種類が多いこと、「またぎ」によってそれらを踏まないように気をつけて歩いていることがわかる。作者は春の息吹きを身をもって楽しんでいる。 (せいじ)
(おてのくぼさかずきほどやひなあられ)
招かれてお母さんと一緒にひな祭りの集いにきてくれた幼子を想像しました。ご褒美に雛あられを貰ったのでしょうね。飾られたひな壇の前にちょこんと正座して、紅葉のような小さな掌をくぼめて差し出し、こぼさないようにと緊張しながら雛あられを受けとる愛らしい幼子の所作が見えてきます。掌に焦点を絞り他は一切省略されているのですが、連想によってどんどん情景が広がりますね。俳句は省略が大事だということを教えられます。「掌」は、辞書では「てのひら」としか読めないと思うのですが、俳句では「て」と読ませる用例も多く、前後の言葉を見てどちらに読むかを判別します。
- 合評
-
-
小さな女の子が両手を合わせて差し出す窪み。色とりどりの雛あられが、盃ほどの量でも、差し出された小さな手には溢れるばかりの量に思えます。 (もとこ)
-
掌のくぼみに乗った雛あられを、盃ほどの量であると言っています。可愛い掌だと思います。 (なおこ)
-
小さな女の子の手の平の窪みにのせた雛あられ。盃ほどと言うからには、赤ちゃんかもしれない。いずれにせよ、可愛い一句です。 (豊実)
-
雛祭りの日、着物にきかえたちっちゃい女の子が雛あられを分けてもらっている。差し出された手の窪は盃ほどの小ささ。本当に愛らしい。手は右手だろうか左手だろうか。「お掌」に気品を感じる。 (せいじ)
-
子供の手のひらに雛あられがのっています。小さな手にはほんの盃ほどの量ですが、子供本人は手にいっぱい貰って喜んでいるのです。 (素秀)
肩掛けをいま膝掛けに講義聞く コメントを書く
(かたかけをいまひざかけにこうぎきく)
「…をいま」という表現にこの句のポイントがある。肩から外して畳んで手元に持っていたものを膝にかけた…のではなくに、肩に掛けていたものが膝の上に移動したという瞬間の意の「…をいま」だと思う。「講義聞く」からは大勢の聴講者と講義が進行中であることが連想でき、当時の暖房システムから考えると講義中に会場の人いきれが徐々に加わって上半身は暑いくらいになってきたのでそれを外し、集中力が途切れないように畳まずそのままそっと膝の上にかけたというような情景ではないだろうか。
うつぎ解のように講義が始まる前にとって膝の上においたとも考えられるが、どちらにしても「…をいま」の措辞が肩から膝へ移動した一連の所作であることを暗示していると思う。「肩掛けをいま膝に掛け」でも句になるが説明っぽくなるのを避けて、「肩掛けをいま膝掛けに」になったと思われる。このあたりの推敲が非凡で大いに学ぶべきところであろう。この句には女性心理の機微が隠されているようにも思えるので男の私には自信がなく、あらためて女性の意見を聞いてみたい。合評は追記も大歓迎です。
- 合評
-
-
「いま」が気になる。そもそも肩掛けは戸外で利用するもの。講義を聞くうちに、待てよ…と襟を正し、肩掛けをしたままで聞くには失礼かと気づき、(いま)そっと膝掛として利用することにした。講義の内容が素晴らしいものであったのかもしれない。(そうけい)
-
暖房があっても暖気は上に行くので足元が冷える。受講前に肩掛けを膝に掛替暖かくして講義に集中しよう。一枚の肩掛けは今膝掛けとなりとても便利。そんな句だと思う。季語は肩掛けです。 (うつぎ)
-
肩掛けも膝掛けも冬の季語です。長時間の冬の講義の厳しさが、いま膝掛けに、で良くわかります。 (素秀)
-
講義が佳境に入ったころ、足元は冷え始め、肩に掛けていたショールを膝に掛けかえたのだと思います。膝掛けが季語だと思いました。肩に掛けていた『ショール』が冬の季語であり、寒さを凌ぐために 1 枚のショールをうまく使っていることを表現した俳句だと思います。 (なおこ)
-
何の講義かは分からないが、講義を聞く部屋は現在のように暖房が完備されていないのだと思う。寒い中でじっと座ったままでいるとどこよりも膝が冷えてくる。耐えられずとっさに肩掛けを膝掛けの代りとして使った。「いま」に機敏さを感じる。外用の防寒具を内用の防寒具として代用するとっさの機転が面白い。肩掛けも膝掛けも冬の季語だが、実際この場にあるのは肩掛けなので、この句の季語は肩掛けだと思う。 (せいじ)
-
寒い部屋で長時間の退屈な講義を聞いているのでしょう。手持ちの肩掛けを膝にかけて凌いでいます。 (豊実)
-
今日から昭和40年の作品となる。
口いつぱい太串さして鮎を焼く コメントを書く
(くちいつぱいふとぐしさしてあゆをやく)
素秀解のとおり海魚は活きの良い姿で焼き上げるために「踊り串」といって金串をうって平焼きしますが、川魚は水分が多いので口を下にして焼きます。焼いている間に口から余分な水分が滴り落ちで身がふっくらと焼き上がるからです。川魚は身が吸い付きやすい木串や竹串を使います。この串は裾が広がっていて焚き火や炭火の周辺に縦にさして焼くのですが、魚の重さで下へずれないようにするための工夫だということです。「口いつぱい」というのは大げさですが、カッと大口をあけた状態であることを連想させています。俳句の絵としては、まるまると太った鮎が良い香りを放ちながらこんがりと美味しそうに焼けていく様子を想像したい。
- 合評
-
-
この鮎は、料亭などの上品な立ち鮎ではなく、釣たての獰猛な鮎。口から金串を差し込み、川岸で焼き、かぶりつく情景が思い浮かびます。 (もとこ)
-
口が一杯になるほどの太串ですから竹製か木製の串を持って熱々を丸囓りするような川辺で焼かれている鮎を想像しました。美味しそうではあるが太い串に哀れみも少し…。 (うつぎ)
-
そこまで太くなくてもというぐらい太い串を口に押し込まれた鮎。鮎が気の毒なような滑稽さを感じました。 (豊実)
-
川魚は口から海魚は目から串を差すなどと言いますが、太串とはいえ口いっぱいになるのですから少々小ぶりな鮎なのかも分りません。口いっぱいのいきいきとした描写で美味しそうに焼けている鮎が目に浮かびます。 (素秀)
(つまたりしいくさのころやとりくもに)
「鳥雲に入(い)る」は仲春の季語で俳句では「鳥雲に」と省略されることが多く、冬鳥たちが春になって北方へ帰るとき、はるか雲間に消えゆく情景をさす。長旅の無事を祈る気持ちと別離を惜しむ感情とが含まれる。「いくさ」は太平洋戦争のことではないかと思いたい。加代子さんは大正10年の生まれ、太平洋戦争は昭和16年〜昭和20年であるから当時は20〜24歳になる。またこの句が詠まれたのは昭和38年なので戦後18年前、42歳の作品である。
戦時中の既婚歴があったかどうかは詳しく聞いたことはないが後年の北人さんとは再婚であったと聞くから、若くして結婚され戦争中にご主人をなくされたのかもしれない。「鳥雲に」の季語から連想すると、ご主人が亡くなられたのはソ連軍の捕虜となったシベリア抑留と関係するのではとも想像できる。北へ帰る鳥たちを眺めながら旅路の無事を祈るとともに、ご主人の無事帰還を祈り待ち続けた頃の思い出が蘇るのであろう。
- 合評
-
-
妻であるが故の戦とまで言わないといけないような苦しい日々があった。鳥が雲に消えて行く空を見ているとしきりにその頃が思いだされる。 (うつぎ)
-
「鳥雲に」の情緒はどのようなものだろうか。調べてみると、「鳥雲に入る頃は春の喜びではあるが、冬と別れる惜別感もある。冬の厳しさ、凛然たる美しさが薄れて、心身の張りが失せたような淋しさ、鳥の姿の欠落した風景に呆然と立つ人間の感情もある」とあった。とすれば、私の勝手な想像ではあるが、作者はこの季節に夫を亡くしたのではないだろうか。「いくさ」についてもいろいろな想像ができるが、一つには夫の病いが思われる。妻も夫とともに戦ったが夫はついに帰らぬ人となった。雲に消える鳥の姿に夫が重なる。ちょっと想像が過ぎるだろうか。 (せいじ)
-
いくさの頃をどう解釈するかが問題かと思います。妻という戦いの頃か、妻という兵士の頃か。どちらにしても鳥が雲に消える頃、戦いの最中にいたと読むべきなのかと思います。 (素秀)
-
この句は昭和38年の作です。
(ひとつぶのなみだうづめてひをけなづ)
火桶は骨董品として高値で売られているのネットで見ましたがを、昭和37年代には普通に使われていたんですね。下五の「火桶撫づ」によってうれし涙ではないことがわかります。悲し涙なのかあるいは悔し涙なのでしょう。悲しさや悔しさにうち勝たねばと自身に言い聞かせながらも火桶の中の炭火の炎をじっと眺めていると思わず不覚の涙が火桶の灰に落ちたのである。「いかんいかん」と我に返りあわてて灰を寄せて痕跡を消し、火桶の縁を撫でながら気持ちをリセットしているのである。映画の一シーを見ているようです。
- 合評
-
-
この涙はこの火桶にめんじて癒され許そうと!灰をかき寄せ火桶を撫でじわじわと伝わる温もりに浸る時の経過を感じる。 (そうけい)
-
火桶の中の灰に涙がポトリと落ちた。火桶を撫でながら悲しみをこらえているのでしょう。 (豊実)
-
火桶は木をくり抜いて内側に銅板などを貼った暖房器具。火鉢は陶製です。灰にふと落ちた涙を火箸で混ぜたのでしょう。何があっての涙なのか、とりあえず作者を慰めているのは火桶だけであったと言う事でしょうか。 (素秀)
-
火桶は木製の丸い火鉢のことと知りました。炭火の温もりとともに木の温もりも感じます。悲しみは今日だけのことではない。一粒の涙は今日一日の悲しみ。一日の終りに悲しみを灰に埋めて火鉢の温もりに慰撫されている女性。炭火は消えて温もりは火鉢の縁に残っているだけかもしれません。撫づが切なく感じられます。 (せいじ)
金網をとび出て薔薇のひらきけり コメントを書く
(かなあみをとびでてばらのひらきけり)
園芸種の薔薇は四季咲きのものが増えているが、俳句では初夏の季語とされていて、秋に再び咲くものを秋薔薇(あきそうび)、寒い冬の時期まで咲き続いているものを冬薔薇(ふゆそうび)と詠まれていてそれぞれ風情が異なる。冬に強剪定された薔薇は春になると新しい枝を伸ばし蕾をつける。この句の薔薇は元気がよく金網の網目から飛び出し、網目のサイズよりも大きく花を開いているというのである。「出し」と「出て」の違いに着目されたうつぎ解に感服です。金網は外部からの侵入者を防ぐ防犯のためのものであるが、内からそれを飛び出しているというところに滑稽さもある。椿や山茶花など他の庭木でも似た様子は見かけるが、「とび出て」の感じは薔薇にふさわしい。
- 合評
-
-
薔薇がひらいている驚きと、出しではなく出てに薔薇の意思を感じさせます。ひらいたのを見て見てと薔薇が言っている様に作者は感じたのでしょうか (うつぎ)
-
咲いてからでは通り抜けることができない金網の目。蕾ができる前ぐらいに金網の目を抜けて茎が伸び、薔薇の花が健やかに咲いた。 (豊実)
-
薔薇は初夏の季語。ツルバラなのかも知れません。フェンスの金網を抜けて蔓が伸びて花が開いている。これから盛りを迎える薔薇の勢いが感じられます。 (素秀)
クローバをおしつけながらシーソ漕ぐ コメントを書く
(クローバをおしつけながらシーソこぐ)
「シーソ漕ぐ」なのでクローバを押し付けてるのは足だと分かります。「おしつけながら」の措辞がたくみで踏まれても踏まれても又起ち直ってくるクローバのたくましさが感じられ季語が活きています。この句から学ぶべき点は、一人称で詠まれていることです。実際はシーソで遊んでいる子どもたちの様子であった可能性があり、写生を強く意識しすぎて嘘がつけないと「クローバをおしつけシーソ漕ぎをりぬ」と三人称表現になります。三人称の場合は、楽しそうに遊ぶ子どもたちの姿が主役になり季語の働きが弱くなりますが、一人称にしたことでクローバとそれを押しつけている足だけがクローズアップして見えてきます。三人称表現が駄目という意味ではなく、必然性がなければ一人称にしたほうが句に余裕が生まれて焦点を絞りこむことができるので力強い句になるという意味です。
- 合評
-
-
季語のクローバがよく効いている句だと思います。ふわふわした緑が見えておしつけるの措辞もぴったりです。足で漕いでいる様子がよく伝わり見ている人を幸せな気分にさせます。 (うつぎ)
-
シーソーの板の端が当たるところは草が剥げて地面がむき出しになっていることが多いので、クローバーを押し付けているのはシーソーを漕いでいる人の足、靴かもしれません。シーソーを漕ぐには反動をつけなければならないことを考えると、おしつけるがよくわかります。 (せいじ)
-
シーソの端でクローバをつぶすのは申し訳ない。でも、シーソの周りに沢山のクローバが広がっている長閑な風景が見えます。 (豊実)
-
クローバーやレンゲが敷き詰められるように生えていると入って行きたくなるものです。寝転がって空を仰ぐ解放感は春そのものです。この句はシーソーを漕いでいるもですが、同じような気持ではないでしょうか。 (素秀)
-
クローバーが一面広がる草地の遊び場でシーソーをしている女の子を思い浮かべました。シーソーの板が地面につくとき、クローバーを押し付けているようでかわいそうだけれども、楽しいからシーソーを漕ぎ続けている。春を楽しみながらも、ちょっと申し訳ないような気分がうかがわれます。 (せいじ)
(ずいどうをでてきしまどやらつかあぶ)
確かにこの句、車内から見た窓景色と隧道を出てきた車窓を外から見た様子のふた通りにとれます。そうけい解にあるように私も「出てきし」の措辞にちょっとひっかかる。もし前者だとすると「隧道を出でたる窓に落花舞ふ」という感じに詠むのが普通で、「落花」が主役で「窓は」脇役になる。ところが揚句では「窓や」で切れが入っているので「窓」が主役で、その結果「落花」は脇役になっている。作者は隧道の出口を見ていて忽然と現れた車窓に驚きその瞬間を写生したかったのではないかと思う。「浴びる」は、高所から降るものを「頭から浴びる」という意味の省略だと思うので、隧道をでて花吹雪のなかを過ぎゆく車窓だとするほうが景が大きくなるように思う。ただし、いつも書いているように俳句鑑賞に絶対正解はない。
- 合評
-
-
落花を浴びると幸せな気分になります。ましてや暗いトンネルを通り抜けて来た直後です。窓越しであっても明るさと落花に感動されたのではないでしょうか。苦難の後にはきっといいことがあるよと飛躍してとる人がいたかもしれません。 (うつぎ)
-
隧道を出てきしの、きしと、窓やの、や、から作者は乗り物を外部から見ている。急に出てきたその窓に落花を浴びている。その花の中突き進む近代の乗り物と自然の素晴らしさを対比しているように感ずる。 (そうけい)
-
長いトンネルを抜けると、花吹雪で、列車の窓に花びらが舞い込んできたのだと思いました。 (なおこ)
-
山間のローカル線を想像しました。長いトンネルをやっと抜けて出てきた車窓に、目も眩むような明るい光と降りしきる落花があった。窓と自分が一体化しているようです。驚きと喜びが感じられました。 (せいじ)
-
トンネルを抜けると、そこには美しい桜並木があり、列車の窓に花びらが降ってきた。(豊実)
-
隧道を車で通ったのでしょうか。それとも電車なのかも分かりません。トンネルを抜けた途端に花が散るさなかで、窓から花びらが舞い込んできたのかと。(素秀)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
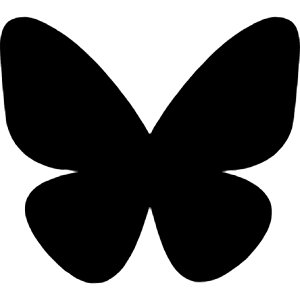 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()