2020年3月
目次
これこそは美爪術したりさいたづま コメントを書く
(これこそはマニキュアしたりさいたづま)
虎杖の若芽はウドに似、緑色の茎に紅色、微紅の斑点がある。茎の先の二葉の美しい紅色をマニュキュアをしたのだという。この着想には全く驚く。美爪術の漢字を当ててあるもののマニキュアのカタカナ語とさいたずまの古語のとりまぜの表現なのに違和感がないのが不思議で思わず笑ってしまう。まことに天衣無縫、自由自在ぶりである。
- 合評
-
-
さいたづまはイタドリの古名、伸び掛けた葉の先端が赤くマニュキュアのように見える。古名とマニュキュアの取り合わせが、自由自在です。 (素秀)
(じゆうがんにかぜをおこせしかすみかな)
ふと目にした銃眼を覗いてみたのは幼子のような好奇心。いつもこうした心持ちで自然と接することが俳句では大事である。案の定景色は霞で見えなかったが覗いた瞬間目に風を感じた。牆壁で遮られてわからなかったがわずかに風が流れていて繊細な感覚の目には隙間風のように強く感じられたのである。その驚きを直感だけで理屈を言わずに詠んだ直感直叙の句である。
- 合評
-
-
その昔この銃眼から弾丸が雨霰のごとく降り注いだ、そんな歴史に想いを馳せているのだろうか、または実際に小さな開口部を覗いてみたのかも知れない。霞がかった景は、まるで戦国時代の絵巻物のようだ。 (ひのと)
-
銃眼を覗くと風が吹き抜けてきた。見れば霞が棚引いている。この風はあの霞と繋がっているのだろうか。 (素秀)
よきお能ここを基とす雲雀かな コメントを書く
(よきおのうここをもととすひばりかな)
求めに応じて詠まれているのでいわゆる贈答句、挨拶句の類となる。「観阿弥創座地」の記念碑の建つ名張市上小波田はゆるやかな山に取り囲まれたしずかな田園地帯。能のもとという田楽、猿楽は、農民たちが田植の時に笛や太鼓で歌い踊った舞から高められた芸であることに併せ、小波田の地を思い合わせると雲雀の季語は動かないと思う。
- 合評
-
-
「観阿弥創座地」と脚注あり、名張市観阿弥顕彰会から句碑建立のために求められた句。(みのる)
-
能舞台に雲雀の鳴声が聞こえたのか、あるいは能の演目の雲雀山と掛けたのでしょうか。 (素秀)
-
ここを基とすという措辞から、この地に構えた能舞台がこの雲雀の鳴き声のように長く続いていきますように、という作者の願いが込められているようだ。 (ひのと)
(すみうすきいちしようそくやそうえきき)
確かにお悔やみや満中陰で薄墨をつかう習慣はあるがそれでは季語の宗易忌が生きてこない。この場合の「墨うすき」は水墨や俳画、絵手紙でよく使われる青墨かと思う。墨色がうすいということに利休の茶の心を連想されたのではないかと思う。書や俳画を能くされ茶も好まれた青畝師の古格を踏まえた作品である。
- 合評
-
-
宗易忌(利休忌)は陰暦2月28日であるが菩提寺の大徳寺では一ヶ月遅れの3月28日に法要と茶会が催される。(みのる)
-
お悔やみ状を受け取ったのか、あるいは作者自らが書き上げたのかはわからないが、恐らく身近な誰かが亡くなったのであろう。作者にとって特別な忌日となったことは間違いなさそうだ。 (ひのと)
-
満中陰志の礼状が届いたのではないでしょうか。薄墨の便りが利休忌のころに届いた、あれから月日の経ってもう春ではないかと。 (素秀)
(おびづかにあるべかりけるおちつばき)
虚子は生前椿を愛し、戒名は「虚子庵高吟椿寿居士」。比叡山横川の虚子塔の辺りは弟子の植えた椿が林となっている。帯塚の辺りにも椿の木が数本植わっている。文法的には矛盾と感じるかもしれないが帯塚に佇って詠んだものと考えたい。塚の辺りに落ちている椿を見て、適当の意の「あるのがよい」と得心したのである。
- 合評
-
-
帯塚は虚子の20年余り使い古した兵児帯を埋めた塚で太宰府都府楼跡に程近いところにある。(みのる)
-
作者はどこからこの落椿を見ているのだろうか、ふと庭先に落ちたものを詠んだのか、はたまた本当に帯塚に植えられるはずであった椿が存在していたのだろうか。いずれにせよ、この椿も師の帯塚にあってしかるべきものだったろうに、儚くも落ちてしまったという寂寞感に包まれている。 (ひのと)
-
あるべかりける、ですからどこかで見た落椿で帯塚に思いをはせたのでしょう。 (素秀)
(とりくもにいりおわんぬとよるはしら)
春、北方へ帰る鳥がはるか雲間に消えていく情景を鳥雲に入るという。鳥が雲に入ってしまった…で一たん切れて「と」と柱に倚りながら、尚も遥か彼方を見やっている作者が出てくる。去っていくものと、とどまっているものの対比が面白く詠まれている。また帰る鳥に対する心情も伝わってくる。主客合一の句。
- 合評
-
-
「畢んぬ(おわんぬ)」は「おわりぬ」の音便で「オワッタ」。 (みのる)
-
鳥が雲の彼方へ去って行くその瞬間を眺めていたのだろうか、凭れかかっている柱は作者の名残り惜しい心持ちまで受け止めているようだ。 (ひのと)
-
倚る柱が気になります。燃え尽きた感がすごいのですが。 (素秀)
(かげろふやどうぎようににんのかさすすむ)
「糸遊」は陽炎のこと。「同行二人」は二人連れであること。西国巡礼者がいつも弘法大師と一緒にあるという意味で笠などに書きつける語である。遍路とか巡礼と言わずに笠だけをクローズアップして写生した。「笠進む」と遠ざかっていく笠に焦点を絞ることで見送る作者の眼差しや心象まで見えてくるのである。
- 合評
-
-
同行二人の傘ということから遍路の様子であることがわかる、糸遊の季語や進むという動詞によって春の長閑さの中にゆっくりとした動きも感じられる。 (ひのと)
-
糸遊の揺らぎに弘法大師の背中を見たのかも知れません。 (素秀)
厨子よりも出でまさんとし御開帳 コメントを書く
(ずしよりもいでまさんとしごかいちよう)
観世音立像には両足を揃えていらっしゃるのが多いが、中には片足の親指の先を少し上げられているものや片足を数センチ前へ踏み出しておられる(遊び足という)のもある。いづれにしても扉が空いた瞬間に厨子から外へ出ようとなさっている感じだと直感したのである。動かれる筈のない仏様が「仏様の方から私の方へと近寄ろうとして下さる」クリスチャンである作者にはそのような信仰心理が潜在的に育まれているのかもと思う。
- 合評
-
-
ご開帳によって今まさに姿を現した秘仏の生き生きとした様子は、まるで厨子から外へ出て行ってしまわれるかのようだ。 (ひのと)
大法話いまつづきゐる彼岸かな コメントを書く
(だいほうわいまつづきゐるひがんかな)
知恩院での作とある。大法話の「大」は特別の法話なのか、高僧の法話の意味か、或いは大寺の雰囲気を表現するための大かと思われるが大法話と始まるゆったりした調子によって大らかな句柄になっている。俳句は瞬間を捉えるほど力強くなると紫峡師から教わった。瞬間写生とするための「いま」だと私は考える。「なほつづきゐる」とした場合との違いは歴然と思う。季語が彼岸なので彼岸法要であることは言うまでもない。
- 合評
-
-
大法話長長続く彼岸かなにすると如何でしょうか (董雨)
-
臨場感と法話に感銘を受けています。 (素秀)
-
感銘を受けているのは作者の青畝師です。言葉足らずでした。 (素秀)
-
いまが難しいです。正にいま法話の核心部に入って来たと解釈しましたが。堂の様子や聴いている人の表情など想像させる句だと思います。 (うつぎ)
-
青畝先生はクリスチャンでしたね。だとすれば外から法話の様子に気づき彼岸だなあという感慨だと思えてきました。彼岸かなですから。 (うつぎ)
-
ありがたい法話が聴衆を彼岸(極楽、あの世)に近づけていく様だと感じたのではないでしょうか。 (素秀)
苗札がひとりたふるることありて コメントを書く
(なえふだがひとりたふるることありて)
この作品は『自選自解』に収められていて「水をやって土が沈んだとき、真直に立てた苗札が脚が短かったのか自然に傾いて倒れた。わざと倒したのではなく全く自然に倒れれている。また私は挿し直すが、けだるい春の日が私にささやいた一つの動きだったように眺めた」とある。「苗札が」の「が」が「の」でない点に作者の意図があると思うが難しい。「ありて」の止めは次なる句へ橋渡しする連句の手法であるが余情を醸すのに効果的だと思う。
- 合評
-
-
苗札をひとりと擬人化しています。倒れている苗札の写生だけではなさそうです。 (素秀)
-
苗札がひとりでに倒れているのはよくある事てす。何か特別な思い入れのある苗だったのでしょう。直に挿し直したと思われます。 (うつぎ)
(よどじようにおふるみくさをあめのうつ)
淀城は鳥羽・伏見の戦いで消失したため現在は石垣と濠の一部を残すのみ。単に古い城跡に対して新しく生いそめた水草の取り合わせを詠んだとするのではなく、淀君のあわれを連想する作者の思いが込められていると鑑賞したい。叙情的なことばで直喩せず「雨の打つ」という写生にその思いが託されている。
- 合評
-
-
堀と石垣が残る程度の廃城に、水草が伸び春の兆しは見えるが、少し冷たい雨が無情に降っているなあ。 (素秀)
(そうしんのデウスにうたひそつぎようす)
註に「小林・聖心女子学院」とあり、お孫さんの小学校卒業の時の作品だそうです。講堂で卒業証書を受けたあと聖堂へ移動してミサが捧げられる。正面に高々と磔像が掲げてあり聖歌を賛美するのである。「磔像のイエスに…」ではなく「痩身のデウスに…」という具体的な写生によって非凡な作品になっている点を学びたい。
- 合評
-
-
デウスの解釈がポイントでしょうね。私はイエス・キリストの磔像かなと思います。 (みのる)
-
幼稚園がカトリック系だったので実感できます。家は真言宗なのですが。 (素秀)
いそがしや木の芽草の芽天が下 コメントを書く
(いそがしやこのめくさのめあまがした)
青畝師は好んで「天が下」をよく使われた。『太平記』の「天ケ下には隠れ家もなし」の用例のように、本来は、国土、天下、日本全国等の意であるが、大いなるもの(万物を生かされる神の存在)という捉え方もあると思う。眼前の些少な芽立ちを詠んだだけなのに、「天が下」の一語を据えたことで句に広がりが生まれ天地躍動、復活の春を迎える喜びに溢れている。
- 合評
-
-
青畝先生らしい滑稽味のある作品ですね。 (みのる)
-
天が下を使ってみたいと思いました。 (素秀)
-
天が下は、単純に空の下とも読めるし大いなる物の下とも思えます。 (素秀)
-
峠解ではなにも触れていませんが、私も大いなる者(創造者、キリスト教の神)を感じますね。 (みのる)
だるま草河童に幌を掏られけり コメントを書く
(だるまそうかつぱにほろをすられけり)
だるま草は座禅草のこと。ミズバショウに似ているが仏焔苞は紫黒色で形が達磨の座禅の様子に似るところからこの名がある。だるま草のすがれて幌(仏焔苞)の無くなったのを河童に掏られたという随分飛躍した着想であるが、だるま草の生える水場の感じがわかれば、なるほどと頷かされる。初心者には薦められない作法であるが虚を詠んでも虚と思わせないのが青畝俳句の真骨頂である。
- 合評
-
-
だるま草(座禅草)の実物は見たことがありません。分布の南限が滋賀県とのことです。 (素秀)
-
座禅草ですが六甲山の高山植物園に咲いています。 (みのる)
-
花が開くときに発熱するとか、独特な匂いがあるとか。ネズミなどに喰われた痕を、河童に掏られたと表現したのでしょうか。 (素秀)
(くめのこのつぶてをなぶるはるがらす)
田に降りてついばむ鴉に向かって石礫を投げるという子供達の行為は、「古事記」に歌われた闘争性を遺伝的に受けつでいるのかもと思った。そんな久米の子らの礫でさえ利口な鴉はからかうようにしてあしらっている。春の鴉は繁殖期なので活動的、温かくなって子供達もまた賑やかに野に遊んでいるのである。
- 合評
-
-
久米の子は古事記に詠まれています。 (みのる)
-
久米の子を調べました。久米兵士の強力な礫すら軽々かわすほど、春の鴉が軽快に飛んでいる景かと思います。 (素秀)
(いくたびのはるのおもひでさいぎようき)
西行は諸国行脚の末、河内の弘川寺の空寂上人を慕ってそこに住み「願はくば花の下にて春死なむそのきさらぎの望月のころ」の願い通りに73歳で入寂した。芭蕉が西行の跡を慕ったように青畝師もまた西行の遺跡を多く訪ねておられる。西行忌にあたって「いくたび同じような春の思い出を重ねてきたことであろうか」と感慨された作品。
この句の春の裏には、花、
桜が存在する。
- 合評
-
-
西行忌に春の思ひ出とストレートに重ねています。あえて春を使った理由が知りたいところです。 (素秀)
-
西行法師といえば、「願はくば花の下にて...」の歌が有名です。その辺りにヒントがありそうですね。 (みのる)
-
桜の咲く春に死にたいと歌った西行法師と、青畝師ご自身の春の思い出を重ねての感慨でしょうか。 (素秀)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
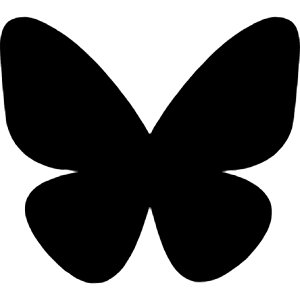 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()