2022年2月
目次
黄楊の雪大きく割れてゐたるかな コメントを書く
(つげのゆきおおきくわれてゐたるかな)
一読、黄楊でもなんでもいいように思えますしただの報告の句では…と思いました。でもよくよく考えてみると雪国での「雪解」を捉えた作品ではないだろうかと思います。みなさんの合評にあるように黄楊は生垣が多く、ときおり動物やキャラクターの形に剪定しているものもあります。おそらく生垣を虜にして深々と雪をかぶっていたのが、雪解が進んでふと気づくと大きく隙間があいて割れていたのである。「ああ、もう春がすぐそこまで来ているのだな」という感興だとすれば、なんとか鑑賞に耐えうるかもと思いました。素十さんごめんなさい。
- 合評
-
-
黄楊の生垣に今年は雪の多い年でした。ふと見るとその雪も大きく割れて、黄楊が貌だしああもう春がそこまで来ているんだと 春を実感している喜びの句だと感じました。 (よし子)
-
「雪」が冬の季語。黄楊は冬も緑色が美しく、小さな葉が密に生えるので、目隠しの生け垣に適した植物のようです。黄楊の緑色と雪の白のコントラストが目に浮かびました。生け垣の上に積もった雪が重みで落ち、割れたように見えている。美しく整ったものではなく、壊れた形のものに美を見出す作者の感性がすごいと思いました。 (むべ)
-
生垣、庭木?我家の庭に枝割の黄楊があります。形の整えられた枝は丸く平たく重なっている。枝と枝の間又は上枝から下枝への雪がバサと落れば割れたように見える。大きく割れていると大胆な表現をしているので面白く感じられたのでしょうか。 (うつぎ)
-
生垣の黄楊かと思います。ひとつなぎに選定されていますが、枝の疎らなところがあり、そこだけ積もった雪が凹んで割れているように見えるのかと。それにしても、大きく割れてゐたるかな、で済ませてしまえるのは凄いとしか言えません。 (素秀)
-
きれいに剪定された黄楊を覆っていた雪が溶け始めて割れたのではないでしょうか。庭の黄楊の様子にも春の気配を感じています。 (豊実)
-
常緑樹の黄楊は小さな硬い葉がびっしりとつき、枝分かれしていても剪定によってはくっついて見えます。雪が降るとこんもりと積もりやすく、雪の重みで枝分かれがくっきりと見えてきます。私の故郷の黄楊の木を思い出しました。何気ない風景をこのように詠めることに驚きます。 (あひる)
-
小さな花がいっぱいついた庭の黄楊の木に、季節外れの春の雪が被さっているのを想像した。黄楊は背の低い木で、ふつう、丸く盛り上がるように剪定されている。近接して植わっている二つの黄楊の木に雪が被さり、二つに割れているように見えたのではないだろうか。 (せいじ)
(あしかりのてんをあふいでくしけづる)
男も手櫛を使うが、揚句の場合は「芦刈女」として鑑賞するほうが情がありますね。女性の場合、長髪は束ね括って帽子をかぶるか姐かぶりをして作業されていると思う。それでも芦刈はずっとうつむいての作業になるのでどうしても乱れがちになる。繁忙期にはゆっくり腰をおろして休むこともできないので腰を伸ばして立ち休憩をしているのである。ため息をつくために天を仰いでいるのではなく、女性が長い髪を梳るときごく自然に顔を上に向けたり横に曲げたりした所作になる。女性らしいその仕草をみて作者は斯く写生したのである。そのように連想を広げると艶っぽさもでてきますね。
- 合評
-
-
芦刈の女性が、それまで括っていた長い髪をばらりとほどいて、梳っている様子を思いました。芦を刈るというような重労働をしていても、身綺麗にしていたい女性の気持ちが垣間見えます。まっすぐな芦のしげる中で、まっすぐに天を仰ぎ、まっすぐな黒髪が梳られる・・作者はそれを美しいと思ったのではないでしょうか? (あひる)
-
芦刈の重労働の中でも女性ならではのちょっとした仕草、手櫛だと思いますが見逃さず詠まれている事に感心するばかりです。よい天気なのでしょう。片方の手は腰に当てていたかもしれません。 (うつぎ)
-
腰を曲げての作業で時折り空を見上げては腰を伸ばして休憩しているようです。その時に乱れた髪を直すのですから女性だろうと思えます。重労働の合間にも身だしなみを忘れないようです。 (素秀)
-
「芦刈」は晩秋の季語。晩秋から冬にかけ枯れた芦を刈る女性を指す「芦(蘆)刈女」という季語もあるようで、水に浸かる重労働ながら女性の仕事だったのだなと驚きました。下五の「梳る」は休憩中に櫛で髪を整えているのかな?でも作業に櫛など持っていくだろうか?とわからなくなりましたが、「天を仰いで」できっと長い髪の女性なのだろうな。気持ちよく梳かしているのだろうなと思いました。 (むべ)
-
芦刈が秋の季語。芦は人間の背丈よりもかなり高いから、芦原にいると、密林に迷い込んだように感じるのではないかと思う。穴の底から見ているようであった秋の高い空が、芦を刈り取るにしたがって少しずつ広がって見えるようになる。一服して空を見上げ、乱れた髪を整えているのはおそらく女性であろう。 (せいじ)
-
女性も芦刈の作業にかかわっていたようです。昔は手で刈っていたので、腰も痛くなるでしょう。一休みし、髪を手ぐしでかきあげ、空を見上げている。作業は疲れますが、女性の笑顔も見えてきます。 (豊実)
(みかづきのしづむやひこのうらはうみ)
12歳で故郷の茨城を離れた作者は、中学生時代から帝大医学部に入学するまでの多感な時期を新潟で過ごした。いわば第二の故郷という感じではないだろうか。弥彦山に関しては、以下の説明がある。
弥彦山の標高は、東京スカイツリーと同じ634m。弥彦駅から徒歩で約15分、表参道登山口から山頂まで初心者でも1時間30分と登りやすく、多くの登山客が訪れています。弥彦山ロープウェーや、ドライブコースの弥彦山スカイラインもあり、気軽に頂上までアクセスできることも人気の理由です。
地元の人達に親しまれた「俺が山」であったと思われる。弥彦にもよく登ったであろう作者は山上の展望台から見える日本海や佐渡の景色が目に焼きついている。したがって揚句の景色は山の東側から月の沈む弥彦山をうち仰いで詠まれたものと思う。
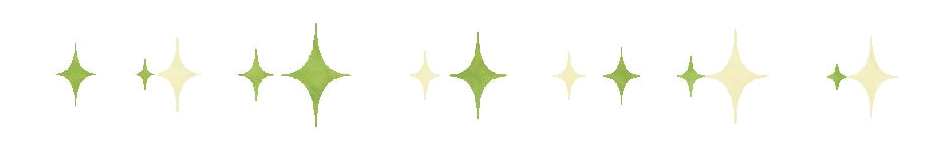
ところで三日月は年中どの季節でも見られるのになぜ秋の季語とされているのでしょうか。その点に触れないとこの句の鑑賞をしたことにならない。正解か否かは自信ないが私なりの感想を書いてみます。
まず、俳句では「月」そのものが秋の季語として育まれてきました。仲秋の名月を愛でるという日本古来の伝統から来ている。なので俳句の季語としては、
陰暦8月初めの月を「初月」、陰暦8月2日の月を「二日月」、そして3日の月を「三日月」としたのである。つまり季語としてのそれは、「三日月形だから三日月」なのではないということである。ホトトギス新歳時記には、以下の説明がある。
三日月は、夕暮西の空にごく細くかかる。二日月まではほとんど見ることができないので、「新月」といえば、初めて西の空に見える三日月を言うことになる。天文学上では朔の月を新月というが、地上からは見えない。
こうして考察すると揚句の三日月は、作者がこの年初めてみた新月ということになり、同じ伝統俳句を愛するものとしては、弥彦に沈みゆく新月を仰ぎながら作者が感じたであろうと思われるしみじみとした感興を共有させられるのである。
- 合評
-
-
去年の秋西空の三日月が、没した太陽に照らされ金色に輝き余りにも綺麗だったのですぐ見てと友達にラインしたが返って来たときはどこ?ともう消えていた。この句もすぐに沈んでしまうが故の三日月の美しさを弥彦山の向こうは海と言って惜しんでいるように思える。 (うつぎ)
-
秋の三日月は太陽を追うように沈んでいくので、西の空低くにあります。三日月が弥彦の山に沈む頃、太陽は裏の海に沈んでいて静かではあるけれどもすっかり暗くなっているようです。 (素秀)
-
弥彦とは弥彦山のことで、弥彦山にしずんでいく三日月を弥彦村から詠んだ句かなと思いました。作者のところからは見えないけれど、その山の裏には洋々と広がる日本海があることを知っていて、海にしずむ三日月を心の中で見ていたかも知れません。少しひんやりとした、美しい風景です。 (あひる)
-
三日月が秋の季語。弥彦は新潟県の弥彦のことだろう。弥彦村から見ると、西の弥彦山(東京スカイタワーぐらいの高さらしい)の裏側に日本海が位置する。作者は、そのことを聞いて、この弥彦山に登り、日没後の西の空にかかっている三日月が日本海に沈んでいくのを眺めているのではないだろうか。清澄な秋の空気を感じることができる。 (せいじ)
-
裏とは弥彦山の裏かなと思います。新潟を旅行中で、昼には弥彦山の上から佐渡島が見えたかもしれません。地図で見ると海と弥彦村の間に弥彦山があります。山に沈む三日月を見ながら今日一日の旅を振り返っているのではないでしょうか。 (豊実)
-
「三日月」が秋の季語。弥彦は新潟県の弥彦村でしょうか。(弥彦観光協会のサイトがすばらしすぎて長時間見入ってしまいました。行ってみたいです……)三日月は月の出も入りも西ですし、弥彦村の西7~8kmには日本海があるようなので、「弥彦の裏は海」は、作者が東の弥彦から西を眺めていたのかなと思いました。春三日月はお月様が寝ていますが秋三日月は立っているので、立ったまま海に吸い込まれるような月没だったかもしれません。海も山もある湯どころ、弥彦神社を擁する弥彦村は観光地でもあったかもしれませんが、この句からは静けさを受け取りました。 (むべ)
(じゆんじんやかぜおんじのかんぜおん)
私は見たことがないのですが、ホームページに以下の説明があった。
観世音寺には素晴らしい仏像が残っていることで知られています。平安時代から鎌倉時代にかけて造られた仏像18躯・石造狛犬・舞楽面などが安置されており、すべてが国の重要文化財です。それらの内には、約5メートル前後もある巨大な仏像<馬頭観音立像・不空羂索観音像立像・十一面観音立像>もあり、圧巻です。
写真では金箔像のようでより荘厳な感じです。御身拭(おみぬぐい)という晩春の季語があるのでその行事を直前に控えて一年分の塵が積もっているのでしょう。「春塵」という季語の斡旋だけで他には何も説明していないのにかくも荘厳な雰囲気を醸させているのにただ驚く。省略というよりは「寡黙の力」というほうが適切なのかも…
- 合評
-
-
何処の観世音でもない。寺の名に冠する程の立派な観世音である。うっすら埃を纏っている。遥か砂漠から吹かれてきた砂塵ま混じっているに違いない。何も語られていないのが返って作者の感動を伝えているように思う。 (うつぎ)
-
観音様を覆う塵ですから単なる埃もありがたく感じられます。春塵も春が来たことを思えば疎ましいものだけではないようです。 (素秀)
-
福岡県にある観世音寺と太宰府天満宮は幼い頃のわが家の三社参りや、たまにドライブのコースでした。天満宮は梅が咲き、梅が枝餅を売る多くの茶店があり賑やかでしたが、観世音寺は対照的でした。ひんやりとして、しーんと薄暗く、大きな仏像が聳えるように並んでいるだけの幼心に退屈な場所でした。その一体一体の仏像の頭に肩に春塵があって、お掃除できないだろうな・・と思ったような記憶があります。この句は、その時の光景を言いつくしていると思いました。 (あひる)
-
春塵が春の季語。九州の大宰府にある観世音寺であろう。7世紀後半から8世紀にかけて造営された古刹であり、かつては本堂に、本尊として聖観音座像、左右に十一面観音立像と不空羂索観音立像、東西の壁際には十一面観音立像と馬頭観音立像が祀られていたとのこと。作者は、観音像がなんと多いことよ、観世音寺というだけのことはあるなあと思ったのだと思う。春塵を纏った多くの観音像を見て、春塵→霾天→黄沙→唐→西方浄土と連想を広げたのではないだろうか。 (せいじ)
-
観世音寺の観音菩薩に春塵がうっすらとかぶさったのでしょう。観世音のリフレインに観音様への信仰心が感じられます。 (豊実)
-
「春塵」が三春の季語。ぜひ作句してみたいあこがれの季語です。観世音寺について調べてみたところ、大宰府の由緒ある天台宗のお寺のようです。特に高さ5mくらいある3体の木彫りの観世音立像は圧巻とのこと。安置されている建物の中は暗くひんやりと静かで、建物の外には強い春風で塵や埃が舞い上がっている。作者も世の喧騒を離れしばし静かな気持ちで仏像に対峙しているのではないでしょうか。 (むべ)
(ひやくしやうのちすじのわれにむぎあおむ)
みなさんの合評に補足の必要はないと思うので、倉田紘文氏の一文を紹介して私の鑑賞とします。
素十は茨城県北相馬郡山王村(現在は藤代町)に一農家の長男として生まれた。この<百姓の血筋>が、素十と自然とを宿命的に結びつけたと考えられる。
それは、「自然をどの程度に尊重しているかによって句の価値が定まる。自然、人生を肯定する俳句が私らの俳句である」の素十の言葉からも十分に伺われようし、さらには「写生といふ言葉から私は自然を大切に叮嚀に見るといふことを考へてをります」からも理解できる。
- 合評
-
-
「麦青む」は三春の季語。中七の「血筋の吾に」の助詞「に」がすごいなぁと思います。麦畑を眺めている作者に向かって青麦がそよそよと語り掛けるような光景が目に浮かびます。大地と天候を相手にする農業に誇りを持っていらっしゃる感じもあります。農家の血筋ではなく百姓の血筋なんですね。リアリティと実感がこもった言葉選びだと思いました。 (むべ)
-
青々として真っ直ぐに伸びている麦を見ていると気が沸き立ってくる。百姓の血筋を引いているからだろうか、そうに違いないと自問自答しています。 (うつぎ)
-
青々とした麦畑はもう見ることも少なくなっています。稲の青田と違うのは季節感でしょうか。冬が終わってそろそろ暖かくなり出した頃の麦の青さはまた格別なのかも知れません。さあこれからと言う百姓の血が騒ぐ感覚でしょうか。 (素秀)
-
麦青むが春の季語。青々とした麦畑を見ると血が騒ぐのであろう。大地を耕して生きてきた先祖の血が自分にも流れていることを実感したのだと思う。「百姓」と自嘲気味に言いながらも、百姓の血筋であることに誇りを持っているように感じる。 (せいじ)
-
麦青むが春の季語。麦畑が青々と広がる風景を見ると、農家に生まれ育った人には、そこに見えている以上のものが見えてくるのだと思います。麦蒔き、麦踏み・・その時々の両親の働く姿や、会話の響き、子どもの自分も出来る限り手伝った思い出。麦畑を見ただけで万感の思いが迫ってくることでしょう。 (あひる)
-
青く茂った麦を眺めながら、百姓を生業とし自分を育ててくれた両親に改めて感謝の気持ちを感じているのではないでしょうか。 (豊実)
(かもうちにいえのにようばうこをいだく)
山守をしながらこの時期には鴨打をしながら生計をたてて清貧に暮らしている若い杣の一家を連想する。鉄砲を使う以上少なからず危険も伴う。無事を祈りつつ幼子を抱いて夫を見送る妻の不安げな表情も見えてくる。女房ということばからは着飾ることもなく質素ななりわいの雰囲気が伝わる。みなさんの合評の通り、決して裕福が幸せの必須条件ではないことを伝えているようにも思える作品である。
- 合評
-
-
「鴨打」が冬の季語。鴨猟に出かけようとするご主人と、見送る奥さん、赤ちゃんを作者は見かけたのでしょうか。戦中戦後にかけて鴨は生息地の開発と乱獲で激減したそうですが、素十さんの時代はとり尽くさない持続可能な猟が行われていた時代だと思います。「子を抱く」でご夫婦はまだ若いことが察せられます。このご家族がつづがなく暮らせますようにと言う祈りのような気持ちも感じました。 (むべ)
-
猟に出る主人を捕れたらいいね。でも怪我のないように気をてけてと見送っているのだと思います。子を抱くで若いお父さんであること、つつましくも暖かい生活を窺わせます。 (うつぎ)
-
鴨猟が専業ではないかも知れません。農閑期でもあるし鴨でも撃ってこようかと出かけるのでは。妻子は夜の鴨料理を期待して見送っているような気がします。 (素秀)
-
鴨打が冬の季語。猟を生業としている家であろう。鴨打に出かける夫を、子どもを抱いた妻が見送っている。猟銃という物騒なものを持っているが、その背後には支え合う家族がいる。猟師であろうとサラリーマンであろうと何ら変わるところはない。 (せいじ)
-
鴨打が冬の季語。鴨打の家とあるので、鴨打はこの家の大事な収入源なのでしょう。鴨を打つ現場は、生きている動物の命をいただくことですから、平和な風景というわけにはいきません。けれども、ひとたび家庭に目を向ければ、そこには暖かい家庭があり、女房が赤ちゃんを抱いています。 (あひる)
-
夫は山へ鴨狩りへ、妻は家で子守をしながら家事をして、夫の帰りを待っている。日本昔話の一場面のような情景を想像しました。 (豊実)
(おおいなるたねゐまはりてひときたる)
春、苗代を作るとき、発芽を促すために稲の籾種(もみだね)を浸すのに使用する小さな池のことで、一節には「田な井」で田の中にある井戸とも。ゆえに「たない」と読むのが正しいのかも知れない。いづれにしてもそんなに大きいものではなさそうなので、揚句の「大いなる」の意をどのように解したものかと悩む。どのくらいの期間浸しておくのかは調べたけど定かではないが、ちょうどよいタイミングというものがありそれが苗の良否にも影響があるので、日々見回っているのであろう。
農協という仕組みができ現代はすべて分業化されて種井から始める農家はないと思うが、昔はすべての作業を農家単位でしていたのだと思う。
- 合評
-
-
「大いなる」は種籾の芽出しを担っている大事な井戸というようなことだろうか。種浸しをしている人が芽の出具合を確かめに井戸に回ってこちらに来るよ。ととりました。米作りの工程は近代化され今は変わっていますが句は昔の農村風景を思い出させてくれます。 (うつぎ)
-
「種井」は晩春の季語。調べてみたところ池や川、田んぼの片隅に作った井戸、とありました。傍題は「種池」「種浸し」だそうで俵のまま籾を浸けて発芽を促す作業とのこと。「大いなる」とありますので、かなり大きな池のようなところだったかもしれません。いくつもの工程を経て収穫の秋まで無事に迎えることは本当に大変だったことと思います。豊作を願う心も感じました。 (むべ)
-
種井は見たことがありませんが、湯船のような物の中で籾種を水に浸し、発芽を促すのだと聞いたことがあります。田植えよりも前にそのような目立たない作業があることに驚いた覚えがあります。この句では「大いなる」という言葉に、苦労や忍耐にも増して希望や喜びを感じます。この籾種が太陽や雨に恵まれて豊かに実ることを願いたくなります。 (あひる)
-
籾種を浸けているのは見たことはありませんが、田んぼの中にところどころ井戸があるのは知っています。昔は種井として使われていたのかも知れません。子供の頃は井戸のある田には絶対入るなと言われていましたから、おそらく何人かは落ちているのだと思います。最近だと田んぼの井戸はほとんどが厳重に蓋をされているか、埋めて井戸仕舞いをしているようです。 (素秀)
-
種井が春の季語。残念ながら見たことがない。この句の「種井」は、「大いなる」「まはりて」とあるから、田の中に作った種池のことではないだろうか。籾種を袋か俵に入れて20日ほど浸けるとのことであるが、こういうプロセスもあるのかと、つくづく農作業の大変さを感じた。今はほとんど行われず、農協で苗床づくりまでするとのことであるから、農作業もかなり軽減されているのだろう。 (せいじ)
-
種井の籾種の発芽の様子を見回っているのではないでしょうか。大いなるは秋の収穫に対する願いと期待の大きさかと思いました。 (豊実)
(たうちぐわひとりあらふやひとりまち)
粘り気のある田の土がこびりついた鍬は水たまりのようなところでジャブジャブしただけではとれないので、少し水勢のある用水路に水際まで下りていけるような小さな足場があり、地域の人はみなその同じ場所で鍬を洗うのでしょう。先の一人が洗い終わるのを待ちながら声をかけている様子が分かりますね。春の夕日は既に山の端に傾いていて、明日のお天気なども話題になっていることでしょう。
- 合評
-
-
田圃の側の用水路は草が被さって狭いが方方の田の取水口のある所は大きく水も溜まりながら流れている。そこで鍬を洗っている人と次洗おうと待っている人を詠んでいる。鋤き終わった話か世間話か農夫二人の声や恰好も見えてきます。 (うつぎ)
-
鍬などの農具を大事にしている農家の人の日常が思われます。農具をきれいに洗って大事にする人の畑では良い作物が育つというようなことを、子どもの頃聞いたことがあります。農業用の用水路が洗い場にもなっていたのでしょう。一日の農作業を終え、ほっとして和やかな気分だったことでしょう。 (あひる)
-
鍬で鋤き返しているのは牛なども入りにくい棚田かも知れません。作業が終わって川で鍬などを洗っていますが簡易的な石段がある洗い場は狭くて一人が洗っていると終わるのを待つしかないのでしょう。昔は川でおむつなども洗う共同の洗い場がありました。 (素秀)
-
「田打」は三春の季語。田んぼを鋤き返す作業が一段落し、使っていた鍬を洗っている・それを見ている光景。使った農具や収穫した野菜をどこで洗うのだろうとかねがね気になっていたのですが……田んぼに水を引く川や用水のそばに洗い場があったのでしょうか?また、洗っている人と待っている人は夫婦や親子かなと思いました。心地よい疲れやほのぼのとした春の田の美しさが伝わりました。 (むべ)
-
田打が春の季語。夫婦ふたりで田の土を鋤き返したあと、専用の水場で順番に自分の使った鍬を洗っているのではないかと想像した。作者自身のことかもしれないし、第三者かもしれない。夫婦は無言で作業をしているが、そこには阿吽の呼吸がある。ほのぼのとした暖かさを感じた。 (せいじ)
-
田打の作業を終えて、土のついた鍬を畦の水路で洗っているのでしょう。一人しか踏み込めないような狭い場所で足下に注意しながら洗っているのでは。次に洗う一人がその様子を見ながら待っています。 (豊実)
(もちのきのうへのふゆひにちからあり)
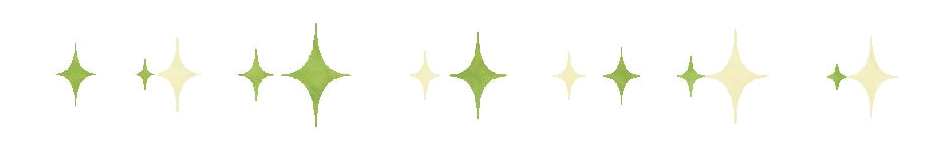
最近は庭木や街路樹としてのコンパクトサイズのモチノキがよく目につくが、本来はかなり大木になるらしい。「もちの木の上の」の措辞によって揚句のモチノキもうち仰ぐくらいのサイズらしいことが想像できる。そしてその上枝に鈴なり状態の赤い実に燦として冬日が絡んでいたのである。モチは枝先に赤い実をたくさんつけるので野鳥にとっても冬の間の貴重な食べ物である。
同じ大木の栴檀も金鈴子と呼ばれて黄色い実が空を覆うばかりに鈴なりになるが、こちらは10月頃なので枝に絡むのは秋日になる。冬日は秋日に比べると雲隠れが多く大抵は弱々しいというのが普通であるが、大木のモチノキに絡んでいる今日の冬日にはいつになく力強さを覚えたのである。
- 合評
-
-
黐の街路樹の道を通って時々買い物に行く。真っ赤な実をよくこんなについたものだ、鳥が汚して大変だといつも思っていた。この句を見て単純明快、冬日に力ありだけで 黐の実や葉の濃さを浮かび上がらせ句自体が力強い。我が鈍感さを思い知らされました。 (うつぎ)
-
「もちの木(花)」は夏、「もちの実」は秋の季語ですが、この句では「冬日」が主季語だと思いました。私の住んでいる地域では、地主さんのお屋敷などに防風・防火のためにクロガネモチという近縁種が植えられています。雌雄異株で実をつける木とつけない木があります。赤い実もあったかもしれませんが、冬でも常緑のもちの木のつややかな葉に、冬日があたって輝くような光景だったのかなと思いました。 (むべ)
-
冬の太陽の日照時間は短いです。今、もちの木の上にある太陽は赤い実を生き生きと照らしています。けれども少し日が傾けば寒々と夕暮れてくるでしょう。でも、まだ、もうしばらく、太陽は力を保ってくれそうです。 (あひる)
-
もちの花は夏、実は晩秋の季語です。冬に赤い実を付ける木は多く区別は難しいのですが、赤い実の艶を増しているのは冬日の力だろうと言っています。 (素秀)
-
冬になっても、もちの木のたくさんの真っ赤な実は蒼天をバックに光り輝いており、また、葉っぱも艶やかな緑色を保持している。そのようなもちの木の生き生きとしたありさまを、冬日によってもたらされていると見て、「冬日に力あり」と表現したのではないだろうか。 (せいじ)
-
もちの木を調べたら、御神木として植えられているところもあるようです。冬の日射しに、希望の温もりを感じたのではないでしょうか? (豊実)
(たべてゐるうしのくちより)
牧牛ではなく農家の耕牛のようですね。一仕事終えて牛が引っぱっても倒れないような太い木に繋がれて休ませながら畦草を食べているとも考えられますが、うつぎ解のように牛舎で朝食としての刈草を食べているというのが正解かも知れません。舌に絡めて口に含めたものをクチャクチャと噛みしだいている動作の中にチラッと赤のまんまが覗き見えたのです。秋の収穫後伸びた穭とともに鋤返す秋耕の季節を感じます。機械化の進んだ現代ではもう見られない風景です。
- 合評
-
-
「蓼の花」は秋の季語。飼育されている牛が食事をしている風景でしょうか。もぐもぐという擬音が似合いそうですね。粗飼料の青草や乾草、稲、藁などの間に蓼の花が混じっていて目立ったのではないでしょうか。今のように輸入されたトウモロコシや大豆かすの配合飼料ではないところにロマンを感じます。 (むべ)
-
牛のいる農家の朝の仕事は餌用の草刈りからです。露もろともに刈ってきた草を牛に与えます。牛のもぐもぐしている口に赤い蓼の花が混じった。この赤によって草の新鮮さも出ている。牛にとっては蓼の花が混じろうがおかまいなし。只々旨いのだ。 (うつぎ)
-
牛は一度飲み込んだものを胃から口の中に戻し、再び噛んで飲み込むという反芻をしますので、いつまでもいつまでもモグモグと噛んでいます。蓼に花がついていようがいまいが気にせず、モグモグと噛み続けていたのでしょう。こぼさないようにと気をつけたりなどしません。蓼の花は牛の口から覗いたり引っ込んだりしていたかも知れません。ゆっくり楽しんでね・・と言いたい気分です。 (あひる)
-
蓼の花が秋の季語。もぐもぐと動かしている牛の口から赤い米粒のようなものがはみ出している。よく見ると蓼の花であった。牛も蓼の花を食べるんだという驚きが感じられる。この牛は農家で飼っている役牛ではないだろうか。豊作の秋も感じさせる。 (せいじ)
-
蓼の花は派手なピンク色で牛の口からはみ出て咀嚼に合わせて揺れているようです。蓼食う虫も好きずきと言い、少し苦みの強い蓼を好む虫もいるという意味ですが、牛にしたら少々の苦みなど関係ないのかも知れません。 (素秀)
-
咀嚼する牛の口から蓼の花がこぼれ出ている。牛小屋ではなく放牧の牛でしょう。のんびりとした時間です。 (豊実)
(ひつぱれるいとまつすぐやかぶとむし)
甲虫は夜行性なので教会学校のキャンプで子どもたちと一緒にヘッドライトをつけて甲虫の採集に行きました。今も昔も甲虫は、少年たちの憧れです。いまはどのくらいするのかわかりませんが私の記憶では一匹800円くらいの相場でした。二匹の甲虫の角にタコ糸を結びつけて互いに反対方向へ引っ張らてせどちらが力が強いかを勝負させるのです。横綱級の強い甲虫の持ち主は鼻高々です。
揚句も又そのような甲虫の綱引きを写生したのでしょう。残酷といえば残酷ですが、任天堂のゲーム機で勝ち負けを争っている現在の子どもたちよりは遥かに健康的であったと思います。数年前に能勢の吟行で線路沿いの道を歩いていたときにおじいさんが腐葉土の山をひっくり返しておられた。甲虫の幼虫が眠っていそうだなと見て通り過ぎました。
- 合評
-
-
「甲虫」は夏の季語。角に糸をつけられて引っ張らせている様子。「糸まっすぐや」にぴーんと張った糸だけでなく、見つめている少年たちの熱い眼差しや周囲の濃い緑も見えてくるようです。こういう遊びがあったのでしょうか。弟がいますがやっていた記憶がありません…… (むべ)
-
当に今、引っ張っているのですね。「糸真つ直ぐに」で緊張感が伝わって来ます。何を引っ張っているのか甲虫の力も見えます。遊びの対象で少し可哀想な気も。 (うつき)
-
甲虫は幼い頃の兄の宝物でした。家の桜の木にいて「クワガタと甲虫はどちらが強いか」と戦わせたりしていたような気がします。この句では、糸がまっすぐになるほどの渾身の力で甲虫が何かを引っ張っているのでしょう。そのそばで子どもたちが顔を上気させて応援し、甲虫は本能でぐいぐいと前進しているようです。生き生きとした夏の情景です。 (あひる)
-
つながれているのか、何か引っ張っているのか糸はピンと張っています。カブト虫の力強さが良く判ります。カブト虫の句でこれ以上のものは無いのではないでしょうか。 (素秀)
-
甲虫が夏の季語。市街地で育ったのでカブトやクワガタはなかなか手に入らなかった。百貨店で売っているのをじっとながめていた。甲虫に何か重いものを引っ張らせているのか、二匹の甲虫に力比べの引っ張り合いをさせているのか、いずれにしても、ぴんと張った糸の描写から、甲虫が懸命に踏ん張っている様子がうかがわれる。汗をかくなら汗までも見えそうである。 (せいじ)
-
子供のころ甲虫の角に糸をつけて物を引っ張らせてよく遊びました。「まつすぐ」という単純な言葉に甲虫の力強さがよく表現されています。 (豊実)
(しゆんげつやむろふじのそうふところで)
春月やとあるので美しい春の月を懐手の僧がうち仰いでいるのであろうことはわかるが、室生寺の境内の一体何処に佇っているのだろうかと公式ホームページにある案内図を睨んでみた。五重塔の前の険磴だろうか、はたまた金堂前の有名な鎧坂だろうか、あるいは室生川にかかる太鼓橋だろうか…と連想してみるがいまいち手がかりがなく、この句に関しては全くお手上げである。春の大イベントを明日に控えて緊張感を覚えつつ天候状態をも案じながら空を打ち仰いでいる…という感じもする。
- 合評
-
-
涅槃の満月かなと思いました。丁度今頃か一ヶ月遅れですからまだまだ寒いです。寺の行事があり素十さんも宿坊に泊まったのかもしれません。GHの吟行が懐かしいです。 (うつぎ)
-
昨夜が春満月でした。懐手でまだ寒いことが伺えます。それでも冬の月とは違うしっとりとした雰囲気を感じさせます。 (素秀)
-
春の月の美しさに、寒さも忘れて出てきてしまった僧、しばらくすると寒さを感じ、思わずふところ手をしてしまったようです。室生寺の階段と五重の塔、そして見たことのない室生寺上空の明るい春の月が僧の姿とともにカラーで浮かんできます。。 (あひる)
-
「春月」は三春、「ふところ手」は三冬の季語ですが、おそらく2月くらいではないでしょうか。夜はぐっと気温が下がり、お坊さんも薄着で寒そうに見えたのかもしれません。「室生寺」という固有名詞で、五重塔や杉の大木のそばに月がかかっている光景が浮かびました。春の季語「朧月」ではないので、くっきり見えたのかな?と思いました。 (むべ)
-
春月が春の季語、ふところ手が冬の季語だが、これは春の句である。室生寺といえば五重塔を思い出す。これを一枚の写真に収めるのに苦労した記憶がある。春とはいえ山の中にある寺はまだ寒く、五重塔にかかる月をながめている僧は懐手をしている。暖かい感じのする春月がまだ寒い寺全体を愛撫するように照らしている。女人高野と呼ばれる室生寺に春月がよく似合う。 (せいじ)
-
室生寺と言えばシャクナゲの花を思い浮かべました。花が咲いてるかどうかわかりませんが、まだ寒さが残る春の夜に一人の僧がふところに手を入れて満月を見上げている。神聖な空気を感じます。 (豊実)
(なひあぐるなわをあたまのうへまでも)
みなさんの鑑賞が的確で補う余地はありません。小学生の低学年くらいの頃、母方のおばあちゃんが木槌で藁を叩いたり納屋で縄をなっていた姿を微かに記憶しています。ネットで縄を綯う動画をかなり探して見ましたが両手を翳すような高さまで綯っているのは見つかりませんでした。でも両手で数珠を揉むような動きの繰り返しで縄が出来上がっていくのは手品を見ているような感動ですね。
「縄綯ひの両手さしあぐ影法師も」という例句を見つけました。薄暗い納屋の灯りに縄を綯う人とその影法師を詠んだ句です。こちらは縄綯いで凝った肩ををのばそうとしたともとれます。素十さんの句がいかに具体的な写生であるかがよく分かりますね。何時頃だったかは忘れたけれど、少年時代はまだ荷造りに縄を使っていた記憶があります。
- 合評
-
-
『ホトトギス季寄せ』では三冬の季語「縄仕事」、『俳句歳時記・冬角川書店編』では子季語「縄綯ふ」がありました。近くの日本民家園で縄仕事の実演を見学させてもらったことを思い出し、その手際の良さに感嘆したことを覚えています。上手に綯えると真っ直ぐな縄ができると聞きました。農閑期にも仕事はたくさんあるのですね。道具や設備の揃わない時代、人の手の技はすばらしいものがあったと思います。(特に日本人の手先の器用さは世界的にもすごいと思います。)この句には迫力とリアリティを感じました。 (むべ)
-
幼い頃縄を綯うのを側でよく見ていました。座って臍の当たりから肘がのびきるまで即ち頭の上まで綯い又下に降ろし藁を足しながら綯うの繰り返しです。少しの暇も惜しんで農家の人はよく働くものだと見ていたのかもしれません。 (うつぎ)
-
「かあさんのうた」を思い出しました。「おとうは土間で藁打ち仕事おまえも頑張れよ♪」縄を綯う前に藁を打って柔らかくするようです。素手で藁を綯ひあげる手は荒れて節くれだっていたことでしょう。静かな冬、農閑期の心のこもった作業です。 (あひる)
-
わらを綯っていくと自然と手は上に上がっていきます。子供のときにやった事があります。昔は誰でも出来たのではないでしょうか。ちょっとしたコツでそれなりの縄が出来ます。真っすぐで綺麗な縄はどうやってもできませんでしたが。 (素秀)
-
縄綯ふが冬の季語。数本の藁を両手でより合わせて一本にするのだが、出来上がった縄は両手の下の方に伸びて行く。したがってこの句は、より合わせる両手を、胸の前から顔の前へ、顔の前から頭の上へと上げていった結果、縄が頭の上にまできた様子を描いているのではないだろうか。より合わせる両手は祈る形をしているから、今年もよい年でありますようにと祈り上げているようにも見える。 (せいじ)
-
私は縄を綯ったことがないですが、縄を綯っていく内に縄の先端が持ち上がって頭の上を越したのではないでしょうか?熟練の技に感心したのでは。 (豊実)
(いえちさくもくせいのかのおおいなる)
垣をはみ出すほどの大樹の木犀という意味ではなく、木犀もまた狭庭の一隅にあって素朴なものであるが、最盛期の今その香りが道に溢れるほどにまで満ちて家全体を包み込んでいるよ…というのである。貧しくとも我が家、小さくとも我が家…という安らぎに満ちあふれている。一読「清貧に生きる」という良寛のことばが浮かんだ。
良寛さんに、「焚くほどは風がもてくる落ち葉かな」の句がある。貧しく厳しい暮らしの中にこそ、奥深い楽しみや味わいがある…そんな良寛の心が見えてくるようだ。良寛は、徹底して「もたない暮らし」を貫いた。でもそれは決してやせ我慢などではない。ともするとマイナスにもみえる「貧しさ」や「孤独」は、時に自分を見失わないための座標軸を与えてくれるということだと思う。
俳句鑑賞は表現されている事実を翻訳するだけではなくて、斯く詠んだ作者の心情をも探りたい。
- 合評
-
-
小さい家であるけれども木犀は家を包み込む程に香っている。住むにはこれ以上のことはない。作者の満足感が伝わってきます。 (うつぎ)
-
「木犀」は晩秋の季語。「家小さく」がとてもすてきな措辞だと思いました。たとえば、コンパクトな敷地にすっきりとした平屋建て。住人の暮らしぶりや生き方も反映されているかのよう。もしかしたら作者の住まいだったのでしょうか?そして、「香の大いなる」から木犀はきっと金木犀だったのだろうなぁと思いました。家全体を包み込む木犀の香りに、童話やおとぎ話の世界観も感じました。 (むべ)
-
作者の家なのでしょうか。小さい家の小さい庭に多分それほど大きくない金木犀の庭木があるのでしょう。小さい木だけれども香りは負けないぞと言っているようです。 (素秀)
-
素十さんの幾つかの俳句は、二つのものを対比させることで奥行きが出ているようです。ほだ木の表と裏、母馬と仔馬、花と蜘蛛の糸…。ここでは目に見える小さな家と、目に見えない大いなる香。いつまでも味わっていたいような気がします。 (あひる)
-
木犀が秋の季語。木犀はよく香る。家の敷地を越えて広範囲に及ぶ。匂いに色を付ければ、大きな家でも小さく見えることだろう。大いなるものへの畏敬の念を感じる。 (せいじ)
-
金木犀の大きさと小さな家のギャップが面白いです。私が子供の時住んでいた小さな借家の前に大家さんの大きな金木犀の木があったのを思い出しました。 (豊実)
くもの糸一すじよぎる百合の前 コメントを書く
(くものいとひとすじよぎるゆりのまへ)
なぜ百合なの…と気になったので調べてみたら、蜘蛛には臭覚があるとの情報を得た。百合というとハウス栽培の園芸種が年中流通していて季節感がうすいが、季語として詠まれるものは山百合と考えるのが妥当かと思う。山路を吟行していると涼風にのって山百合の甘い香りがしたので近づいてみたら既に先客がいた。姿は見えないが夕日に光る一筋の蜘蛛の糸に気づいたのである。
百合の甘い香りに誘われて翅虫たちが集まってくるのを蜘蛛は知っていて、夕暮れをまって網づくりをしようとまず要の糸を一本引いていたのだと思う。虫を誘い寄せて花粉を運んでもらおうと百合は香りを放ち、その虫を捕らえようと蜘蛛は網を張る。自然界の命の連鎖を写生している句だと思う。
- 合評
-
-
百合の花の前を、一本のくもの糸が風に流された。たまたま気づいた何気ない瞬間を描写したのだと思います。 (豊実)
-
蜘蛛の糸と百合だけが大きく描かれ、糸の光や百合の瑞々しい花びらが質感を持って迫ってきます。周りの風景は描かれなくても充分に見えてくる感じです。 (あひる)
-
くもの巣はそうでもないが一筋となると気づき難い。光線の加減でキラと光ったのかもしれない。すっくと立った大きな百合をバックにかそけきくもの糸の一筋対比がみごとです。 (うつき)
-
「くもの糸」は三夏「百合」は晩夏の季語。「一すじよぎる」で細い糸1本が百合を背後にあざやかに浮かびあがります。白い百合ではなく、姫百合や鬼百合、もしかすると黒百合だったかもしれません。頭の中には涼し気な夏の野山が広がります。 (むべ)
-
蜘蛛の糸1本に焦点を絞っています。百合の花は背景しかも少しぼかしも入っているようです。さらに言えば何の花でも良いのかも知れません。 (素秀)
-
くもの糸、百合が夏の季語。山百合かなと思う。山歩きをして見つけた百合の花をじっとながめていると、蜘蛛が糸を垂らして上から下りてきた。百合の花に集まる虫を捕えようとして、これから網を張ろうとしているかのかもしれない。こんなところにも自然の営みがある。 (せいじ)
(おおほたをかへせばうらはいちめんひ)
囲炉裏で大榾を燃やすことはあまりないと思うので宮焚火あたりを想像してみた。いつぞやGHで早春の中山寺を吟行したときに福火と称して寺領の山で枝打ちしたり朽木を伐採したものを燃やしていた。かなりな太さのいわゆる大榾もどきも櫓に組まれてくべられていた。小枝は勢いよく燃えているのだが大榾には容易に燃え移るという気配はなく黙したままである。ひとしきり火勢が落ち着いた頃火守り役のおじさんが大榾の向きを少し変えた途端に真っ赤な裏面が現れたのを覚えている。
大榾は小枝のようにチョロチョロと炎を上げたりはしない。鍛冶屋の炉から出てきた真赤な鋼のようなそのような表情なのである。「一面火」は「一面火の海と化す」の省略形だと思うが、まさに大榾の真っ赤に燃えた裏面の形容にぴったりだと感心させられた。大好きな句である。
- 合評
-
-
大榾を返したところ以外にも燃えている、その様子を見せなかった大榾の秘めたる力、燃え盛る炎に喚起されるものがあったのでは。焚火を想像しました。 (うつぎ)
-
大きな木が燃えにくく、消えそうに思えたのでしょう。でも、裏返してみたら思いがけない一面の火、もう一部は熾火となっていたかも知れません。それとも、すぐにボッと新しい炎があがったかも知れません。一面火と言い切る表現が斬新で印象深く「確かに!」と思いました。 (あひる)
-
「榾」は冬の季語。炉や竃を燃やすためのたきぎですね。(なかなか詠む機会のない季語で憧れます。)ここでは囲炉裏でしょうか?家族や友人と囲炉裏端で食事をしているか、はたまたお酒を酌み交わしているか……大きい榾を裏返してみたら、表からは想像もできないほど赤々と燃えていたということかと思います。体と火との距離が近いので、裏返している作者も暖かいというより熱いのかもしれません。ロマンがありますね。 (むべ)
-
榾は薪の中でも太いものを言うようです。なかでも大榾ともなるとかなり大きいものなのでしょう。一見燃えてないように見えたものの、ひっくり返したら良く燃えていた。一面火でボッと炎が立ち上がるようです。 (素秀)
-
榾が冬の季語。燃えていないようにみえる大きな榾を裏返したら火が燃え盛っていた。囲炉裏や暖炉を燃やすときに誰もが経験することであるが、そのような日常の小さな発見を的確に客観描写するだけで、囲炉裏を囲む人たちの生活全体が見えてくるから不思議である。素十の句は読む者の想像力をかき立てるものが多く、味わい深い。 (せいじ)
-
囲炉裏にくべる小枝はすぐに燃えるが、大枝は火が定着しにくい。じっと置いていた大枝をひっくり返すと裏は真っ赤に燃えていた。さあ、その上に小枝を追加しよう。 (豊実)
(かんじきのたかみをこえていきしあと)
雪国の里山の朝風景かと思う。かんじきを履いて雪を踏みゆく人々の足跡も夜な夜な降り積む雪が消してしまうのだけれど、朝早くから雪の峠道を越えて行ったであろうしるき足跡を見つけたのである。どんな人が何の目的で何処へ…という情報は全く無いので想像するしかないが、作者は知っているのかも知れない。もし知っているとすれば、朝まだきの深雪を一歩々々踏みながら出かけていったであろう人の姿も目に浮べながら足跡を眺めているのではないだろうか。そうしなければ暮らしていけないような貧しいその人の境遇を思いやり同情しているような気分も感じるのである。
- 合評
-
-
かんじき(樏、橇)橇の字を当てられているのでソリと取りたくなる。でも足に履くかんじきでしょうね。こんな朝早くに既に一歩一歩踏みしめ峠を越えて行った人がいる。春はまだ遠い。 (うつぎ)
-
一面の銀世界にかんじきの足跡が律儀にくっきりとついています。坂道を登って下って、朝早くから。雪国で懸命に生き抜く姿が見えるようです。この足跡も雪が降れば消えていくことでしょう。 (あひる)
-
ソリでも跡は残るでしょうが、橇はかんじきでしょう。町の坂道かなと思います。かんじきの跡が続いているが坂の頂上で見えなくなっている。町中でもかんじきがいるほどの豪雪地、しかも積もったばかりの新雪のようです。 (素秀)
-
橇が冬の季語。橇は「かんじき」と読んでいるので「そり」ではなく履物の下につけるものだと思う。高みは峠ではないかと想像した。昨夜も雪が降った。作者は用事があって朝早く新雪の峠を越えて行こうとしている。誰もまだ通っていないと思っていたが、もうすでに人が通った痕跡があった。こんなに早くと驚いたのであろう。 (せいじ)
-
かんじきをつけて雪道を歩く大変さが伝わってきます。上り坂ではその足跡も間隔が狭くなっていたんだと思います。 (豊実)
-
「橇」は晩冬の季語。この地域(新潟?)は積雪期には荷車ではなく橇が日々の営みを支える重要な足だったのでしょうか。「高み」は丘のようなところか、はたまたものすごい積雪の上なのか……容赦なく迫る自然と、それに沿うような人の暮らしぶりが伝わってきます。 (むべ)
ばらばらに飛んで向かふへ初鴉 コメントを書く
(ばらばらにとんでむかふへはつがらす)
「初鴉」は、第一句集のタイトルにもなっているくらいなので作者にとっても思い入れの深い作品なのだと思う。森羅万象生きとし生けるものにとっては日常の営みと何も変わりはないのだが、見る側の気分によって、なんとなく新鮮に思えたり目出度く感じたりするという不思議な季感だと思う。「初」の字がつけば何でも新年の句になるかというとそうでもなく俳句が醸し出す微妙な感覚を捉えるには練達された写生なくしては難しいと思う。
「ばらばらに飛んで」の措辞がいかにも鴉らしい習性を捉えていると感じるのは異論のないところであるが、「向こうへ」という平明なことばに深い意味を感じる。つまりそれは、作者の視点の前方は展けているらしいということ、鴉たちは飛び去ったのではなくて渓向こう、或いは川向うの木立へ移動しただけという印象を感じさせている。具体的な状況説明は一切省略されているので、鑑賞者が想像するしかないのだが、平明なことば使いの中に空間をイメージさせる力があるのだということを思わされる。
- 合評
-
-
季語は「初鴉」。もしかして作者は初詣に来ていて、寺社の境内でこの光景に出会ったのかなぁと思いました。私は寺社を訪れる機会はほとんどないのですが、鴉が周囲の杜を塒にしていて、境内も庭のうちなんてことがあるでしょうか。「ばらばらに飛んで」に空間的広がりを、「初鴉」にめでたさ、清浄な空気を感じました。 (むべ)
-
向こうへは川か池か隔てるものの向こうだろうか。方向は同じでもてんでバラバラに其々の意志を見せている。目出度いとされる正月の鴉にふさわしい。 (うつぎ)
-
初鴉は元旦のまだ明けやらぬ空に声をあげる鴉とのこと。神社の杜を塒としていた鴉が、初詣の人に驚いて飛び立ったのだろうかと思います。夕方、鴉が木立ちに群れているのを見たことはありますが、翔んでいる鴉はいつもばらばらです。 (あひる)
-
鴉は群れで暮らしながらも仲間意識は薄いイメージがあります。都合がいいので群れているのでしょうが、何かあればてんでばらばらに飛んでいくのでしょう。作者が見た鴉も好き勝手に散らばったと見えます。ところでカラスの漢字は2種類、鴉と烏があります。鴉は牙が付いてなんとなく禍々しく感じられます。これは歯の牙ではなく鳴き声のガーに漢字をあてたものだとか。烏の方は色が黒くて目の位置が良く判らないところから1本線が抜けています。1本足りない間抜けな鳥ではないようです。 (素秀)
-
初鴉が新年の季語。元日の早朝に聞く鴉の声はめでたいものとされているようである。鴉の飛び去るさまがばらばらであったというところが写生なのだと思う。鴉は一年中家の近くにいる身近な鳥で、昨今は人間と知恵比べをしているが、新年に当たり、作者は鴉に今年もよろしくと挨拶をしているかのようである。 (せいじ)
-
雀、鳩ではなく何故鴉なのか考えてみました。この三種の鳥の内、確かにばらばらに飛んでいきそうなのは鴉かなと思いました。鴉は神の使いとも言われているように、一羽一羽に威厳を感じたのかもしれません。 (豊実)
(かりのさをかれきのうへにいちもんじ)
雁は秋に北方から渡ってきて春にはまた故郷へ帰っていくが、俳句では渡ってくる雁が詠まれる。さて、この句も省略が効いていて難しいですね。作者は枯木立の中に立ってその頭上を通過する雁を見たのか、枯木山すれすれに一の字に通過する雁をやや距離のある処から見たのか…という点が鑑賞のポイントになると思う。瞬間写生句として鑑賞すると前者の可能性が高いと思います。
高空で編隊をなすときの雁の棹はV字ですが、低く着陸寸前のそれは限りなく一の字に近いのかも知れない…と考えると後者かもと思い直しました。素十俳句はゆっくりと時間をかけて詠むという特徴があるからです。高空からV字をなして渡ってくる雁を見つけた作者は、だんだん近づいてくるその様子をじっと観察していて、やがて高度を下げ枯木山の上に差し掛かったそれが一文字に変わった瞬間の感動を写生したのかなと想像してみた。
- 合評
-
-
「雁」は三秋、「枯木」は三冬の季語で、この句の主役は雁だと思うのですが、木の葉が落ちているようなので、12月くらいの寒い時期だったのではないでしょうか。雁行はV字編隊をよく見かけるような気がしますが、一文字は珍しかったのではないでしょうか。「一文字」という字面と音にひかれるものがあります。 (むべ)
-
ふと見上げた時の雁の棹に作者は見入っています。v字から一文字になったところかもしれない。山の枯木と一文字の雁、線描画を見るようです。 (うつぎ)
-
雁は V字型に編隊を組んで飛行します。これは理由があって先頭が作る気流に乗って後ろの雁は体力を温存しているのです。もちろん先頭は時々交代します。一文字に見えたのはそろそろ目的地が近いのかも知れません。枯木の山の上に雁が飛ぶ、しばらく見入るような光景です。 (素秀)
-
雁の棹はへの字が多いように思いますが、旅も終わりに近づいたこの時は横一文字だったようです。枯木山の上空のこの光景は壮観だったことでしょう。去られるのは寂しいですが、来てくれる雁の群には心がわくわくします。 (あひる)
-
雁の棹が秋の季語。雁の棹とはよく言ったものだ、横に真直ぐに並んで今年もやってきたよ、ほら、あの枯木の上に、お帰りなさい、といった風情だろうか。「一文字」に凛としたものを感じる。 (せいじ)
-
雁が列をなして渡ってきた。枯木が彼らを出迎えているようです。 (豊実)
毛見のあとより一人出て先に立つ コメントを書く
(けみのあとよりひとりでてさきにたつ)
毛見衆ともいわれるように検査時の役人は複数でやってくる。贈収賄を避けるためだと思う。毛見のあとより…なので先に立ったのは毛見衆ではなさそう。どちらにしても毛見のさじ加減で査定が決まるので案内する側は機嫌を悪くされないように気遣いをする。うつぎ解にあるように案内する人が平身低頭、接待顔で次の田へ案内しようと先に立ったのであろう。
私も現役の頃、通産省の技官の検査を何度かうけた経験があり、その折の気配りは大変であった。雑談の端々で検査官の趣味(ゴルフ、釣り、麻雀など)を探り出し、不本意ながら話をあわせてご機嫌をとるようなこともあった。あまり良い思い出ではない。
- 合評
-
-
3冊持っている歳時記のホトトギス新歳時記にだけ毛見が載っていた。この句の時代は地主が小作人の田を検分することを言ったようです。何人か役人もいて後ろの人は地主だと思う。先頭になって次の田へ案内しようとしています。 (うつぎ)
-
「毛見」は晩秋の季語。享保の改革で課題の多かった検見法から定免法へ変更されたと日本史では習いましたが、作者の時代には、政府への納税ではなく小作人が地主に納める田畑の使用料のような意味合いで「毛見」が行われていたようです。この一人は地主さんか、地主さんに頼まれた毛見の衆で、小作人たちにとっては招かれざる客だと自覚があるのか、実検を済ませたら挨拶もそこそこにさっと行ってしまった……という様子かな?と思いました。農村部のシビアな一面を見たのではないでしょうか。 (むべ)
-
毛見の中の一番偉そうな決定権のある役人が、最後に前に出てきて年貢高を決める一言を言ったんではないでしょうか? (豊実)
-
毛見は稲の稔りぐあいを調べる役人ですが、今でいえば税務署員でしょうか?私の実家は小さな酒造業でしたが、よく税務署の人が抜き打ち調査に来ていました。帳簿をくまなく調べられ、酒の瓶詰めの際にごまかしは無いか・・など疑われ、母はその度に胃が痛くなっていました。きっと、毛見に厳しく作高を調べられた田んぼの持ち主は、うれしい気分ではなく、一人さっさと家へ向かったのではないでしょうか? (あひる)
-
毛見、検見とも言います。年貢の割合を決めるために稲の出来具合を調査する事ですが、この句の時代だと小作人の田を地主が見ていると読むべきでしょうか。毛見を行う人は幾人かいたようで田から後から出てきた人が先に立って歩きだしたのかと思います。 (素秀)
-
毛見が秋の季語。この句は難しい。毛見は、江戸時代のような過酷なものではなかったかもしれないが、小作人にとってはやはり嫌なことであったのではなかろうか。一人に注目し、嫌なことはさっと済ませてその場を後にしている様子を描いているように思った。一人は作者自身かもしれない。 (せいじ)
づかづかと来て踊り子にさゝやける コメントを書く
(づかづかときてをどりこにさゝやける)
代表作として有名な作品であるが諸説の鑑賞がある。山本健吉氏は「外遊中の作で、作者が感動を得た実際の出来事はヨーロッパの踊り場風景である」と断定している。一方、高弟の倉田紘文氏は「素十がドイツ留学から帰国して二年後、新潟市郊外での作品である」と明言している。
沢木欽一氏もまた健吉説を否定していて「農村のどこにでも見られる盆踊り風景で、やぐらを中心に男女が輪を作って踊る。踊り子はうら若い女性で、ずかずかと来てささやくのは村の青年である」と鑑賞している。さらに、「青年の無遠慮さ、大胆さが『づかづかと来て』に活写されているのは勿論であるが、この男女の特殊な親密さを作者は驚きと好感をもって眺めている」と結んでいる。
大筋として私も沢木説に同感であるが、男女の関係、何をささやいたのか、その瞬間の二人の表情や動作、その後の二人の行動等々は一切不詳なるがゆえに諸説生まれるのであろう。どうしても説明したくなるのが普通人の心情だが、それを完全に封印して一瞬だけを切り取ってデッサンした。確かにドガの絵にも匹敵するくらいの力強さがあると思う。
- 合評
-
-
「づかづかと」が多くを語っている。盆踊りの輪の女性に近づき耳元で何か囁いている。人目を気にするで無くこれ見よがしです。無粋な中年のおじさんを想像しました。誰だろう、何だろう、高揚した盆踊りの一齣を切り取っています。 (うつぎ)
-
「踊り子」は秋の季語。八月の盆踊り会場の光景でしょうか。本番と考えるとかなり不躾な感じもするので、リハーサル中だったか、曲と曲の間のインターバルだったかもしれません。踊り手ではなく踊り子なので若い女性を連想しました。「づかづかと来」たのは意を決した若い男性だとドラマ性がありますね。デートの申し込みなのか、けんかの仲直りだったのか……眺めている作者に、夕方の涼し気な風が吹いてくるようです。 (むべ)
-
代表句の一つと言われるほど有名な句です。いろいろと想像はできますがやはり盆踊りの輪に突然入ってきた男が何かささやいたと読むべきかと思います。踊り子は当然女性で踊りのあとでの約束事でもしたのでしょうか。強引だけれども若さを羨む作者の気持ちも少し見えます。 (素秀)
-
最初は伊豆の踊子、京都の舞妓さん、フラメンコなど外国の女性を連想してみました。ところが、俳句の世界では、踊りという季語は盆踊りをさしているとのこと。そうすると、この踊り子は盆踊りの輪の中にいたのではないでしょうか?それは浴衣を着た若い女性かも知れないし、年配の方かも知れない、男性だって踊り子と言えるでしょう。けれども「づかづか」という措辞によって、来たのは男性、「ささやいた」の措辞によっておじさんではなく若い男性、踊り子はやっぱり若い女性かと思いました。づかづかと来たのですから、恋のはじまりというわけでもなさそうです。にぎやかな盆踊り風景の片隅で、若い男女の秘密の話があったのかも知れません。 (あひる)
-
踊り子が秋の季語。盆踊を踊っている若い女性に無遠慮に荒々しく近づき何やらささやきかけている若い男性。この句の主役はこの若い男性であろう。盆踊は男女の恋の場でもある。「づかづかと」に若者の一途な気持ちが表れているように思う。 (せいじ)
-
踊り子が踊っている最中に、厚かましそうな男がお目当ての踊り子にづかづかと近づいて、何かささやいている。ちょっと迷惑な感じがする。 (豊実)
(ももあをしあかきところのすこしあり)
桃は袋掛けするものだという先入観があったのですが有袋桃と無袋桃とがあるのだと知りました。無袋桃の方が甘いそうです。揚句は無袋栽培でオーソドックスな桃色に熟す種類なのでしょう。こんなことが句になるのか…と思ってしまいます。皆さんの合評の通り「これから」という期待感を写生したのです。
熟成過程での桃の色の変化についていろいろ検索してみました。蔕に近い部分から赤くなるのかと思っていましたが、そうでもなさそうで縫合線のあたりから赤みが広がっていく感じでした。薄く透けた袋越しでもこの色の変化は見分けがつくようですが、この句が詠まれた時代の袋掛けは新聞紙だったと思います。脱線しますが青畝師のユーモアな作品があるのでご紹介しておきます。
リクルート事件の袋掛けにけり 青畝
初学時代にひいらぎの合評でこの句に遭遇したとき「なんのこっちゃ?」と思いました。新聞紙で袋掛けしていた時代の句として新鮮極まりないですね。脱帽ものでした。
- 合評
-
-
桃はまだ青いが赤みがさしかけてきて瑞々しい。青さの中に日に日に赤くなっていく桃の力を感じているのでしょう。 (うつぎ)
-
桃に赤みがさしてきた…でもまだまだ食べ頃にはほど遠い、早く熟れてほしいなあと子どものような心で詠まれていると思いました。ありのままにものを見る目に純粋さが感じられます。 (あひる)
-
まだ青い桃の実にわずかに赤味が差して熟れ始めています。熟れるまで待つ時間も楽しみの一つのようです。 (素秀)
桃が秋の季語。桃の実の熟れるのを待ち焦がれている様子がうかがわれる。まだ青いがもう赤いところが少しあるという子どものような視点が初々しい。桃青が芭蕉の別号であることを思うとき、自分の俳句はまだまだだが少しはうまくなったかなあという思いも込められているような気がするが、考え過ぎだろうか。 (せいじ)
-
「桃」は「桃の実」で初秋の季語。8月のまだまだ日差しが強い頃かもしれません。桃の木になっている実が、青い実もあればやや赤い実もあるということなのか、一個の桃の実にフォーカスし、全体的に青いけれど、ほんのり赤くなっている箇所があるということなのか…「赤きところ」で後者かなと思いました。青と赤という二色が登場して、インパクトのある句になっており、かつ桃の熟れる様子から季節の巡りや時間の経過を感じました。 (むべ)
-
ありがたいことに、今年も桃が実った。まだまだ青いが、ほんのり色づいている。収穫するのが楽しみだ。 (豊実)
(おやうまはくしけずらるゝこうまとび)
「仔馬跳び親馬は梳らるゝ」と詠めばわかりやすいと思う。本来ならばそう詠むべきところを作者はあえて逆にしたのである。思うに動きのある主役の仔馬をあと出しに表現したかった…つまり「動と静」ではなく「静と動」という形にこだわった結果ではないかと思う。耕作や荷役に労した馬を浅い水辺に立たせてからだを洗い汗を流してやる「馬洗う、馬冷やす」という季語がある。馬体は普通ブラッシングで、梳られるのはうつぎ解にあるように鬣と尻尾で前髪もどきが少しあるものもある。産後を労われて静かに安らいでいる母馬のそばで仔馬は元気に跳ねているのである。
現代ほど農機が普及していなかった時代、使役としての馬や牛ははとても大切にされていて人の生活に密接であったので馬や牛に関係する季語も多い。自家用の農耕馬を繁殖させることはまずなかったと思うので、揚句の場合は素秀解の通り牧場の風景と思う。
- 合評
-
-
中七と下五の間で切れていると解釈しましたが、ちょっと珍しい切れ方だと思います。落ち着いた様子で毛並みを手入れしてもらっている親馬、そのそばで跳ね回っている仔馬をイメージしました。しあわせな風景です。 (あひる)
-
仔馬が春の季語。「梳らるる」はここで切れるのか、それとも仔馬にかかるのか。後者だと跳ぶのは親馬になりそうなので、ちょっと想像しにくいかも。親馬は梳られ、仔馬は跳ぶ。人間の子どももうれしいとすぐにぴょんぴょんと飛び跳ねるが、それと同じだなと思った。最後はなぜ「跳ぶ」ではなく「跳び」なのだろうか。 (せいじ)
親馬は大人しく鬣や尾を梳かれている時その周りで仔馬はじっとしておれず元気に飛び跳ねている。静と動の親子馬を目を細めながら見入っているようです。 (うつぎ)
この春に生まれた仔馬が親馬の周りを跳ね回っています。親馬は平然と毛をすいてもらっている、うららかな牧場の春の風景です。 (素秀)
仔馬のお披露目会というものがあるようです。仔馬の名前を発表し、小さな障害を跳んで見せたりするようです。その横で親馬は櫛で毛並みを整えられながら仔馬を見つめているように思います。 (豊実)
「仔馬」が春の季語。生まれて間もない仔馬がたてがみやしっぽを梳き櫛で手入れされているところを、母馬が飛び越えていったのでしょうか???ということは馬房ではなく外で起こった出来事かもしれません。危ない、危ない……周囲の緑は春の日光に照らされ、まだ少し冷たい風が馬場を吹き抜けていく、そんな中で起こったヒヤリハットな事件かなと思いました。はつらつとした春の空気が伝わってきます。 (むべ)
(をとりかもめすをつつきぬかなしけれ)
空を飛んでいる鴨がデコイに騙されて舞い降りてくるのだという説明は読んだ記憶があります。デコイの囮が雌鴨に寄り添われてあたかもつついている様な所作に見えたと解しても面白いかなと思いましたが、流石に鴨も偽物に近づいていくほど鈍感ではなさそうなのでやはり生きた囮でしょうね。
うつぎ解、せいじ解にあるように、「けれ」は、係助詞「こそ」を受けて逆接や強調の意を表す文語表現です。囮の身であることをも忘れて本能のままに求愛行動をしてをる鴨の性こそ悲しいものだ…というところでしょうか。
- 合評
-
-
雄の囮鴨が雌を突付いている。苛めかじゃれているのか、求愛かもしれない。囮とて囚われの鴨、実に悲しい。係り助詞こそが省略されているが結びのけれでより深い悲しみを述べている。 (うつぎ)
-
囮には生き囮と型囮(デコイ)があるようですが、ここでは生き囮が撃ち場で数羽つながれて、飛んでくる鴨を呼び下ろして銃で撃つか無双網をかぶせるかして捕まえる、という猟法のようです。雌をつついているのはおそらく雄なのでしょう。求愛行動だとしたら、本当に悲しい。雄は人間に利用され、求愛した雌は獲物として人間に捕まってしまうのですから。 (むべ)
-
雌をつつくという状況がよくわからなかったので、ネットで調べたところ、鴨場猟というのがあった。飼育して慣らした鴨を囮として泳がせ、野生の鴨を鴨引堀に誘導し、叉手網(さであみ)や鷹を使って捕獲するというもので、鴨場は、現在、宮内庁の埼玉鴨場と新浜鴨場の二か所ぐらいしかないらしい。素十には「囮鴨めす沢山にゐて遊ぶ」という句もあるから、どこかの鴨場に招待されたのかもしれない。囮鴨たちが遊んでいる。雄が雌をつついたりもしている。「悲しけれ」と已然形なので、強調の「こそ」が省略されていて、本当に悲しいことだと断定していると理解した。じゃれ合って楽しそうに遊んでいる鴨たちが、同類を捕獲するための囮として使われることに、作者は言い知れぬ悲しみを感じたのではなかろうか。 (せいじ)
-
囮鴨が題材ですから、鴨たちは猟の対象として描かれていると思います。そんな中でも雌鴨を追い、突付いている鴨がいる。突付いているのは雄鴨でしょう。その情景を悲しく感じたのかなと思いました。 (あひる)
-
囮猟に使う木彫りの鴨でしょうか。雌の囮を突いている雄鴨の様子を哀れと思っています。 (素秀)
-
囮鴨とは狩猟で囮に使う鴨で、模型もあるようですが、この句の場合つゝきぬなので、本物でおそらくは雄鴨なんでしょう。撃たれて死んでしまった雌をつつている。狩猟とは言え、悲しい情景です。 (豊実)
(しゆんげつやはたけのかぶらぬすまれし)
食べ切れないとかで畑に放置してあった蕪であろう。白菜やキャベツ、ルッコラ、小松菜、蕪などのアブラナ科の作物は3月頃になると茎立ちして菜の花になります。スーパーとかでは手に入らないもので、花咲く直前に収穫して春の味を楽しむとのこと。ところがそれを盗みに来る奴がいるという。
「春月や」と詠嘆しているので、月はいままさに出ている…というのが俳句の約束である。人間の仕業とするのはあまりにも寂しく、季節柄その盗人は冬眠から覚めた裏山の狸あたりではないかと想像してみた。夜な夜なやってくる犯人を現行犯逮捕するべくこの夜も見回りに来てみるとやっぱり!というようなシチュエーションかなと思う。春月の照らすなかに慌てて逃げていく犯人の影を目撃したのかも知れない…と想像すると滑稽味も感じますね。
なぜ蕪なのか…は、断定しづらいけれど、比較的抜きやすい、好物であった、ということなのかなと…
- 合評
-
-
春の朧気な月と白く丸い蕪は響き合うものがある。春だから蕪はもう抜き易く茎立ち始めていたのかも知れない。盗むそれなりの理由があったのだろう。春月を見て作者も優しい気持ちになっているのでは。 (うつぎ)
-
蕪は抜き残したものではないでしょうか。収穫も大方終わって発育不良などの蕪を放置していたようです。盗まれたとしてもそれほど惜しくないような感じがします。 (素秀)
-
戦後のことを描いた映画や文章などで、お腹を空かせた人が他人の畑の作物を盗んだり、そのまま生でかじったりするのを見たことがあります。この俳句はそのような時代のものではないでしょうか?盗まれた蕪のことで怒っているのではなく、朧な春の月を見上げながら、盗んだ人の心情にも想いを馳せているのかも知れません。 (あひる)
-
畑の土に掘り返された跡がある。精魂込めて作った蕪が盗まれたのだ。朧な月が悲しんでいるように見える。 (豊実)
-
春の月をながめながら、今日、畑の蕪が盗まれたことをふと思ったのではなかろうか。澄み切った秋の月でも冴え冴えとした冬の月でもなく、潤んだような春の月がこの句にはよく似合う。蕪は旬を過ぎている。戦前の貧しい食糧事情も偲ばれる。 (せいじ)
-
「春月」は春、「蕪」は冬の季語ですが、ここでは春月が主季語ととりました。やわらかい朧月夜は蕪泥棒が畑に入るには絶好の機会でした。新月ですと蕪の位置がわかりませんし、皓々とした満月では目撃されてしまいます。もちろん実況中継ではなく、おそらく翌朝に作者はそのニュースを聞いたのでしょう。それなのにありありと想像できる言葉遣い。農家さんにはお気の毒ですが、どことなくユーモアもあります。 (むべ)
歩み来し人麦踏みをはじめけり コメントを書く
(あゆみきしひとむぎふみをはじめけり)
麦踏みは両親から話を聞いたぐらいで見たことはなかったのですが、農業体験のある家内は子供の頃の懐かしい思い出だという。ネット動画で見ると子供や女性たちが横向きになって足踏みするように麦踏みをしている様子を見ることができる。万歩計などない戦後の苦労人達が皆元気だったのは麦踏みで足腰を鍛えたためなのかと思う。
作者は、進行方向の道の向こうから来る人に気がついて、まもなくすれ違いそうだな…と予測していたのに、急に畑に入り後手を組みながら足踏みを始めた。やがてそれが麦踏みであることに合点したのである。「歩み来し人」の措辞がいかにも素十さんらしい言い回しで、その時間経過の描写がじつにうまいなと感じました。「時間経過を詠まず瞬間を写生せよ」と繰り返し特訓を受けた私には到底詠めそうにない句だなぁ〜とため息も出るのです。
- 合評
-
-
作者は広々とした麦畑の様子を句に詠もうと、ずっと見ていたのではないでしょうか?すると、歩いてきた人影が麦踏みを始めた。遠くの光景とも思えるし、結構近い所での光景とも思えますが、言葉を交わす程の距離ではなかったような気がします。絵を描くように俳句を詠む作者の楽しそうな様子が目に浮かびます。 (あひる)
-
前進で歩いて来た人が畑に入り横方向に進みだしたことに「あ〜、麦踏みだったのか、もう春だなぁ」と興味深く見入っているようです。 (うつぎ)
-
麦踏みをするとは思っていなかったようです。思いついたように歩いてきた人が突然麦踏みを始めたので作者も少し驚いているようです。 (素秀)
-
麦踏みが春の季語。「歩み来て」と「歩み来し」の違いを考えてみた。前者だと歩いて来てから麦踏みを始めるまでに時間があるように読めるのに対して、後者だと歩いて来てすぐに麦踏みを始めたと読めるのでそこにインパクトがある。散歩をしているようにみえた人が、そのまま麦畑に入って麦踏みを始めたのであろう。驚きとともに、大変な作業を何でもないことのようにさらっと始める農家の人への敬意が感じられる。 (せいじ)
-
「麦踏」は初春の季語。昔小麦の収穫を体験したことがありましたが、その時麦踏についても教わりました。「歩み来し」という上五から、芽が出ただけの見通しの良い麦畑に作業者が手ぶらでやって来て、作者がおやと思ったのではと察します。何をするのかと見ていたら、おもむろに蟹歩きを始めたよ、ああ、麦踏なんだ……と納得したのではないでしょうか。まだ寒い季節の農作業で大変そうだという気持ちも感じました。 (むべ)
-
私は麦踏みをやったことないですが、根気がいって黙々と行う作業のようです。「歩み来し」で、休憩していた人が何気なくやってきて、また作業を開始する雰囲気が伝わります。 (豊実)
菊つみてはや盛り上がる籠の中 コメントを書く
(きくつみてはやもりあがるかごのなか)
てっきり野菊摘みだと思ってしまった私は食用菊だというみなさんの合評に完敗、なるほどと思いました。食用菊がハウス栽培されるほどに食文化が変わった現代とは違って、この句の詠まれた時代は露地栽培で、畦道からその様子を写生できたのでしょう。作業する人たちの手際はよく、摘み始めたかなと見るまもなくたちまち籠の中に嵩をなして盛り上がっていくのです。花だけを摘むのではなく少し枝葉もつけて摘み、出荷するときに丁寧に花だけを剪ってパック詰めにする感じですね。
懐石料理の飾りに添えてあるのをよく見ましたが私は苦手で食べませんでした。美味しくない…というのではなくてなんとなく花に申し訳ない気がして…
- 合評
-
-
籠に盛り上がる菊…の状況が分からなかったのですが、みなさんの合評から食用菊かと思いました。自家用に栽培しているのを、おばあちゃんと孫で摘んで、籠に入れていったのかも知れません。秋の澄んだ空気の中で、明るい笑顔が見えるようです。 (あひる)
-
籠を手に菊を摘みに来て「はや盛り上がる籠の中」。すごいですね。無駄のない言葉で籠の中で盛り上がるほどの色鮮やかな菊、摘みに来ていますので、空はきっと晴れ渡った青空。シンプルな言葉なのに読み手に色彩をしっかり印象づけています。 (更紗)
-
普通の菊なら摘みてではなく切ってと言うだろうし春菊なら菠薐草でも言えるので句にならない。ここは食用菊でしょう。大輪の菊の籠はすぐに一杯になり鮮やかな色が零れんばかりです。 (うつぎ)
-
菊が秋の季語。この菊は野菊ではなく栽培している菊のようである。供花用に茎から摘んでいるのか、あるいは、ひょっとして春菊(菊菜)を摘んでいるのかもしれない。春菊とすれば春の句になるが。食用に花を摘んでいるとは思いつかなかったが、そうかもしれない。いずれにしても、一斉に収穫をして籠がすぐに一杯になった様子が的確に表現されていると思った。豊作でたくさん収穫できる喜びが感じられる。 (せいじ)
-
食用菊のようです。菊の収穫で検索したらまさしくカゴを持って花を摘んでいます。嵩はあるでしょうが軽い菊の花はカゴに一杯になっても片手に掛けたハンドバックのようです。 (素秀)
-
「菊」は秋の季語。中七の「はや盛り上がる」を読んで、この菊は食用菊ではないかと思いました。新潟がお里のご近所さんから「かきのもと」という菊を時々いただくのですが、かつては農家の庭先や畑の隅に食用として植えられていたそうです。新潟つながりでもしかして……と思いました。見て美しく食べておいしい菊が籠の中にいっぱい入っている、収穫を感謝する心も感じました。 (むべ)
-
「はや盛る上がる」という措辞から、多くの女性がおしゃべりしながら楽しそうに菊を摘んでいる様子を想像しました。籠の中に盛り上がった菊もそのおしゃべりを聞いているかも。 (豊実)
(きつきやうのはなのなかよりくものいと)
桔梗の特徴は風船が膨らむような蕾と開いたときの如何にも高貴な雰囲気の青紫の花弁でしょうか。GHでも訪ねたことのある京都廬山寺の庭園は紫式部の邸宅跡とのことで桔梗の名所としても有名です。青畝師に下記の句があります。
手触れなば裂けむ桔梗の蕾かな 阿波野青畝
これから開こうと裂け始めた花弁の隙間からハナグモが現れて糸を垂れている…という、うつぎ解に通じるものがありますね。ハナグモを観察しながらふと芥川龍之介作「蜘蛛の糸」のワンシーンがよぎったのでは…という素秀解もまた的中の感じがします。一筋スーと垂れている糸ですね。
こうしていろいろと関連付けながら連想していくと、「凌霄花の花の中」よりは「桔梗の花」なのかなと妙に納得してしまいそうですが、正直ちょっと難しい句だなというのが本音です。
- 合評
-
-
なぜ桔梗なのかと考えると風船の様な蕾を持つからだろうか。開いた時の蜘蛛の糸を見て蕾の中に蜘蛛が潜んでいたとは。作者の驚きが出ています。花蜘蛛は花や葉の害虫を食べるそうです。 (うつぎ)
-
「桔梗」は秋の七草のひとつですね。作者は七草を愛でるために桔梗を切り花にしたのかもしれません。桔梗の蕾はふくらんで、小さな穴からだんだん花びらが開いていきます。その穴の間からもしかしたら蜘蛛が入ってしまったのかもしれません。庭先でもうすぐ開きそうな桔梗を切ってきて花瓶に生けた。さあ、花が開いてきたぞ!と桔梗のなかを覗いたら…あらあら「くもの糸」。「花の中より」の「より」が効いていると感じました。 (更紗)
-
秋の季語「桔梗」の花の中からくもの糸が出ているのを見つけた作者の観察力、またその光景を句にする発想力に驚きます。美しいものだけではなく、自然界のセンス・オブ・ワンダーが句になると、このように生き生きと営みを伝えることができるのですね。 (むべ)
-
ハナグモは巣は張らないようですが、おしりから糸を垂らしているものもあるとか・・なんだかかわいいです。端正な桔梗の花と、かそけきクモの糸がズームアップされており、それだけで色やまわりの様々が見えてくるようです。花と蝶ではなく、クモであるところがユニークです。 (あひる)
-
薄紫の桔梗の花のふくらみから蜘蛛の糸が。花を足掛かりに巣を張ろうとしているのかもわかりませんが、作者は芥川の蜘蛛の糸を思ったようにも思えます。何を救おうと糸を垂らしているのかと地面に目を落としたかもわかりません。 (素秀)
-
桔梗が秋の季語、くもの糸が夏の季語だが、季節は桔梗の花の咲く8月~9月の初秋であろう。桔梗の花は幾何学的に整った花であり、それはそれでとても美しいが、整い過ぎているという不満も覚える。掃き清められた参道にある一片の花びらのように、くもの糸が桔梗の花にアクセントをつけていて、見る者に興を起こさせる。蜘蛛の糸は花に蜜を吸いに来る虫を捕える物騒な物であるが、「くも」と表記したことによって、そのような殺伐さを感じさせない。 (せいじ)
-
桔梗の花の中にハナグモのような小さなクモが住んでいたのでしょう。花をじっくり観察して生まれた句だと思います。 (豊実)
過去記事一覧
2026年|
01|
02|
03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2024年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2023年|01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2022年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|07|08|09|10|11|12|
2021年|
01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2020年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
2016年|
06|
07|
08|09|
2015年|
07|
08|
2014年|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
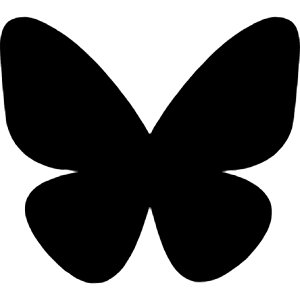 Bluesky
Bluesky
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()