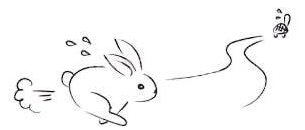
休まず継続することが一番の近道です。
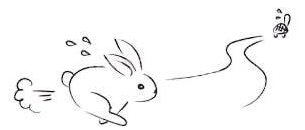
休まず継続することが一番の近道です。
俳句がわかり始めると初心の頃の素直さを忘れがちになり必ず不調に陥ります。
そんなときには原点に帰ることが大事です。以下のページをお気に入りに入れておきましょう。
上達のために守るべきことは、それほど多くはありません。
心象や人事の句は理屈っぽい作品になりがちです。初学のうちは、これらを封印して自然写生に徹しましょう。
散歩でもいいのでとにかく外へでて自然と対話して感動を見つけましょう。
未完成でも気にせず平明な自分の言葉でどんどんメモしていきます。
伝統俳句は季語が命です。季語の覚え方には以下のステップがあります。
俳句をはじめて一年経つとほぼ基本的な季語を覚えます。
三年を経ると季語のもつ本質(味わい)が解ってくると言われています。
季語は知っていても、その本質を実体験していなければ正しく使うことはできません。
一つの季語でもいろいろ表現にバリエーションがあります。
例えば「春」という季語を例に歳時記を見てみましょう。
春立つ、春の朝、春浅し、春深し、春宵、春行く、春の空、春の雲、...
単に春と詠むより具体的になりますね。
的確な季語を斡旋することが佳句を生む秘訣なので、季語のバリエーションを覚えることはとても大事なのです。
選句力は作句力よりも大事です。選句をおろそかにする人は上達しません。
選句力を養うことこそが作句力を向上させる最も近道なのです。
まぐれで佳句が授かる事はあっても、まぐれで佳句を選ぶ事は出来ません。
選句には個性や人格が現れます。真剣に真摯に対処しましょう。
句会中に私語をしたり真剣に選ぶ姿勢のない人がいますが、これでは上達は望めません。
あれこれと考えた末に納得して選ぶ…
これは間違い、分からなければパスし琴線に触れたものだけを直感で選びます。
テキパキと選句し粛々と清記稿をまわさないと他の人の迷惑になります。
パッと見て、サッと選ぶ
という習慣をつけましょう。
ぐずぐず時間をかけて選ぶ癖がつくと、あとからは中々直しにくいからです。
選句力を向上させるためには鑑賞の学びが大事です。
![]() には自由に参加できる合評の部屋があります。勇気をだして参加することであなたの鑑賞力は一変するでしょう。
には自由に参加できる合評の部屋があります。勇気をだして参加することであなたの鑑賞力は一変するでしょう。
吟行時の心がけについて説明します。
独り吟行は時間の制約もなくお喋りもしないので集中して作句できる利点があります。
けれども、
10句出来るまでは忍耐して頑張る
という強い意志を持つことが必要です。
互いに刺激しあって意欲的に作れますし、物知りの先輩に教えて貰えたり質問できたりという余録もあります。
大事なのはお喋りし過ぎないこと、集中して作句している人の邪魔をしないことです。
三人以上のときは必ず句会をしましょう。苦渋ながらも句を詠むようになりますし何よりも句会は楽しいものです。
ここと決めた処で徹底的に頑張り心を集中させることが大切です。
次から次へと頻繁に移動するとそれが出来ないからです。
同じ処で粘ることで思わぬ変化や動きを発見できる確率が高くなります。
表面的な部分だけを写生するのではなく、見えないものを見抜く観察力(心眼)も身につけたいですね。
漫然と眺めているだけでは句は詠めません。まず季語を探しましょう。
季語を見つけたらその場所に腰を落ち着けて句が授かるまで粘る。これが吟行の基本姿勢です。
いきなり佳句を詠もうと構えても駄目。
その前に感性の扉をノックして開いてあげるところからはじめます。
平凡でも未完成でも何でもいいので、まず一句詠みましょう。それが呼び水の働きをしてくれるのです。
同じような句がたくさん出来ても気にしないで、とにかくどんどん句帳にメモしていきましょう。
あとで推敲するときにA句の上五とB句の中七、下五を組み合わせるといい句になった…ということもあるからです。
多作しているうちに徐々に調子が出てきます。そこからが勝負どころです。
仕事や家族のことなど気になるようなことは全部忘れて集中し、五感を研ぎ澄まして心を遊ばせます。
これが上手にコントロールできるようになると、俳句はよい気分転換になってストレス解消にも役立つのです。
適当に作って添削してもらう…というのではなく少しずつ自分で推敲する訓練も大切です。
選者がどのように添削して採っているかを復習しそこから学びましょう。
句帳にある句を手つかずのまま放置してはいけません。完成、未完成を問わず何度も見直して完成度を高めましょう。
時間をおいてそれをすることで気づくことも多いので必ず推敲の習慣をつけましょう。
曖昧なことばを使うときは必ず事前に国語辞典で確かめておきましょう。
他にもっと適切なことばが無いかを調べるのも大切です。
類想、類句トラブルは日常茶飯事のように遭遇します。自他に関わらず明確な信念をもっておくことが大切です。
その句はわたしが先に作ってる!
などと大騒ぎする人がいますが、気にしないことです。
同じ情景を観察して類句、類想が生まれるのは当然だからです。
また天から降ってきたかのように素直に一句が生まれることがあって、
誰かの句集か歳時記などで見て記憶に残っていた句ではないか?
と、自分を疑うようなこともあります。
どちらにしても初学のうちはあまり気にしないほうが良いです。
必要以上に気にすると句が詠めません。
類想と気づかずに投句してしまうことは恥ずかしいことではありません。
ただ指摘されたり、そうとわかったときには潔く捨てましょう。
"どちらが先に作ったか"
などと論争するのは見苦しいものです。
類句が生まれるのは個性に欠けているからのだと謙虚に受け止めましょう。
つまらない類句論争をするよりも、類想のない個性的な創作を目指すことのほうがよほど高貴な志です。
好不調の波は誰にでもあります。挫折して休憩すると振り出しに戻ります。
多忙だから、不調だからという理由で作句や投句を休んではいけません。
感性の成熟は、スポーツの筋トレと同じで、休むと振り出しに戻ってしまうからです。
どんなに忙しくても一日一句を心がければ月に三十句は作れるはずです。
感性が鈍くなるとついつい頭で考えて作るようになりやがて不調に陥ります。
そんな時は少し作句を離れて恩師や先輩の句集を読み返してみましょう。
句集は小説と違って読み返すたびに新しい刺激が得られます。だから何度も何度も読むことで狂った感性を軌道修正できるのです。
投句はできなくても選句だけは続ける…というのも大切なことです。
ゴスペル俳句での学びに物足りなくなったので、さらに上を目指したい…
という思いが湧いてきたら結社に入会して学ばれることをお薦めします。
プロについて切磋琢磨することが上達への最短の道だと確信するからです。
以下に詳しいアドバイスを書きましたのでご覧ください。
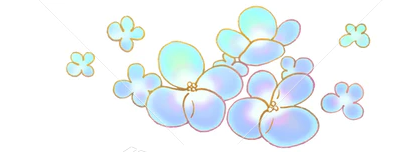
もし、あなたが ![]() での学びを卒業して結社で学ぶ道を選ばれるなら、それは私にとっても望外の喜びです。
での学びを卒業して結社で学ぶ道を選ばれるなら、それは私にとっても望外の喜びです。
上達への近道がお役に立ちましたらひとことエールをお送りください。