
みのる俳句の信念について説明しています。

みのる俳句の信念について説明しています。
初心者にとって指導者選びは何よりも大切です。指導者の信念に疑心や不満を抱いたまま学びを続けても上達は望めず時間の無駄になるからです。
みのるの俳句は、『有季定形の伝統俳句』を基としています。
恩師阿波野青畝先生が昭和48年7月4日付の読売新聞に「俳句の信念」という一文を発表されています。![]() の信念もまたその諭しを礎としていますので、記事の内容をそのまま転載させていただくことにしました。
の信念もまたその諭しを礎としていますので、記事の内容をそのまま転載させていただくことにしました。
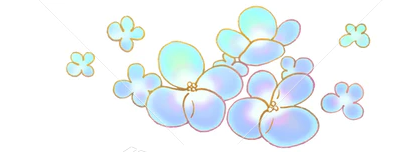
以下の記事は、阿波野青畝師の著書『俳句のよろこび』(富士見書房)より転載したものです。
たとえば自由律の、
雪積もる 夜のランプ 放哉
でも、
あすは元日の爪でもきろう 山頭火
でも、これを口でうたえば対象が目に見え情感がつたわる。つまり日本語が日本語として自然だからですある。
しかし伝統としての俳句は、季語と定形が約束であるから、上掲の句は詩として価値を認めるが俳句ではないということだ。俳句でなくとも新しい名目の詩を生かすことは不名誉ではないと思う。芸術の自由な園にはいろいろの詩のジャンルがうまれることはわれわれを楽しくするであろう。
![]()
しかし伝統を守りそれを新しく育てようとする者は、あくまで約束を守らねばならぬ。真に約束の意義に徹すれば、約束は自由を束縛しないのである。節度を持つ美しい表現は約束なる枠があるからだ。そこには表現の自由という魅力をわれわれは発見する。
俗に、苦あれば後に楽ありという。何もかもが自由であることは無上の楽しみではないことの実感は、約束の枠に苦心してそれをマスターしえた人たちに湧いてくるだろう。
![]()
芭蕉も鬼貫も誠を唱え、誠を責むべしと教えた。誠は内部に抱いている詩精神であって、この詩精神はそのままでは発育しない。対象に直感して詩精神を昂揚させる。このとき、どうしても創作したいという強い意欲となって出る。
俳句はまことに短小の詩型で、複雑な事態を取りいれがたい。それは叫びに似た簡潔な要素だけを受けいれ、千万言に匹敵する強靭な力を見せることができる。ところが今日の複雑な世態にある人の心は収拾がつかない。簡潔な俳句になじみきれなくて、むりにぎしぎしとつめこむか、あるいは奇形の、たとえばアバンギャルドが現れたりする。そういう現象に向かって、私など理解しようがない。そうなってゆく気持がわからぬことはないのだが、俳句というユニフォームがほころびたら着て出られなくなるのである。
![]()
私は、われわれの日本語を正しく、そして美しいしらべを発揮するように用いるべきだと痛感する。ことばは生きもので、それぞれ生命をもっていると考えるのである。清音と濁音とでも、その音が耳にはちがった感情の波をつたえる。
どでどでと雨の祭の太鼓かな 虚子
この句は「どでどで」とある濁音のひびきで太鼓の皮が湿ってたるんでいることを直感すると同時に、雨中の祭り風景の気分が眼前する。
音楽をきくように句の味わいがにじみ出てくるのだが、これは日本語を正しく叙しているから美しいのである。「雪つもる 夜のランプ」というのも日本語が美しいと思う。
![]()
日本語が正しく美しいということで、私たちは日本人である誇りに自信をもつ。遠く『万葉集』や『古今集』の古典から引き継いでいるわれわれの宝でもあるわけだ。日本語にはわれわれの歴史があるので、何から何まで委曲に叙述しないでも意を達してくれる。そういう点では日本語が不完全であるといわれているのだが、俳句のような韻文文学においては、その不完全さを逆に面白くさせ、融通無碍の妙味を見せるのである。
無は有を含む無であるという東洋的思想から、俳句が短い詩であり、短い語をつづって極めて簡素に叙することは、無限のことばに引けを取らないだけの力があることを信ずる。
今の若い世代の初心者に、このことは理解できないとのそしりが出るだろうが、ぜひこれを克服し、鍛錬に鍛錬を重ねるうちに、日本語であるかぎり必ず暁が白むように無明から解脱してくるに違いない。
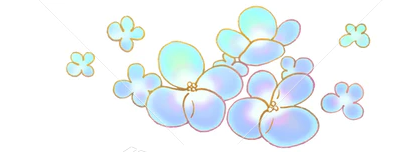
次に季語についていう。
俳句は日本の風土に生まれ育ってきた。つまり日本のこの自然環境は、われわれが俳句という短い詩によって挨拶し礼賛するようにあるものである。
日本人は昔から挨拶を好む。挨拶とは自然に呼びかけたり社会の人に挨拶したりして、まろやかな情緒を訴える手段である。
誰もが知るとおり、日本の気候風土は四時の変化が規則的にくりかえしている。しぜんに季語という便利なことばが編み出され、それを使うことによって多言は要らぬし、ほんの季語一つで連想の世界をひろげることができる。
ところが毎日のニュースは自然破壊汚染で賑わっているが、これも極限に至るまでに自然保護を呼びかけてきた。緑を還さねばわれわれの生存がたちまちおびやかされることは必定だ。俳句をやる人は日本の自然が失われることを悲しみ、今の自然を後世に詠みのこしておきたいという気持ちであり、反面には世の終わりを待つ危惧を抱かされるといった原状であろう。
季語を見ると愛惜にたえぬ古い季語が消えてゆき、新しく登場する季語がニューフェースで増加する。若い人はこのニューフェースに今日的の意識過剰でとびつく。えてして不消化で失敗する。
![]()
さて私事にふれてはなはだ恐縮するけれども、こんど私に蛇笏賞を与えてくださったのでつくづく考えてみると、私の作品はどうもはずかしいものと思う。ただ長いあいだ伝統を守るために日本語を正しく日本の風土を愛する一念を貫いて、恩師虚子先生の教えどおりに後世の人に渡したいと努力した、それだけのことを買われたのだとして受け取ろう。
(「読売新聞」昭和48年7月4日)
青畝師の記事転載はここまでです。
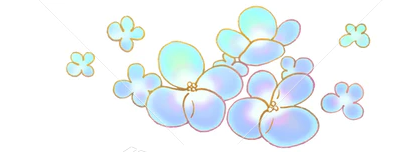
この記事が発表されたのは昭和48年ですから50年前です。半世紀を経ても色褪せぬ力強い内容は、今の時代の私たちが読んでもため息が出るほど納得でき、あまりにも的確な論旨の前にただただ頭を垂れるしかありません。
昨今は、IT界においてもまた書籍界においても伝統俳句の影は薄れがちで、現代俳句が主流となりつつあることを憂いますが、たとい少数派と呼ばれても青畝師や紫峡師から託された教えをしっかり継承して、伝統を守りつつ「温故知新」「古壺新酒」の志をまっとうしたいと願っています。
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。
Feedback
Twitter
 Mastodon
Mastodon
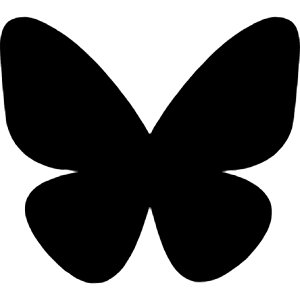 Bluesky
Bluesky