

こんにちは、やまだみのるです。
阿波野青畝師の『掌俳話』を俳句バイブルとして書き写しました。旧新約聖書66巻と同じ全66話の構成です。
![]()

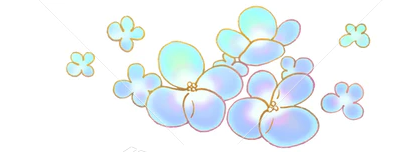
若い頃に比べて日本の自然や社会が大きく変化したという感じを強くします。
それはゆっくりでなく、またたく間に急速化していると思います。たとえば、若い頃の新年の空が澄んで美しかった。明けぬうちに起きて若水で洗面する時の星の瞬きが、なんと清々しかったことか。
しばらくして初日の出る東へ向かって手を打つ音の嬉しかったことを思い出す。
今は公害々々で、初空というても日の光がにぶい。往来は排気ガスの匂いを感じ、そらぞらしい賀客の表情に生活のつかれが残っているように見えます。
こうした今日にあっても、私たちは心のふるさとといえる自然本来の姿をあこがれずにはおれません。
また、新年は新年らしく心持を清々しくさせる社会を求めます。
元日や神代のことも思はるる 守武
声俳壇に出句なさる方は必ず季語を忘れずに詠み込んでおられます。
それは俳句に季語が生命になるからであります。季語のない句は俳句でないのですから採ることができません。
なぜ季語が必要かということは、俳句は極端に短い詩であって多くを盛り込んで叙べられないために、余情とか連想とかに由って意味をできるだけ広くするのであります。
日本という国の特色は春夏秋冬の秩序が正しく、昔から美しい自然を賛美し、こまやかな季節感情に感動する伝統的な精神を養っております。
そこで季語が制定されるのであります。季語はあらゆる季節的要素を圧縮して短い言葉となっているが、それはまた無限に広がる可能性に富んでいます。
季語をよく生かせる人は立派な季節詩をなし、生かせない人は無意味に終わってしまいます。季語の働きを手品師のように自由自在に駆使するとき、多くを語らずして人の肺腑にしみ込む作品が出来上がります。
もともと俳句は沈黙の詩なので、そういう力を利用するわけであります。
「造化に随ひ、四時を伴とす」芭蕉の紀行文の笈の小文に、右のことばを記している。
造化というのは造物主のこと、やさしく説けば自然と解釈してよろしいかと思う。ことに私どもは、自然を最も大切にして、つねに自然を愛し、自然から離れることは絶対にないのである。
大まかに分類して、春夏秋冬という順序に規則正しく変化してそれを年々くりかえしている。これを注意深い目で見れば、実に微妙な変化に興味をそそられるので、四時を伴とするということが、俳句を詠む私どもにとってぴったりとする言葉と言われるわけである。
そこで季の目印となる「季語」の設定があり、季語によってそのじぶんの季節を連想して感情を叙べることができる。多くを語らないで、むしろそれ以上の広がりのある緲々とした感情を端的に季語に託するという方法をとる。
ここに私の倚っている机がある。机だけでは季語にならぬから季がない。しかし私が見るところには季のない机はない。きっと何かの季語を背負う机と見て感じる。
例えば春灯の机でもあり、そばに火鉢をひかえる机なので、こういうふうにどんなばあいにおいても自然の変化に伴う季節感情がついてまわり俳句を詠む好材料として、私どもと倶にこの人生にあるというものだと思う。
私どもは自然に反するという行為は出来ないのである。あくまでも自然と一致しないではいられない。ありがたいと思っている。
ある対象を見たときに生き生きとした感情が揺らめきます。
その感情をなるべくそのままの純粋さを損なわないように、しかもその時の対象を常識によって覆い隠さぬようにと充分に注意する必要があります。
子供は感じたものを遠慮せずに素直に発表してくれます。これは直感であります。自分の感情で傍から加えられたものと違います。
常識とか概念とか言われているものは直感と反対に他より教えられて知る一般的になったものであります。そこには生きた感情が消えて一般化し、自分でないものがのさばるのみです。
子どもの発表はただ幼稚であるが、この直感を巧妙に、強力に工夫すれば立派な作品を生み出せるのです。
ところが、常識的な、それは借り物に過ぎない内容で俳句を詠む人が多い。俳句らしい俳句を真似る人が多いと言うことを私は残念がります。
自分を見出せ、それは自然を自分の心で感じ取ることにあるという訳であります。
加賀の千代尼に次の朝顔の句があります。
朝顔や釣瓶とられて貰ひ水
人口に膾炙される句は「朝顔に」で、この一字の差で良い俳句と悪い俳句とに分かれることをよく注意されたいのであります。
「朝顔や」は良い俳句である。なぜならば咲いている朝顔の爽やかさを礼讃するからです。夜遊びした村の若者の悪戯で釣瓶が無くなったので仕方がなく貰い水をしたという意味になります。田舎の夏の朝の感じを味わいます。
「朝顔に」は悪い俳句である。偽物だからであります。なぜ偽物か。朝顔は蔓をもっているが僅か一夜では釣瓶の竿に絡みつきません。万一絡みついたからとてわざわざ貰い水する酔狂はしないでしょう。見せかけの通俗な風流心である。誠の詩を解せずに、こんな見えすいた嘘を承知で、人口にもてはやしているのです。
俳句は自然の真実を愛します。自然に即す、「松のことは松に習えと」と芭蕉が言いました。偽風流を排斥して一番素直な心で向かいましょう。
私らの作る俳句は伝統を重んじます。
古来一貫した精神の良い長所を守り抜きながら、新しいものを求めようと心を砕いているのです。
古いものがよいというのではないのです。古いものがなぜ今もなお生命を保ちつづけてきたのか、そこには何かの理由が厳存しているものです。一口に言えば真理があるからで真理は永久性を具えてみだりに忘れ去られるものではないのです。
古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求むべし、と弘法大師が説かれたそうですが、伝統というものは、古人が求めてきた精神をよく考え、この精神に強く感化されながら、更にこの精神を成長させたいという熱烈な欲求に創意を発揮しようとすることで守らるるものです。それ故に私らの俳句は今日の時代が反映して新しくなります。
私らの生活している周辺の自然風土、つまり神のお造りくださった自然を愛し、自分の正直な心によって自然を詠嘆する。自然を生写しに描写する。借り物でなく自分の目で心で感じ取ることが大切であります。そういう意味で、私らは新しいものを追求せねばならないと思います。
俳句はもとより、伝統の文学としての一つであります。
自然を愛する日本人が、血の流れの中に先祖より遠く受け継いできた詩の形式が俳句であります。
この種の形式を自分勝手に壊したり変えたりすることはできない。例えてみれば角力のあの土俵があるようなものです。土俵が狭いからといってあれを取り除いて自由な広さに改めたら、それはもう角力の魅力がなく、角力にはならない。
これと同じ道理ですから、俳句は十七音という短詩型に不思議な魅力を持たせていると言えます。
俳句の容器にもる内容を新しいものにすべきであります。新しみは重要な要素です。
現代に生きる日本人の感覚なくしては新しいものが生まれない。つねに生々とある自然を見つめ、借り物でなく自分の目で見、心で感じ、自分の創造意欲を発揮しなくてはなりません。これを。「古壺新酒」という短い詞で虚子先生が示されたのです。
伝統の文学である。しかし伝習ではないという点を強く戒めておきます。
私は長い間俳句に携わってきたおかげでしょうか、私たちが生存する風土のありがたさを忘れてはならないと思います。
あけくれ私たちの接している大自然から量り知れぬ恩恵を受けて生きているのです。ずっと前に自然を征服するという言葉が流行したとき、こんな言葉は間違いだと抵抗を感じました。
近ごろ公害を喧しく言うようになり、自然保護という言葉を目撃いたします。 これも主客転倒で、自然がいつも私たちを救っているのにそれに気づかず、人間が自然を保護せよという意味が愚かでありませんか。
自然を愛する心を喪失して、人間が神を忘れ増上慢をつのらせるから、今日のように人間が住めなくしてゆく、それを尤もらしく自然を保護せよと叫び出す。
「松のことは松に習え」と芭蕉が言ったのは俳句だけのこととせず、徹底して自然に帰一する謙虚の一念を燃やすことを悟りたいものです。
日本は水に恵まれた国であるが、その水が命を脅かすようになったのは、誰の犯した罪であるか、われわれはよく反省しなくてはなりません。
俳句はよく滑稽を詠む。ユーモアを感じるとき笑いの表情が綻びます。
最近甲虫が流行で伊吹山で一匹百円とあり。町で買うと三百円もするそうです。驚きましたね。
一筋に糸まっすぐや甲虫 高野素十
細い糸に繋がれている甲虫が這いだした。が糸の長さ以上の距離へ行くことができない。つまり糸に制約されているのですが、それを知らぬカブトムシは懸命に足がいているためにピンと糸が張っているところを見ると何か哀れであり、またその偽りなき実景がおかしみを示します。
ごみを掃き取ろうとして庭隅にかがみました。こそこそと這い出た一匹の昆虫と衝突したので私も昆虫も同時にハッとしたのです。すると間もなく臭い空気が鼻に流れてきました。この虫の放った排気ガスでした。
ミイデラゴミムシを放屁虫と俳句では詠んでいます。
放屁虫貯えもなく放ちけり。相島虚吼
貯えもなくは面白いですね。危険を感じた虫の慌てぶりが見られます。この滑稽さは前の句よりもよく理解できます。でも前の句は目に捉えたありのままを描いて、滑稽はその景色の裏にぴったり附いているのであります。
又俳句は挨拶の心がこもっております。
人と人との出会いには挨拶の言葉を交わされる習慣があります。挨拶を交わしてお互いの場がなごやかに美しくなることはご承知であります。
昔から日本人は挨拶を大切にしてきました。そして挨拶の心で詩歌を述べたのであります。その中でも俳句が一番よく季候の挨拶を述べます。
それは季語を詩の約束としていることが立派な証左です。いきなりに用件を持ち出すよりも、まず今日は冷えますねと呼びかけて相手の心を親しくひきつけようとします。
さみだれを集めて涼し最上川 芭蕉
大石田の連中にもてなしを受けた芭蕉は、眼前の景色をほめて涼しと挨拶の心を示したのです。
岸に蛍をつなぐ舟杭 一栄
連句ですから主人側も右の脇句で歓迎しました。
さみだれを集めて早し最上川 芭蕉
奥の細道の文中に「早し」と改めています。これは舟下りの実景としてあの急流のすさまじさを表現したのですが、やはり自然に対しては挨拶の心を失っていないと思います。
滑稽に始まって、それがお互いの親睦の挨拶となっている俳諧(俳句)であることを申し上げたが、それは即興を旨とすることが必要になります。
今日はその即興の事を話してみましょう。
俳句は最も短い詩型であるゆえに、さらりと当為即妙に処置するのがふさわしいわけであります。深い思想やら複雑な人間関係をおりこもうとするのは。甚だしい無理を冒かねばなりません。
俳句として面白く効果を上げるものは、打てばひびいて立つという気合であります。
つまり即刻の感興を表現するということになります。考えに考えたものや、理屈をこねまわし、または読者を不愉快に導くような手段や、そういうふうな即興でないものは成功いたしません。
初時雨猿も小蓑を欲しげなり 芭蕉
しぐれに濡れる猿の姿を見るなり、即座に感興をこの句に叙したのであって、よどみを見せずその気分を十七字に盛りたいものです。
流れゆく大根の葉の早さかな 虚子
見たままの即興です。
元日や神代のことも思はるる 守武
俳句の元祖と言われている荒木田守武の句である。
俳句という名称は後から出来た。当時は発句と言ったのである。
発句というのは、俳諧連歌の発句の意味がある。俳諧連歌を略して連句という。連句は長句(五七五)と短句(七七)とを交互に連ねて長編となる。そこで連句の第一番に出発する句を発句とするから、発句は五七五の形をとらねばならない。
発句はまず連句を行う最初の挨拶を述べる。季節の挨拶をすることが習慣になっているので、発句は季語を用いることになった。
わが国の風土は四季のうつりかわりが正しく、春夏秋冬と変化するにしたがって自然も人事も詩や歌の良い材料となり、且つ優れた文学を生んできたことは周知のとおりである。
発句が季語を用いるという長年月の経験によって、季節の感情が豊富となり、繊細となりいろいろ多種多様の面を表現し、またはそれによって俳人はさまざまの性格を発揮する。
俳句の母体は和歌である。和歌から連歌が派生し、連歌が俳諧連歌に移ってきて発句が生まれたという歴史を振り返ってみてほしいのである。
俳句は目で鑑賞するのか、耳で鑑賞するのか、こういう議論がありました。
耳で聞くだけでは何のことか分からない場合が多々ある。やはり目で字体を読むべきであるというので、片仮名で書くか、画数の多い漢字で書くかによって作者のキメ細かい感情を知ることができるというのは成るほどと思います。しかし目のみに頼るのは弊害も生じます。
もとは歌うということから詩歌が始まってきたのです。歌われるものを耳で聞き、そして共に同感しあうということを本来とするので、ちょっと音楽に似たものを持っています。
耳で聴いて分かるのはリズムがあるからです。リズムは人間の感情の波であります。喜怒哀楽の感情を説明抜きで我々に伝わってくるのは言語のリズムが示してくれるのですから、やはり目のみではなく十分耳で楽しく受け取れる作品であって欲しいと私は思うのであります。
近来若い世代の人はこういう点で惑うていて、とにかく刺激の強いようにと難解なお化けのような句に誘惑されがちであります。
日本語のような不完全な国語はない、とよく人から言われます。
それはその通りだと思います。決して完全な意味を伝えられません。
例えば「ヒ」という音です。これは太陽の日を指せるし、明かりの灯を指せるし、時間の日を指せるし、反対に氷の冷たい氷にもなり、水を通す樋や物を織る梭にもなるので、漢字の力を借りて少しは区別をつけています。
このように曖昧で分かりにくい言葉を我々は平気で使用し、案外のんきに黙っていられるのはなぜでしょう。
それは想像力が発達して、その意味の的確を探りつかめるからだと思います。
極端かもしれませんが、無言は多弁とも言います。素晴らしい想像力を働かせることです。
只十七字の短い俳句、不完全な言葉の十七字詩は仮に千万言費やしてもいい尽くしたと言う感じが起こらぬものです。しかし心が引かれて深いものに触れた気持ちが満足を与えます。
言う人の生命が言葉に宿るからでしょう。言葉はリズムを出して微妙な感情を伝えます。句作者は感情と言葉とのリズム(ひびきあいの一致)を工夫したいものであります。
半月ほど日本を離れてインドという異郷に触れてみた。
インドは日本と違って広い国である。常夏の国と聞いていたが、昼は暑くて夜急に冷えたので驚いた。自然の風物は一月であったから日本のように枯野という光景ではあったが、ブーゲンビリアとかハイビスカスとかが真っ赤に咲いているし。孔雀とかインコとか色彩に富む珍鳥が飛んでいるしして非常に変化していることをはっきり身に感じた。
一年中の変化を研究すれば興味もあるであろうが、しかし日本の風土のような正しい時候の変遷を見ることが不可能のように思うのであった。
日本という気候風土が自然に俳句という詩を生み出したもので、そういう自然を賛美するために、我々日本人の血の中に詩質を受け継いでいるのであろうかと自信し得るようになった。
私は日本人の旅行者としてインドの句を多く作った。それは結局日本人という立場にある感覚であるから、永住するインド人から見ると見当違いしていると思う。致し方ないと思う。
私は日本に帰って水のありがたさを知った。この風土この季節を心から感謝すべきである。
先年欧州を見聞きしてみて、欧州の秀れた長所を知ると同時に、わが日本の長所を反省するようになった。
日本の長所を甘く見ていた結果、大切に感じなかったからである。こんどインドの地を踏んでみると、やはり同じことで、日本の長所が際立ってありがたく身に心に感じてならなかった。
人々は慣れてしまうとその長所という価値を忘れるものである。
で、俳句という短文学は日本の風土から発生して伝えられているのみならず、今なお愛されてこれに精神的生命を託する人士の多いのはその証左と言えるのである。
私は日本ばかりが世界一のように言っているのではない。外国にもそれぞれに適した長所が数えられる。「各々處を得る」という語のように、俳句は日本が生み、そして育っているということを強調したいのである。
それは自然が規則正しく変化すること、国民性が誠に淡白であること、一見不完全に見える日本語もそのレトリックに余韻を持たせることができることなどにあるので、まことに日本人は庶民詩人の性質を備えているというわけである。
この頃の人は言わないが、俳句に切れ字がある、切れ字が大切なことだと昔はやかましく唱えたのである。
「や」又は「かな」とか「けり」とかいうのは切れ字の役目をする。芭蕉は、切れ字は名詞にもその他にもあるといっていたから、や、かな、だけが切れ字ではない。
さて、切れ字とは何か。なぜ切れ字が必要であるのか。一と口にいうと切れ字は意味がそこで一旦切れる。ずるずると後へのびないようにはっきりした折目をつける。そのために音楽の方で言う「間」に似た空間ができて、その空間は無意味な空間ではなく、含蓄の多い空間であるから、俳句のような短い詩に連想を呼び起こす一種のため息に似た感動が湧いてくることになる。
この切れ字を適当に使った俳句は、ごく簡単なことをしているにかかわらず、俳句の内容が広がっていくことになり、例えば鐘が響いて遠くまで広がってゆき無限の味わいがいつまでも漂っているというように鑑賞される。
つまり言葉少なくして情長しという具合になれば俳句は他の文学に負けない強みを持つわけである。
語と語の衝撃、そこにも切れ字の役目が働く。切れ字ということを我々は等閑(とうかん)にしていてはいけないと、私は思っている。
さきに切れ字について叙べ切れ字の必要を話した。
俳句は省略の詩である。多くをおしゃべりすることを嫌い、できるだけワンポイントを力強く訴え、印象づける韻文である。
ある感動を詠嘆する。詠嘆または風詠というものは韻文の要素である。ところが一般に散文化の傾向があって、詠嘆よりも報告に走っているようである。これは欧米文化の影響と思われるのであるが、益々余韻余情がなくなってしまう。印象づけることよりは顛末に繁雑を極めるばかりである。
一読朗々と響き、音楽のように妙境に誘い入れるためには階調がなくてはならない。俳句には俳句の階調が備わっている。その階調は切れ字によるところが多い。
私はこの階調を常に頭に入れて、それから新しく創造してゆく努力をしたいと専心しているのである。
俳句は短い韻文詩であるから、単純化して詠み込む方が得である。
何もかも押し込めようとしてもだめである。
複雑な人間関係とか社会思想とかは俳句では重荷になる。そのにおいというものを感じさすしかできない。そういう場合省略ということを考えなければならない。省略してワンポイントを強く打ち出すので、叫びのようなものだと思う。詠嘆である。
月さして一間の家でありにけり 村上鬼城
もっと簡単にすれば「月さして一と間」で自由律でゆけばよろしいが俳句が五七五調と季語を守らねばならないので、右掲の句が出来た。下の「の家でありにけり」は重要な意味を持つ言葉ではなく、いわば虚字である。しかし俳句の余韻余情はこの虚字に因るのでこれを大事と考えてもらいたい。
要するに単純化と言うことは余韻余情を生み出す簡潔さであって、謙虚な態度なのである。音楽に「間」というものの効果を必要とする。短い俳句にも同じことである。
氷山の一角という譬えは俳句に一番よく通じる。
ということは、俳句は最も短く小さい形の文学である。しかし俳句に含まれる内容は非常に大きい。測り知られぬ余情の広がりがあるからである。
海面に出て我々の目に映る氷山と、海中に隠れ沈んで我々の目には見えない部分(これは七倍の大きさがある)とを連ねて見ると実に大きな氷山として驚異に値する。
目に見えるものから目に見えないものへと伸ばして全体をひっくるめて鑑賞するように俳句という短い文学が生きているのである。
季語、切字、省筆、謙虚などは俳句に必要とされる。それは俳句の内容を大きく盛るためにする手段でもある。
ある対象にぶつかって我々は興奮する。驚きを受ける。なんとかそれを言い現したくて仕方がない。
我々はそれを直感と呼び、直感を逃がさないようにして読者に訴えるのである。
だが、このとき誰も彼もが知っている概念にもたれかかって概念で説明するからいけないのである。概念はつまり常識であって、作者の生マの直感がない。
その直感が通じぬ場合もあろうが、工夫すれば通じる。いな、通じないとしても。概念にごまかされるよりは作者にとっては大切な直感であり、創造であり、その人のものになるのである。例えば、
十薬の花に五弁がありたるよ 高浜虚子
十薬の花は四弁の花で、五弁はめったにないことは、十薬の花を見る人の常識である。だから十薬といえばああ十字形した白い四弁の花とすぐ頭に浮かぶ。
ところが虚子先生の驚きは五弁を発見してこれはまあと叫ばれた。五弁がありたるよという直感を我々に示した。
常識を超えたところに魅力があるのであって、四弁だと言ったのでは常識で誰でもよく知っているから。興味がわかないのである。
つまり四弁の中に紛れ込んで五弁のあること、自然の持つ不思議があるというのが大変面白いと言ってよいのである。
自然破壊を叫ばれて前途が暗い思いにさせられる一方で出版界は歳時記ブームを巻きおこしたと見られる。
歳時記は俳人の虎の巻として必携の書である。春夏秋冬の自然現象から人事百般にわたる季題を寄せ集めて説明してあるし例句を添えた書物である。最近は俳人のみならず、各方面にも布衍(ふえん)していて、☓☓歳時記△△歳時記という工合に応用されていることはご存知かと思うが、要するに自分の庇護を忘れることができず、むしろ自然の恵みを認識するためにあるという見方ができる。
自然破壊を反発して起こった機運がこのような一つの形となって現れてきたと、私は喜んで将来の暗さを逆に明るく見通しているのである。
自然を美しく生かすために人間の知恵を高揚して行くことが正しい文化のあり方であって、自然を征服するという増上慢は絶対に許されない。
俳句を作る人は対象となるものをよく観察しなさいとすすめます。
先入観を捨てることです。つまり、自分を空しうして素直に物を見つめていると、きっと発見する驚きがやってきます。そのとき思わず心がときめく、その印象をしっかりとらえて誰かに話しかけたいという気持ちが離れません。
先入観が入り込むと、その発見を歪めてしまい、勝手な注釈をつけがちになり、もう概念的な、きらりとした新しさを失った死物同様に見なされてしまうので、それが恐ろしいのであります。
けれども、見ている方は人間なのですから、心を持っています。心を捨てることができません。発見によって心が生き生きと活力を表して創作力を生むのです。
物心一如というのは、こういう場合であろうと思います。対象(自然)と人間とがあたかも一体になったような陶々然たる気持ち。それこそうっとりとさせられる境地ではないかと考えられます。
良い俳句を作る練習には二つあるように思う。
一つは良い俳句を読まねばならぬ。これは良い俳句から学び取り、自分への滋養を吸収する。たとえば古格を知り格調に馴れ、切字の働き、含蓄をもつ言語を選ぶための練習である。であるから古今にわたる立派な作品を鑑賞する。暗記せずともよいがすぐ思い出させるのほどなじんでおけばよい。
もう一つは周囲をよく観察する。いわゆる写生の目を常に向けておく習慣が必要である。句の生まれるヒントは向こうからやってくるのだが、といって棚ボタで待つようではいつまでも来ないのだから、自分で努力して変化する周囲に気をつける。するといろいろな興味を惜しみなく与えてくれる。自然の美の発見や想像が自分をして行為せしめるようにするであろう。
右の二つの練習は、物の本質である大観を捉えることと、作者たる自分の発見創造とをアレンジしつつ上達する一つの方法であると思う。
剣法でいう白眼の構えと青眼の構えとに似ている大事なことである。
いまや石油危機という困難な時期に直面しています。
いま静かに考えると石油の恩恵に私らは慣れすぎてきたということでしょう。便利なものに走りすぎて物を大切に取り扱わなかったのです。大切にせねばならないという気はあっても、世間の大きな波に取り残されて約立たぬ人間になる恐れがありました。
ところが今になって私らは大自然というものの本来の姿を見出したのではないか……とそんな感じがします。人工のために忘れかけた自然、その秩序、その生活などが再びよみがえりを見せてきたようです。
私らは便利さを奪われて当座はうろたえるでしょうが、ありのままの自然がじかに私らに触れあう、そこに虚偽なき心の喜びがあると思います。
歳時記に集められた季語を見ると、自然という悠久な不思議なものをそこに感じとれる。俳句とはその自然と自己との触れ合いであり、挨拶でもあるのであります。
芭蕉の遺した言葉を紹介しておこう。
風雅には万代不易と一時の変化とがある。この二つの究まる根本は結局一つである、といっている。つまり風雅の誠は一つだと決めているのである。
理屈をのべる事は面白くないが、自然という対象は四時常態で昔も今もあはれだと感心する歌が多いので、こういうものを不易と名づける。だがそればかりやれば古人の涎をなめるのと同様でつまらないものである。
自然という対象は気をつけて接すると千変万化してとどまるところがない。その変化する驚きに敏感でなくてはならない。芭蕉のいう風雅の誠とは、心をとぎすまして自然に体当たりをすれば変化を発見して直ちに句に作すこと、すなわち誠の俳諧だと説かれている。
四時変化する中に一貫した四時常態が存在する道理を認めるのである。
私たちが常に俳句に新みがなければならない、一歩でも新しく前進する必要がある、と唱えるのは芭蕉の風雅の誠の教えに従うためでもある。
「三冊子」という本に芭蕉は、松のことは松に習えといいそして私意を離れることが大事であると訓えている。
松を松らしく描くためには自分が松になった気分で描くのであって、松をこういう形に作り直してみようと勝手に変えたりしては不可ない。それは私意を入れることになり松に習っていないのだとの教訓だと思う。
この道理はよく分かるのである。けれども初心の時は懸命になって対象を見つめるのであるが、少し慣れてくると自分の考えが恣(ほしいまま)に加わる。自分の考えは大抵はよく見えても底が浅く、忽ち作り事であることがばれて賤(あや)しさが見えるのだが、気がつかないのである。こうなると対象を見つめることをおろそかにして、ただただ自分の勝手な考えをふりまわす、つまり私意に溺れる。
その私意をつっ離して一途に自然の姿を自分の心に融かし込むほど辛抱して見つめる。そうすれば、自分は自然と一如になっている気分がして何ともいえぬたのしい陶酔状態に入るに違いない。
われわれの実作の上にこの苦しみと楽しみとがいつもまつわりつづけている。
四月八日は虚子忌である。
その日に床にかけたままにしてある一幅を眺めながら、今回はそれについて語ってみましょう。
実は私の作った句を家内が表装させたのであって、人に見てもらうほどの品ではなく、ただただ私どもの思い出に役立てばよいと思っている。その句は
春空に虚子説法図描きけり 青畝
知恩院で七回忌の法要があった時に詠んだ。
桜が咲き公園は人出に賑わっているし、うち仰ぐひろびろとした空はうすく霞み、日の光も長閑かに柔らかくさしている日で、お勤めの鐘がいかにも京都だなと心にひびくのであった。
そんな空をじっと見上げると、私はいろいろの虚子先生のイメージが浮かんきて、丁度スクリーンに次は何が写るかという興味を期待する。
そうすると、俳句は「客観写生」でなくては…とおっしゃるお姿が出る。又「古壺新酒」の譬を以て形式は変えなくても内容は新しくすべきだ…と唱えられるお姿が浮ぶ。
又々「花鳥諷詠」とは花と鳥に限らない宇宙大自然の相で、芭蕉も笈の小文で造化に従い造化に還れと言ったように自然を詩に詠むのが俳句だよ…と親切に教えられる慈顔となってくる……と言うふうに先生の思い出が生き生きと湧いてくるのであった。
私は釈迦説法図というものを見た。いまの虚子先生の姿こそ例えるならば虚子説法図ということができると考えてともかく自信を抱いてこの一句を得たのであった。
土芳の「三冊子」にこんなことを記しているのです。
「師(芭蕉)のいわく、絶景に向かうときはうばわれて叶わず、物を見て取る所を心に留めて消さず、書き写して静かに句にすべし。うばわれぬ心得もあることなり。……」
初めて句を志す人は絶景ばかりをねらう癖があります。絶景を見ずに句ができぬとでも考えているのでしょう。
実際、われわれはこの反対側で、絶景なんてとても容易に句にまとめることはできないのです。心がしずまって興奮状態から冷めると、その時のイメージが灼きついているから平常心で詠むのが案外に成功し易いいので、この経験は確かだと思います。
で、日常の目に触れ耳に聞く平凡な事柄を句材として、それを詠むことを初心者ばかりでなく誰にも奨励致します。
日常のことがらは平常心で注意すると、かえって気づかなかった興趣を発見し、そして創造力をもたらす可能性が湧いてますます面白くなります。
絶景のばあいの興趣は酔ってしまった状態になっては物を忠実に見つめられなくなるので、その興味は後でぼやけて何が何であったか、読者に伝えることができないわけです。芭蕉でも松島では句がなかったと書き加えていますが、一寸参考までに申し上げます。
現代の社会生活がいかにも息苦しい思いであるとして、それにしばらく目をそむけるべく社会とはあまり関係の薄い自然の風景に視線を向けようという立場で俳句を作る人達がある。
又それとは反対に現代の社会生活を句材として自分たちの戦から意気込みを表現すべきであるとして、それこそ生きているしるしだからという立場で俳句にしようと考える人たちがある。その他の立場もあるようである。
俳句は宗教に似たものであるから、現象の奥に潜んでいる哲学的な思想を示すべきであると唱えた人たちも確かにある。
私はいずれを是としいずれを非としたくはない。その人たちの偽らぬ心を表現上に生かした作品を採る。だから第一に表現の巧拙が問題を解決すると思う。
表現に成功した作品は、いろいろな立場が充分に理解される。従って新しい創作を素直に認めることが可能である。
今年は珍しく、八月八日の立秋はさわやかに朝風が風鈴の舌にたわむれ、この涼しさを嬉しく感じた。
今までは手紙のはじめに立秋とは申しながら大変暑うございますという具合な書き方をしてきたのに今年こそはさすがに立秋の名にそむきませんと挨拶することであった。
よく耳にすることは季題が混乱する、季題が無用になるので作句が難しいと訴えられる。ことに経験浅い若い人ほど、その声の多いのはもっともであろう。
しかし自然の姿がそのままに保たれる場所を発見した時のその驚きは全く命が甦る喜びを感じる。
自然の中にいて慣れてしまえば感動がない状態に置かれる。結構なことが結構と受け取れない皮肉が起こる。
だから私は季題が混乱すればするほど季題の妙味を追求する欲望が強まってこなくてはならないと思うのである。季題を無用と考えるなら俳句よりもほかの詩に鞍替えしなさい。
俳句はあくまでも自然の秩序や変化を観察してそこに詩情を湧かすことである。
彼岸の入が来ました。昔から暑さ寒さも彼岸までと言います。その彼岸です。
彼岸花が赤く咲きだしたことを不思議に私は感じます。いや不思議でもなんでもないことでしょうが、彼岸のくるのと彼岸花が方々に赤くあらわれるのとが軌を一にする。その自然のはからいがあまりに正直だと感心したわけです。彼岸花を曼珠沙華として俳句に多く詠まれます。
木犀もこのごろ匂います。黄疸になったとき物が黄色く見えたので私は勝手に金木犀を好まなかったのでした。しかしそんなことをもう忘れ去っていま匂う木犀も好いといっております。
かねたたきは明るい昼も遠慮がちにチンチンと七つ八つほど叩くように鳴きます。勿論夜は他の虫と共に合奏に加わります。
自然がこうして移り変わりがあるのは面白いではありませんか。それでいて順序というものを変えないで繰り返しを続けています。
自然を愛する俳人は人間(人工)に騙されても決して自然に騙されたことはないのです。
詩は志を述べると言われます。
俳句といえども私の心に湧いた感情を相手に通じさせなければなりません。
ところがです、自我に執着すると通じないのです。一度自我を捨てて無我の境地に向かうことが必要で、つまり私というものを客観視して非人情という立場から冷静に表現するのが秘訣のようであります。
自分をよく理解させるために相手の側から観察するという客観描字の手段をとるべきであります。
それ故に俳句は客観して、内部に主観を見通す訳になります。
情熱と非人情とは裏表である。非人情は非々人情であるという一見矛盾のようなことを漱石の「草枕」に表しています。
無我もしくは無私、そういう境地に立たないと本当の自分の心が通じないものであります。
俳句は短詩型であるだけに自我を説明する余裕もないので、直感直感で突進致しましょう。
俳句は至って短い詩型である。単刀直入に直感を表現する。
切れ字を用いるなどして多くを語らない。
とにかくこんなことを並べて考えたならば、完全無欠の俳句は木に登って水を求める類であり、できるはずがない。
では俳句は何を求めるか? 未完成の美を求めるものである。完成ではない形において、更に完成しようとする可能性を高める。それは無限に向かう美の追求である。
幸いに日本人は連想力に優れている。一を知って十を悟る稟質(ひんしつ)を持つ。また日本の国語が不完成でもわれわれには通じ合う。これは短所を活かせれば長所となることで、短歌でも俳句でもこの方法を採って生かしている。
まどろっこしい説明は不愉快になる。物のひびきに応じる答えをよろこぶ。 日本人の特性として直感を貴び簡潔を好むからであろう。
俳句会をさして、昔は運座と呼ばれていた。
誰も運座と呼ばぬようになり、その語さえ知らぬようになったこのごろ、俳文学を研究する人の口から、座という言葉が出るようになってきた。
いったい座とは何か。座は連衆の意味である。気の合うグループの集まりが座に相当する。
座を最も必要とするのは連句を巻く場合である。独吟は自分一人でやれるが、連句の妙は数人が一座して応酬しあう、その雰囲気の楽しみは格別深い。こうしていると挨拶とか存問とかいって人同士の気持ちのつながりができて、自分のことにのみこだわる欠点をなくする。
現代の俳句は仮に悪く言うならば自我に偏し一から十まで個人主義に徹している。自分のことにさえ頭を労せばよいという癖がありそうである。
そこで私は昔の人が楽しんだように座の精神を甦らせてほしいと思う。ドライでは味気なさすぎる。人の心、物の心に血を通わせるべきである。
「造化に随い造化に帰れ」という芭蕉の文章の中の言葉をよく考えてみたいと思います。
まず造化とは、万物を創造し化育した神、又は天地宇宙自然などのことを指すのでありましょう。
芭蕉は詩人として自然界を造化と呼んでそれに権威づけて造物主のはたらきを加味していたのではなかろうかと考えます。たやすく言えば、自然を尊び愛し愛される心がある。これが基本になっているのだと解しています。
俳句を作るものである吾々は、自然のあるがままに逆らわずにむしろ自然を尊重する精神になって随うならば、いろいろと自然が教え示してくれて吾々の感情を豊かに膨らませてくれます。
それには自然を向こう側の存在とせず、吾々の内側のものとしなくてはぴったり致しません。例えば松のことは松に習え、私意をもってはならぬ、と言われるのは自然と一致する努力が肝要ということなのです。
造花に帰れと言うことは私意を捨てて自然の豊かな懐の中に抱擁される。そういう気分を養えと奨めているのだと思います。
言うは易しく誠に難しい修行ですが。
空を飛ぶ鳥のごく短い瞬間は静止の姿で表われる。
これは全く動きのない静止とは違っている。とぶ動きを内蔵している静止の姿である。
このことを頭に入れながら俳句を作ってみよう。
大体対象の自然はいつも流れているのである。冬が去り春が来ることも流れの時間である。花が咲き散りはてるのも流れの現象である。常識はその流れをまとめて説明するのである。
しかし俳句を詠むにはこの常識を避けるべきである。直感を尊重する。直感というのは即刻の感動、短い瞬間に対象の形を補足するのである。それはワンポイントをねらい打ちすることになろう。
捉えた対象は静止の姿であるがゆえに実に具体的なのである。流れるとぼやけるのである。
芭蕉は「飛花落葉の散り乱るるもその中にして見とめ聞きとめざればおさまることなし。」と教えたのはその瞬間を堰きとめて詠めということである。
花が咲き野山の霞がたなびく頃になった。
私は芭蕉の「辛崎の松は花より朧にて」を脳裏に浮かべる。なぜかといえば去来抄で問題にされた「にて」留めのことである。最後に芭蕉は其角や去来が解くのは皆理屈である。自分はただ花より松の朧にてで面白かっただけだと述べている。
ものは形にとらわれがちに解釈する。「にて」は連句の第三に使うのだからと決めると、自由無礙(むげ)の境地が失われる。
自由と放縦とを一緒に見ては話にならず、真実の自由とは形に縛られず、のびのびと働けることである。形を十二分に尊重しなければならないが、その形にとらわれるのではだめだということと思う。
判ったようなわからないような気がする。これは悟って知るほかはない。
ただ辛崎の松がうす墨色にやや華やかな空気に包まれてほんのり姿を浮かした景色をいつも眼前に見る気分になれば、それで言うことはないのだ。
そのように努めて素直にやりたいものである。
ことに俳句は平明に叙するを好しとする。
先師虚子は「虚子俳話」の中に力説されている。
平明とはどういうことか。 平らかに調子良くすることが平である。 印象を明瞭に、そして表現を曖昧にせぬことが明であると思っている。
黄金を打ちのべると、柔らかく平らになってゆく。そういう気持ちで従順に詠むべきであると芭蕉がさとした。
次に表現は意思伝達なのだから、簡明なのが一番よろしい。鬼面人をおどすような、舌を咬むような、何を叙べたいのか一向に分からぬ難解の俳句は下の下と私は考えるのである。
今述べた平明は実に優しく見える。しかしながらこれは実に困難である。どうすればよいか。
平素の修練を重ねるしかない。修練によって了得することができる。
つつじの燃えている雲仙に来て俳話を行った。次のような趣旨を語ったのである。
譬えに喫煙用のライターを見てください。よい油を入れてありますから発火すると燃え続けるでしょう。油もなく空っぽであれば火花を飛ばすだけでもえませんね。
さて俳句をつくろうとすれば油が必要です。油は作者の愛です。自然を愛する真心です。自然をよく観察して自然と自己が融けあう気分を養うことです。
「松のことは松に習え」ということです。
そうでなかったらいくら事物を見て詠んでも印象とならずに消滅するのです。
芭蕉は言い了せて何か有ると戒めました。心に残るものの大切さを訓えたのであります。
自然は春夏秋冬の変化を示す。
自然は詩人に倦ますことをやらない。
白い卯の花が盛りだった。乙女峠の坂道は短いが私の足にやや急だと思ってゆっくり登ろうとした。
そこにホルバート神父がにこにこと佇っておられた。ちびたスコップを片手に路肩の修繕に労働されていたのだった。
ゆきずりに私たちへ会釈される。そしてこんな仕事せぬと身が錆びますと、使用せぬナイフの錆びるのに譬えた洒落をとばされた。
マリア堂まで辿りつけたのもこの一言に元気を与えられたおかげである。
ふだんなまけていて俄に句作しても効果がうすい。俳句は錆びないように日頃の努力が重要である。表現技能も肥え、観察も新しく細やかにすることができる。
一に明晰、二に明晰、三に明晰、と志賀直哉が文章の道に戒めたとか。
なるほどその言が当たると、直也の書かれた作品を読んで首肯してきた。
このことは簡潔を重んずる俳句にうつしても同じことが言えると思う。
作者の心を打つ対象が明晰であれば、鑑賞が楽しくなる。
明晰とは詳細にというのではない。ポイントを明らかに絞るのである。つまり要領を得ることである。作者自身が朦朧であったり饒舌であったりではダメである。
楽しい鑑賞は作者の説明を聞くことではなく、作者のこころへ素直に共鳴させられることだ。
作者の心を明晰な対象が無言の広がり(余情)と共に語ってくれる。
俳句を作らぬ人でも加賀の千代が詠んだ「朝顔につるべ取られてもらい水」なら聞いたことがあるという。
人口に膾炙(かいしゃ)しているからである。
先年千代の前の住んだ松任の寺で見た横物の真蹟(しんせき)は「朝顔やつるべ取られてもらい水」。上五のテニヲハの「に」と「や」が違う。
これは一句の生死に大きく影響する。それを説明しよう。
「や」は切れ字なので、朝顔が咲いた、さわやかだよ…と感嘆して小休止の格好。水を汲もうとすると釣瓶が見当たらぬ。誰かのいたずらだと思って近所で貰い水をするという田舎ではよく経験される句となるのである。
「に」の場合では朝顔に釣瓶とられる意味でこのことは自然でない。女の思いやりを誇張するのが主眼で、自然を偽るわけである。悪く言うと娼婦の媚に騙されるのである。
子規が月並を排斥した。月並とは「朝顔に」という俗臭ある句をさしていう。
純真に自然を愛する詩情を持たねば良い作品とならない。
人との交流にはまず挨拶をする。一般に季節のことをいう。
俳句においては季語を忘れてはいけないとしている。季節の挨拶を以って存問する文学である。
挨拶するには相手がある。相手に聞いてもらうことなのである。それ故に相手に明瞭な伝達をすべきであるから、自分だけのメモではない。
ここに二通の葉書を受けた。
一つは「菊花薫るの好季」という常識的な挨拶である。も一つは「庭先の栗落ち止みましたら柿が色づきそめました」と具体的な挨拶である。
前者よりも後者の挨拶は生きている。その人の消息であって借物ではないからである。
スト権が長引きそうな気配で世間は困惑している。
予定の行動が取れず取り消しということを打ち合わせ私は冬日のあたる家の縁側でこの一文を書くのである。
少し残っている錦木のもみじが日光を透かしている葉のみ鮮紅色に冴えて朱玉さながらに見える。錦木という名をつけられた理由も頷ける。
柿一つ残しておくのを木守柿といって来年の幸を祈るのだが、我が庭の柿はたくさん残っている。手の届かぬ梢だからやむを得ない。二羽の鵯が仲良く熟れた柿を選んで啜りあった。途中ちらっと縁側の私に視線を向けるのが可愛かった。その柿は柘榴のごとく裂けて爛(ただ)れているのだった。
「造花に随ひて四時を友とす。見る處花にあらずといふ事なし……」ふいと頭に浮かぶ古人のことばが柿の甘露みたいに味わえて楽しい。俗事を忘れることだ。
今ペンを持ちながら暮れる年がせつなく感じられます。
バチカンで聖年の聖扉が閉ざされたのであります。年のあゆみがこのごろ足音を立てているようにも聞こえ、あるいは時計のセコンドの刻みのようにも見えるのです。
芭蕉の有名な一句を紹介いたしましょう。
年暮れぬ笠きてわらじはきながら。
元禄の作者ですからわらじです。靴ではないのです。
雲水か乞食かと一見される粗末な旅人姿です。笠を頭にかぶり足は遠い道を歩くためのわらじをまだ脱ぎもせずに、つまり泊まるべき宿を得ていない道中で、年が暮れてしまったというのです。
この句は芭蕉の旅好きである境涯をそのまま表現しています。
私はこの句から更にわれわれの人生の有りようの暗喩を見つけて心の置き方を考えさされると思ったのです。
最近になって目につく語は「原点にかえれ」である。
各の方面においてしきりと原点にかえらなくてはならないと説かれる。ちょうど曲がり角に来た。このまま突進しては危険だということであろう。
物質的にあまりにも一辺倒だったので精神的なことが疎外された。原点へ戻ってやり直す時期が来たのだということで、もっともだと私は思う。
「初心忘れるべからず」と古人が芸に就くものを諭した。これも原点を忘れては大成しないとの警めである。
伝統を感じて陳腐と早合点すること、何でも新奇をねらって人を驚かして見せたいというのが現今の世相だったのである。
時代は常に変わりつつある。原点に帰ることは無理。しかし原点をよく考えることによって反省しながら中庸を得る道、そこに新しい世界をつくることは我々のやりがいある仕事だと信じて間違いなしと思う。
空いている畑のほとりに立てば草が萌え萌えそめる。
あるべき場所には正直に蕗のとうが現れて春来るの喜びが湧いてきた。
俳句を作る楽しみは季節の挨拶があるからである。何かの形でいつも自然は季節を教えてくれ、その上更に人の感情を誘い出すことも忘れないのである。
俳句は人事を詠んでもよい。自由である。ただし季節を媒体として季節に溶け込んでいる人事を詠むめば間違いはない。
作家吉屋信子は俳句もたしなみにした小説家であるが、かつてこんなことを話した。
「滝の上に水現はれて落ちにけり 後藤夜半」は有名であるが、水を改めて「人」とすれば小説になるところですと指摘したそうだ。
俳句と小説との差というものを巧みに解いているのである。
かつて天草にわたって本渡の教会を訪ねたとき、ちょうど復活祭に出会えた。
旅立ちの日は風邪の名残があってためらったけれど約束を破れないままに家を出た。幸いにも熱は出ず気分が次第にましになった。そんな時の復活祭を迎えたのであるから、忘れられない。今も聞こえそうなチャイムに目もとをこすって床を離れた朝を思い出すのである。
こらえてきた冬を終わって陽気な春に迎えられる自然の秩序は、四旬節の黙祷の後に来る復活祭の喜びと軌を一つに体験し得られて、俳句する我々の幸福をしみじみ思うのである。
あの時の風邪は煙草をまずくした。それから私の禁煙である。記念すべき禁煙となった。
他のことは問わず、ただ俳句は季節を詠むものです。
自然という対象はいつも季節の衣に包まれています。人間の行住坐臥でも勿論季節がつきまとうているのであって、季節のないものは俳句の材料として不適格なものといたします。
芭蕉は笈の小文」で四時を友とす…といっていました。造化(自然)に随うといい造化に還ると繰り返しました。そして造化を花月に代表させています。これは季節現象の代表としてあげたのあって単に花や月だけの狭義でなく、自然にまといついた季節現象や季節感情を指したのであります。
それ故に季語の扱い方を最も丁寧にかつ周到した配慮を巡らすべきだとひたすら念じています。
万代不易ということと一時流行ということとは何か反対をさしたもののように思っては間違うのである。
変化が絶えずあるから不易の実態を明らかに見られるのである。
今筆を執っている私はかの春過ぎて夏来るらしの歌にあるとおり山川草木が日々変化してとどまらぬ目前の現象に対し深い興味をわかせている。嫌われる毛虫が青梅に巣くいはじめた。るりの羽をはばたいて二三の蝶がとびまわる。産卵のためらしい。こういう変化を発見しながら、自然の秩序があって永久に変わる事の無き心理を認める。蝶の生態には真理があることは万代不易として現存すると教えられる。
芭蕉は「赤冊子」に不易と流行の二つに究まりその本一つなりと説く。そして常に変化に心を寄せるのが風雅の誠であるという。まことにそうあるべきだ。
俳句は十七字と季題の二つの約束がある。
十七でなければならないのに俳句と川柳とがある。
季題はただ俳句のみである。
何ゆえに季題を約束とするのか。
俳句の歴史を見れば、俳句とは連歌から俳諧連歌が生まれその第一句目を発句と呼んだ。発句は以下の付句(第二句目を脇句の七七とする。)との立場を異にする。それは挨拶を行う役目がある。その時候への平たく言うと "お暑うございます" の如き挨拶を大らかに叙べる。
その挨拶の目的は自然を賛美しそして人生の幸福を心に祈る仕組みであって、季題が生じた訳である。
明治になって発句を俳句と改められ、もっぱら俳句の一本立になった。付句する俳諧連歌、略して連句と言うがそれはあまり振るわない。
付句の一部から川柳が生まれ、現在も多くの作者を出しているが、季題の約束がない。人事の機微や風刺を唱える世界を創るようになったのである。
きのうはマリア様の被昇天であり、また日本降伏の敗戦記念日であった。
悲喜両極のまじわりあった感情で迎えた。
今日は送り盆の日、京都に大文字がともり各地で灯籠流しをするであろう。
最近になって行事が観光的に見られるばかりで、主要な目的がなんであるのかとまどいさせられてしまうものが多い。
雲海は泰し八月十五日 青畝
霧ヶ峰で雲海を見た。八ヶ岳の鋭い矛はわずかにのぞき、さらに富士の霊峰が盃を伏せた正しい形を薄く現していた。
この印象がふと八月十五日に浮かび出たので句にした。過去現在未来の三世を通じての真の平和な念願を一生懸命に捧げるものである。
贈られた月下美人というサボテン属の花が豪華に咲きました。
芳しい匂いが部屋に充ちました。が夜の三、四時間たてば忽ちに萎えしぼみました。もののあわれです。
すべて草木の花はそれぞれの特徴をもった美しさがあります。その美しさもしぼんだり散ったりしてしまえば消えます。私たちはその儚さを惜しみ、いまさら美しかったことを心に深くとどめるものです。
もし造花のごとくいつまでも散らぬ花があればこのように花の美しさに憧れるでしょうか。
人は飽きっぽいせいか、見慣れて注意しないでありましょう。
で、儚いことに愛着がつのり、そうして一期一会として僅かな時間を十分にしなければならぬという大切なことを教えてくれます。
私の恩師虚子は、俳句は存問であると言われました。
存問という語が聞きなれないので広辞苑を調べたら、安否を問うこと、慰問することとあるのですっきりしたのであります。
つまり挨拶する我々のその態度は相手を心に引き止めようとします。見逃すことではないのです。
俳句を作るとき自然という対象に必ず接しますが、自然に向かって安否を問うという親しみをもっていないと、自然はあたたかく私たちに近づいてまいりますまい。
自然の諸相があけひろげに許されたとき俳句が生まれしかも新しい発見を拾いものに授かります。
自然を征服するとはいかにも勇ましく見えるが、自然のほうが抵抗するので、人間の増上慢によって失敗します。
流れゆく大根の葉の早さかな 虚子
漬物などにする大根引の頃の冬の田園風景を見ると、すぐ自然の冬のさまざまが連想される。俳句は存問であることを同感せずにはなりますまい。
俳句はわずかに十七音しかない文学なのです。
小説のように人情の葛藤を網羅することは不可能と理解すれば、複雑なものを避けて最も簡単率直であるものに興を感じてそこに重点を置くという方針が適当であることを会得するでありましょう。
そこでわれわれ日常に使う挨拶が俳句に取り入れやすいと思います。
挨拶というのは相手と出会うときに表現する会釈で、相手に好感を示すものなのです。これは風土に対し生活に対し自他お互いに平和な気持ちを感謝することではないでしょうか。
簡単に短い言葉で用が足りる。クリスマスが近づきました。お子たちも喜んでいらっしゃるかと存じまして…と申しますと、もう時候のことも伝わるので、こういうところに俳句の基本があるのです。しかし文学としては概念にとらわれず、自分の誠から生まれる言葉によって近しさを創ってゆかねばなりません。
これからしばらく季語を解説してゆこうと思う。
季語は俳句において重要な役目を負うものである。エネルギー源と見るべきものである。
除夜から新年になったばかりの感じを言う。「去年とやいはん今年とやいはん」と言われるごとくその境目の気持ちに初々しいほやほやの新年が生まれる。
去年今年貫く棒の如きもの 虚子
新年は目出度いから縁起を良くするために言い換える。これはねずみを嫁が君といい換える。
嫁が君出て貧厨のめでたさよ 狐峰
おさがりと読む。元日に降る雨をいい換えた。雨は縁起良くないという理由。雪も御降に加えてよし。
御降の祝儀に雪もちらりかな 一茶
餅は新年である。その餅を入れた七草粥とかあずき粥とかの場合に粥柱と言う。
天われにこの寿を賜う粥柱 風生
七日の朝薺を刻み込んだ粥である。十五日はあずき粥である。
薺粥箸にかからぬ緑かな 蝶衣
季節の変化に恵まれた日本の風土に季語の必要は当然であります。
時代とともに行われぬ季語もあり、新しく生じる季語もあってしぜんに交代します。しかし忘れてしまう古い季語でも遺産として大切なことがあるでしょう。
礼記から出た空想季題である。魚を捕食する獺が春のある期間先祖を祀るため魚を川岸に陳列すると言い伝えています。子規居士(こじ)の別号は獺祭書屋で、自分を獺に譬え書物を大切にする意のようであります。
新聞などに使われる気象語であります。二月の末か三月の初めの頃の暖かい暴風で台湾坊主とも俗間で言います。実際にこれが南からやってくれればにわかに春らしい日本を見る感じがいたします。
禁教の江戸時代にキリストを信仰する者に強制して絵像を踏ませたのであって、廃れた季語となりました。歴史に興味を寄せる面白い季語ではないでしょうか。
四季の変化ある自然を風詠するのが俳句である。
要約すれば俳句は花鳥諷詠であると旧師虚子が仰ったことを我々は守るのである。新しい俳句は四季の変化に敏感となり表現を工夫すれば生まれてくる。
さて中春の季語解説にうつる。
春一番ともいう強い南風が三月頃に吹く。漁師の言葉で暴風が貝殻を難波へ寄せるという。その頃四天王寺は聖霊会が行われる。また別に「涅槃西風」というのがあるが貝寄風と似た風と考えればよい。
季節の一つ名をいう。その頃には冬眠の蟻や蛙などが地中から這い出てくる。それが転じて地虫穴を出る…という季語と同じ意味に用いられてきた。
彼岸の大潮は干満の差が大きく特に鳴門海峡はものすごく渦が巻くので、見物のために舟が出る。
たとえ要談する場合があっても、まず挨拶を忘れない。
挨拶はたいてい時節のことに触れる。そして相手の安否をたずねてみるのがわたくしたちの日常生活の習慣となっている。和やかな気分を作るのがこの挨拶にある。
さて季語は季節の言葉である。気候風土に恵まれているために豊富に季語は生まれる。枚挙に遑ないが、ここには珍しく解説を要する題を拾うことにする。
陰暦四月を卯という。卯の花が咲く頃で、雨がかなり多い。この長雨が卯の花を腐らすほど降るという意。さみだれとか梅雨よりやや早い雨をさす。
ついでに卯波という季語はこの頃の海に立つ波である。波の穂の白さが卯の花を思う。
春より遅れた桜の花をいう。残花ともいうが、残花では春の部にし、余花を夏の部に分類される事もある。これは気分の味わいで分けるので実体の相違ではない。
昔から奈良で行われている興福寺の薪能は篝を焚いて夜まで四座が演じた。春日明神に奉納して演じるので今日の観光目的ではなかった。
今日では各地でこの薪能を真似て行われるため、本来の意味がぼやけてしまうようになった。
大石田に迎えられて一巻の連句を巻くとき芭蕉は時候の挨拶を発句に現した。それが、
五月雨を集めて涼し最上川
であった。客人として座敷の涼しい気分を述べることが挨拶である。その後急流を下航して涼しを早しと改めているが、それは連句の場合よりも自由に対象を受け止めた実感にぶつかった故である。最上川の本領をつかんで奥の細道に採録した。
さて六月の季語を解題しよう。
わくらばと読む。夏の青葉に混じって変色している葉のことで葉が病みついたという意か。また常盤木落葉がある。冬に落葉しないで新しい若葉と交代して落ちるのは夏である。
古来詩歌に詠まれるが、六月ごろは甲高い声で鳴き血を吐くなどといわれる。
昔の人は郭公と時鳥とを混用したが、両者の鳴き声は違う。カッコーとひびくので閑古鳥とも言われ、淋しい感じがする。とにかく六月は多くの鳥がいる。ポンポンと鳴く筒鳥や十一というように聞こえる十一やブッポーと鳴く仏法僧もいて夜間でも耳にすること稀ではない。
昔から詩歌に「季のもの」と言われていた。季節を表す事物を指す。
また俳諧では「季題」と言い季のものを詠む題目となして行われた。
現今は題目を与えてもらって詠むのではなく、自由なテーマのもとに季語を含めて詠む傾向になったので「季語」と我々は呼ぶ。例により季語解説にうつる。
雷雨に伴って氷塊の降ることがある。農作物を荒らされるのを雹害という。歌に氷雨(ひさめ)ともいわれたりするが俳句では霰とか冷雨に氷雨を用いている。
軟らかい潤葉樹の葉を几帳面に小さく巻いているのがある。褐色に枯れているゆえ発見し易い。これは小虫の卵が葉に巻き込まれたもので時鳥の落し文…と優雅に名づけている。あたかも時鳥の季節と合うからだろう。
蚤虱馬の尿する枕許…と芭蕉の詠んだ蚤は、戦後生まれた人には蚤の痒さなど理解されるのだろう。昔は生活の中に忘れられぬ存在だった。
時代の変遷は自ずから季語にも影響を及ぼして廃れる季語が生じるし更に新しい季語の登場が現れる。
季語は独断で製造されるのではなく、一般の共感から通用されていくものであろう。日本文化として現代廃れた季語も抹殺せずに遺しておく方がよいと思う。また新しい季は乱立しやすいけれどもよく精選して後代に伝えていく価値を持たせたいと偏に念願する。
次に季語解説にうつる。
富士山が赤く染まって珍しく望めることであるが、俳句では夏季とする。主に甲斐側は夏の早暁に生ずる現象で素晴らしい日の出の反映である。
注意して見ないと目につかぬ微かな毛の如きもの。実はクサカゲロウの卵だが、障子や電燈の笠などに発見する。昔から迷信があり、不吉の前兆という人もあり逆に善兆とかつぐ人もある。
しまんろくせんにち…面白いことばと思う。有名なのは浅草観音の七月十日の縁日である。この日に参詣すれば四万六千日も参詣した大功徳を授かるというので別名功徳日と称されている。東京では青鬼灯の市が立つ。
時候の移り変わりによって季節の感覚の鋭く又周到に行き渡った小説などを読んだときやはり生き生きとした命の通うのは不思議である。
小説の虚構を忘れさせて素直な自然に読者を安心させる。
さて、季語解説にうつる。
いろいろの秋草の咲きまじる野のこと。高原にはお花畠がある。花は桜ということに定められているが花野は違うので注意したい。草の花は秋草の花で秋である。
七夕祭の前日に硯をきれいに洗う。そして書道の上達を願うのである。墨滓(すみかす)で汚れた硯を洗うだけでは季語にならぬ。梶の葉という季語もある。梶の葉に文字を書いて七夕様に手向けるからである。梶は桑に似ている。
名月の前をいう。十五日は月が満ちて名月。望の夜ともいう。降ると雨月であり曇ると無月。十六日は十六夜でまた既望という。十七日が立待、十八日が居待、十九日が寝待、二十日が更待、というように月が遅れて出る。また月が細くなるのである。
古人はかように月に憧れ月を愛でて生活していたことが分かる。
朝夕がどかとよろしき残暑かな
右は私の句であるが昨今の朝はひやひやした空気にひたされ爽快さを覚える。ことに残暑が長く厳しい場合ほど切実に爽快感がよく受けられる。
ようやくに残る暑さも萩の露 虚子
庭の萩に白い玉のような露一粒を見て、真昼は暑くても、やれやれ秋だ、残暑の威力は衰えてきたことを知る。
さて、季題解説にうつる。
新季題であるが、昔から言われている。あっという間に秋の太陽が沈んで暮れる。釣瓶を井戸に落とすごとく早いから。
もののあわれを感じる事で冷気が体にこたえるごとく秋の季感を強く受け心に染み入る場合を言う。
涼しを通り越した荒涼たる感じをいう。ものすごく心細い秋の感じをさす。冬に近い気分でもある。
変化しないもの変化するものこの二つが巧に組み合わされることを、過ぎきし時候を振り返るとき不思議なくらい感じました。
今年の夏はひどく暑いので夏好きの私も夏負けに弱音を吐いたのですがやがて秋がやってきました。長かった残暑も現在はさわやかに澄み切った秋に包まれて快適です。夏から秋に移る軌道は不易です。不易は流行を含めるものであるから面白くなるのだと思います。さて、季語解説に──
十一月に吹く西風をいう。出雲へ神々が集まるときで出雲は神有月といい、その他は神無月という。木の葉が散ったりとかく荒涼とした景色へと一変する。凩という季題もある。神渡は宗教味が混じっている。
冬になってこの葉が落ちるように人間の毛髪もまた油気が乏しくて抜け落ちる。そのわびしい感じが伴っている。鳥類の羽抜けるのは夏だから別になる。
きもり又はきまもり。すっかり落葉した木に残る果実をいう。来年の豊作を祈る心が寄せられている。木守柿はよい例。
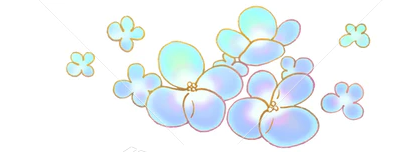
掌俳話は、キリスト教信仰誌である『声』に連載されたものです。 (1972~1977)
作句に行き詰まったとき、不調に陥ったときなどに読み返すことで原点に帰り軌道修正することができますので、あなたの俳句ライフのバイブルとしてご愛読いただけることを祈念いたします。
タイトルの「掌」は、"主観と客観は一如であり掌の表裏の関係" と説かれた下記からの引用と思われます。
わたしの手をごらんなさい。
やわらかい手の平が主観とすると、かたい手の甲が客観となり、いつも表裏の関係をなしています。
この表裏を引き離せば、わたしの手の命はなくなり、手の存在を失うということを考えてください。
やわらかい手の平は、握りしめれば内部にこもります。
主観というのは、作者の心ですから、常になくてはならないものですが、それは表面には現れずして内部にこもり、外部からはちょとも見えないことがあります。
かたい手の甲はつねに表面に出ていて、握りしめてもこれを内部に隠すことはできません。
客観というものは作者の心が感じている相手であり対象物です。作者の心がもしも鈍って感じないときには目の前に対象物が厳と存在していてもその作者にとっては無きに等しくなります。
つまり、主観がなければ客観も存在しないということです。
作者は、客観写生をするためには、つねに主観を活発にはたらかせなくてはならいという道理です。
いくら宇宙に万相が無限にころがっていて作者の応接にいとまがないといっても、中心の作者の心が無感応であったならば、ゼロに等しいことです。
著書『俳句のこころ』から引用
![]()
メーリングリストで配布したPDFファイルを一巻に結合しました。必要な方は印刷してご利用ください。
感想やお問合せはお気軽にどうぞ。